お気に入りの音楽を聴いているとき、楽しくリラックスした気持ちになれるのは人類共通の現象。しかしプラスαで、音楽には直接的に肉体的なダメージを癒す力があるかもしれない、というデータがあります。そこにはどんなメカニズムがあるのでしょうか?
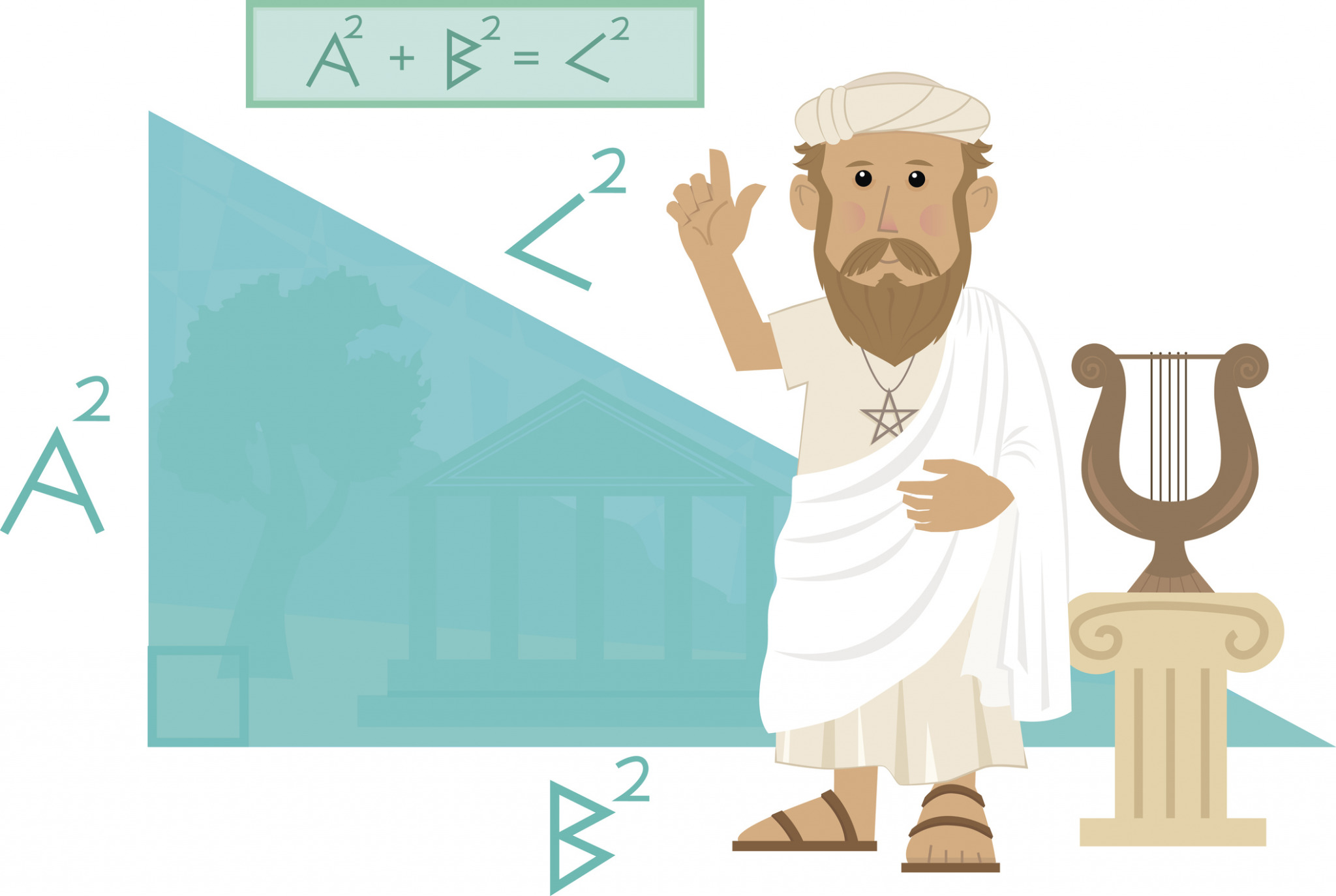
音楽に人の身体を癒す力があるという考え方は、古代ギリシア時代にはすでに存在していました。例えば今から約2500年前、哲学者のピタゴラスは「音楽は代替医療として使用できる」と主張しています。
それから長い時が経ち、音楽療法が医療の手段として使われ始めたのは第二次世界大戦後のこと。アメリカ軍の負傷兵病院で音楽を流したところ、メンタル面での不調を訴える兵士に効果が認められたため、急速に研究が進みました。1950年には全米音楽療法協会が創設され、音楽療法という医療ジャンルが確立されました。
ただしそれはうつなどの精神疾患に対する心理療法の一環としてであり、ピタゴラスが主張したように、音楽が肉体的な回復を促すという視点ではありませんでした。しかし、2017年〜2018年にかけて行われたある研究で、「音楽はメンタルとの相関なしに、一次的に肉体のダメージを癒すことができる」可能性を示唆する結果が出たのです。
そのある研究とはジョン・S・ライド博士によって行われた「音楽が赤血球に与える影響」というテーマの研究です。これはクラウドファンディングで資金を募り、米ラガトース大学の研究者グループにより行われました。
その手法は、
ヒトから採取した血液の小瓶を体温と同様の温度(37℃)に保たれた培養器に入れる
→ 培養器をデジタルアンプとスピーカーを配置した部屋に入れる
→ 小瓶ごとに異なる種類の音楽、静かな環境、ホワイトノイズに20分間曝す
→ それぞれの小瓶の中の赤血球数を調べる
というもの。
血液はO型の女性から採取されたもので、アンプはSMSL社のSA-36A、スピーカーはソニーのSS-TS3が使用されました。
実験結果は以下。静かな環境を1としたとき、生存能力のある赤血球数が何倍かを音楽のジャンル別に示しています。
クラシックのオーケストラ、ハープ、ピアノ → 2.22:1 〜 7.93:1
ラップ、ポップ、ギター → 7.33:1 〜 23.4:1
男性ボーカル → 2.1:1 〜 10.7:1
女性ボーカル → 5.26:1
女性ボーカルと演奏 → 18.1:1
音程を声で発声 → 4.13:1
ダンスミュージック(テクノ-ハウス) → 14.42:1
音楽療法の装置が出す音 → 11.72:1
ゴング → 5.5:1
スピリチュアルな東洋の聖唱 → 17.69:1
ホワイトノイズ(85デシベル) → 4.61:1
ホワイトノイズ(105デシベル) → -0.21:1
面白いのは、明らかに心が安らぎそうなクラシック音楽よりも、ダンスミュージックやラップやポップなどの激しめの音楽を聞かせた血液の方が、元気な赤血球の数が断然多いこと。
研究者グループは、「女性ボーカル」と「女性ボーカルと演奏」の数値に大きな違いがあることに注目し、「ベース音などの低音が含まれる音楽の方が赤血球を活性化させやすい」と推測しています。さらに踏み込んだ仮説では、「低音に含まれる低周波が心拍と同じように振る舞い、ヘモグロビン分子が酸素を取り込む働きを助ける可能性がある」としています。
とすると、激しさはなくても低音域が続く「東洋の聖唱」の数値が高いのにも納得がいきます。
また、以前取り上げたバイオフィードバック/バイオレゾナンスの、身体に特定の周波を送ってダメージを修復する治療法は、上の実験結果に似たアイディアと言えます。
次に注目したいのが、105デシベルのホワイトノイズに曝した血液では、ほとんどの赤血球が死滅したという実験結果。105デシベルというと、間近で鳴らされる自動車のクラクションや、電車が通るときのガード下の騒音レベルです。
ただし、85デシベルのホワイトノイズに曝した血液では元気な赤血球の数がアップしています。となると、有害なのはホワイトノイズではなく、大音量ということでしょうか。筆者がクラブに行くときにも、同じようなテクノ音楽の中で「心地よい」と感じるときと、「うるさくて耐え難い」と感じるときがあります。低周波を含む音楽であっても、85〜105デシベルのあいだに、超えてはいけない境界線が存在するのかもしれません。
これはまだ試験管レベルの実験結果ですが、臨床実験で同様の結果が得られたなら……騒音レベルが高い立地に暮らしている人は、健康のために引っ越しを考えた方がいいのかも?
参考リンク: Testing a 2,500 Year-Old Hypothesis 音楽療法士の私が音楽療法の歴史を簡単にご紹介『日本での現状』とは?
(佐藤ちひろ)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!