2023年4月、徳島県神山町に全寮制の私立高専「神山まるごと高等専門学校(以下、神山まるごと高専)」が開校し、一期生となる約40名の学生が入学した。実に19年ぶりとなる高等専門学校の新規開校ほか、民間企業11社から約100億円の寄付や出資をもとにした学費無償化の実現。テクノロジー、デザイン、起業家精神を掛け合わせたほかにはないカリキュラムなど、開校前から高い注目を集めてきた。
データのじかんを運営するウイングアーク1stも企業版ふるさと納税を活用し寄付している。
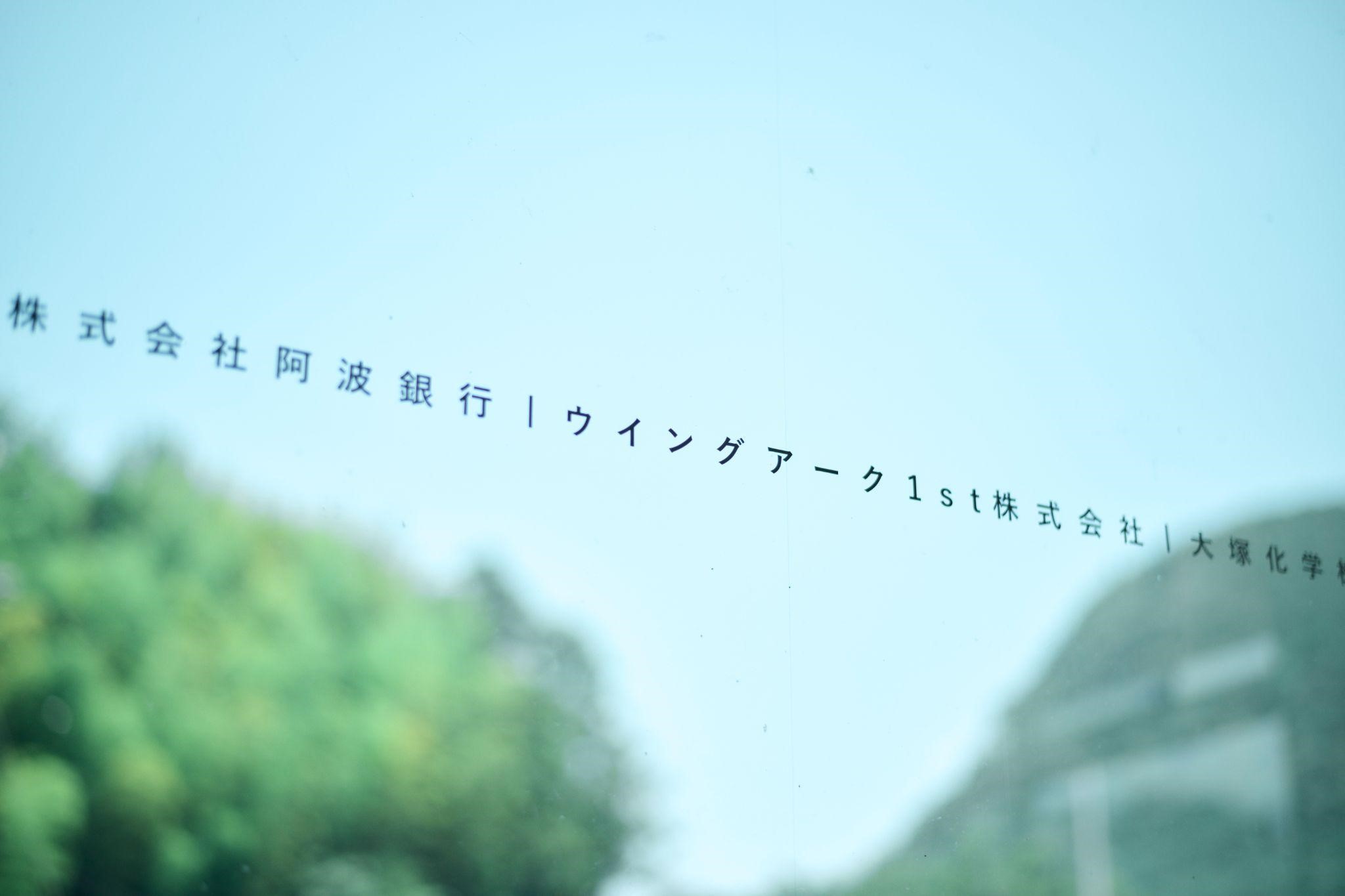
教育業界はもちろん、地域振興やイノベーション・プラットフォームとしても注目が集まっている神山まるごと高専。今回は、その屋台骨である松坂孝紀事務局長にデータのじかん主筆の大川がインタビュー。新進気鋭の私立高専が見据える教育と、学生だけでなく同校にとっても「最初の夏休み」を迎えて早くも変わった起業家精神を養うための学生の「支え方」について聞いた。
神山まるごと高専 事務局長 松坂 孝紀 氏(写真左) /データのじかん 主筆 大川 真史(写真右)
インタビュアーの主筆の大川は、大学時代に地域経済学を専攻していた。2014年、(独法)経済産業研究所のファカルティフェローでもあるゼミの担当教授が、神山町について定住者や産業振興を目指さずに関係人口を増やす「まちづくりのイノベーション」として、神山まるごと高専のある徳島県神山町を取り上げるなど注目していたという。
―― 高等教育をはじめ戦後から殆ど変わらない教育システムに感じる「まずさ」がピークを迎えるタイミングでの神山まるごと高専の開校でした。個人的にワクワクしかない印象です。まずは松坂さんの高専での役割を教えていただけますでしょうか。
松坂事務局長(以下、敬称略):私の役回りは民間企業で言うCOO(最高執行責任者)のような役割ですね。CEOは本校の理事長で、Sansan株式会社の創業者でもある寺田親弘。学校というプロダクトの責任者は学校長で、ZOZOの技術責任者だった大蔵峰樹。私は学校全体の運営を担っています。
―― 「新設の私立高専の事務局長」というキャリアはなかなか選択肢に入らないように思います。松坂さんが神山まるごと高専のプロジェクトに参画した理由を教えてください。
松坂:これまで社会人向けの教育事業会社のマーケティング職や経営企画のほか、人事系コンサルティング会社の経営といった人材・教育の領域で仕事をしてきました。その中で地方自治体の人材・教育の案件を多く扱っており、地方と東京との格差を目の当たりにしました。一方、自分の中で「新しいモノが生まれるのは地方である」という一つの信条にたどり着けたのが、神山まるごと高専のプロジェクトが非常に魅力的に映った大きな理由だと思います。
―― 松坂さんが気付いた「地方と東京の格差」とは?
松坂:地方自治体の困りごとで非常に多いのが「人」であったので、私たちは「町づくりを担う人づくり」のためのプロジェクトを実施してきました。そこで東京生まれ東京育ちの私は、初めて地方の実情を知りました。教育や情報といった様々な地方と東京の格差は、当時の私が漠然と描いていたイメージよりもかなり大きかったのを覚えています。数ある格差の中でも特に「就労の格差」と「教育の格差」は深刻で、人口動態にダイレクトに影響すると感じていましたね。
――その一方、「新しいモノが生まれるのは地方である」という考えは、イノベーションの観点から個人的には大変共感します。松坂さんもそう信じている理由について教えてください。
松坂:一言でまとめるなら「明確にニーズが目に見える」ことだと思います。「駅前に〇〇が欲しい」という具体的なニーズは地方で当たり前なんですが、そんな声は東京だと意外と拾うのが難しいんですよ。明確なニーズはある意味、それに応えるための「エネルギー」になります。だからこそ、エネルギーの大きい地方こそ新しいモノが生まれる土壌が豊かなのではないかと考えているわけです。そんな私にとって「地方から人材を育てる」という神山まるごと高専が刺さりましたね。
―― 課題やニーズの解像度が高いため熱量があるという事ですね。私もメインストリームではない「オルタナティブ」がイノベーションを起こし次世代のメインを創るのではないかと考えています。都市よりも地方という松坂さんのお考えとも合致する部分が多いと感じました。神山町に移住して2年経った松坂さんから見て、移り住む前後で印象などは変わりましたか?
松坂:住む前から神山町について様々な資料を読み込み、死ぬほどリサーチしていたのでさほどギャップはありませんでしたね。一番のギャップというか驚きは近隣の方から「野菜をかなりの量いただける」ということでした(笑)。とはいえ、実は地元の方から「松坂さんは神山町が合わないかもしれない」と言われたこともあるんですよ。
―― 今の雰囲気からは少し想像できない言葉ですね。その理由は?
松坂:私たちが当たり前のように使っている「まちづくり」は危険なキーワードで、その実、まちは「つくられたい」とは思っていないと。
―― なるほど。かなり強烈な言葉ですね。
松坂:ですよね。今でもかなり胸に刺さっています。私自身、コンサルティングを主な業務としてきていたので、まずは大きなビジョンや絵を描き、それに向かうためのシナリオを書き、それを実現するためのプロジェクトマネジメントを行うのが当たり前でした。そのような「意図した成功や成果」を挙げるためには、その過程で生まれる「雑草」のような情報や事象はリスクでしかないんです。一方、神山町のまちづくりはバックキャスト的なアプローチではなく、少しずつ色んなモノを耕すなかで、意図しない出来事といった「何かが生えてくる」というスタンスでした。町の人はみんな「雑草が大木に成長する」ことを心から信じていて、その有機的な活動のなかで少しずつ「まちがつくられていく」という切り口で、まちのデザインの仕方をデザインしていると気付かされました。神山町の強みであり、私の移住のきっかけともなりました。
―― 凄く本質的なエピソードだと思います。私も神山町の取り組みを追いかけていますが、これまでの様々な取り組みの延長線上に神山まるごと高専が生まれたという認識です。地域おこしのためにハコを作って高専を誘致しようというきっかけではないのが象徴的ですよね。同時に「これからどうなるんだろう」というワクワクが搔き立てられるのだと思います。
松坂:そうですね。神山まるごと高専は、全国初の学校法人を設立した私立高等専門学校ということで多くのメディアで話題にしていただきましたが、ぽっと出で生まれたのでなくその裏には30年以上にわたって神山町が耕してきた土壌から芽吹いたのだと感じています。
―― 敢えて「高専」を選んだ理由を教えてください。
松坂:理事長の寺田が創業したSansan株式会社がサテライトオフィスを神山町に作ったのが最初の縁でした。神山町にどんな教育機関をつくるかと思案するなかで、最も成立できる可能性が高かったのが、寮があるのが一般的なイメージかつ中学生の進路としても確立している高等専門学校だったのです。
―― 周辺環境や条件だけでなく、高専のメリットやポテンシャルについても考えられましたか?
松坂:もちろんです。15歳から20歳という人生の中でも、心身ともに特に大きく成長して変容するこの時期に、大学受験に取り組む必要が無く、社会と接する機会を提供できるのが最も大きいのはメリットといえるでしょう。高校時代のほとんどを受験勉強に費やし、大学時代はその反動で就活や卒業論文以外はモラトリアムを満喫した人は私だけではないと思います(笑)。一方、高専は自身で決めた専門分野について、受験を考えることなく集中して学びながら社会に出る準備ができることは極めて有効だと感じています。また、高専は全国の学生の進路先としては1%で年間1万人程度しかいません。その1%しかない選択肢を選べる人は「人と違うことをする」という起業の根幹ともいる「腹づもり」も、私たちが描く学生像と相通じる点があるとも考えていますね。
―― 確かに、私の周りにも高専生がいますが「ゼロイチマインド」は随一だと感じています。また、オルタナティブだからこそ高専生同士のつながりが強い印象ですね。
松坂:そうですね。高専出身者同士だと「高専出身なの!?」という会話は珍しくないですが、大卒同士で「大学出身なの!?」とはなりませんからね(笑)。近年は国内外で再評価され、海外でも高専を設立する動きもあります。高専は日本初の非常にユニークな教育システムだと思います。
―― 戦後誕生した高専は長らく工業(ハードウェア)を中心とした技術革新の基盤を担ってきました。一方、ポスト工業社会を迎えつつある昨今、これまでとは異なる役割が求められるのではないでしょうか。
松坂:時代が変わっても高専の一番の根幹は「ものづくり」であると思います。いつの時代も自ら手を動かせる人の価値が極めて高いのは間違いありませんから。一方、ものづくりに特化するあまり、高専生のキャリアとしては「製造業の最前線」や「開発部隊の一員」として働くイメージが強いと感じています。だからこそ、私たちは「モノをつくる力で、コトを起こす」をミッションに掲げ学生を育てようとしています。
―― 「コトをおこす」においては国が推進している「アントレプレナーシップ教育」とも相通じる部分はありますか?
松坂:「アントレプレナーシップ教育を小中学校から行えば起業家が育つか?」という問いに対しては、私自身は必ずしもそうとは言い切れないと考えています。本当に重要なのは「手の動かせるアントレプレナー」であること。そうなると高専生にアントレプレナーシップ教育するか、もしくはアントレプレナーシップ教育を受けた学生にものづくりを教えるくらいしかありません。となると、最短コースなのは「高専生にコトづくりを教えること」なのではないでしょうか。だからこそ、私たちは情報工学×デザイン×起業家精神を掛け合わせた教育方針でカリキュラムをゼロから組み立てました。
―― PBL(課題解決型学習)やアクティブラーニング、反転授業にも通じる話だと感じました。一方、「自分でつくる人」というマインドセットやアディチュードを育てるという感覚は、既存の教育機関ではなかなか気付けないと思います。この点についてはどうお考えですか?
松坂:PBLは昔から高専でも実施されていました。ただ社会人になるとリスキリングはあったとしても、PBLやアクティブラーニングという言葉を聞く機会ってほぼないと思うんですよね。ここに学校での教育と社会人としての教育に大きな乖離があると考えています。神山まるごと高専は従来の学校とは異なり、バックグラウンドがビジネスや現場目線の講師やスタッフが多いと言えます。従来の教育の良いところは踏襲しつつ、ビジネスの現場から見た教育も実践しようとしています。重要なのはPBLを導入することではなく「結果的にPBLになっている」ことなのだと思います。「〇〇をやること」や「〇〇を導入すること」はあくまで手段であり本質ではありませんから。
―― 個人的にオープンスクールにも参加しましたが「教育エンターテイナー」を自称する方、学生を先生のように接する方、「まずはC言語から教える!」と断言する方など、非常にユニークな講師が集まっているように感じました。個人的には講師の皆さんが学生に「教える」「ガイドする」「サポートする」というよりも、学生を「応援する」というスタンスでいるように感じたのですが、学校として講師を選ぶ基準や共通理解はありますか?
松坂:採用段階においては当校の特殊性を理解して「一緒につくっていける」という立ち位置を理解していただける方は一貫したポイントですね。結果、意識せずとも全21人中13人(約6割)の教員が民間で働いたことのある人だったのは、かなり特徴的な組織になったと思います。あと、大川さんに私たちが学生を「応援する」スタンスを感じていただけたのはとても嬉しいですね。実は開校から2カ月ちょっとで学生に対する私たちの基本スタンスを「支援から応援へ」に変更したのです。
―― そうでしたか!詳しく教えてください。
松坂:一般的に教育現場では生徒指導という言葉が使われていますが、当初から私たちのスタンスにはマッチしないと考えており「支援」という言葉に置き換えていました。実際に「学生支援チーム」という組織も存在していました。ただ、開校してしばらくすると「どこまで支援すべきなのか?」といった議題があがるようになり、学生と講師間の結果的にコミュニケーションコストが高くなってしまいました。そこで立ち返ったのが「そもそも支援というスタンスが正しいのか」という点です。支援とは「一人では立てないという」という前提に立ち、大人が先回りして杖を渡すといった行動が求められます。実はこれって、私たちが起点になってしまっているので、「コトを起こす人」を育てる観点ではあまりやるべきでないことなんです。だからこそ、”学生のやりたい”が起点となり、私たちはそれに応える「応援」が基本的なスタンスだと改めて共通認識とし、必要に応じて支援や指導を行うことにしました。それを持って5月末にはチーム名も学生応援チームに改称したのです。
―― 素早い対応ですね。それ以上に物凄く共感します。社会人や企業におけるキャリアディベロップメントも「キャリア支援」ではなく「キャリア応援」ではないでしょうか。人事応援課といった部署が存在しないのも、神山まるごと高専のような「起点」を定めて応援する基本スタンスを見逃しているのかもしれません。
―― 開校する前後、地元の方の反応はいかがだったでしょうか。
松坂:私が移住してきたときには「本当に高専できるんだね」というくらいの温度感でしたね。やっぱり「事故が増えるんじゃないだろうか」とか、これまで色々な新しい取り組みを興してきた神山町の方であっても、不安を感じて慎重になるのは当然だと思います。私たちだって一期生が5年後に卒業式を迎えることを考えると不安も感じます。結局コトを起こす以上、未知はどこまで行っても未知なので不安を解消するためには、「誰がコトを起こすのか」が大事なのだと思います。そのために必要なのはコミュニケーションですね。そういう意味では開校直前のお披露目会(オープンハウス)では、一週間の実施期間中に人口約5000人中1500人の町人の方が来校してくださるなど、非常に興味を持ってくださっていると感じています。それに私たちはもちろん、学生と町の人たちのコミュニケーションも欠かせません。既に学生が町内でバイトをしていたり、町内の小中学生に向けて学生がプログラミング体験会を企画、実施したりなどコミュニケーションが生まれ始めています。
―― 早くも新しいつながりが生まれているのですね。四半期を振り返った感想とこれからについて教えてください。
松坂:保護者の方から「家に帰ってくるたびに成長している」という声が、学生が未知に挑み続けるプロセスを歩めていると実感しています。「応援」するスタンスで今後も「学生のやりたい」を後押ししていきたいですね。
(取材・TEXT:藤冨啓之 PHOTO:渡邉 大智 企画・編集:野島光太郎)
「データのじかん」がお届けする特集「Local DX Lab」は全国47都道府県のそれぞれの地域のロールモデルや越境者のお取り組みを取材・発信を行う「47都道府県47色のDXの在り方」を訪ねる継続的なプロジェクトです。
Local DX Labへメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。