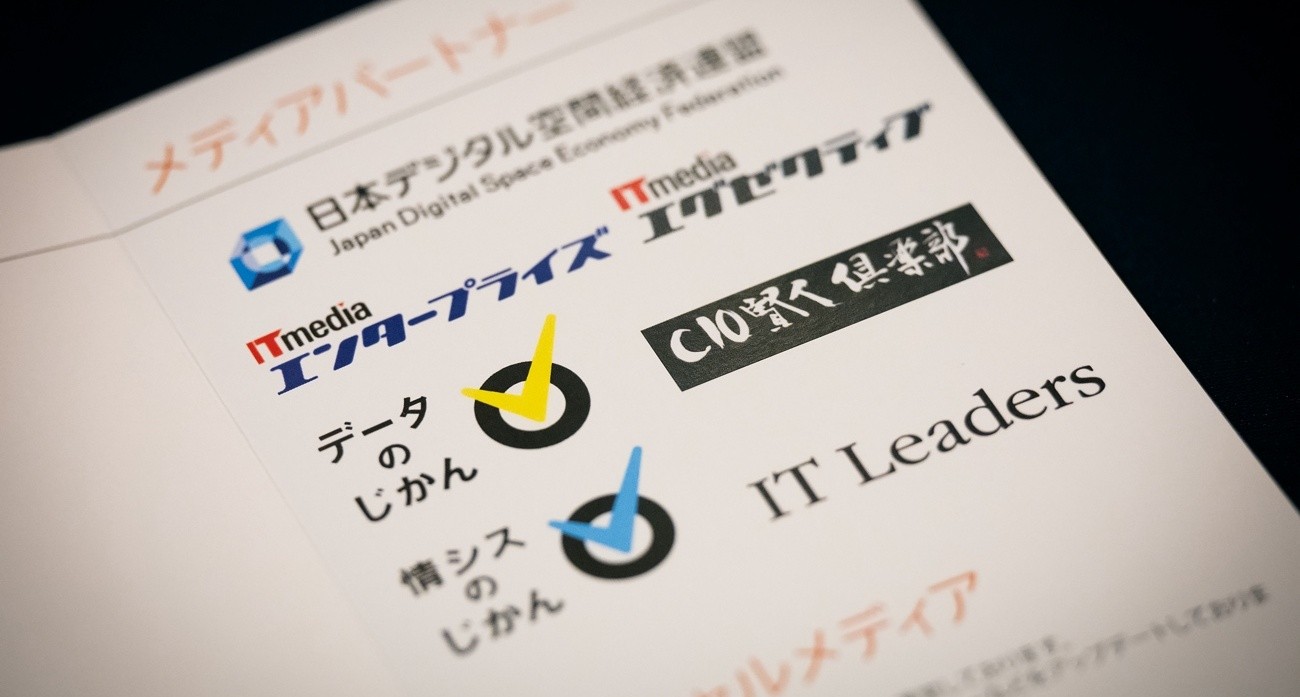
1990年代初頭に半導体を主導する「電子立国」を目指していた日本は、その後バブル経済の崩壊を境にグローバルなデジタル化競争で遅れを取り、経済の低迷から抜け出せない状況が続いている。この現状の背景について、民間企業での経験が長い経済産業省の河﨑幸徳氏と、金融業界からIT業界に転じた福永哲弥氏が、IMD(国際経営開発研究所:International Institute for Management Development)の「世界デジタル競争力ランキング」や「競争力ランキング」のデータなどをもとに、次のように分析した。
1.デジタル投資額と名目GDPの横ばい
日本では、2000年から2020年にかけてデジタル投資額と名目GDPがいずれも横ばいの状況が続いている。一方、米国ではいずれも右肩上がりの成長を見せている。
2.デジタル競争力ランキングで67カ国中31位
2024年のデジタル競争力ランキングでは、総合評価で前年より1ランク上昇したものの、人材やデジタル技術スキルの項目で順位を落とし、調査67カ国中31位にとどまっている。
3.世界競争力ランキングの急落
世界競争力ランキングでは、1989年に1位だった日本が2024年には38位に転落している。特に「政策・政府の効率性」と「ビジネスの効率性」の評価が低く、ビジネスの効率性は世界51位。その小項目である「経営のプラクティス」は世界61位とほぼ最低ランクであり、デジタル技術スキルや上級管理者の国際経験、ビジネスのアジリティに関する評価も極めて低い。
河﨑氏は、米国のIT投資とGDPが比例して上昇している傾向を参考にすれば、日本には伸びしろがあると指摘。その上で、自身の前職である銀行業界の例を挙げ、次のように語った。
経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課 地域情報化人材育成推進室長・デジタル高度化推進室長 河﨑幸徳氏
「地方銀行のシステムはかつて、60行以上がそれぞれ独自のシステムを大手ITベンダーのホストコンピュータ上に構築して運用していました。その背後にはベンダー側に多重下請構造が慣習として存在していました。独自システムとすることで差別的優位性を獲得できていたかどうかは(企業側の評価なので)分かりませんが、銀行の利用者にしてみれば、どの銀行のシステムもほぼ同じ機能を提供していると感じていたはずです。私が経験したシステム統合では、大きく違っていたのは融資利息を小数点以下第何位まで計算するか、ぐらいであり、もちろんお客様に有利な桁数に統一しました」(河﨑氏)
この個別のシステム開発・運用の仕組みに転機をもたらしたのは、1996年の金融ビッグバンに始まる金融自由化の波だ。金融機関は生き残りを図るため、コスト削減を積極的に行い、その一環としてシステムの共同化が進められた。その後、金融機関の経営統合が進み、人材不足や経済環境の変化が続く中で、システム標準化と業務標準化によるコスト削減に努めてきた経緯がある。
「システムの共同化・標準化は今後どの業界でも起きるはず。金融業界は他業界に先んじて取り入れて変化してきました。この経験を広く他業界にも伝えるのが、私の役割の一つかもしれない」(河﨑氏)
一方、福永氏は、デジタルが事業実践に十分取り入れられていないことを日本の課題として挙げた。その背景には「バブル崩壊を通じて、それまでの経営の成功体験が否定され、経営者が自信を失ったこと」があると指摘する。
「それまでの成功体験が否定されたことで、企業ごとの独自性を含む経営判断が揺らぎ、事業価値向上のための施策を自信を持って実行できなくなりました。『失われた30年』の後半における停滞は、これが一因だったのではないでしょうか」(福永氏)
一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA)会長 福永哲弥氏
さらに、コスト削減や効率化を目的とした情報子会社への業務アウトソーシングが進む中、システム構築や運用に関わる投資に対する経営の意思決定が弱まってきたと指摘する。これにより、事業の遂行上必要なシステムと、将来の経営を見据えた「あるべき姿」のシステムが分離され、後者の投資が極端に抑えられる傾向が生まれた。
「投資=コストという価値基準は、発注者と受注者の間の人の貸し借りの対価、労働時間が基準になるのは、労働集約型業務の典型。この基準では、本来の目的であるべき価値創造に向けた投資ができません。本来は事業価値をいかに上げるかという観点でシステムや事業を考え、投資する必要がありますが、経営者の自信喪失がその視点を歪めてしまったと考えています」(福永氏)
末續氏もこれに関連し、「IT投資は日本では年商に対して概ね1.1~1.5%程度の比率だが、海外では2%、3%という例が多く見られます。ITをコストセンターとして見る傾向が根強いのは、経営者の自信のなさが原因なのでしょうか」と質問を投げかけた。
日本化薬株式会社 執行役員 情報システム部長 末續肇氏
福永氏はこれに同意し、次のように述べた。
「事業ポートフォリオがこうあるべきと断言できる経営者が、大企業でも中堅・中小企業でも少ないのが現状です。将来の事業のあるべき姿を見極め、そのためにデジタル導入をどう進めるべきかをリーダーシップを持って言い切れることが必要です。ただし、見通しが誤っている場合もあります。その場合でもすぐに修正し、迅速に対応できる『経営のアジリティ』が求められます」(福永氏)
また、福永氏は「最新技術のPoCを実行する企業が増えているものの、そこに企業の中核を支えるほどの投資を行う例は少ない」とも指摘。その上で、「投資額が大きくても、投資の方向が間違っているかどうかを確認し、迅速に修正するアジリティがあれば、イノベーションにつながります。その判断権限がCIOに与えられていないのではないでしょうか」との見方を示した。
河﨑氏も、中小企業のデジタル化の遅れを課題として挙げ、「日本の中小企業の生産性は大企業の約3割にとどまる」と指摘し、この状況をデジタル導入で改善しない限り、生産性向上は難しいと述べた。特に人口減少の中で、中小企業の財務や経理といった間接部門の人材は高齢化が進んでおり、新たな人材の確保も困難な状況にある。この問題に対処するためにも、間接業務のデジタル化を進め、経営資源を本業に集中させる必要があると提言した。
従来のようにコンピュータを購入して償却するというアプローチでは限界があります。間接業務からSaaSを積極的に導入し、共同化しやすい分野で効率化を図るべきです」(河﨑氏)
ビジネス環境の変化と生成AIをはじめとする最新IT技術を前に、経営がどのようなアプローチを取るべきかについても議論が行われた。末續氏は「生成AIの登場により、ユーザー側とベンダー側の行動の境界が変わってきているのではないか」と疑問を投げかけた。
福永氏は「ITの目的は企業による価値創造にあり、この点は将来も変わらない」と述べる。既存のIT技術は生産性や効率性の向上を目的としており、そのために構築されたITインフラを基盤に企業は事業を進化させ、新たな価値を生み出してきた。一方、生成AIなどの最新デジタル技術は、それ自体で新しい価値を創造できる可能性を持つ技術である。
「既存のデジタル技術と、生成AIを含む新たなデータデジタル技術を両輪として活用し、人口減少社会の中で生産性向上を目指しつつ、新しい価値を創造していかなければなりません」(福永氏)
さらに福永氏は「共創」というキーワードを挙げ、ユーザーとベンダーの関係を見直す必要があると述べ、「発注者と受注者という関係を超え、お互いに協力して新たな価値を創造する関係に転換するべきです」と指摘。さらに、そのための役割分担や基準の明確化が重要だと提言する。
これまでのユーザーとベンダーの垂直分業形態の業務委託/受託を水平分業形態に変えるために、それぞれの役割を定義できる基準が必要だということである。その上で現状のSIerの姿勢に苦言も呈する。「ITパートナーという表現をよく聞くが、これは美辞麗句。パートナーという曖昧な言葉で役割分担を明確にしないまま一緒にやろうというのは経営のリスクになりかねません」(福永氏)。
さらに「これからの環境ではITとOT (Operational Technology)はアーキテクチャとして統合されるべき。その世界では、CIOはCEOと並ぶ存在になります」と語った。
また、河﨑氏は国としてのデジタル人材育成事業の一環として、2000年から始めた未踏事業を紹介。「尖った独創的なアイデアや技術を有する若手人材を発掘、育成しており、彼らが起業したスタートアップの中には世界に通じるものも多数あります。彼らと皆さん方大企業が連携して新たな価値創造を目指すことも可能です。これまで関東地域からの応募が中心でした。が、昨年からは、昨年からは、地方にも未踏人材が存在しているとの仮説のもと、彼らを発掘するための事業(AKATSUKIプロジェクト)も2023年から始めています。是非これらの活動にも協力いただきたいです」。
最後に福永氏は、CIOに次のように呼びかけた。「経済産業省は、半導体+AIに2030年までに10兆円を投じる計画を進めおり、対象の一つにAIモデリングを行う『GENIACプロジェクト』があります。このプロジェクトでは技術コミュニティも形成されていますが、現状ではITサービス企業を含めて参加者はほんの一握りです。こうしたコミュニティに積極的に参加し、時代の先端に触れることで、経営に資する役割を果たすことがCIOにとって重要です」。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。