



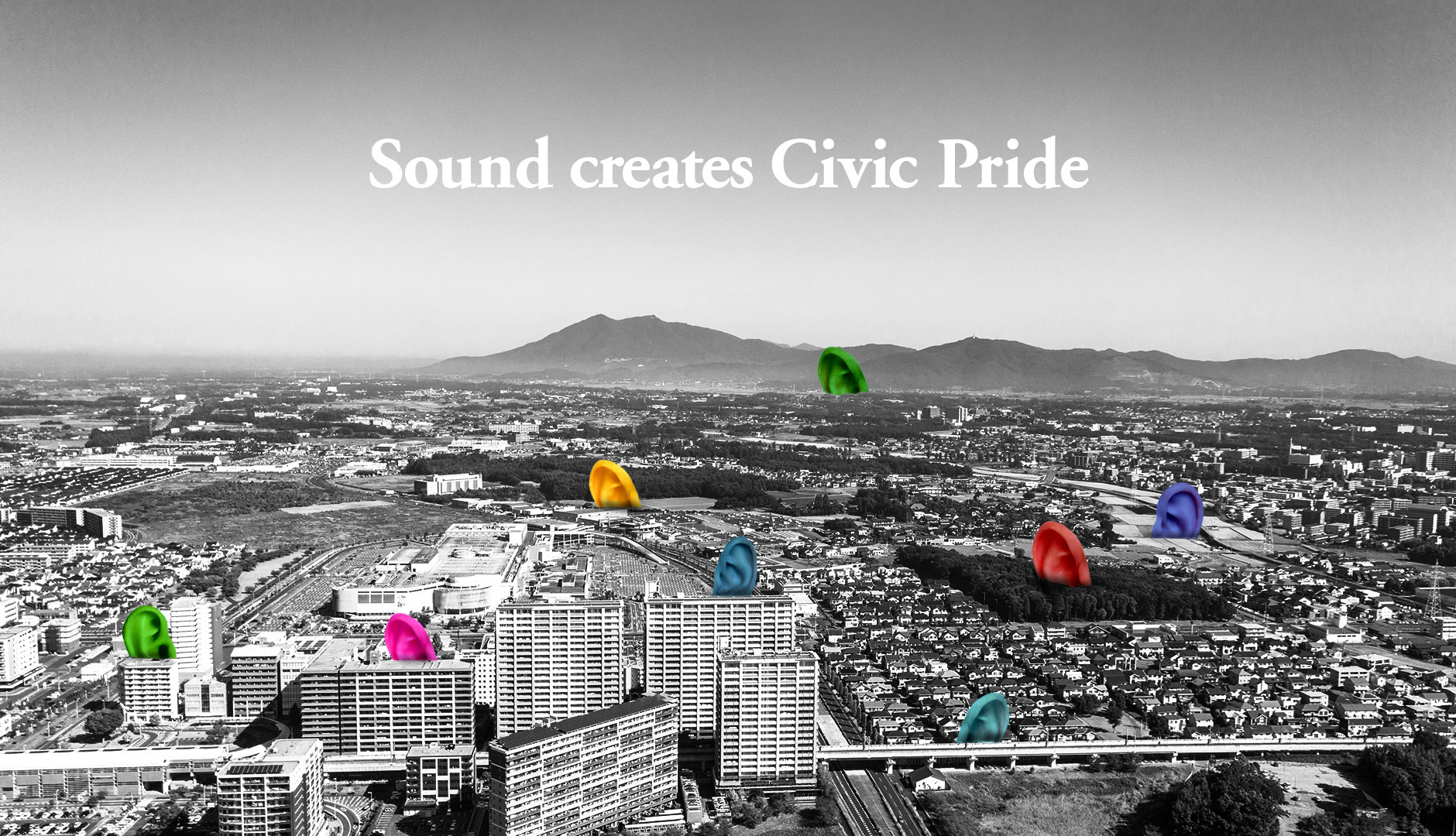

カナダの作曲家マリー=シェーファーは「理想的な共同体は、聴覚的にもうまく定義され得る」として、「共同体を定義する方法」として「音響共同体」という概念を提案しました。
シェーファーは『世界の調律(平凡社ライブラリー)』の中で「音響共同体」の歴史的な事例として、教会の鐘の「音」によって結びつけられていた教区や、中東におけるミナレットからの「祈りの時刻を告げる声」によってつながる共同体について言及しています。
また、プラトンも「国家論」の中で理想的な共同体の規模を「5040人」に設定していますが、その根拠のひとつとして、一人の雄弁家が演説するのに都合がよいという点を挙げています。
この「音が聞こえる範囲で形作られる共同体」から多くの日本人が連想するのは「帰宅チャイム」かもしれません。自治体によって流れてくるメロディーは異なりますが、帰宅を促すサインとして夕方(多くの場合午後5時)に耳にするチャイムは郷愁の想いをかき立てます。
ちなみに私が住む福岡県太宰府市では午後5時に「家路」(ドヴォルザーク作曲、交響曲第9番『新世界より』)を放送しています。ただ、その目的はシビックプライドを育てるというより、子どもたちの見守りと防災無線の機器点検とのことです。

さて、地域創生の文脈で活用が期待されている資源の一つに「サウンドスケープ」があります。サウンドスケープはもともと1960年代後半に前出のシェーファーによって提唱された概念です。シェーファーは「Landscape」を参考に、「音(sound)」と「眺め(scape)」を合わせた造語である「Soundscape」を生み出しました。
1978年に「サウンドスケープは、個人あるいは特定の社会がどのように知覚し、理解しているかに強調点の置かれた音の環境」と定義されました。つまり、サウンドスケープは単に物理的な音ではなく、それを受容する人間や社会との関係をも含む概念としてとらえられるようになったのです。
これは、『NEXUS~情報の人類史』の中でユヴァル・ノア・ハラリが述べていた「共同主観的現実」という概念にも共通しているかもしれません。ハラリによると、客観的現実でも、主観的現実でもない共同主観的現実こそが人間の大規模なネットワークを築き上げたとします。彼は『NEXUS~情報の人類史』の中で特に「物語」が共同主観的現実を創り出したといいますが、単に物理的な音ではなく、受容する側も含んだ「サウンドスケープ」もある種の共同主観的現実である考えて良いのかもしれません。
日本でこの「サウンドスケープ」が地域資源としてとらえられるようになった一つのきっかけは1996年に環境庁(現:環境省)が一般公募で「残したい日本の音風景100選」を選出したことでした。この取り組みの趣旨について環境省は「日常生活の中で耳を澄ませば聞こえてくるさまざまな音についての再発見を促す」ことに加え、「良好な音環境を保存するための地域に根差した取組を支援する」としています。

特定の地域やまちを特徴づけ、そこに住むメンバーの「暮らしの拠り所」となり、アイデンティティとしての価値を有する音は多岐にわたります。
前出の「残したい日本の音風景100選」に選定された音は以下のように分類されています。
| 鳥の声や昆虫の声など、生き物に関する音 | 31件 |
| 川や滝、海などの自然現象 | 19件 |
| 祭りや鐘の音など生活文化に関する音 | 37件 |
| 以上の複合音 | 12件 |
| 静寂に関するもの | 1件 |
また、多くの人にとってある場所を特徴づけるのは駅のアナウンスや、列車の発着時のメロディーかもしれません。
例えば、JR西日本グループでは、2015年から大阪環状線発車メロディを導入しました。メロディの導入にあたっては、地域の人たちに大阪環状線やその沿線のまちに愛着を感じてもらえるように「その駅(まち)らしさ」「大阪環状線らしさ」「大阪らしさ」をテーマに駅ごとに異なる発着メロディを採用することにしました。
ちなみに各駅のメロディは以下の通りです。曲はアメリカ民謡から文部省唱歌、やしきたかじんまでさまざまですが、「…らしさ」を住民の聴覚を通じてもらい、「当事者意識にもとづく自負心」であるシビックプライドにつなげたいという狙いがあります。
問題は、「まち」らしさを創る「音」をどのようにデザインするのか、ということです。この点についてサウンドスケープの提唱者であるマリー=シェーファーは次のようにはっきりと述べています。
サウンドスケープ研究の最終的な目標は、サウンドスケープ・デザイン ー すなわち、聴覚環境の意識的計画を導くことにある。けれどもこの考えはしばしば誤解もされてきた。サウンドスケープ・デザインは、決して上からのデザインであってはならず、むしろ内からのデザインでなければならない。それは、自分自身のサウンドスケープを深く理解する人々、その好ましい特性をいつくしむ人々、その欠陥に対して敢然と立ち向かう人々にとってのみ行われ得るものである。(『世界の調律』23ページ )
シェーファーは繰り返しサウンドスケープの担い手は「あらゆる人々」だと述べており、限られた専門家にのみ任せるべきではないと強調しています。それは「まちづくり」のすべての局面に共通しているといえるでしょう。
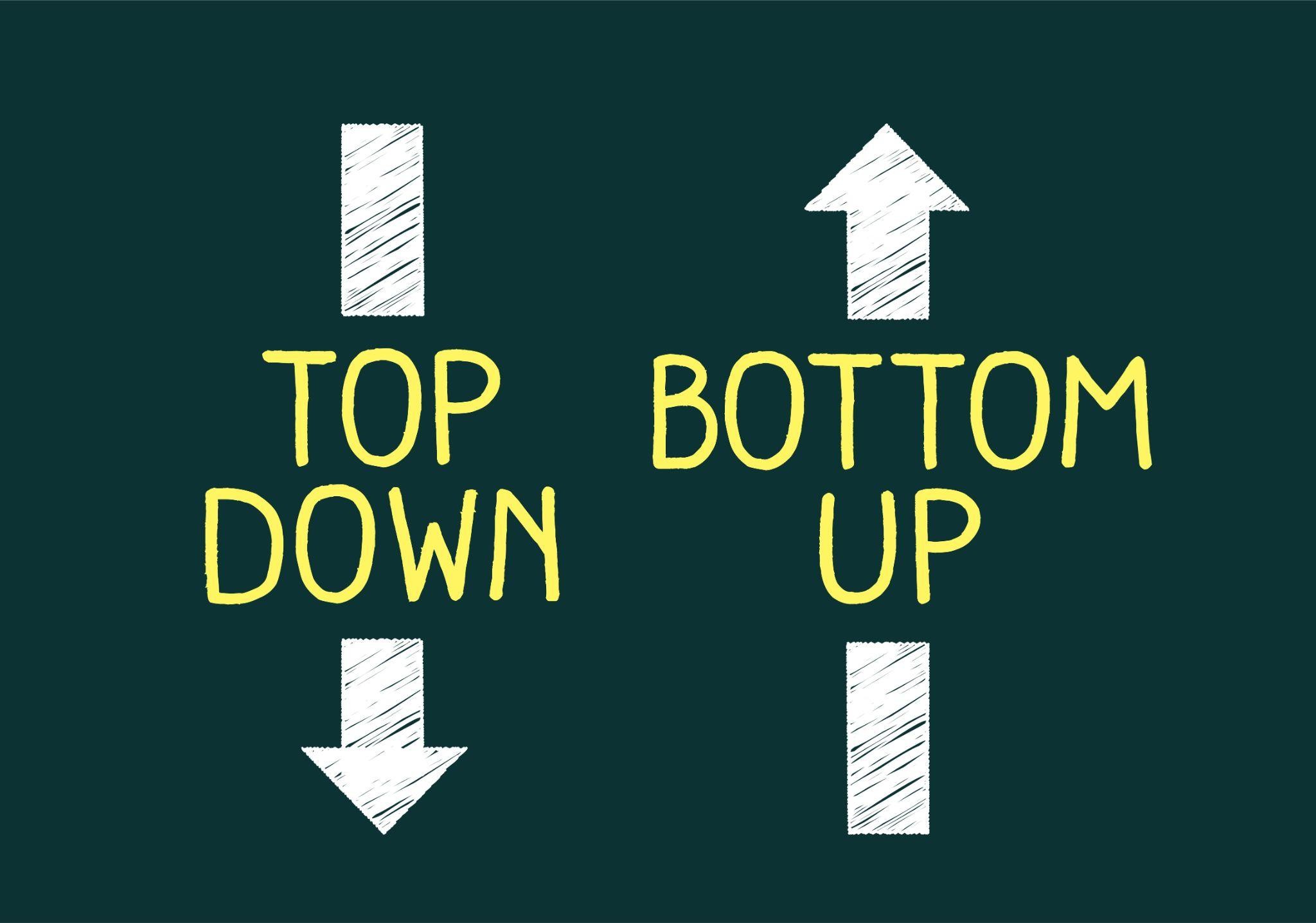
音をデザインすることで「サウンドスケープ」を創るという考え方は、施設を建設したり、イベントを企画したりすることで「まちづくり」をしようと思っている人にとっては逆説的な発想です。なぜなら、視覚的なものをベースに人をつなげようとする考え方では「音」は単なる「偶然」であり、「付随するもの」に過ぎないからです。
しかし、私たちの感覚を鋭敏にして、見えない「音」に意識を向けるとき、意外にもシビックプライドは「音」にかなり依存していることに気づかされるのです。
著者・図版:河合良成
2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。
(TEXT: 河合良成、執筆協力:新田浩之、編集:藤冨啓之)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

