



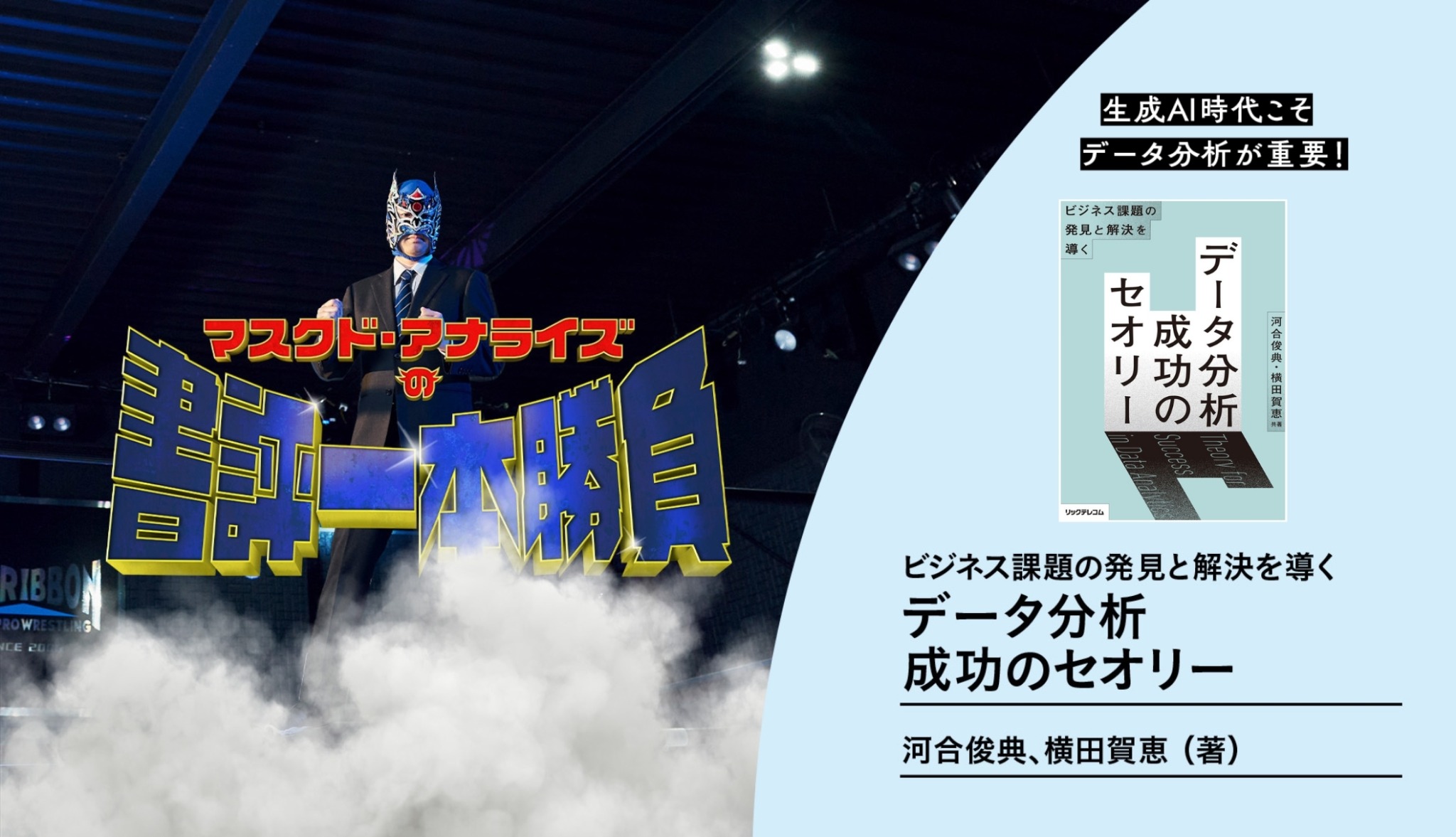
目次
生成AIの登場から3年近くが経過して、ビジネスの場面で生成AIが使われる事も増えました。一方で、生成AIにおける問題点も出ています。一例として生成AIが間違った回答をする「ハルシネーション」による信頼性の問題などが挙げられています。生成AIを導入したものの使い方がわからず、普及が進まないという悩みもあります。このようにIT業界では最新技術に注目して導入するものの、使いこなせずに次の流行に飛びつくという失敗を繰り返してきました。
一方で流行が過ぎたデータ分析は、ノウハウが蓄積されて問題点も解消されてきました。必ずしも最新技術が最高とは限りません。そこで改めてデータ分析に着目するきっかけとして、書籍「データ分析成功のセオリー」を紹介します。
本書の対象読者は「データ分析プロジェクトの提案や実行をはじめて担う方」「データ分析がうまくいかないと感じる方」「業務改善を実現したい人」などです。データ分析初心者だけでなく、普段の業務を見直して改善するという多くのビジネスパーソンの要望にも応えられる内容になっています。
本書はこのような構成となっています。
1章 データ分析における「ビジネス力」の重要性
2章 ビジネス課題の検出
3章 分析アプローチの設計
4章 分析の実施
5章 分析結果を活かす
本書を理解することで、業務課題からデータ分析の流れを設計して、上司や顧客に対して根拠や理由を説明しながら課題解決ができるようになります。同時に、技術ばかりに着目せず、ビジネスにおける課題を探して解決のために様々な施策を行いながら分析結果を活かして成果を出すことを目指しています。過去のデータサイエンティストブームにおいても「どんな課題を解決すべきか?」「どの業務に適用すべきか」という目的が不明瞭なまま、最新技術を利用することが優先されて失敗した背景があります。データ分析も成果につながらなければ、データいじりや数字遊びにすぎません。そこで生成AI時代に改めて、データ分析で成果を出すことに着目してみましょう。
生成AIが登場した現在において、データ分析と合わせてそれぞれの長所の短所を見極めながら最適な活用を行う事が求められます。特に「どんな課題を解決したいのか?」という問題点を探ったり、データと照らし合わせて施策や改善策を実践することは、生成AIよりもデータ分析が有利です。一方でデータ分析に必要なプログラミングを支援したり、データから傾向を探る作業は生成が得意です。生成AIの登場によって、お互いのメリットを組み合わせる事ができるのが現在の強みと言えるでしょう。

では、生成AIブームの現在で、過去のものと扱われがちなデータ分析における強みは何でしょうか。一例としてデータや数字に基づいて、根拠や理由を示して答えを導き出せることです。生成AIも大量のデータから回答はできますが、根拠や理由を示す部分はまだ弱いです。社内業務においては根拠や理由が明確でないものを、実行することはできません。また、自社が保有する独自のデータを用いて、どのような課題を解決すべきかという計画を立てる点でも、データ分析が有利です。
このように、業務における改善計画の立案、施策の遂行、実行結果に対する好感検証など、業務改善に必要な一連の流れで数字と根拠を示せることがデータ分析の強みです。一方でデータ分析から得られた事実から新たな発見や改善策を探るのは、手間のかかる作業です。大量のデータから傾向を探ったり、プログラミングや資料作成などの支援として、生成AIを活用してみましょう。
まずは、生成AIにおいて、万能ではない点を認識すべきです。これは過去のデータサイエンティストブームでも同じ事があり、最新技術でどんな問題も解決できる魔法のように誤解されてしまいます。あくまでデータ分析も生成AIも手段であって目的ではありません。施策を立てて行動に移して、成果を出さなければいけません。
では、データ分析がビジネスにおいて役立つのはどんな場面でしょうか。まず幅広い業種や職種における共通点として、データや数字に基づく判断が少ないことです。まだまだ人間の勘や経験に頼ったり、前例踏襲で同じ仕事を続ける場面が多く見られます。もちろん現在のやり方でも問題はないものの、問題が見つかっていないとも言えます。一方で勘と経験によって「大体OK」でも、「正しい答え」とは言えません。仮に8割が正解なら、2割が間違いです。そこでデータ分析によって、2割の間違いを探して修正しながら正解率を高めてみましょう。ずっと同じ方法で仕事をするより、データ分析で課題発見と改善を繰り返すことで品質が向上します。もっとも、本書では勘や経験を一方的に悪者扱いはしていません。メリットもあるので、相互補完することが重要であると位置づけています。
さらにデータで業務を進めることを習得すれば、より明確に問題点を提示したり、データの裏に隠れた背景を読み取って第三者にストーリー立てて説明する能力が身に付くでしょう。このような経験を繰り返せば、根拠に基づいて業務を進められるようになります。データ分析で本質を捉えて課題解決につなげるスキルは、様々な業務で役に立ちます。
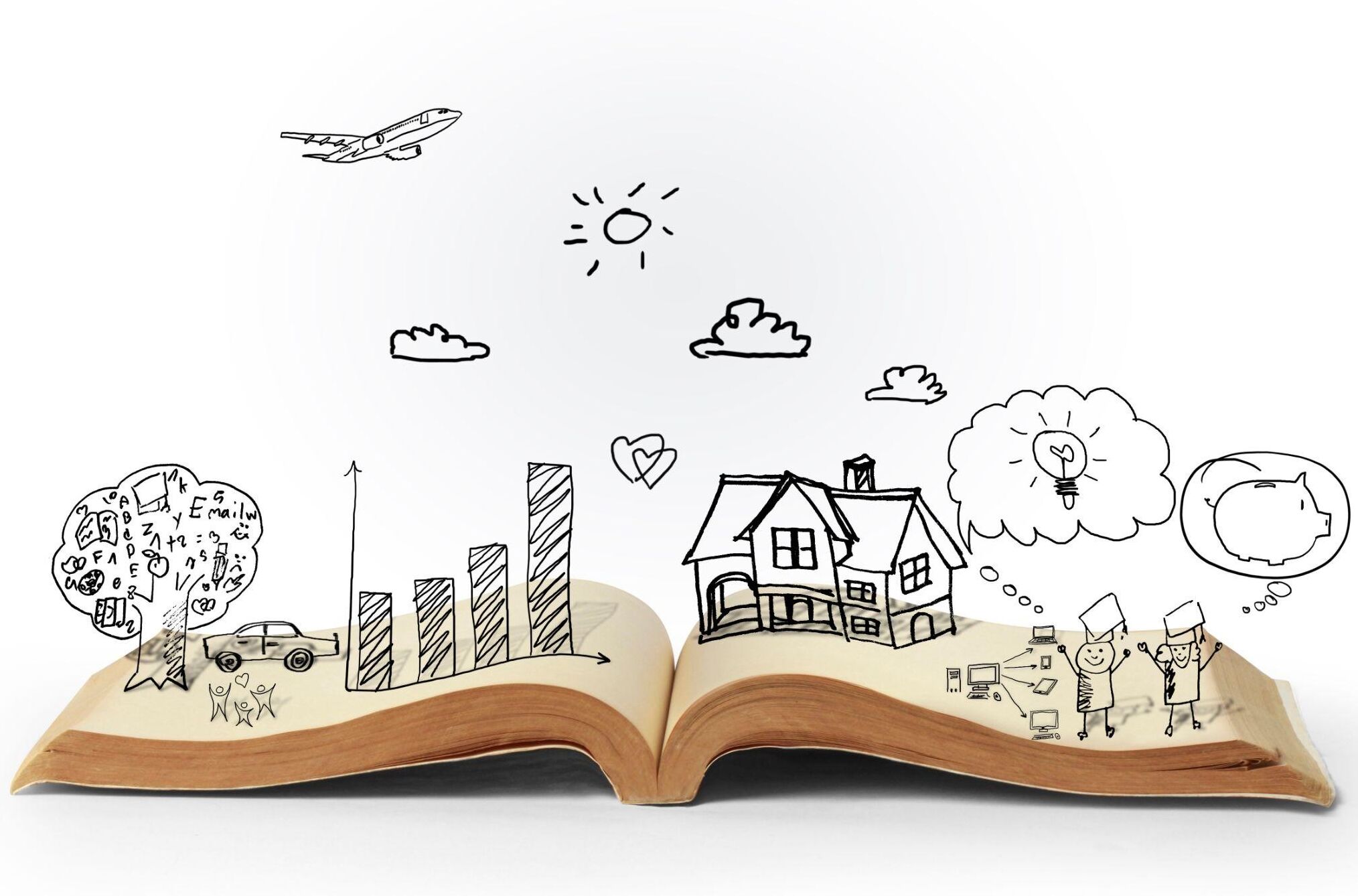
ではどのようにデータ分析を習得すればよいでしょうか。まずは身近なツールであるExcelを使って、自分の仕事からデータ分析を行ってみましょう。その中で自分の仕事を通して既知の内容だけでなく、意外な結果も出てくるでしょう。これはデータ分析によって従来の勘や経験で行っていたことが、間違いだったという気付きを発見しましょう。今では市民データサイエンティストや、データ分析の民主化が当たり前になってきました。まずは基本的な分析から、生成AIによるサポートを受けながら身につけていきましょう。
これからのビジネスにおいては勘や経験だけでは不十分であり、データを用いた意思決定が必要となります。さらに勘や経験による憶測では意思疎通では内容が噛み合わないことがあるのに対して、事実に基づいたデータによる共通認識なら認識の齟齬がなくなります。
そこで本書ではビジネスパーソンが身につけるべきデータ分析の能力として、データサイエンティスト協会から提唱されているスキルの詳細を解説しています。2章でこの点を解説しており、ビジネス現場におけるデータ分析に求められる課題設定や業務に適用する構想力を解説しています。特にビジネス課題の検出は個別に章を割いて解説しています。コンビニの店長の立場で解説したり、ビジネス現場で求められる課題発見の方法のノウハウなどを豊富な図を用いているのが特徴です。
本書の3章にある分析結果をわかりやすく伝える方法も重要で、グラフの種類やデータの集計方法、複数の図による伝え方、KPI(重要業績評価指標)ツリーにおける分析などが紹介されています。データの分析結果を用いて本来取り組むべき課題や問題点を掘り下げる手順も参考になるでしょう。また分析結果から指標を作ったり、発見のきっかけとなる切り口を探る方法も解説されています。こうした能力は自分で分析するだけでは身につけるのが大変なので、本が役立つ点です。
4章ではデータ分析の実施において必要な準備から分析を行って解釈するまでの流れを紹介しており、自分の環境に合わせて行うことで理解も深まるでしょう。本章に限らず解説された内容を一緒に試しながら、一歩ずつ手を動かして体験することが大事です。

これまで多くのビジネスパーソンは、自身の経験に基づいて業務知識を積み重ねてきました。こうした業務知識が重要である一方、個人の能力に依存するのは否めません。そのため改善や新たな取り組みにおいて限界が生じてきました。そこで自身の業務知識にデータ分析を組み合わせる必要性が出てきました。しかし、データ分析の基礎的な能力がなければ改善策は進みませんし、データ分析能力だけでは対象業務における解析や改善策が進みません。そこで「データ分析だけ」「業務知識だけ」ではなく、担当業務を経験する本人がデータ分析を習得して、課題を設定しながら、分析結果を解釈して、改善策の立案と実行と効果検証を行えるサイクルが必要です。
そこで本書でビジネスパーソンにデータ分析における一連のノウハウを学び、更に課題図書やスキルチェックスリとで能力を延ばすことが推奨されています。現在では生成AIのおかげでデータ分析のハードルが下がっており、Excelの関数やマクロだけでなく、グラフやレポートも作成できるようになりました。生成AIブームデータ分析がより身近になった今こそ、データ分析による学習と問題解決がより簡単になったのは大きなメリットと言えるでしょう。
いまやデータ分析やビジネスパーソンの必須スキルになりつつあります。まずは皆さんの身近な場面から気になった課題を解決すべく、「データ分析のセオリー」を読んでみてはいかがでしょうか。


“データサイエンス界の東京スポーツ”がリングイン!
覆面AIコンサルタントのマスクド・アナライズが、巷に溢れる書籍を現場目線でジャッジ。AI・データ分析プロジェクトの最前線で戦ってきた男が選ぶ、本当に使える一冊はどれだ?
流行りの技術か、本物の知見か――忖度無用のガチンコ書評、一本勝負!
詳細はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

