佐々木:
これまでのご経歴について、お話いただけますでしょうか。
マスクド・アナライズ(以下、マスクド):
私は新卒からIT業界で働いてきました。直近の職歴としては、AIやデータ分析のスタートアップ・ベンチャー企業に所属し、企業のデータ分析支援や人材育成といった業務に携わりました。
当時はビッグデータやデータサイエンティストブームの時期で、企業のデータ分析支援や、プロジェクトの提案から管理、分析ツールの使い方など、実務に根差した取り組みを幅広く手掛けましたね。その中で、企業がデータ分析を通じてメリットや利益を生み出す方法、あるいはエンジニアやデータサイエンティストがどのように開発・分析を進めるのかといった点を支援するのが、主な仕事でした。
その後、私が所属していた会社は急成長した反面、その歪みから業績が悪化し、組織縮小となりました。結果として私も退職することになりましたが、その当時からSNSを通じてマスクド・アナライズとして活動しており、イベント登壇や記事執筆などの機会もいただいていたことから、そうした活動を軸に独立しました。
現在は引き続き生成AIブームが続いていますので、そういった側面のイベント登壇・書籍や記事の執筆・企業向け研修・コンサルティングなど、企業向けの支援活動に携わっています。特に生成AIの全体像を把握している人材は限られていますし、社内の知見だけでは不足する場面も多く、外部の意見や協力が必要になることも少なくありません。そうした場面で、私は企業と一緒に生成AIの導入から推進に至る取り組みを行い、企業の中でデータ活用やAI活用が進むように伴走しています。
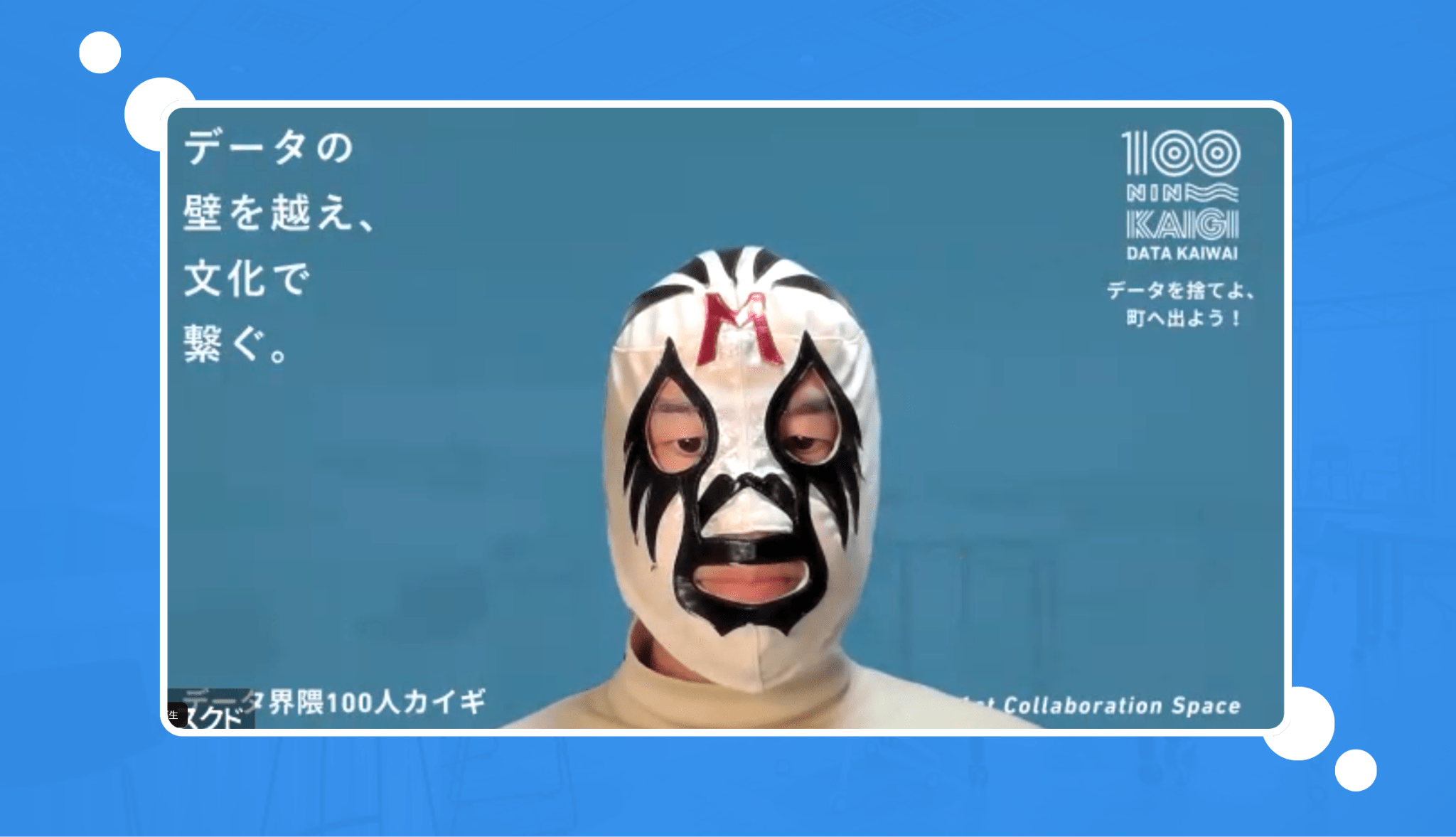
データ界隈100人カイギ キュレーター マスクド・アナライズさん|AIコンサルタント
佐々木:
「データ界隈100人カイギ」にキュレーターとして参加することになった経緯をお伺いしても、よろしいでしょうか?
マスクド:
私自身がさまざまな企業や組織と関わってきた中で、やはり「知見やノウハウが企業や個人の中だけで留めてしまうのはもったいない」と感じていました。現在は特定企業に属さない立場で多くの方と知識や経験を共有することで、新たな気づきが生まれたり、意見を交わしながら内容を磨き上げるような場を作りたいです。
佐々木:
「まさにデータを捨てよ、町へ出よう」みたいな形だったんですね。「データ界隈100人カイギ」で期待しているところはなんですか?
マスクド:
仲間ができることが挙げられます。どうしても社内では相談相手や支援してくれる人が限られてしまうため、社外の人と一緒に連携することによって、悩みの種を解消できるのは強みですね。こうした同じ境遇の人たちが意見や悩みを話せる場があることは、社内で孤立しがちな推進担当者にとって、精神的にも余裕ができると思います。
佐々木:
マスクドさんの担当するテーマについて、想いや考えを聞かせてください。
マスクド:
「生成AI」に関する書籍の著者や出版に関わる方々と一緒に、テーマを設定して議論する場を作りたいです。生成AIの情報は非常に多く、取捨選択が難しいという話をよく耳にしますし、私自身もその点は強く感じています。とはいえ、毎日SNSで最新情報を追い続けることは現実的に難しいでしょう。
そういった中で「本」という形は、確かに情報の早さでは多少遅れるものの、まとめて質が高く信頼できる情報を得られるという点で非常に価値があります。そのため、「生成AI活用に必要な情報や知識をまとめて、役立つ書籍とはどうあるべきか」「SNSや動画投稿サイトとの差別化」「著者や出版社が読者に提供できるメリット」といったテーマで、著者・出版関係の方々と話し合いをしたいですね。
佐々木:
私も仕事で生成AIを活用する場面が増えましたが、最新情報やツールの使い分けなどで悩むことも多いです。他にはどのようなテーマを考えていますか?
マスクド:
生成AIを含めたIT全体として、女性の参加者がまだまだ少ないという点です。佐々木さんも活動の中で感じるかもしれませんが、生成AIを使う女性が少ないです。単純に「使う機会がない」「知る機会が少ない」という点だけでなく、様々な要因があると考えています。
もちろん生成AIは性別に限らず、年齢や立場などに関係なく、多くの方にとって開かれた技術です。だからこそ、女性の方々を含めて使ってもらうきっかけが増えればと思います。例えば、いろいろな立場の方が関心を持って参加しやすいイベントを企画したり、生成AIに触れるハードルを下げる取り組みなどを通じて、裾野を広げていきたいですね。
くわえて、もうひとつ構想しているのが私が個人的に好きな「プロレス」と絡めた企画です。例えば私が以前に取材経験があるDDTプロレスさんは、サイバーエージェントのグループ会社です。動画サイト「ABEMA」との連携など、デジタルデータとプロレスを掛け合わせた新しい切り口で面白い発見があるのではと構想中ですね。
佐々木:
プロレスとデータがどう絡んでいくのか、これから楽しみにしております。
今後、場を作る際にどんな視点で企画を進めていきたいといったポイントがあれば、教えていただけますか。
マスクド:
大きく2つの方向性で考えています。
1つ目は、やはり「多くの人に興味を持ってもらう」という観点から、生成AIを身近なものと組み合わせて活用するという切り口です。先ほどお話に出たプロレスのようなスポーツ・エンタメ分野や、旅行・買い物・食事といった日常生活に根ざしたテーマと掛け合わせて、「生成AIをどう役立てるか」を探ることは面白いかなと。実際に私が知っている例でも、女性が生成AIに自分好みの擬人化イラストを作ってもらうなど、趣味的な活用もあります。そういった「まずは興味を持ってもらうきっかけ」として、楽しく柔らかいテーマにしたいですね。
2つ目は、対照的に産業や業務での活用という堅めのテーマです。たとえば建設・交通といった現場作業での生成AI活用などですね。さまざまな会社や業界の方に集まってもらって、「業界問わず共通するテーマ」や「独自のノウハウや活用事例」を意見交換しながら、お互いの知見を磨き合っていく。そんな場を作れたらと考えています。
この2つ、「柔らかいテーマ」と「硬いテーマ」をうまく行き来しながら企画したいです。
佐々木:
今後、登壇してほしいと思う人はいらっしゃいますか?
マスクド:
登壇していただきたい方について、具体的に2つの軸で考えています。
1つ目は、サイバーエージェントさんですね。サイバーエージェントさんは親会社として、ゲーム、ネット広告、Abema(動画配信)といった非常に幅広い領域で大量のデータを扱っていらっしゃいます。ゲームや動画のようなエンタメ寄りの面白い分野もあれば、ネット広告のようなビジネス寄りの領域もあるので、非常に幅広いテーマでお話ができる企業だと思っています。前述のDDTプロレスに加えてプロレスリング・ノアの親会社でもあるのでプロレスの企画と絡めた企画ができればと思います。
2つ目は、出版関係の方々です。私自身も生成AIに関する書籍の執筆や出版に関わっており、著者さん、出版社の編集者さん、さらには書店さんといった関係者の方々を集めて、「どうすれば生成AIの本を多くの人に読んでもらえるか?」というテーマで立場を超えた議論をしてみたいですね。私自身、本が好きなので、「生成AI本をどう盛り上げるか」について話せたら嬉しく思います。
著書も多数執筆しているマスクド・アナライズさん。
『会社で使えるChatGPT』『データ分析の大学』など、業務改善から組織導入まで実務に活かせる知恵を詰め込んだ書籍は、色あせない“本質的な知識”として多くの読者に支持されている。
佐々木:
これまでのご経験の中で、データ活用において特に大切にしている信念や心情、こだわっている点がありましたら、教えていただけますか?
マスクド:
データを扱う上で、楽しく・面白く伝えるということが非常に重要だと考えています。 特に生成AIなど難解なテーマを扱う場面も増えていますので、まずは関心を持ってもらうことが大切です。もちろん「正しく説明する」ことは基本ですが、正しさだけでは相手にうまく伝わらないことも多いんですよね。正確さを踏まえつつも、面白さ・わかりやすさ・楽しさも織り交ぜながら伝えることが、結果的に理解や興味につながるのではないかなと思います。
佐々木:
確かに、やらなきゃいけない立場だからという形でデータ活用やツールを使うのでは、これからどんどん進化していく中で、なかなか続けていくのは難しいのかなと感じました。
データと「文化」や「人」という観点で、マスクドさんならではの視点で意識されていることがあれば、ぜひ伺いたいと思っています。
マスクド:
「人」という観点はやはり非常に大きいですよね。
データや文化において、人の関係はとても難しいテーマだと感じています。会社や組織ごとに文化や価値観が全く異なりますし、一方である場所で通じたことが、別の場所で全く通用しないこともあります。
そのため、柔軟性が大切だと思っています。 相手に合わせて、どう関わっていくのか?どう伝えるのか?どう仕事を進めるのか?という部分を、できるだけ早く汲み取って、相手に応じたアプローチをとることが重要です。特にイベントやセミナーなどの場面では、参加者が求めるものが毎回異なるので、ニーズを的確に読み取って、その人に合った情報や体験を提供することが大切ですね。
佐々木:
これから登壇や参加を検討されている方へのメッセージがあれば、教えてください。
マスクド:
やはり一番大事なのは気づきだと思います。自分だけでは分からないことや、知らなかったことがあるはずなので、新たな視点を発見を「データ100人カイギ」で持ち帰っていただき、それが原動力やアイデアにつながっていくことを期待しています。
交流によってこんなやり方があったんだ」とか「こんな面白い活用があるんだな」といった気づきが必ずあるはずです。こうした発見を、日々の活動や業務に役立ててもらいたいです。
| イベント名 | データ界隈100人カイギ#02「ラーニングヒーロー会」 |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年7月18日(金) 18:30~21:00 |
| 会場 | ウイングアーク1st株式会社コラボスペース 〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー36階 |
| 主催 | データ界隈100人カイギ運営事務局 |
| 対象者 | データに携わる全ての方 ・ITツールベンダー ・コンサルタント ・Chief Data Officer(CDO) ・データサイエンティスト ・エンジニア ・ビジネストランスレーター など |
| 参加費・定員 | ・現地参加:1,000円(定員:40名) ・オンライン参加:500円(定員:20名) ・学生の方:現地・オンライン参加ともに無料(定員:10名 ※各5名) |
| URL | 2025年07月18日開催|データ界隈100人カイギ#02|ラーニングヒーロー会 |
イベント参加申込は
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!