




10月も中旬に差しかかり、朝晩の空気にひんやりとした秋の気配を感じるようになりました。
この時期になると、そろそろ“秋の長雨”――いわゆる「秋霖(しゅうりん)」が気になる頃です。夏と冬の気圧のせめぎ合いで前線が停滞し、ぐずついた天気が続くこの現象は、昔から季節の変わり目を告げる風物詩とされてきました。
気象庁の観測データによれば、この秋霖も年々タイミングがずれ、降り方も極端になってきているそうです。
それではまず、今回紹介する記事をダイジェストで紹介します!!
現在、中学1年生の息子が小6の終わりに差しかかる頃、我が家では「中学でどの野球チームに所属するか」について、約3ヵ月にわたるチーム選びの紆余曲折がありました。前回の記事では、中学野球チーム選びが難しい背景や、子どもとの対話を通じて「どんな野球をしたいか」という軸を定め、チーム選びをはじめた経緯についてご紹介しました。今回はその続編として、実際に気になる硬式チームを見学・体験した経験から、チーム選びのプロセスについて振り返ります。不確実な情報の中からの意思決定を行った“リアル”と、それでもなお残る「決め手の見えにくさ」について、ご参考にしていただければと思います。 (・・詳しくはこちらへ)
2022年11月におけるChatGPTの発表以来、世間は空前の生成AIブームを迎えています。一方で以前に流行したデータサイエンティストをはじめとしたデータ分析は話題になる機会が減っています。書店では生成AIの本が大量に出版される中で、データ分析の本は見かけなくなりました。では、生成AIの登場によって、データ分析がビジネスの現場で不要になったのでしょうか。 (・・詳しくはこちらへ)
データのじかんを閲覧頂いているみなさま!!こんにちは!!【データのじかんフィーチャーズ】担当の畑中一平です。【データのじかんフィーチャーズ】は、最新の話題や事件に焦点を当て、これまでに「データのじかん」で紹介した記事の中から厳選してピックアップし、詳細にレポートして皆さまにお伝えする企画です。2024年4月に施行された「孤独・孤立対策推進法」をきっかけに、孤独や孤立を多角的に考える必要性が高まっています。第43回目となる今回では、日本における現状をはじめ、テクノロジーの活用、ペットとの関係、地域や趣味のコミュニティの意義、そして前向きな“ひとり時間”としてのソリチュードまで、5つの視点から深掘りしました。具体的な事例や関連データも交え、課題と向き合うためのヒントを紹介します。 (・・詳しくはこちらへ)
こんにちは。「データのじかん」編集部です。都市の中心で、「広告とは何か」を再定義する8日間が始まります。2025年10月17日(金)から24日(金)まで、東京・虎ノ門で初開催される「虎ノ門広告祭」は、広告・表現・テクノロジーの最前線が交錯し、“社会との対話をどう設計するか”という問いに挑みます。生成AIの進化や、データ活用によるコンテンツの個別最適化が進むなかで、私たちは何を「届ける責任」を持つのか──。本記事では、「データのじかん」読者の皆さんに向けて、この広告祭の背景と見どころを掘り下げてご紹介します。 (・・詳しくはこちらへ)
2010年から11年2か月にわたり金沢市長を務めた山野之義氏。同氏が市政を変革するために掲げたのは、「金沢市の発信力を高める」という明確なビジョンでした。地元の誇りを第一に掲げ、観光客誘致に偏らないまちづくりを推進し、スポーツ文化や建築文化の醸成に注力されました。一方で、市役所のフリーアドレス化など、DX推進にも積極的に取り組まれました。その歩みとリーダーシップについて、ウイングアーク1st 代表取締役 社長執行役員CEOの田中潤が伺いました。 (・・詳しくはこちらへ)
能登半島地震に際し、ソフトバンク株式会社は、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(通称スペースX)の衛星通信サービス「Starlink Business(スターリンク・ビジネス)」を活用した簡易基地局による通信確保に加え、水循環システムや人流データの活用を通じて被災地を支援しました。その最前線に立たれたのが、前金沢市長であり、現在は同社法人統括戦略顧問を務めておられる山野之義氏です。山野氏は、有事におけるテクノロジーの活用について「平時からの利用が重要である」と語り、制度や機器以上に、トップの判断と姿勢こそが命綱になると強調されています。 (・・詳しくはこちらへ)
まいどどうも、みなさん、こんにちは。わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。今週は高市早苗さんが自民党の第29代総裁に選ばれたり、田園都市線で事故で止まっていたり、秋深し、なはずなのに暑い日が続いたりと日本列島は大わらわでしたが、わたくしもそれなりにおかげさまで多忙にしておりました。どんな多忙かと言いますと、なんとわたくし、終了間際の大阪万博の方へ少しばかり潜入させて頂きまして、現場の雰囲気を五感フル回転で味わって参りました。幼い頃から、「世界の国からこんにちは」の曲と岡本太郎氏の作品である太陽の塔のインパクトが脳に刷り込まれているせいで、大阪万博というとなんとなく懐かしい感じがするのですが、実はわたくし当時はまだ生まれておりませんでしたので、この懐かしい気持ちも実は単なる錯覚なのですが、とにかくEXPO2025をこの目で見てきたことは事実であり、今回は万博の数ある展示の中でもかなり注目されているかの「人間洗濯機」についてお話してみようかと思っております。 (・・詳しくはこちらへ)
データのじかんNewsのバックナンバーはこちら
2025.10.06 公開

中学硬式野球チームの選択にあたり、保護者や子どもたちは何を基準に判断すればよいのでしょうか。本記事では、実際に複数のチームを見学・体験した家庭のリアルなプロセスを通じて、“データにない”情報の重要性に迫ります。
助言をくれたのは、すでに硬式チームに子どもを通わせている先輩保護者。「気になるチームはすべて見ておいたほうがいい」という一言をきっかけに、筆者一家は7〜8チームを訪問。その結果、ネットや口コミでは分からない「現場の空気感」や「チームの素顔」に多く触れる一方で、かえって選択肢の幅が広がり、判断が難しくなる場面もあったといいます。
そこで見学時に確認すべき評価軸を整理し、チーム理念、育成方針、出場機会、進路支援、費用面などを丁寧にチェック。進路実績や戦績といった数値化された情報だけでは見えてこない、子どもとの相性や保護者としての納得感を重視する姿勢が印象的です。
最終的には「強豪で揉まれるか」「育成型で出場機会を得るか」という二択に向き合いつつも、子ども自身の意思と、チームの雰囲気がもたらす“縁”が決め手になると実感した過程がつづられています。
2025.10.10 公開
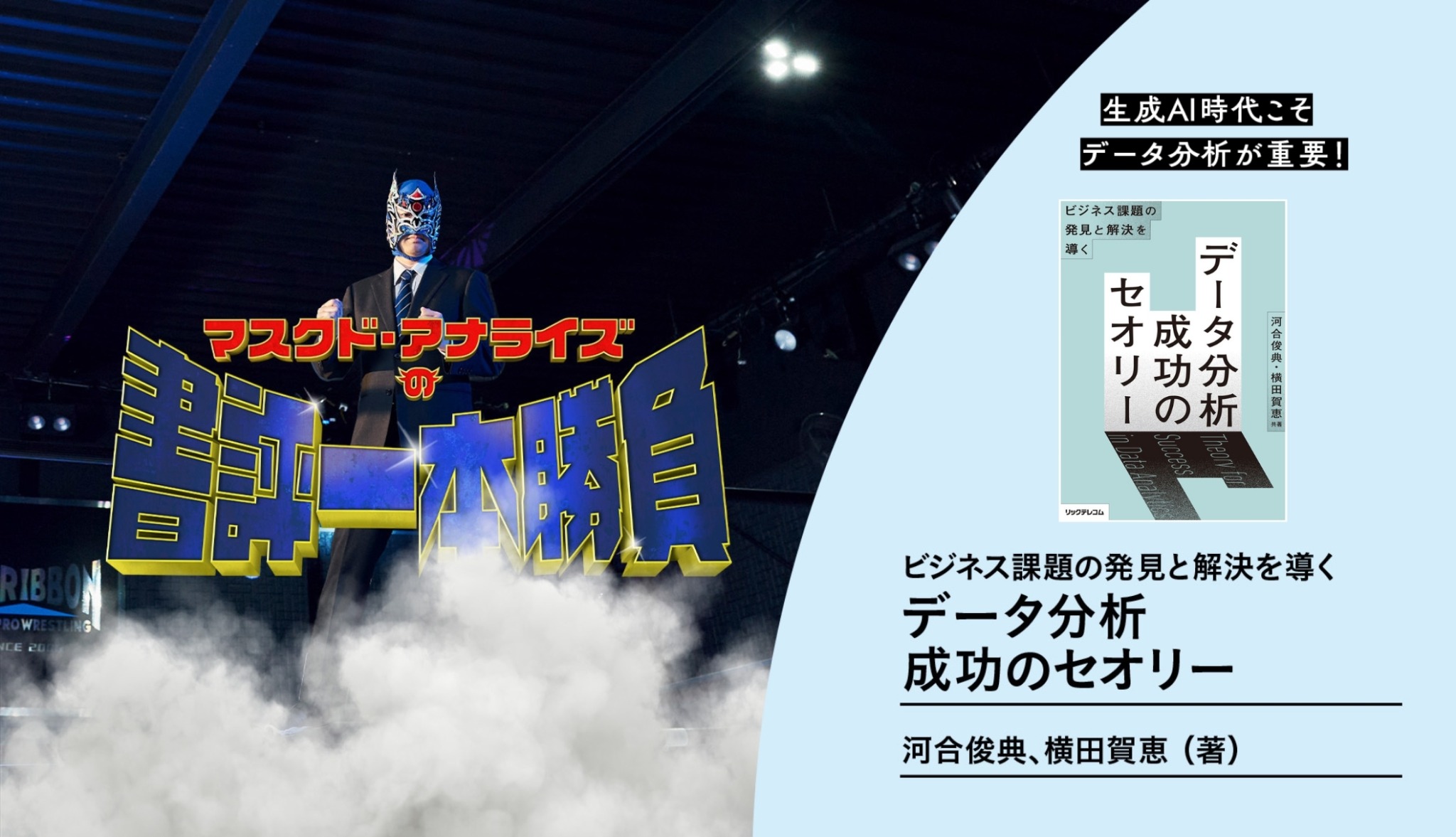
生成AIの活用が進む一方で、「思ったように使いこなせない」「結果に根拠が見えない」といった課題も浮き彫りになっています。そんな時代だからこそ、ビジネス課題にしっかりと向き合い、根拠とともに解決へ導く力として「データ分析」に再注目する動きが広がっています。
本記事では、書籍『ビジネス課題の発見と解決を導く──データ分析成功のセオリー』を取り上げ、生成AIとデータ分析の“いいとこ取り”の実践方法を紹介。分析初心者から業務改善を目指すビジネスパーソンまで、広く役立つ知見が詰まった一冊です。
ビジネス課題の見極め、分析の設計と実施、成果の活用といった流れを体系立てて学べる構成となっており、「分析は手段であり、目的は課題の解決である」という視点が全編にわたって貫かれています。
生成AIによって分析の入り口は広がった一方で、「何のために分析するのか?」という本質的な問いを見失いがちな今、データに基づいた意思決定や業務改善の必要性はかつてなく高まっています。
最新技術に振り回されず、自身の業務と向き合いながら分析力を高めていく——本書は、そんな“地に足のついたデータ活用”を志すすべてのビジネスパーソンにとって、実践的なガイドとなるでしょう。
2025.10.11 公開

2024年4月、「孤独・孤立対策推進法」が施行されました。少子高齢化や生活の多様化が進む中で、誰もが孤独や孤立に直面し得る社会となったことが背景にあります。しかし、孤独は単なる個人の感情の問題ではなく、健康や社会参加にも深く関わる課題です。
日本の現状を見ると、高齢者だけでなく、若年層や子育て世代においても孤独感が広がっています。特にコロナ禍で、人と人との距離が物理的・心理的に開いたことが影響していると考えられます。調査では「相談できる人がいない」と答える割合が増加傾向にあるとも報告されています。
一方で、テクノロジーやペット、地域コミュニティ、さらには意識的な「ひとり時間」といったさまざまな要素が、孤独や孤立と向き合うためのヒントになり得ます。こうした課題を多角的に考えるために、今回のデータのじかんフィーチャーズでは『孤独と孤立』をテーマに、『実態』『テクノロジー』『ペット』『コミュニティ』『ソリチュード』の5つの観点から紹介します。
2025.10.05 公開

広告は、社会との“対話”である──。
そんな思想を出発点に、広告・表現・テクノロジーの最前線が集結する「虎ノ門広告祭2025」が、2025年10月17日(金)から24日(金)までの8日間、東京・虎ノ門ヒルズの複合文化施設「TOKYO NODE」で初開催されます。
会場では、ジャンルを越えた約300名のクリエイターによる100以上のセッション、展示、体験型企画が展開予定。俳優の松田翔太氏、ラッパーのダースレイダー氏や荘子it氏、俳人・コピーライターの岩田奎氏、NHK『タローマン』の藤井亮氏など、広告業界の枠を超えた表現者が集う“越境的な場”が実現します。
プログラムでは「広告×社会×テクノロジー」を軸に、観客参加型のイマーシブセッションや即興詩の企画、生成AIと広告倫理をテーマにした討論など、表現とメディアの現在地に迫る議論が展開されます。情報を「どう届けるか」を問う設計力が、今ほど試されている時代はありません。
広告を単なる販促手段ではなく、「未来をどう語るか」という社会的問いとして再定義しようとする本イベント。広告・広報関係者だけでなく、地域づくりや教育、情報発信に携わるすべての人にとって、新たな刺激と発見が得られる8日間となるでしょう。
2025.10.08 公開

ソフトバンク出身であり、2010年から3期にわたって金沢市長を務めた山野之義氏は、民間と行政の両フィールドで組織変革を実行してきたリーダーです。本記事では、ウイングアーク1st CEO・田中潤氏との対話を通じて、山野氏が大切にしてきた「トップが前に出て語る」リーダーシップの実践について深掘りしています。
山野氏は、市役所のフリーアドレス化やペーパーレス推進、電子決裁、RPA導入など、DXを着実に推進してきました。その背景には、変化を一方的に押し付けるのではなく、職員と信頼関係を築きながら丁寧に浸透させる姿勢がありました。
また、東日本大震災での震災廃棄物受け入れや、能登半島地震での支援活動など、困難な局面においては常に自らが矢面に立ち、市民や関係者と向き合ってきた姿勢が印象的です。「責任をとる」とは辞任することではなく、「課題解決に向けてやり抜くこと」と語る山野氏の言葉には、リーダーの覚悟がにじみ出ています。
本記事では、金沢市政での実績と、その後のソフトバンク戦略顧問としての取り組みを通じて、変革を成し遂げるために必要な条件──それは制度でもテクノロジーでもなく、「人」と「信頼」であるという信念が伝わってきます。組織を動かす立場にあるすべての方に、ぜひご一読いただきたい内容です。
2025.10.08 公開

2024年元日に発生した能登半島地震。その初動支援の現場に立っていたのが、元金沢市長であり、現在ソフトバンク法人統括戦略顧問を務める山野之義氏でした。災害時の通信インフラ確保に向けて投入された「Starlink Business」や、WOTAの水循環システム「WOTA BOX」「WOSH」など、最先端のテクノロジーが実地でどのように機能したのか──その成果と課題が語られています。
現場で機器が活用されずに放置されていた事例や、支援情報が市町に届かずスムーズに設置できなかった実態から見えてくるのは、「テクノロジーはそれだけでは機能しない」という教訓。英語マニュアルや特殊な規格など、細部に至る障壁が「平時の準備不足」によって有事で顕在化するのです。
一方、住民の声から迅速に通信環境が整備された事例も紹介され、技術の有効性と「現場の温度差」をどう埋めるかという課題も浮き彫りに。また、水インフラやモビリティ支援、人流データの活用など、ソフトバンクグループ全体で展開された災害支援の取り組みが詳細に記されています。
山野氏が一貫して訴えるのは、「平時からの活用こそが真の備えである」という視点。災害対策の成否を分けるのは制度や機材ではなく、それを活かすリーダーの判断力と姿勢である──。本記事では、自治体と民間が連携して“命を守る”ために何ができるか、そのヒントを具体的な経験から読み解きます。
2025.10.08 公開
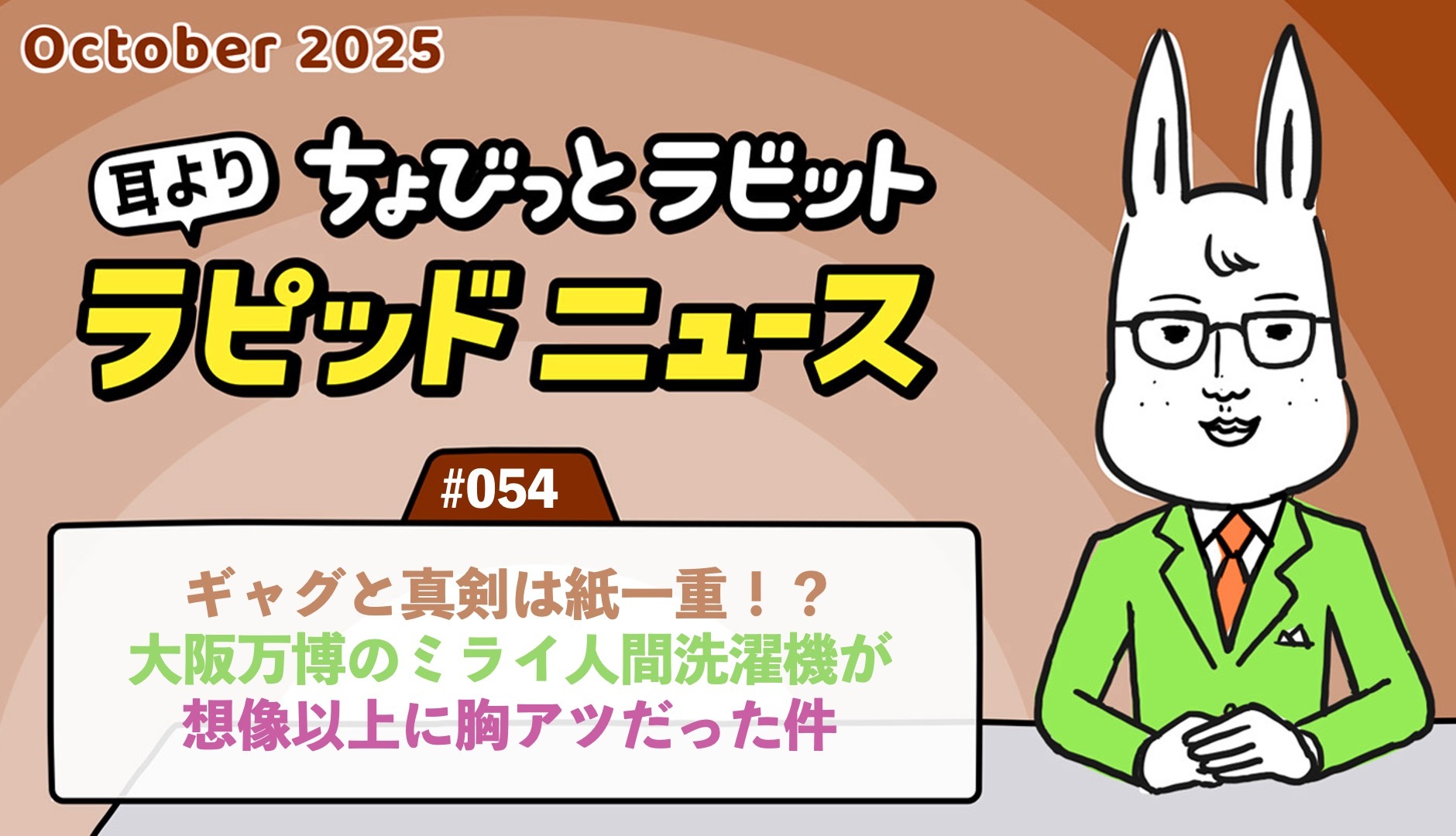
“人間洗濯機”はギャグか、それとも未来か?──
今回の「ラビッドニュース #054」では、2025年大阪・関西万博に展示された「ミライ人間洗濯機」にスポットを当て、その開発者・青山恭明氏のドラマティックな半生と、テクノロジーへの情熱に迫ります。
原型は1970年の大阪万博に登場した三洋電機の人間洗濯機。当時小学生だった青山少年は、その体験をきっかけに「いつか自分でこれを完成させたい」と決意。やがて設立した株式会社サイエンスでは、ファインバブルやウルトラファインバブルといった“泡”の技術に特化した製品を開発し、大ヒット商品「ミラブル」シリーズを生み出します。
そして今回、青山氏は再び万博の舞台に立ち、“泡で洗う未来”を最新技術で体現。石鹸も摩擦も不要な人間洗濯機は、皮膚科学的にも環境負荷の面でも注目される展示となっています。
記事では、来場者の体験レポートも交えつつ、「笑えるのに本気すぎる」このテクノロジーの魅力を独特の筆致で紹介。ギャグと真剣は紙一重──そんな言葉を体現するような、技術者の執念と夢の結晶を追います。
万博ならではの“驚きと再発見”に満ちた展示の裏側を、ぜひご覧ください。

今回は『ソフトバンク法人統括戦略顧問の山野之義氏が語る「平時と有事をつなぐテクノロジー」の真価』という記事を紹介させて頂きました。
本記事を読んで印象に残ったのは、山野之義氏の「テクノロジーは平時から活用してこそ有事に生きる」という言葉でした。
この一文を目にして、ふと筆者の趣味であるキャンプのことを思い出しました。実は筆者のキャンプは、家族の「もしものときの備えになるかも」という考えから始まったものなのです。最初は防災の延長のつもりが、今ではすっかり日常の楽しみの一つになりました。
テントを張って火を起こし、水を確保する──そんな一見シンプルな作業の中にも、いざという時に役立つ知恵や感覚が詰まっています。電気もガスもない場所で過ごす時間は、便利な生活では見えにくい“自分の力で生きる感覚”を思い出させてくれるものです。
ただ、訓練のつもりで臨むキャンプは、必ずしも快晴である必要はありません。雨風に見舞われたり、焚き火がうまくつかなかったりと、思い通りにいかないことも多い。でも、そうした“うまくいかない経験”こそが、防災のリアルな学びになる気がします。
山野氏が語る「平時と有事をつなぐ」という言葉を借りるなら、キャンプもまさにその実践の場なのかもしれません。
自然の中での時間は、楽しさと同時に、暮らしのリスクを体で感じる貴重な機会です。次のキャンプは、きっとまた新しい“備えの気づき”をくれるだろう──そう思うと、天気予報が少しぐらい悪くても、なんだかワクワクしてしまうようになってきました。
それでは次回も「データのじかんNews」をよろしくお願いします!

データのじかんは、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。
越境者の興味・関心を高める話題や越境者の思考を発信するレポート、あるいは越境者の負担を減らすアイデアや越境者の拠り所となる居場所などを具体的なコンテンツとして提供することで、データのじかんは現状の日本にあるさまざまなギャップを埋めていきたいと考えています。
(畑中 一平)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

