近年、待機児童や、病児保育、障害児保育などをはじめとする保育についての問題が取り上げられることが多くなり、身近な社会課題として保育が広く認知されるようになってきました。人と人のコミュニケーションを重視する保育業界において、ITやデータはどのように活用されているのでしょうか?
今回は、認定NPO法人フローレンス(以下フローレンス)の代表理事である駒崎弘樹氏にお話を伺いました。フローレンスは「待機児童問題」「病児保育問題」「障害児保育」「虐待死問題」など、親子に関する社会課題を解決する活動を行っています。
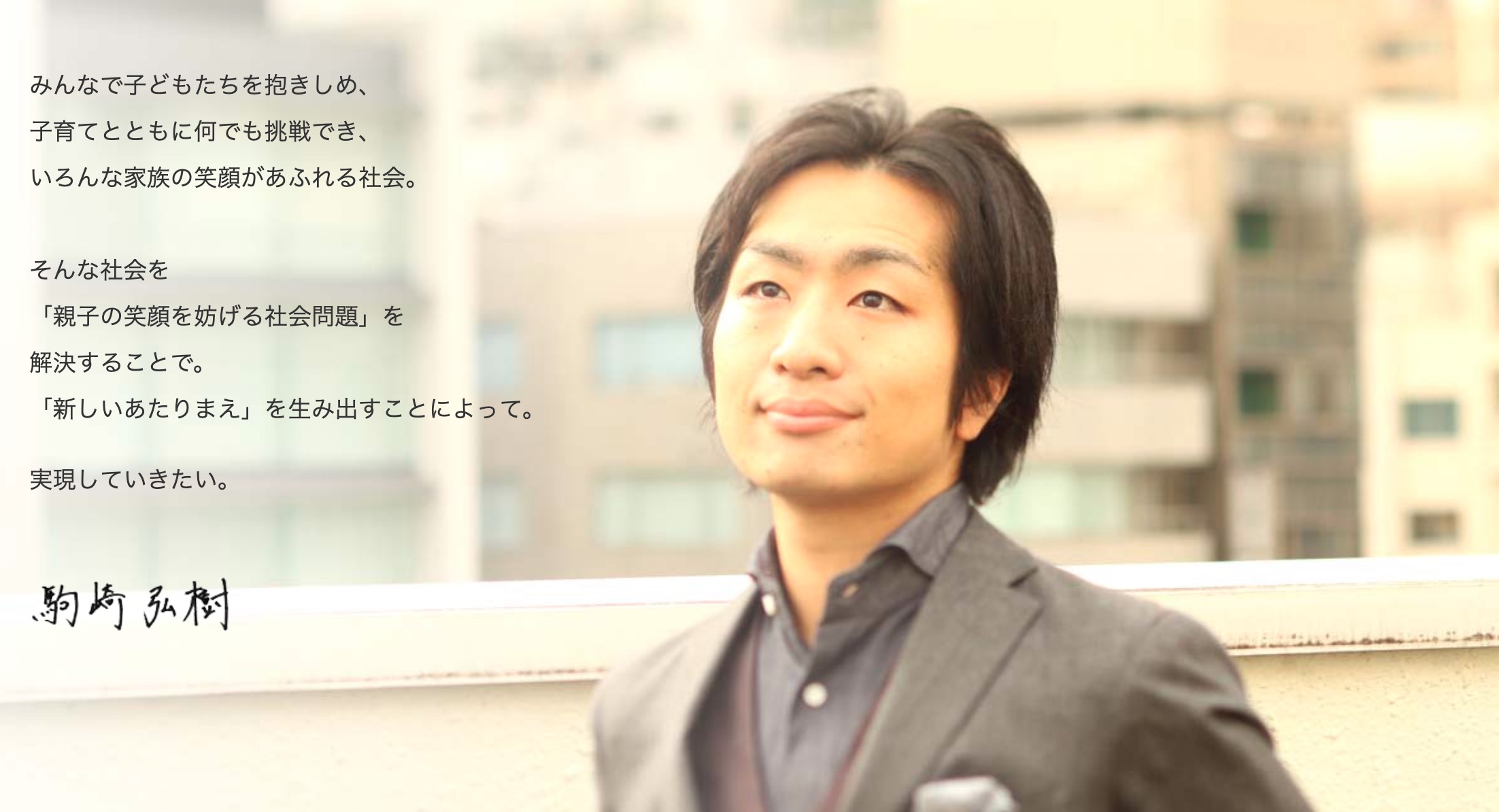
出典:フローレンス公式サイト
駒崎 弘樹(こまざき ひろき)
1979年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業後、2004年にNPO法人フローレンスを設立。代表理事を務める傍ら、厚生労働省「イクメンプロジェクト」推進委員会座長、内閣府 「子ども・子育て会議」 委員他を務める。著書に『「社会を変える」を仕事にする: 社会起業家という生き方
岸田 – 対人関係が重要視される保育の分野において、これまでITやデータ活用の試みはあったのでしょうか?
駒崎 – 小学校以上の教育業界、いわゆる大学受験を目標とする教育においては、テストの点数など、ある程度データを用いて可視化することが可能であるものに関しては、これまでも「将来の投資」の対象として有効であるということが広く認識されていました。
一方で、保育業界ではそのような点数化の試みが難しかったという経緯があり、これまで「将来の投資」の対象としてなかなか認知されてきませんでした。しかし、「5歳までの教育が人の潜在能力の大きさを左右する」と提唱するノーベル経済学賞受賞者のヘックマンが、「ペリー就学前プロジェクト」により就学前の教育効果が非常に高いということを定量的に明らかにして以降、幼児教育の投資対効果が重要であるという認識が生まれました。これは保育業界におけるデータ活用の一つの大きな出来事だったと思います。
岸田 – 具体的に幼児教育はどのような能力に影響を与えると言われていますか?
駒崎 – 上記実験結果では、より良い幼児教育を受けた子供と、その教育を受けなかった子供を追跡調査によって比較しています。それによると、前者の子供達は、後者の子供達にくらべ、生活保護の受給率が低かったという結果が出ています。また、同調査では、幼児教育はテストのスコアやIQに影響を与えるわけではなく、非認知能力、つまり社交性のような部分に大きな影響を与えるということがわかっています。このように、幼児教育の重要性は世界的に認知されてきており、実際に世界的には義務教育の年齢が下がり始めています。
岸田 – 教育分野と保育分野は比較されることが多いですが、幼児教育分野と保育分野は具体的にどう違うのでしょうか?
駒崎 – 多くの人が誤解していますが、実は保育という言葉の中には、教育という意味が含まれています。ですので、本来的には両者に違いはありません。ただし、大学受験を目的とする教育と大きく異なるのは、テストのスコアを取るための画一的な教育ではなく、「自由」をベースにした教育であるということです。全員に同じことをさせるのではなく、一人ひとりが考えて、仲間と一緒に問題を解決していく能力を養うのです。
岸田 – フローレンスの事業の一つとして、こども宅食というものがありますが、これはどういった取り組みなのでしょうか?
駒崎 – これまでの政策というのは、「必要な人は手続きを行いに役所に来てください」というお店モデルが基本でした。しかし、これでは忙しい人や、本当に支援が必要な人に政策が行き届きません。
こども宅食は、このようなモデルを脱却し、各家庭に訪問して食べものを届けるという、アウトリーチモデルの支援です。また、評価指標やロジスティックモデルを細かく設定し、プロジェクトとして初めて、社会的インパクトを定量的に評価するというトライアルも行いました。
岸田 – 食材を家庭に届けることで、生活保護のように直接金銭的な補助を行うのではなく、間接的に金銭面での補助を行うという狙いもあったのでしょうか?
駒崎 – 初期アウトカムでは可処分所得の向上が挙げられましたが、それに加えて精神面でのポジティブな変化があったということも挙げられます。こども宅食では、定期的に担当者がご家庭を訪問するため、対象家庭とのコミュニケーションが密に行えます。これにより、社会との繋がりを感じることができたという意見もありましたし、その他にも、気持ちに余裕が生まれた、子供と過ごす時間が増えたという意見もありました。
先ほども申し上げた通り、幼少期の体験というのは、子供の非認知能力に大きな影響を与えます。経済格差とともに文化格差があり、これは体験や経験からもたらされるものです。
つまり、精神的にネガティブである(余裕がない)ことにより、体験や経験が不十分になってしまうという環境は、文化格差につながる恐れがあるということです。こども宅食により精神的にポジティブな変化があったということは、大きな意義であったと思います。
岸田 – こども宅食のインパクトレポートの中で、文京区世帯調査との比較がなされていますが、かなりデータの乖離が見受けられます。これはどのようなことが原因として挙げられるのでしょうか。
駒崎 – これはこども宅食のアウトリーチモデルが作用した結果だと考えられます。いわゆる「生活に余裕のない」ご家庭においては、そうした経済的状況を不特定の外部に対して発信することに対して抵抗を感じている方々も多いです。こども宅食では、対象のご家庭と密にコミュニケーションが取れるため、このようなバイアスを取り除いた、生の声をアンケート結果としていただけたのではないでしょうか。
岸田 – データ活用を前提としたプロジェクトにおいて、バイアスを排除できるのは非常に重要ですね。今後も保育の分野においてデータを活用していくにあたり、どのようなことが期待されるのでしょうか?
駒崎 – 本来であれば、政策というのは需要から作られるものです。ほかの業界も同じかもしれませんが、保育の分野では、情報の横展開が不十分な側面がありました。個人情報保護はもちろん重要ですが、これが悪く作用しているという現実もあります。まずはデータの連携を前提とした法整備がなされることが大切だと思います。そして、関係各所でデータ連携ができ始めると、適切な対応ができるようになります。これは「起こる前に適切なアプローチを行う」という意味です。何かが起きた後に対応するよりも、起きる前に解決することで、救われる命があるだけではなく、コストも抑えることができます。
岸田 – こども宅食のデータ分析を通して、駒崎さん自身が驚いた結果や、実は認識が間違っていたという事例はありますか。
駒崎 – 自分の認識での貧困層の分類が誤っていたということです。具体的にいうと、貧困層の中でも様々な状況があり、自分の思っていたメッシュが非常に粗いものであったということです。今後はこのメッシュを細分化する必要があると感じました。所得の分類だけではなく、例えば都市と地方というメッシュも考え直さなければなりません。クラスターや傾向をひとまとめにはできると思いますが、都市の中の地方、地方の中の都市、といった分け方も考える必要があります。
岸田 – データ活用を行うには、世間的にデータリテラシーが高まらないといけないということですね。
駒崎 – その通りです。これは教育によって変えていけるものだと思っています。つまり、暮らしとの地続きでデータや算数、数学を教えていくべきだということです。例えば、統計学の始まりは伝染病の予防からと言われていますが、保育業界においては、データを学ぶことによって虐待の子供を減らすことができるということを教えることもできます。
また、例えば組体操を止めるということに対しても、組体操の意味、事故率のデータ、そこから得られる効果、代替案の検討など、暮らしの中でみんなの役に立つという前提で、教育の中にデータを取り入れていくという試みが必要であると感じます。
岸田 – 最後に、この記事を読んでいる読者の方々にもできる支援などはありますでしょうか。
駒崎 – こども宅食が今一番必要としているのは、皆さんからの「ふるさと納税」による運営資金です。 現在、東京都文京区で行っているこども宅食の運営資金と、こども宅食を全国で広めるために活動する「こども宅食応援団」の運営資金をクラウドファンデイングで募っています。一人でも多くの親子を支えるために、ぜひご協力をいただけたら嬉しいです。
通常のふるさと納税では、納税した代わりにモノが届きますが、こども宅食のふるさと納税はモノの代わりに子供達の未来をリターンと考えていただけるとありがたいです。一般的な支援の形であれば、さりげなく支援を行うということが一番です。先ほども申し上げた通り、貧困層のご家庭の中には貧困を隠したいと思っている方々もいらっしゃいます。そのような方々には、いかに見えないまま支援してあげられるかが重要だと思います。
岸田 – ありがとうございました。
本インタビューを通して、これまで人対人の関係が重視されていた業界におけるデータ活用の重要性を改めて感じることができました。
ITツールの普及により、至る所でデータを取り、蓄積することが可能になっています。しかし、いくらデータがあったとしても、正しいデータかどうかの見極め、データ分析の手法、情報の共有や法整備の必要性などが世間一般的に浸透しなければ、技術に振り回されてしまう恐れもあります。
私も教育者として、「暮らしと地続きの教育」を意識し、一人でも多くの子供たちにデータ活用の重要性を伝え、日本の将来を担う人材のデータリテラシーを向上させていきたいと感じたインタビューでした。
【経歴】
2011 年 東京大学工学部卒
2011 年 インフラ企業に就職
2015 年 同社退社
2015 年 エスカルチャー株式会社設立 代表取締役兼学習塾 ESCA 塾長
【概要】
東京大学卒業後、サラリーマン経験を経て、2015 年にエスカルチャー株式会社を設立。「受験勉強では終わらない、社会で生きる力を養う」という理念で、学習塾の運営と、海外インターン/海外留学コンサルティング事業、就活支援事業を展開している。 学習塾の運営においては、自らも教壇に立ち、サラリーマン時代の経験を活かして、「学問の体系化」「理論と現実」「回答の見せ方」「問題文を読む意味」「学習における知識と思考のマネジメント」など、勉強が社会にどのようにつながっているのかを教えている。
【ウェブサイト】
【経歴】
2011 年 東京大学工学部卒
2011 年 インフラ企業に就職
2015 年 同社退社
2015 年 エスカルチャー株式会社設立 代表取締役兼学習塾 ESCA 塾長
【概要】
東京大学卒業後、サラリーマン経験を経て、2015 年にエスカルチャー株式会社を設立。「受験勉強では終わらない、社会で生きる力を養う」という理念で、学習塾の運営と、海外インターン/海外留学コンサルティング事業、就活支援事業を展開している。 学習塾の運営においては、自らも教壇に立ち、サラリーマン時代の経験を活かして、「学問の体系化」「理論と現実」「回答の見せ方」「問題文を読む意味」「学習における知識と思考のマネジメント」など、勉強が社会にどのようにつながっているのかを教えている。
【ウェブサイト】
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!