



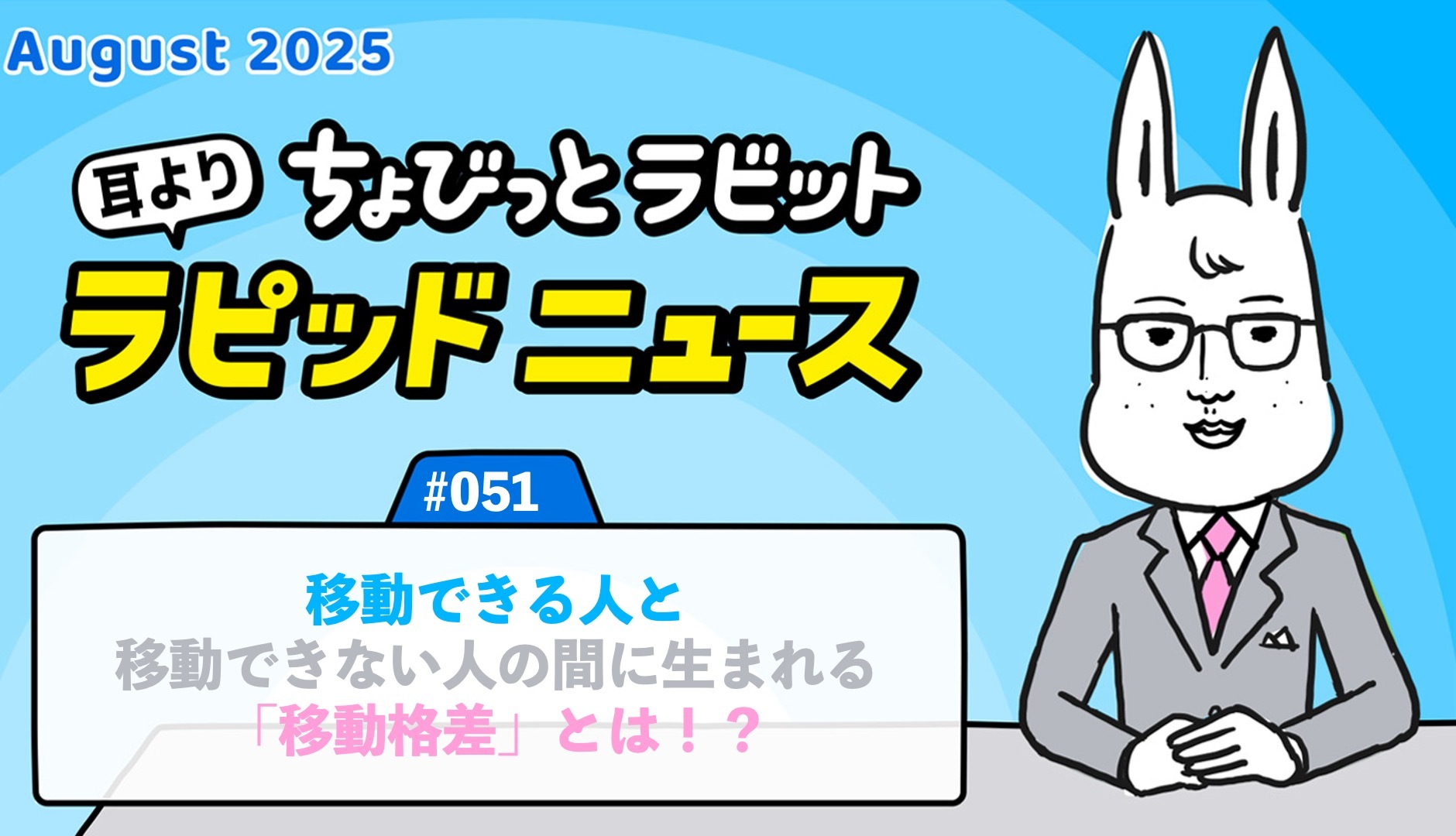
まいどどうも、みなさん、こんにちは。
わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。ハイサイおじさんのメロディーで夏を彩った沖縄尚学の優勝で今年の甲子園も幕を閉じ、八月も後半だというのに、日差しは相変わらずの圧倒的な熱量で日本列島は慢性的な水不足になってたりしますが、みなさまはいかがおすごしでしょうか?
夏の間、わたくしは新潟県、栃木県、群馬県、福島県、そして山形県あたりを移動して過ごしていたのですが、あまりなじみのないエリアだったこともあり、非常に新鮮な気持ちでこの日本列島を愛しむことができていたりします。わたくしのように、ニューヨークで生まれ、日本とアメリカ、そして、人間とウサギ、という国境も言語も種族も異なる複雑すぎるシチュエーションで板挟みになりながら育ってしまうと、「移動」というものは生活と切っても切れない深い関係性にあるわけです。その流れもあって、子供の頃からアメリカ東海岸と日本の往復を何度も繰り返してきた時差ぼけプロフェッショナルなわたくしにとって、国内のこうしたちょっとした移動、というのは全くと言っていいほど普通のことであります。ですので、特に鼻息を荒くして語り継ぎたい伝説のアドベンチャーでは決してないのですが、この移動に対する感覚は人それぞれの価値観というものが強く反映されます。つまり、移動とは単純に人やモノがA地点からB地点に場所を変える、というだけのものではなく、そこには社会的あるいは文化的な価値や意味が付随します。それは決して万人に平等に与えられているものではなく、「移動しやすい人」もいれば「移動が困難な人」も確実に存在します。そして、それによって生み出される格差というものに最近注目が集まり始めています。社会学的にはこれは「移動格差」と呼んでいるのですが、今回のちょびっとラビットでは、この「移動格差」について少しばかり掘り下げてみようかと思っておりますので、ぜひこのページから移動することなく、最後までお付き合いください。
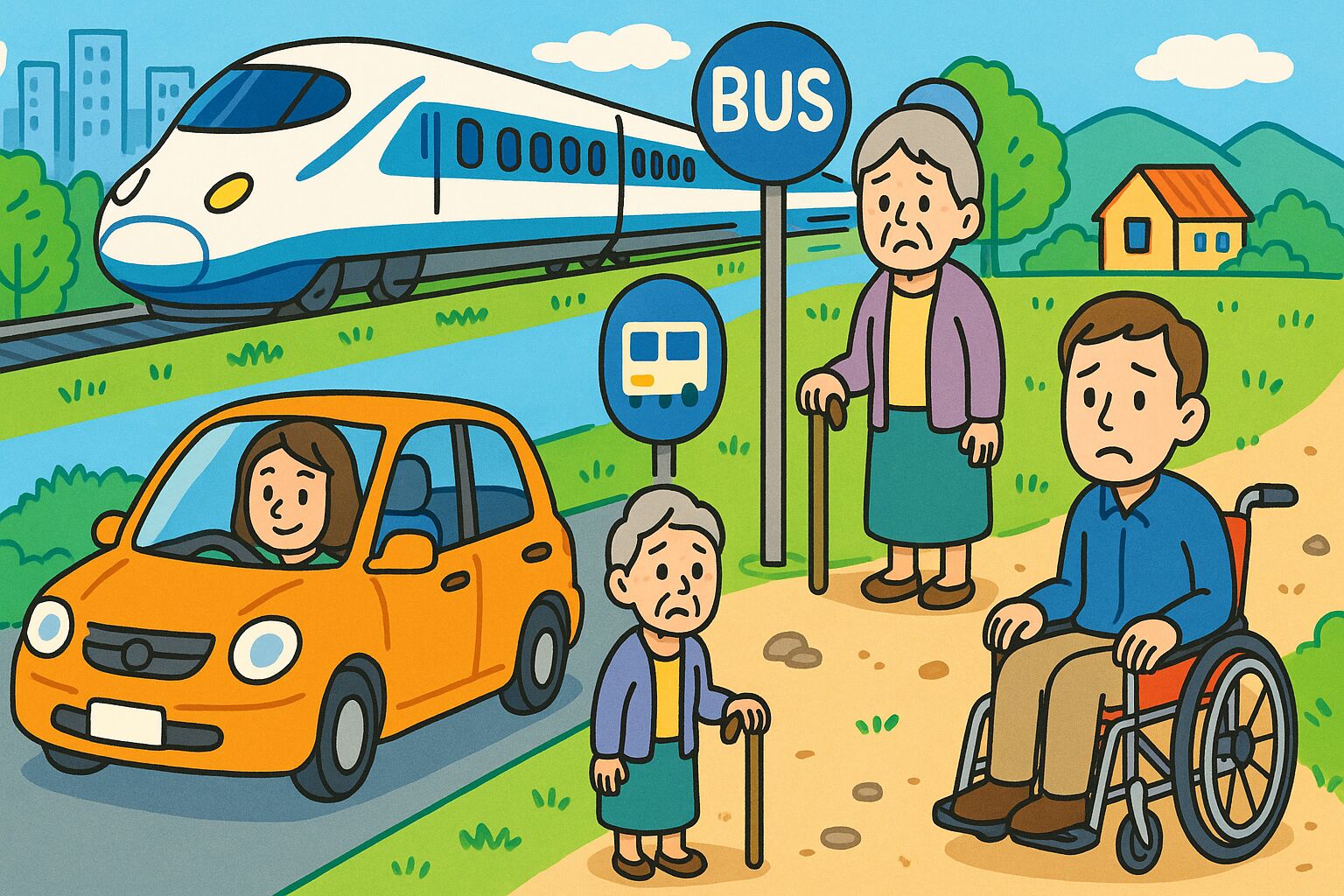
首都圏で生活をしていると、大抵の場所にはさくっと電車で行けてしまうので、この移動格差、という概念をリアルに感じることはもしかしたら少ないかも知れません。伊藤将人氏の著書「移動と階級」では、移動格差を「人々の移動をめぐる機会や結果の格差と不平等、それが原因が生じるさまざまな社会的排除と階層化を意味する概念である」と説明しています。要するに、移動格差とは、人々が生活や仕事、学習、娯楽などのために移動する際に生じる、不平等や不利のことです
住んでいる地域や経済状況、身体的条件などにより、移動の手段や時間、費用、利便性に大きな差がどうしても存在します。たとえば、首都圏ではたしかに電車やバスが町全体を蜘蛛の巣を張り巡らすように発達しており、移動の選択肢が豊富にありますが、地方や過疎地域では公共交通が少なく、自家用車に依存せざるを得ない場合がどうしても多くなります。よしんば公共交通機関があったとしても、1日に数本しかなかったりもしますし、高齢者や障害のある人は、交通機関のバリアフリー対応が不十分であれば自由に移動することができません。さらに、所得が低い人ほど車を持てない、交通費が負担になるといった制約も受けやすくなります。こうした移動格差は、教育や雇用、医療、文化活動などへのアクセス格差にも直結し、社会的な不平等を固定化させる要因となります。そのため移動格差を縮小する取り組みは、地域の持続可能性や公平な社会の実現に欠かせない重要課題とされておるわけであります。
たとえば、美術館やコンサートホールなどが徒歩圏内にある場合と電車を乗り継いで片道2時間と2500円かかる場合、様々な芸術作品や音楽などに触れる機会は徒歩圏内に美術館やコンサートホールがある方が必然的に多くなることが想像できます。コンサートホールでプロの音楽家の演奏を間近で聞いたことがない子が突然音楽家を目指すことは考えにくいわけですし、特に子供の頃のこのような移動格差はそのまま体験格差に直結しやすく、しかも本人にはどうすることもできないことが多い、というのが現実です。移動格差による影響は多くの人が考えているよりも直接的であり、しかも長期間に渡る蓄積により格差は拡大する傾向にあります。
では、この移動格差、というのはどのくらい人の人生に影響をもたらすのでしょうか?
資本主義社会が大好きな、「成功」という部分での影響を考えてみましょう。移動は成功をもたらす、という類の話は確かによく耳にします。ハイパーメディアクリエイターという肩書きで一時期有名になった高城剛さんの著書にも「アイデアは移動距離に比例する」という話があり、現代社会の成功者にとって移動は不可欠な要素である、という主旨のことを述べています。新しい場所への移動は、人との出会いや情報、資源へのアクセスを広げ、学びや挑戦の機会を増やすわけですから、成功に繋がりやすい環境ができやすいことは確かです。実際、都市への移住は教育や就業機会を拡大し、経済的成功につながる例も多く見られます。なので、移動が成功をもたらすという考えには一定の根拠がある、と言っても過言ではないかと思います。JALが2024年に実施した「DREAM MILES PASS」プロジェクトというのがあるのですが、これはロサンゼルス・ドジャースで今年も活躍しまくっている大谷翔平選手が花巻東高校入学からメジャーリーグのトップ選手になるまでに移動した距離である892,440km分を若者にプレゼントする、というプロジェクトでした。このプロジェクトはまさに「移動格差」「体験格差」などの社会課題を軽減し、夢に挑戦する若者たちを支援することを目指すものです。つまり、移動が成功を約束するわけではないですが、少なくとも「成功に移動は不可欠である」という説は間違ってないと言えそうです。そういう意味では幼少期から移動という体験に慣れている人の方が成功しやすい、と言えるのではないでしょうか?
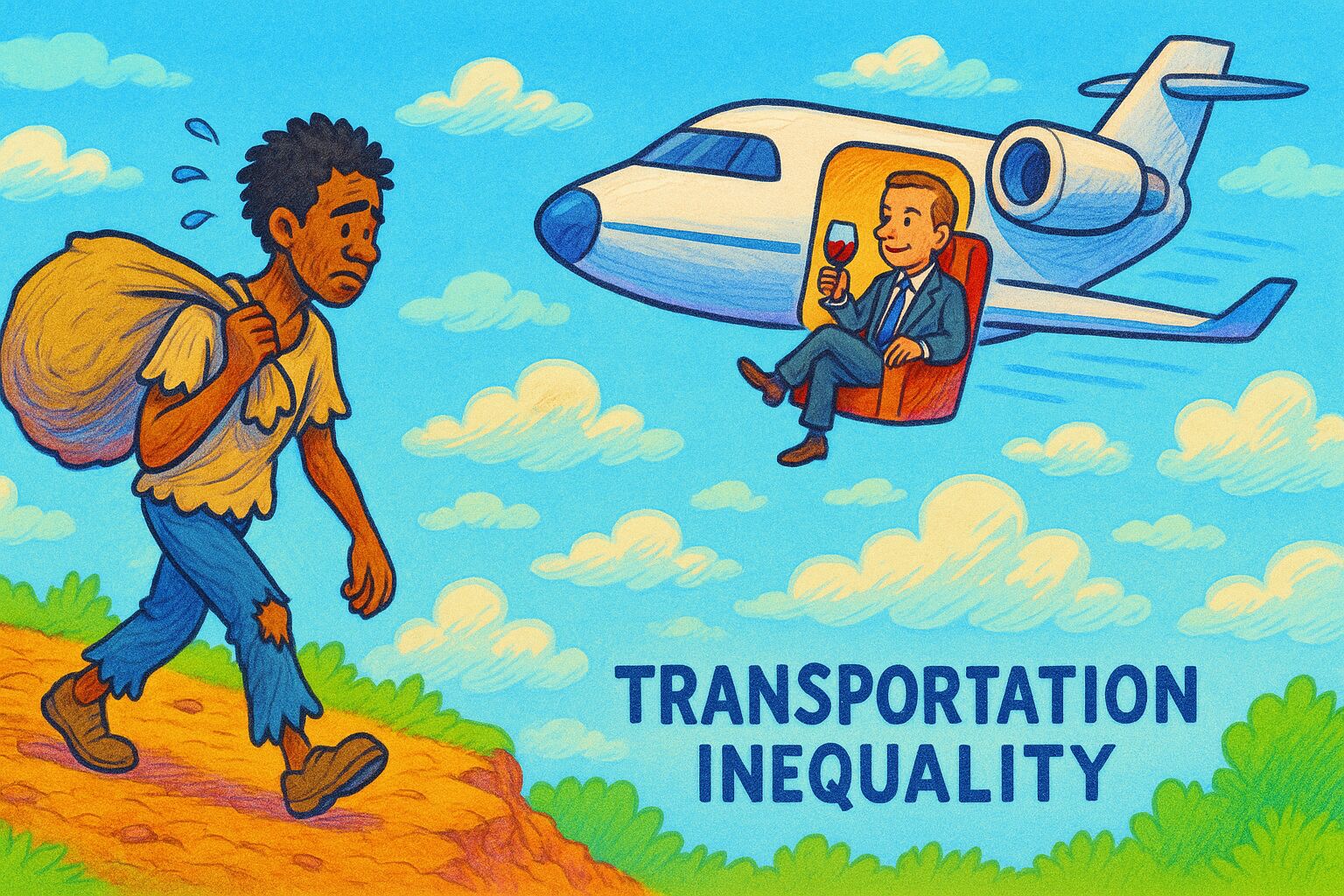
町に出て人と会って話す場合、多くの場合は比較的自由に移動ができる人同士での対話になるので、改めて意識することは少ないかも知れませんが、自由に移動ができる、あるいはその選択肢がある、ということは世界的に見ても人類の歴史的に見ても実はとても恵まれたことです。
自由に移動ができる、という人の割合は世界的に見てもさほど多くありません。日本国内だけで考えても生まれた家庭環境や経済状況などの個人差はありますが、アルバイトをしてお金を貯めて航空券を買う、などある程度は個人の力で解決できる可能性がある部分も含まれます。しかし、移動格差は、構造的な、個人ではとても解決できないもっと大きな問題によって引き起こされているものもあります。過去に日本のパスポートが最強である、という話を取り上げたことがありましたが、世界各国を自由に出入りできる日本のパスポートを持っている人とそうではない国のパスポートを持っている人との間には確実に移動格差が存在します。実際に、前述したDREAM MILES PASSプロジェクトでJALが行った現中高生・大学生~若手社会人の世代への調査によると、約4人に1人が「移動を理由に夢を諦めたことがある」と答えているそうです。
社会問題とは、多くの人に認識されて初めて社会問題となり、存在が認められる、という考えが社会学にはある、と伊藤将人氏は「移動と階級」の本で述べていますが、この移動格差という比較的新しい概念を知ること、そしてその概念を意識的に知る個々人がその解決を、あるいは軽減を目指すことによって世の中はより豊かに、より幸福度の高い場所になるのではないかとウサギながらに考え、この移動格差を多くの人に社会問題として認知してもらいたいという思いから、今回はこの移動格差についてとりあげてみました。ローランド的には、俺か俺以外か、となるのかも知れませんが、世界的には「移動できる人」と「移動できない人」がいるというのが良くも悪くも今の世界の現実なのです。
そんなわけで、また再来週の水曜日にお会いしましょう。ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!それでは、アデュー、エブリワン!
(ウサギ社長)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

