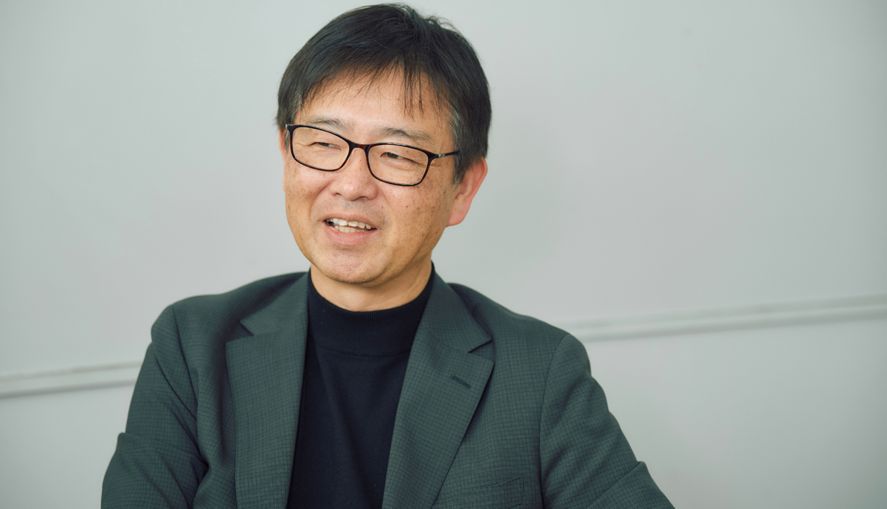
ヤンマー建機株式会社 DX推進グループ 課長 田中 重信 氏
ヤンマーは、2022~2025年度で推進する「デジタル中期戦略」の中期戦略課題の1つに「DXに対応する次世代経営基盤の構築」を挙げている。その達成への道筋として「デジタル基盤の構築」「既存オペレーションの最適化」「新たな付加価値の提供」の3つのステップと、それを推進するための4本の柱を策定している。「草の根DX施策組織化・グループ展開」は3本目の柱に位置づけられ、草の根DXが現場から変革を促す重要な役割を担っていることが分かる。田中氏は、これまでの進捗についてこう語る。
ヤンマーグループのデジタル中期戦略
「2年間で『草の根DX施策組織化・グループ展開』は着実に進み、現場は変革に向けて動き出しています。これからは経営層と現場が一体となり、4本目の柱『データ活用・分析』に挑戦、新たな付加価値の提供を目指す段階だと考えています」(田中氏)
草の根DXは、現場が主体的に動くことが大前提だ。しかし、現場のリソースやスキルにはばらつきがあり、全ての従業員がすぐに積極的に関与できるわけではない。また、活動の初期段階では成果が見えにくいため、モチベーションを維持することや各部門責任者の理解を得るのが難しい場面も少なくない。こうした課題を乗り越えるために、田中氏は「市民開発」と「社内コミュニティ」に取り組んだ。
市民開発とは、現場の従業員がローコードやノーコードツールを活用し、自ら業務課題を発見・解決する仕組みだ。田中氏はその導入に当たり、「現場主導のDXという文脈で市民開発を取り入れる上で重要なのは、情報システム部門とDX推進部門の役割の明確化や、市民開発とプロ開発(専門のエンジニアによる開発)との明確な線引きです」と強調する。
市民開発では、主にリスクが少なく、比較的簡単に使える技術を活用し、現場に密着した具体的な課題を解決。一方で、プロ開発は高度な技術や全社的な課題を対象に行われる。これにより、曖昧になりがちな境界を明文化し、役割の混乱を防ごうとしています。
DXとITを明確に区分する複数の資料を作成。説明する相手のポジションや理解度に応じて、資料を使い分けている。市民開発はDX推進グループが推進し、プロ開発は情報システム部門が管轄する
特に海外のキーマンに市民開発の価値を理解してもらうには苦労があったという。
「一般的に『開発=コンサルなどを入れてSIerと契約して進めるもの』という考えが根強い中で、『現場の業務を熟知した現場のプロが自分達が使いやすいツールを自らつくることが重要』『かつては専門職のツールだった表計算ソフトを、今では誰もが当たり前に使うようになった。同様にローコードツールも一般化するのは時間の問題』、だからこそ、今から現場に使わせるべきだと説明しました」(田中氏)
草の根DXを推進する上で、管理職の理解促進は欠かせない。ここにも、市民開発とプロ開発を明確に線引きするべき理由がある。
「現場には意欲的な従業員が多く、ローコードツールやBIツールの活用に取り組む中で、その利便性や面白さに魅了され、自発的に幅広い業務を手がけようとするケースが見られます。しかし、これらの従業員には本来の業務があります。そのため開発に過度に時間を割き始めると、本業への影響が懸念され、部門長からの信頼を損なう可能性すらあります。このような課題に対応するため、現場のエネルギーの方向性を適切に管理することも必要です。具体的には、先述の資料を提示しつつ従業員の理解を促すとともに、自ら開発することなくDX活動ができるように、プロ開発の申請を可能にしました」(田中氏)
その場合の申請書の作成を現場自身に任せることで、削減工数や効果見込みを自ら考えさせることができる。これにより、従業員の責任感やオーナーシップ(主体性)が育まれる、とその意義を語る。
「削減工数や効果見込み、そして最終的な効果を数字で管理することで、管理職が草の根DXの定量的な成果を理解できるようにしているのです」と述べる。
DX推進グループが設立された2022年から、累計で数万時間削減という業務効率化を達成。「削減時間の数字は、正確とはいえませんが、それでも大きな成果を挙げていることが視覚で分かるでしょう」(田中氏)
管理職のさらなる理解を促すために、「自分ごと化」を促す取り組みも実施している。ヤンマー建機では、新任管理職研修にDX研修を組み込み、講義とグループワークを通じて、DXツールを使って職場の課題をどのように解決できるかを議論することで主体性を醸成し、現場での実践を後押ししている。
一方、「社内コミュニティ」は、草の根DX活動を活性化する取り組みだ。同社にはもともとデジタル技術を業務に活用しようとする文化が根づいており、個々の従業員がデジタルツールを使って生産性向上に取り組む事例が多数存在していた。
「コミュニティを通じて、こうしたDXに積極的な従業員を発掘し、組織化することで、情報交換や学びの場を提供すると同時に、部門を超えた相互支援を促進できます。また、個々の活動を透明化することで、全社的なDXムーブメントを起こすことを目指しました」と田中氏は振り返る。この考えのもと、2023年5月に「DXコミュニティ」が立ち上がった。
DXコミュニティでは、基本的にMicrosoft Teamsをプラットフォームとして活用。目的ごとに「雑談」「お知らせ」「自己紹介」「相談・共有」などのチャネルを作成し、DXに関わる全てのやりとりが集約できるように設計した。
しかし、課題も浮上。「雑談チャンネルの通知が煩わしい」「コミュニティ活動は業務と無関係で遊びのようだ」といった批判的な意見が一部で寄せられた。これに対し、「業務に直結するやりとりはTeamsに限定し、イベント告知や雑談、自己紹介などの内容はViva Engageに移行する」といった改善を実施。田中氏は「コミュニティの運営は、従業員の反応を見ながら常に改善を重ねています」と語る。
さらにコミュニティ活動への懐疑的な声に対応するため、「コミュニティ活動は遊びではなく業務の一環である」というメッセージを強調する工夫も行った。例えば、次のような取り組みが実施されている。
・業務ツール(TeamsやViva Engage)の活用:業務に直結する社内共通プラットフォームを使用することで、業務の一部として認識されやすくする
・ルール整備:内容によって絵文字の使用を控えるなど、業務的な雰囲気を重視した運用
・成果報告:「DXニュースレター」(2週間に1回)や「DXコミュニティレポート」(月1回)を通じて、活動の成果をデータで示し、管理職や従業員全体に認知させる
・参加者の称賛:コミュニティ参加者を名指しでほめることで、モチベーションを高める
「特にデータで成果を提示することは、参加者の意欲向上だけでなく、管理職の理解を得るためにも重要です」と田中氏は改めて強調する。
DXコミュニティの目標について、田中氏は「全従業員の参加を実現すること」と意気込む。そのために、さまざまな工夫を取り入れている。下記はその一例だ。
・クリスマスリレー投稿:従業員が毎日順番に投稿をバトン形式でつなぎ、知識や経験、アイデアを共有する
・短時間の勉強会:通常長時間に及ぶ社内研修を1時間以内に短縮し、参加のハードルを下げる
・DXフォーカスタイム:毎週金曜日に開催している勉強会。マネージメント層の理解を得て、直属の上長が参加を拒否しにくくするようにする
これらの活動は、引っ込み思案な従業員や忙しい管理職も含め、多くのメンバーがDX活動に関与できるように設計している。
田中氏は、これまでの取り組みについてこう振り返る。「もちろんこれまで挙げてきた活動は、私一人で行ってきたわけではありません。DX推進グループのメンバー全員での取組みがあったからこそ、ここまで進めることができました」。
DX推進グループは、草の根DXを促進するために組織されたチームでもあり、その役割は単なるツール選定や導入にとどまらない。現場の従業員一人一人がDXツールを活用して変革を起こせる環境を整えるだけでなく、主体的に変革を生み出す文化を育むことも目指している。
「こうした活動をさらに体系的に進めるため、2024年10月には、チーム全員で話し合いながら行動指針を作成しました」と田中氏。行動指針を定めたことで、チームのメンバーは共通の目的意識を持ち、より一貫性を持った活動が可能となったという。
DX推進グループの行動指針。メンバーの業務を1日止めて全員で作成したという。部門外向けバージョンとは別に、より直接的な表現を使った部門内バージョンもある
「行動指針の1つ目は、現場で意識変革を促し、主体的な行動を引き出すことを目的としています。DX推進グループのメンバーは、基本的に人の課題を解決することに喜びを感じる、サポート精神旺盛な人たちです。しかしその姿勢だけでは、現場にオーナーシップが育たないという課題もあります。そこで、例えば市民開発の支援では、最初は寄り添いながら一緒に取り組みますが、次の段階ではコミュニティの力を活用しつつ、現場の人々が自分たちで進められるよう促しています」(田中氏)
草の根DXをリードする人材を発掘するために、「KEEN Manager」を活用。イベントへの積極的な参加や投稿・シェアが頻繁な従業員を分析し、コミュニティのキーパーソンと成り得る「ネクストスター」を特定。そのような従業員に「コミュニティリーダー」という役割を与え、DXをけん引する「スター」へと成長してもらう仕組みを採用している
DX推進グループの最終的な目標は、ヤンマー建機全体でDXが自然発生的に進む「文化」をつくることだともいえる。同グループは、そのための潤滑油として、従業員一人一人がデジタル技術を活用して変革を起こす主体となり、それが組織全体の強みとなるよう支援を続けていく。「これからも現場の声に耳を傾けながら、柔軟に対応していきたい」と田中氏は力強く語った。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!