




データ活用の普及と共に増え続ける一方のデータ量。
データ活用における最大のボトルネックは、複雑なデータを適切に管理し、データ量のスケールにも柔軟に対応できる環境を構築することが難しい、という点かも知れません。
2023年3月の発表によると、日本のビジネスリーダーの31%がデータの複雑性やアクセスの不十分さによりデータに関する理解不足が生じていると指摘しており、23%は増大する膨大なデータ量に悩まされています(Untapped Data Research┃セールスフォース・ジャパン)。
そこで注目を集める概念が「データファブリック」です。本記事では、データファブリックとは何か、なぜ重要とされるのか、データメッシュとはどう違うのか、どう使い分けるべきなのかなど、必要な知識をまとめてご紹介します。
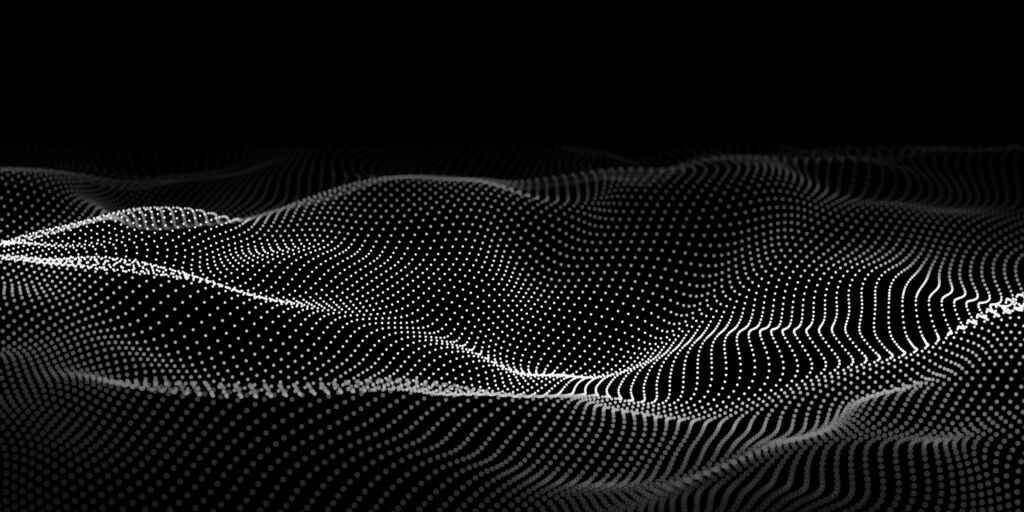
データファブリックは、‟分散されたデータを一元的かつ統一的に管理するためのデータ管理アーキテクチャ”です。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドなど多様な環境にまたがるデータを仮想的に統合し、リアルタイムでのアクセス、ガバナンス、自動化を実現します。それにより、データの物理的な移動を必要とせず、あらゆる場所に存在するデータを利用者がシームレスに活用できるのが大きなメリットです。
データファブリックは、分散されたデータを仮想的に統合し、統一されたビューを提供します。これにより、企業全体のデータ資産を一貫したポリシーや基準で管理することが可能になります。
例:各部門が異なるクラウドサービスを利用していても、すべてのデータに共通のガバナンスルールを適用。
データファブリックは、AIや機械学習を活用し、データの発見、準備、統合、分析のプロセスを自動化します。これにより、手作業によるミスや非効率を削減し、データ活用のスピードを向上させます。
例:必要なデータを自動的に関連付け、利用者に最適なデータセットを提案する。
データファブリックは、データへのリアルタイムアクセスを可能にします。これにより、迅速な意思決定が求められるシナリオで大きな価値を発揮します。
例:IoTデバイスから収集したセンサーデータを即時分析して運用効率を改善。
データファブリックは、データ量の増加や新たなデータソースの追加に柔軟に対応できます。ハイブリッド環境やマルチクラウドにもスムーズに適応可能です。
例:急成長するスタートアップが、データファブリックを利用して新しい市場や製品に迅速に対応。
データファブリックの概念は、2010年代初頭ごろから徐々に形成されはじめました。その背景には、この頃、クラウドコンピューティングやビッグデータの普及が進み、企業内外でデータが急激に増加し始めたことがあります。従来のデータ管理手法では対応が困難になった結果、分散したデータを統合的かつ効率的に管理する新しいアプローチが求められるようになったのです。
その後、2020年代に入り、下記のような要因からデータファブリックはより注目を集めるようになります。
企業がクラウド移行やデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる中で、データがオンプレミス、複数のクラウド、エッジデバイスなど、より多様な場所に分散するようになり、それに適応したソリューションのニーズが拡大しました。
AIや機械学習(ML)の進化により、データの発見、統合、分析の自動化が大きく前に進みました。これにより、データファブリックは単なる統合プラットフォームではなく、インテリジェントなデータ管理アーキテクチャとしての地位を確立しました。
GDPRやCCPAなど、データプライバシーに関する規制が強化される中で、統一的なガバナンスを実現できるデータファブリックが、企業の規制対応を支える重要なソリューションとして注目されるようになりました。
2021年末には、Gartnerが発表した「2022年のトップ戦略的テクノロジートレンド」において、データファブリックが重要なテクノロジーの1つとして位置づけられています。このレポートでは、データファブリックがデータ管理の効率を最大70%向上させる可能性があると指摘されています。

データファブリックと混同されることの多い言葉に「データメッシュ」があります。データメッシュとは何なのか、どのような特徴を持ち、データファブリックとは何が違うのかについて詳しく見ていきましょう。
データメッシュ(Data Mesh)は、‟データ管理を中央集約型ではなく、分散型アーキテクチャに基づいて行うアプローチ”です。特に大規模分散システムやデータレイクの課題を解決するために提唱されました。
データメッシュでは、各部門や事業領域、チームが自らのデータを管理する責任を持ちます。各データソースを「データプロダクト」として扱い、それぞれが独立したガバナンスとAPIを提供します。
データは企業内の業務ドメイン(例: 販売、マーケティング、製造)ごとに分けられます。
ドメインチームがデータの収集、管理、提供を主導します。
セルフサービス型インフラとは、ユーザー自身がIT部門に依存せずに、必要なリソースやサービスをオンデマンドで利用できるインフラ環境を指します。データメッシュでは、各チームが効率的にデータを管理できるよう、標準化されたプラットフォームやツールを提供します。
データメッシュは分散型アーキテクチャに基づいているため、データファブリックと同様、企業の規模拡大やデータ量の増加に柔軟に対応できます。
データファブリックとデータメッシュの違いは以下のようなポイントにあります。
項目 | データファブリック | データメッシュ |
アーキテクチャ | 中央集約型 | 分散型 |
設計思想 | 統一されたポリシーで全データを管理 | ドメインごとの自主性を尊重 |
適用シナリオ | 一貫性のあるガバナンスやアクセスが重要な場面 | 大規模な分散環境で効率的なデータ管理が求められる場面 |
自動化の活用 | AIやMLを使った自動化が主要な強み | 自律的なデータ管理を可能にする標準化インフラが強み |
スケーラビリティ | 既存インフラを活用してスケールしやすい | 組織規模に応じての拡張性が高い |
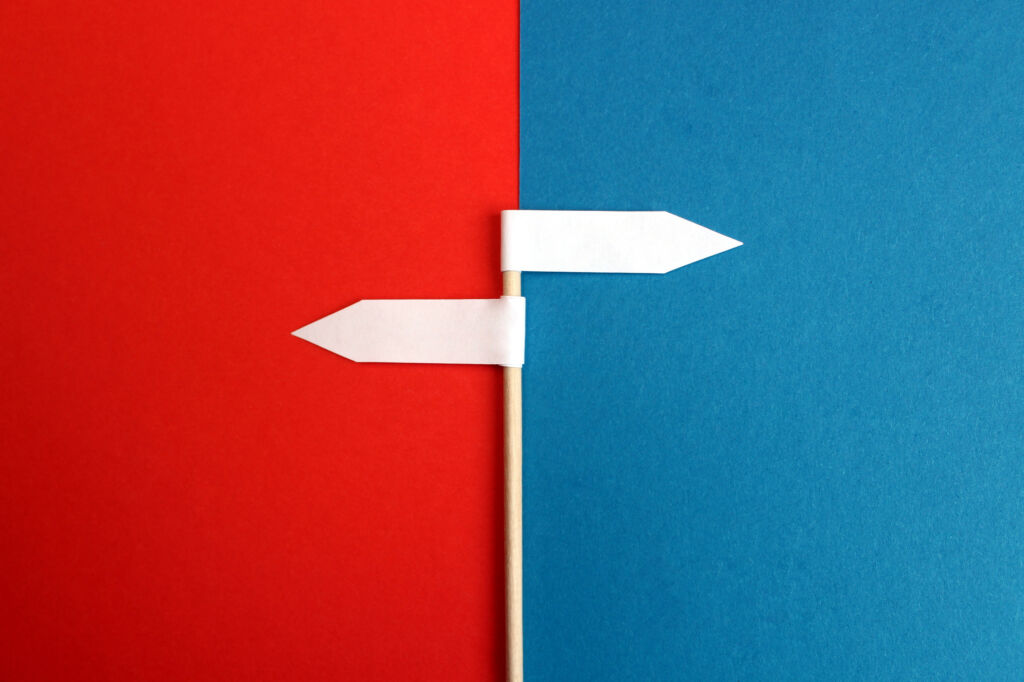
前述の違いをもとに、データファブリックとデータメッシュの使い分けについて考えてみましょう。
データファブリックは、データの集中管理を重視し、IT部門がデータ運用の主導権を持ちたい場合に適しています。その背景にあるのが、以下のような状況やニーズです。
厳しい規制への対応や、セキュリティポリシーの一貫性を確保する必要がある状況です。データファブリックは、分散されたデータ環境全体に統一的なルールを適用し、データ漏洩や不正アクセスのリスクを低減します。
複数のクラウドやオンプレミス環境にまたがるデータを統合し、全社的に一貫したデータアクセスを実現したい場合にもデータファブリックは有効です。これにより、ビジネスユーザーはデータの保存場所を意識せずにアクセス可能になります。
既存のデータ基盤を活用しながら、AIや機械学習を通じた自動化を進めることで、データ管理プロセスを効率化できます。
一方、データメッシュは、各部門が独立してデータを管理・活用できる環境を構築したい場合に適しています。その背景にあるのが、以下のような状況やニーズです。
大規模な組織や分散型チームが存在する場合、中央集権型のデータ管理はボトルネックを生じさせがちです。データメッシュは、各部門やドメインが自らデータを管理することで、効率的かつ迅速な運用を可能にします。
販売、マーケティング、製造といった各業務領域が独自のデータ要件を持つ場合に、ドメインチームが主導権を持ち、それぞれのニーズに応じたデータ管理が可能です。これにより、データ活用の効率性と現場対応力が向上します。
組織規模やデータ量が増加しても、分散型のデータプロダクトが独立してスケールするため、全体の複雑性を抑えつつ柔軟な対応が可能です。
ここまで述べたような特性の違いはあるものの、データファブリックとデータメッシュは競合する概念ではなく、組織の規模や目指すデータ戦略に応じて相互補完的に活用できる場合があります。
データファブリックの統一的なガバナンスと仮想化機能を基盤にしつつ、各部門が独立したデータプロダクトを管理するデータメッシュの設計を取り入れることで、柔軟性とガバナンスを両立できます。
データ管理の成熟度に応じて、データファブリックから始め、後にデータメッシュを採用することも可能です。最初に統一的なデータ管理を実現し、その後にドメイン主導の分散型管理を導入することで、スムーズな移行が可能になります。
企業のデータ活用基盤として存在感を高めているデータファブリックの概念や特性、データメッシュとの違いや使い分けのコツについて解説いたしました。仮想化技術やAI・機械学習による自動化技術の発展により、データベースをより柔軟、動的に利用できる可能性は広がっています。そして、データファブリック、データメッシュは、そのような状況下で必然的に不可欠となりつつあるのです。
(宮田文机)
・Salesforce、データ活用に関するレポートを発表 日本のビジネスリーダーの84%は意思決定でのデータの重要性を 認めているが、利活用は不十分┃セールスフォース・ジャパン
・Gartner、2022年の戦略的テクノロジのトップ・トレンドを発表┃Gartner
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

