




11月も最終週になりました。
今週末の3連休を過ぎれば、秋の行楽シーズンも一区切りですね。お天気に恵まれているせいか、ちょっとした買い物や通院でも渋滞に巻き込まれ、思うように移動できない日が増えてきている気がします。
筆者の暮らす神奈川西部では、小田原・箱根といった定番の観光地に加え、丹沢での登山などで訪れる人も増え、交通渋滞や物価の高騰が“日常”になりつつあります。生鮮食品まで観光地価格になってきている、という声も珍しくありません。
インバウンドや観光客が増えることは地域にとってメリットもありますが、そこで暮らす人にとっては、必ずしも良いことばかりではない——最近はそんなことを考える機会が増えてきました。街づくりの難しさを改めて感じる今日この頃です。
それではまず、今回紹介する記事をダイジェストで紹介します!!
社会を変革するような多くのイノベーションは、「セレンディピティ(偶然の発見)」から生まれてきました。2025年ノーベル化学賞を受賞した京都大学特別教授・北川進氏は、授賞会見で子どもたちに向けて、ルイ・パスツールの言葉「幸運は準備された心にのみ宿る」を引用し、「準備と努力の中にこそ未来が花開く」と語りました。このメッセージは、大人にとっても“偶然の発見や幸運は、周到な準備の積み重ねによってこそ生まれる”という示唆として響きます。東京大学大学院理学系研究科教授の合田圭介氏は、「Serendipity Lab(セレンディピティラボ)」の活動をはじめ、セレンディピティを科学的・計画的に創出するための技術や構造の解明と実践に取り組んでいます。本記事の前編では、合田氏が提唱する「セレンディピティ工学」の全体像、その背景にある科学的潮流、そして“ゼロからの発見”をスケールさせ、成果を最大化する研究室マネジメントの取り組みをご紹介します。
※本記事の取材は、2025年ノーベル賞受賞者発表前(2025年9月末)に実施しています。 (・・詳しくはこちらへ)
「UpdataTV」は、“データでビジネスをアップデートする”を掲げ、変革に挑むビジネスパーソンが集う“変革のターミナル”のような動画チャンネルです。成功体験がない、仲間がいない、どこを目指せばいいかわからない——そんな時に立ち寄れば、実践知やヒントに出会える“新しい居場所”として機能しています。その中の対談シリーズ「フルスタックビジネスパーソンの道」は、専門性・領域・立場を越境しながら活躍する実践者の思考やキャリアに迫り、“越境”から生まれる創造性や成長の論理を紐解く企画です。本記事では、シリーズ第1回「交通整理から名誉教授へ──“越境”で拓いたキャリア軌跡」を、記事として読みやすい形に再構成してお届けします。動画と合わせて楽しんでいただくことで、キャリアに迷うビジネスパーソンにとっても、大きな示唆になるはずです。 (・・詳しくはこちらへ)
「UpdataTV」は、“データでビジネスをアップデート”することを掲げた、変革に挑むビジネスパーソンが集う“変革のターミナル”です。その中でも『デジタルに取り憑かれた者たち』は、日常的にデータを見える化・分析せずにはいられない“データマニア”にスポットを当て、その生活とガジェット、こだわりのデジタル環境を深掘りするシリーズ企画です。本エピソードでは、庭の水やりや養蜂をIoTで可視化し、淡路島での豊かな暮らしをより快適に進化させていく川添さんの“デジタル活用のリアル”が紹介されています。自然の変化をデータで読み解き、生活とテクノロジーを融合していく姿は、都市で働くビジネスパーソンにも多くの示唆を与えてくれるはずです。 (・・詳しくはこちらへ)
まいどどうも、みなさん、こんにちは。わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。暦通りとはよく言ったもので、またもや水曜日がやってまいりましたので執筆の方を始めさせていただきます。秋深しといった感じなのかすでにこれは冬と呼んで差し支えないのか、流行語大賞にも「二季」という単語がノミネートされていたのも頷ける近年の気候でありますが、みなさまいかがおすごしでしょうか?先日わたくしは、今年の7月に発売された発明家の小川コータ氏による書籍「発明で食っていく方法、全部書いた。」を拝読させて頂いたのですが、この内容がなかなか興味深いものでありましたのでご紹介させて頂きます。小川コータ氏はプロ発明家として様々なアイテムを考案している方なのですが、その代表作はなんと言ってもスマホで文字入力をする際に文字を連打しなくても良い画期的な入力メソッドであり、連打しなくても良い分入力スピードも格段にアップするという魔法のようなシステム「フリック入力」であります。 (・・詳しくはこちらへ)
データのじかんNewsのバックナンバーはこちら
2025.11.21 公開

イノベーションの源泉として語られてきた「セレンディピティ(偶然の発見)」を、どのように“再現可能な技術”として社会実装につなげていくのか。本記事前編では、この挑戦を掲げる東京大学・合田圭介教授の研究と、研究室運営の実践に迫っています。
合田氏が提唱する「セレンディピティ工学」は、偶発的な発見を“準備された構造”によって引き寄せ、価値創出へつなげる学際的アプローチです。ペニシリンや電子レンジの原理の発見など、歴史を変えた多くの発明が偶然から生まれたように、今も世界のイノベーションの半分はセレンディピティに支えられています。しかし研究資金は計画性の高い研究に偏りがちで、偶発的発見を推進する枠組みは十分とは言えません。
こうした課題のもと、合田氏はImPACTでのプロジェクト推進や、160名以上が参加する国際コンソーシアム「Serendipity Lab」の立ち上げなど、多様な仕組みづくりに挑んできました。これらの取り組みは、国際的な論文評価やデザイン賞受賞など、具体的な成果として実を結んでいます。
さらに本記事では、“偶然を最大化する研究室マネジメント”にも注目します。分野横断の組織構造、フラットな関係性、多様な人材を生かすための「研究室の憲法」など、研究成果をスケールさせるための独自の仕組みが紹介されています。
セレンディピティを科学し、組織化し、成果へとつなげる——その最前線に迫るのが本記事前編です。後編では、日本の科学研究が抱える構造的課題にも踏み込みます。
2025.11.19 公開
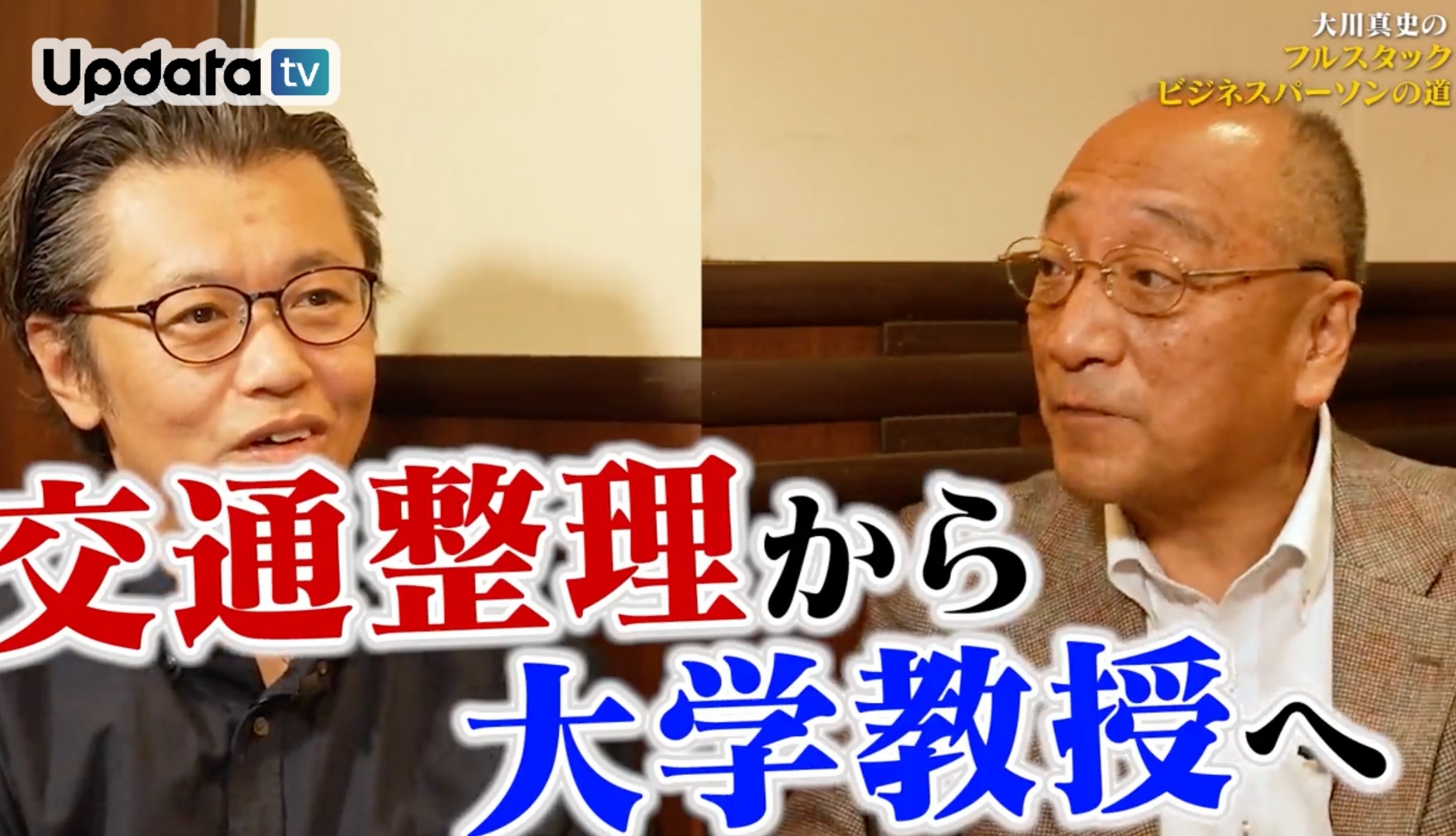
「UpdataTV」は、“データでビジネスをアップデートする”をテーマに、変革に挑むビジネスパーソンが立ち寄れる“新しい居場所”として機能する動画チャンネルです。中でも対談シリーズ「フルスタックビジネスパーソンの道」は、領域を越えて活躍する実践者のキャリアと思想に迫り、“越境が生む創造性”を紐解く企画として人気を集めています。
本記事では、シリーズ第1回となる「交通整理から名誉教授へ──“越境”で拓いたキャリア軌跡」を、記事として読みやすく再構成してお届けします。主人公は、16年にわたる学生生活、企業での現場叩き上げ、極貧の交通整理、サイエンスライター、そして大学教員へ——と、常識を超えたキャリアの折れ線を歩んできた阪井和男氏。すべての局面に共通するキーワードは“場を整え、人と情報の流れをつくること”でした。
博士中退からの就職、家庭との両立崩壊、生活のためのさまざまな仕事。そこからライティングをきっかけにアカデミアへ戻り、明治大学で情報化改革の旗振り役を担うことに。「物理をやるな。情報をやれ」という突然の指示から、全学の情報化推進を託され、学部の枠を超えて組織・文化の越境を続けます。
象徴的なのが、リバティタワーの情報インフラ整備。商用インターネット黎明期に、全館ネットワークや光配線など“100年先の学び”を見据えた設計に挑戦し、反対と調整を乗り越えて実現させました。
阪井氏の歩みは、決して一本道ではありません。しかし、流れが途切れたように見える局面でも「自ら流れをつくる」姿勢を貫いてきました。本記事は、キャリアに迷うビジネスパーソンにとって、大きな勇気とヒントを与える内容となっています。
2025.11.20 公開
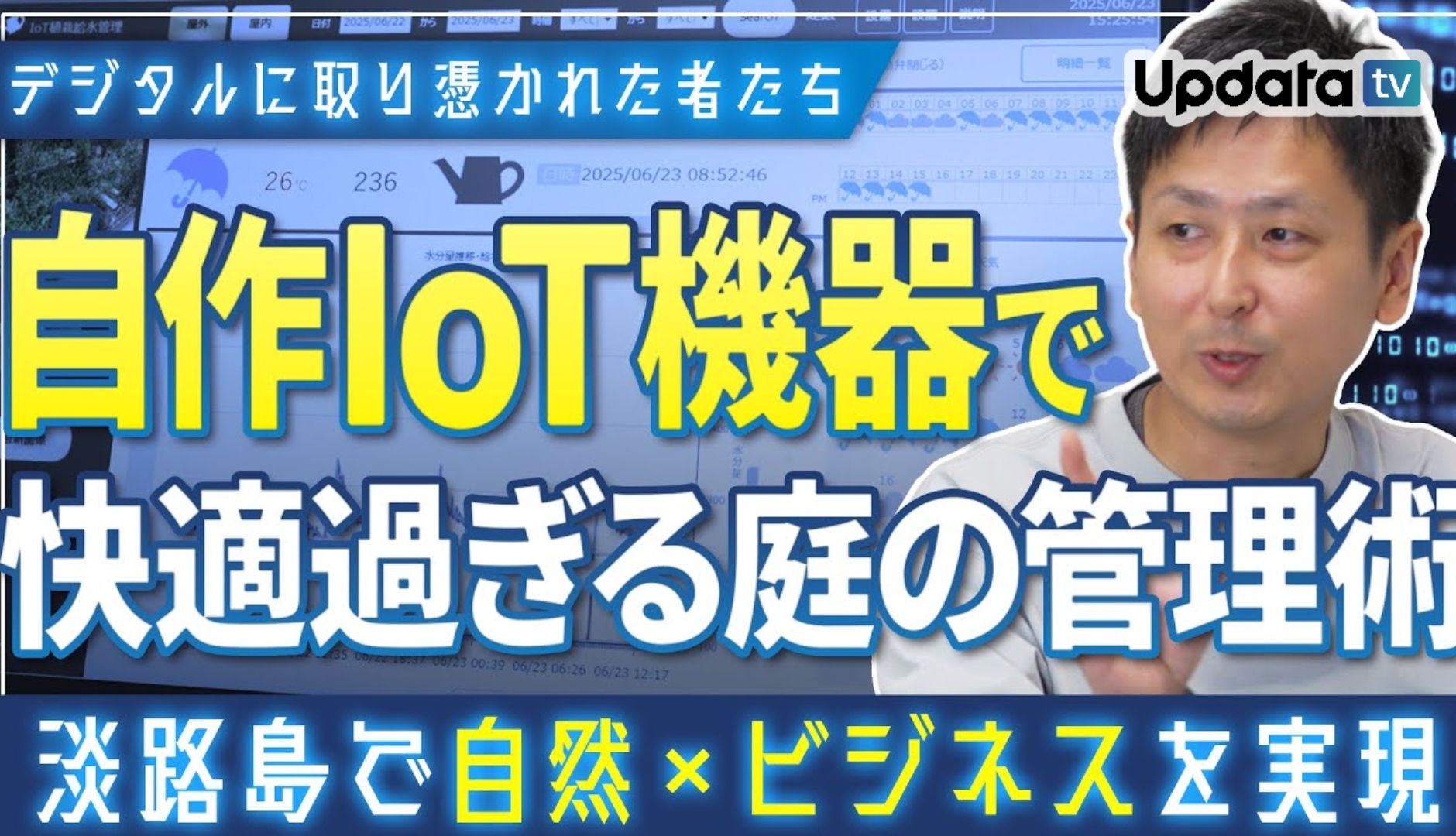
淡路島で“自然×デジタル”の暮らしを実践する川添祐太さんに密着した、UpdataTVの人気シリーズ『デジタルに取り憑かれた者たち』。本記事では、IoTセンサーや自作の自動給水システムを駆使し、生活を最適化していく川添さんのリアルな取り組みを、記事として読みやすく再構成して紹介します。
「UpdataTV」は“データでビジネスをアップデートする”を掲げた、変革を志すビジネスパーソンのための動画メディア。本シリーズでは、日常的にデータを可視化・分析してしまう“データマニア”の暮らしを掘り下げ、ガジェットや部屋づくり、こだわりのセンサー環境など“生活とデータの交差点”を描き出します。
淡路島にUターンし、フルリモートで働く川添さんは、庭や養蜂場にIoTセンサーを設置し、環境データを日々記録。水分量や気温をもとに自動で水やりが行われるシステムや、養蜂場を見守るライブカメラなど、生活に溶け込んだテクノロジー活用が紹介されています。「雨が降っても土が乾いていることがある」という気づきをデータで補完し、自然との調和を技術で支える姿が印象的です。
また、IoT活用の先にある未来として、鳥の来訪パターンの把握や植物開花の予測など、自然観察の自動化にも意欲を見せています。川添さんは「IoTは手段にすぎない。こうあったらいいなを自分で試すことが大事」と語り、好奇心から生まれた実践が本業のソリューションにもつながっているといいます。
自然の変化をデータで読み解きながら、生活を豊かに進化させていく川添さんの取り組みは、都市で働くビジネスパーソンにとっても、新しい働き方とデータ活用のヒントを与えてくれます。
2025.11.19 公開

今回の『ちょびっとラビット耳よりラピッドニュース』では、ウサギ社長が発明家・小川コータ氏の著書『発明で食っていく方法、全部書いた。』を紹介しながら、スマホ文化を一変させた「フリック入力」誕生の裏側に迫ります。ウサギ社長自身も効率重視派としてフリック入力を愛用しており、その便利さや生産性の高さをユーモアを交えて語りつつ、本書の内容を丁寧に読み解いていきます。
フリック入力の着想は2007年。当時主流だった「5タッチ入力」は、多くの人が疑問を持たずに使っていましたが、小川氏は名前を入力するだけで何度もボタンを押す非効率性に強い違和感を覚えます。その“小さなイラ立ち”が、後に世界中のスマホに採用される発明の原点となったのです。本記事では、特許出願から取得まで4年を要した理由、審査基準となる「新規性」や「進歩性」の考え方、フリック入力が特許として認められたポイント(ブラインドリリース)など、書籍に基づいた具体的なプロセスが紹介されています。
しかし、特許を取ったからといってすぐにお金になるわけではありません。世界中のスマホにフリック入力が搭載される一方、個人が大企業にライセンス料を求めるのは現実的ではなく、小川氏は最終的にマイクロソフトに特許を売却する決断をします。この“発明をお金に変える難しさ”も本記事の重要なテーマです。
ウサギ社長は、小川氏の才能や行動力に深い敬意を示しながら、「イラっとする感情こそが発明の種になる」とまとめます。日常の中の違和感を捉え、それを改善する発想へつなげる姿勢——それこそが、発明家に必要な視点であり、読者にとっても新鮮な学びとなるでしょう。

今回は『ちょびっとラビット耳よりラピッドニュース #057 :フリック入力を生み出したプロ発明家・小川コータ氏が語る、発明についての知られざる話!』という記事を紹介させて頂きました。
記事中で「フリック入力」を紹介していますが、実は筆者はいまだにスマホを“5タッチ入力”で使っています。周囲から「そろそろフリック入力にしたら?」と言われることも多いのですが、便利だと頭では分かっていても、いざ新しい操作を取り入れようとすると、どうにも腰が重くなってしまいます。
会話の中で調べ物をする場面でも、ついChatGPTではなく検索サイトにキーワードを打ち込んでしまい、「まだそっちで調べるの?」と驚かれることもしばしば。“そのうち覚えよう”と思いながら先送りにしてしまう感覚も、年齢とともに強まってきたように感じています。
なぜこうも腰が重くなるのか――少し考えてみました。
ひとつは、いまの5タッチ入力でも致命的に困る場面が少ないこと。多少遅くても「まあ何とかなる」と思えてしまうため、現状維持の安心感が勝ってしまうのです。
もうひとつは、新しい操作を覚えるエネルギーが、以前より確実に大きく感じられること。操作を切り替えれば、しばらくはむしろ入力が遅くなる“慣れない期間”が訪れます。この短期的な不便を避けたくなる自分がいて、さらにテクノロジーの移り変わりの速さに疲れを覚えることもあります。
こうした体験を重ねるたびに、デジタル・ディバイド(Digital Divide)に分類されてしまう方々の気持ちが、以前よりも深く理解できるようになりました。便利さを取り入れ続けるには、思った以上にエネルギーがいる。誰しもどこかでペースを緩めたくなる瞬間がある――その当たり前の事実を、最近しみじみと実感しています。
それでは次回も「データのじかんNews」をよろしくお願いします!

データのじかんは、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。
越境者の興味・関心を高める話題や越境者の思考を発信するレポート、あるいは越境者の負担を減らすアイデアや越境者の拠り所となる居場所などを具体的なコンテンツとして提供することで、データのじかんは現状の日本にあるさまざまなギャップを埋めていきたいと考えています。
(畑中 一平)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

