データのじかんを閲覧頂いているみなさま!!こんにちわ!!
【データのじかんNews】担当の畑中一平です。
2023年もあっという間に3か月が経ちました。
コロナ禍で自粛していた送別会がようやく再開されていると思いますが、今年は桜の開花が早かったせいか、東京では、桜は花びらが散り始めていることもあり、今までいっしょに仕事をしてきた人たちとの別れが気のせいか、例年より寂しく感じてしまう気がします。
さて前回に引き続き、読者様がより便利に、より活用しやすく“データのじかん”を閲覧頂けるよう、過去1週間に公開された新着記事の短信をニュースとして、今回もみなさまにお届けしてまいります!!
第48回の2023年4月Part1では、2023年3月27日~3月31日までに【データのじかん】で公開された8件の記事についてご紹介します!!
まずは今回紹介する記事のダイジェストの一読下さい!!
データのじかん週報では、データのじかんの編集部内で会話されるこばなしを週1度程度、速報的にお届けしています。2023年3月24日付データのじかん週報は、主筆の大川が講師を務めた「東商ものづくりゼミナール」とそのまとめ「自社の強みを活かした製品開発セミナー」で得られた思いがけない成果を公開!その要因を突き詰めると、誰もが必要だと考えるコミュニティにおける「課題の共有、共感」の要不要論にまで言及することになりました!
・コミュニティに「掲げる旗」は不要? 始動する誰も見たことのない未来 –データのじかん週報2023/3/24付
年度末や期初に限らず、企業の業績向上を目指す上で、KPI(Key Performance Indicator)の設定やマネジメントが注目を集めています。特に、新年度が始まり、多くの企業でKPIの見直しが行われるため、4月には注目が高まります。KPIは目標達成のための指標として重要であり、適切に設定・管理することが業績向上につながります。それでは、KPIによる数値化マネジメントにより業務はどのように変化するのでしょうか?以下、書籍『数値化の鬼』の著者である安藤広大氏が代表を務める識学総研に掲載されたコンテンツを許可を得てお届けします。
・KPIによる数値化マネジメントを利用することで 何が変化するのか?実際の事例をもとに解説!
安全保障といえば軍事的なイメージが真っ先に思い浮かびますが、近年は政治や経済にまでその概念は拡大しています。「エネルギーも戦略物資も『持たざる国』だからこそ、経済安全保障についてもっと考えていかなければならない」。そう語るのは公安調査庁出身で、現在はTOYA未来情報研究所を主宰、また経済安全保障マネジメント支援機構の上席研究員も務める藤谷昌敏氏です。歴史も踏まえた経済安全保障の全体像と今後の日本の行く末を左右する“新しい”経済安全保障について、前編・後編にわたって藤谷氏にお聞きしたお話を紹介します。
・取り組みの焦点は「経済」へ。日本における“新しい”経済安全保障とは何か? DXリーダーにこそ知ってほしい経済安全保障(前編)
2022年に成立した経済安全保障推進法を契機として、今後、日本は安全保障のための“新しい”体制整備をさらに加速していくことになります。その時に念頭に置いておくべきキーワードが、「自律性の確保」と「不可欠性の獲得」です。この資源を「持たざる国」が、他国に依存することなく経済の安定を図っていくには何が必要なのでしょうか。前編に引き続いて、TOYA未来情報研究所代表 兼 経済安全保障マネジメント支援機構上席研究員の藤谷昌敏氏が、この先、日本が求めるべき”新しい”経済安全保障の在り方を示唆します。
・取り組みの焦点は「経済」へ。 日本における“新しい”経済安全保障とは何か? DXリーダーにこそ知ってほしい経済安全保障(後編)
データのじかん週報では、データのじかんの編集部内で会話されるこばなしを週1度程度、速報的にお届けしています。「2023年3月31日付データのじかん週報」は、データのじかん主筆の大川が、前週に参加した日本最大級の研究機関「産業技術総合研究所」のスタートアップ/オープンイノベーションイベントに参加して感じた日本の技術政策の前向きな「変化」についてお伝えします。さらに大川の恩師が語った、誰もが意識する「創造性」に関する深い話もご紹介。週報を読み終わるころには、あなたの「仕事の哲学」が少しだけ変わるかも!?
・国の技術政策の「変化」に気づいてますか?目からウロコ! 創造性はまさかの「後付け」 –データのじかん週報2023/3/31付
特集「プロトタイピング・プロトピア」は、DX・イノベーションなどでも注目が高まる良質な試行錯誤を引き出すプロトタイピングを活用し、昨日よりも今日よりも、ほんの少しだけでもより良い状態を目指し活動される方々を特集で追って参ります。
・IT初心者の事務員がノーコードで業務の自動化に挑戦したら、会社公認の社内サークル活動に発展して組織文化が変わった話
子育てをする人にとって大きな関心ごととなるのが、教育について、です。教育への関心への根底には、子どもにとってよりよい未来を築きたい、という親の願いがあるのではないでしょうか。子どもへの教育を考えるとき、頭に置いておきたいキーワードの一つが「40年ギャップ」です。
・想像できない未来に向けて教育を模索する時に立ちはだかる「40年ギャップ」とは?
今回のタイムくんは、医療業界と航空業界の失敗に対する対処法の違いに焦点を当てて失敗から学ぶ方法がたくさん紹介されている書籍「失敗の科学」について、漫画でおもしろおかしく、紹介します。
データのじかんNewsのバックナンバーはこちら
2023.03.29 公開
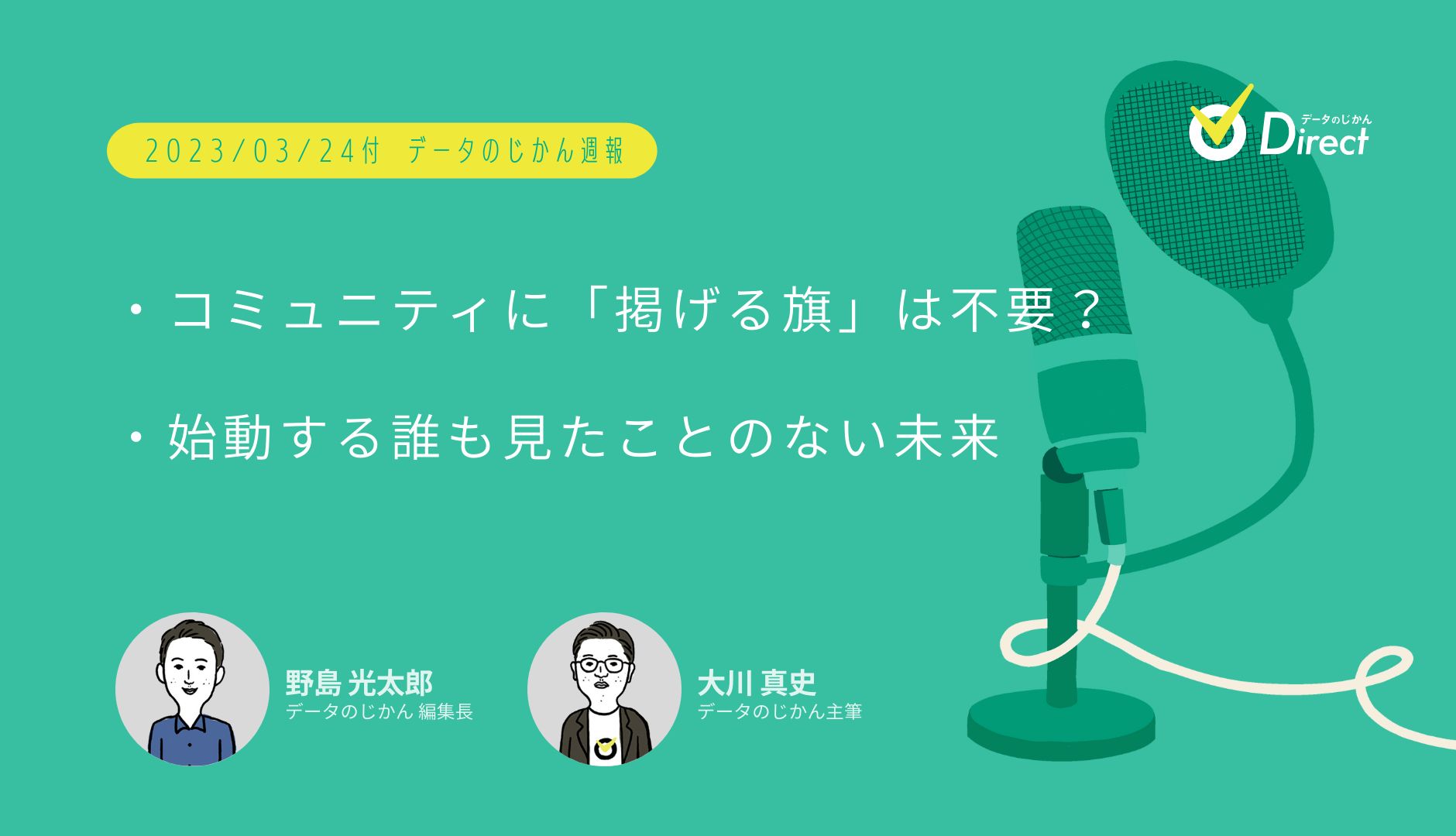
データのじかん主筆の大川が講師を務めた全7回・約5カ月間に渡った東京商工会議所の「名刺代わりになる自社製品の開発を目的としたゼミナール」が終了しました。
カリキュラムの作成からガッツリ担当したのは初めての経験でしたから、私自身も反省や成果をたくさん得られました。何よりも受講者の声をじっくりと聞けたことが大きな気付きを得られました。本ゼミで登壇いただいた菅原のびすけ氏の「プロトタイピングは終わらない」という言葉は個人的にも名言だと思います。
2023.03.30 公開
ビジネスのマネジメントにおいて、「KPIにより数値化させる」という考えは日本でも徐々に浸透してきていますが、完全に浸透しているようには感じられません。
日本企業ではマネジメントの教育が少なすぎると一般的に言われています。マネジメントにこそ、数字は絶対的に必要な要素です。
そこで今回はKPI(key performance indicator)を利用した数値化マネジメントについて改めて考えていきたいと思います。
2023.03.30 公開
今年に入り、ロシアによるウクライナ侵攻はますます苛烈さを増しています。一方では中国とアメリカのせめぎ合いや北朝鮮の問題、そしてアフリカで続く内戦など、いま世界のあちこちで、新たな国家間の課題が持ち上がり進行中です。そうした状況下で、国の領土保全と政治的独立、国民の生命・財産を外部の脅威から守る安全保障への取り組みは、かつてないほど重要性を増していると言えるでしょう。
2023.03.31 公開
2022年5月11日に成立した経済安全保障推進法では、現代の情報基盤というべきクラウドサービスが、その重要な対象に定められました。さらに同年12月には、経済安全保障を確保するための「特定重要物資」の1つとしてもクラウドが指定されています。いまやビジネスシーンはもちろん、私たちの日常生活とも切り離せない存在であるクラウドが、経済安全保障の枠組みに含まれるのは、むしろ必然のなりゆきといえるでしょう。藤谷氏は、こうした現状をどう見ているのでしょうか。
2023.03.31 公開
今週は国内最大級の国立研究所である産業技術総合研究所(産総研)が主催したスタートアップ/オープンイノベーションイベントに参加しました。結論、非常に濃く熱量のある内容でした。数年前までは、この手のイベントは研究者や技術者の理屈・志向が強くて、聞いていても「ありゃー」と思うことが多かったのですが、最近は課題やユーザーに寄り添う姿勢が出てきたなぁと思っていて、今回のイベントも「へー」と感心するピッチとディスカッションばかりでした。
2023.03.31 公開
特集「プロトタイピング・プロトピア」の第一弾は、プロトアウトスタジオ 菅原のびすけさんがアナログ業界や現場の方々をお招きしてデジタルやテクノロジーを活用している話などを伺っていくPodcast「プロトアウトラジオ」から。
食品検査会社で働くIT初心者の事務員の方が、業務の自動化に挑戦していたら、会社公認の社内サークル活動に発展し、社員が自発的にデジタルツールを用いて業務改善を実践する組織文化が醸成されたという素敵なお話です。
2023.03.31 公開
40年ギャップとは教育学で使われる用語の一つです。これは、子ども世代の教育カリキュラムが20年先を見据えて作られているのに対し、親世代は自身が受けた20年前の教育を基準にしてしまうことにより生じるギャップを指します。
実際20年前と現在を比較しても、インターネットの普及やそれに伴う生活様式、消費行動には大きな変化があります。
例えば職業でいうと、ITエンジニアや動画やアニメのクリエイターの需要が急速に高まっています。また、リモートワークの普及により、PCやスマホは仕事に必須の存在として「できて当たり前」な状態が要求されるようになってきています。
一方で、今の20代、30代が10代だった当時、アニメやゲーム、スマートフォン、PCは一部の大人にとって理解しづらいもので、アニメの視聴やゲームやスマートフォン、PCを制限されていた、という人も少なくないのではないでしょうか?
2023.03.27 公開
失敗に関してはちょっとした権威と言っていいくらい高頻度な『ミスミスの実の能力者』こと時田タイムです。失敗しすぎてもうどれが失敗なのかもわからなくなっているかも知れないです。(笑)
でも、失敗ってそんなに悪いことばかりじゃないと思うのですよね。
「失敗しないように」って気をつけすぎていると思い切った発想や提案ができないし(ただ、大きく失敗して取り返しのつかないことになるかも知れないですけど)、「失敗してもその後のリカバリをしっかり出来ればいいや」くらいに思っていると、以外とセンセーショナルな発想や提案ができたりするので、僕は気軽にたくさん失敗するように心がけています。(笑)
データのじかんの大川が「主筆の週報」として上司である野島編集長への週次レポートをメルマガで公開!
【先週】
日本鋳造協会IoT推進特別委員会主催のイベントがありました。前半は会員限定で菅原のびすけさんと下院近業2名と計4人で「人材の育ち方活かし方」をテーマにセミナーと座談会を行いました。後半は「鋳造IoTLT vol7」として8名のLT登壇がありました。データ可視化(BI)などデータをどう活用するかという話が多かったのが印象的でした。鋳造IoTLTの様子は動画で公開されています。
茨城県のベンチャー支援政策のピッチイベントがありました。つくば発シーズ起点のバイオ企業が多く大変興味深い発表でした。後半のパネルの中では「専門家同士のコミュニケーションは甘え」「研究者として若干嘘に近くなるくらい要約せざるを得ない場面も」「一方で研究者として尖る突き詰めると癖が強い広がり方をして熱量を持った質の高いコミュニティが出来てくるのがいい」という話がありました。
【今週】
経産省産構審の研究開発・イノベーション小委員会、経済産業研究所(RIETI)の製造業のデジタル化セミナーなどに参加します。
今回のタイムくんは、『失敗の科学』という書籍の紹介でしたが、ちょうど筆者も『ONE PIECE』の最新刊を読んでいる最中ということもあり、冒頭の1コマ目には大いに笑わせて頂きました。
ところでみなさまのうち、エンジニアリングに携わっている方で、『失敗』を経験されたことがない方はいらっしゃるでしょうか?
失敗の致命度はさておき、おそらく『失敗をしたことがない』という方は殆どいないと思っており、エンジニアという職業柄の筆者も、設計や検証において、成功と失敗をたくさん繰り返してきました。
今思うと不思議で仕方がないのですが、昔のエンジニアリングの現場では、たいして影響のない些細なミスでも、上司や周囲の人が過剰にエスカレートすることが多かったと思います。
エスカレートに巻き込まれたくないが故に、失敗の報告がしづらい、上長の機嫌のいい時にしか報告できない、が現場では常態化してしまい、結果としてそれが『隠蔽』を招くことになります。
筆者自身、失敗を報告せず、そのまま放置して、発覚したあとのリカバリで大変な思いをしたことが多々ありました。
その後、エンジニアリングの現場では、デジタル化が導入された時期を境に、『失敗』に対しての考え方が大きく変わったと筆者は実感しており、データで状況が分かるようになったせいか、『失敗を発生させる状況や環境、手法が悪い』と捉えるようになってきています。
例えば、『手作業によるデータの修正で間違った値を入力した』という失敗をしてしまった場合
・自動でデータの修正が行えないのか?
・修正前後のベリファイチェックを導入していないのか?
・第3者チェックやレビューは実施していないのか?
など、即ち『やり方』に問題がなかったか?について、建設的に議論します。
個人が極力失敗を招いてしまわないようにすることはDX(デジタルトランスフォーメーション)においての『業務・効率化改善』の一環でもあり、こういった『守りのDX』が進んだせいか、最近は失敗におびえることなく、イキイキとコト・モノづくりに取り組んでいるエンジニアが増えている気がします。
それでは次回もみなさま、どうぞ「データのじかんNews」をよろしくお願いいたします!!
(畑中 一平)
データのじかんは、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。
越境者の興味・関心を高める話題や越境者の思考を発信するレポート、あるいは越境者の負担を減らすアイデアや越境者の拠り所となる居場所などを具体的なコンテンツとして提供することで、データのじかんは現状の日本にあるさまざまなギャップを埋めていきたいと考えています。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。