



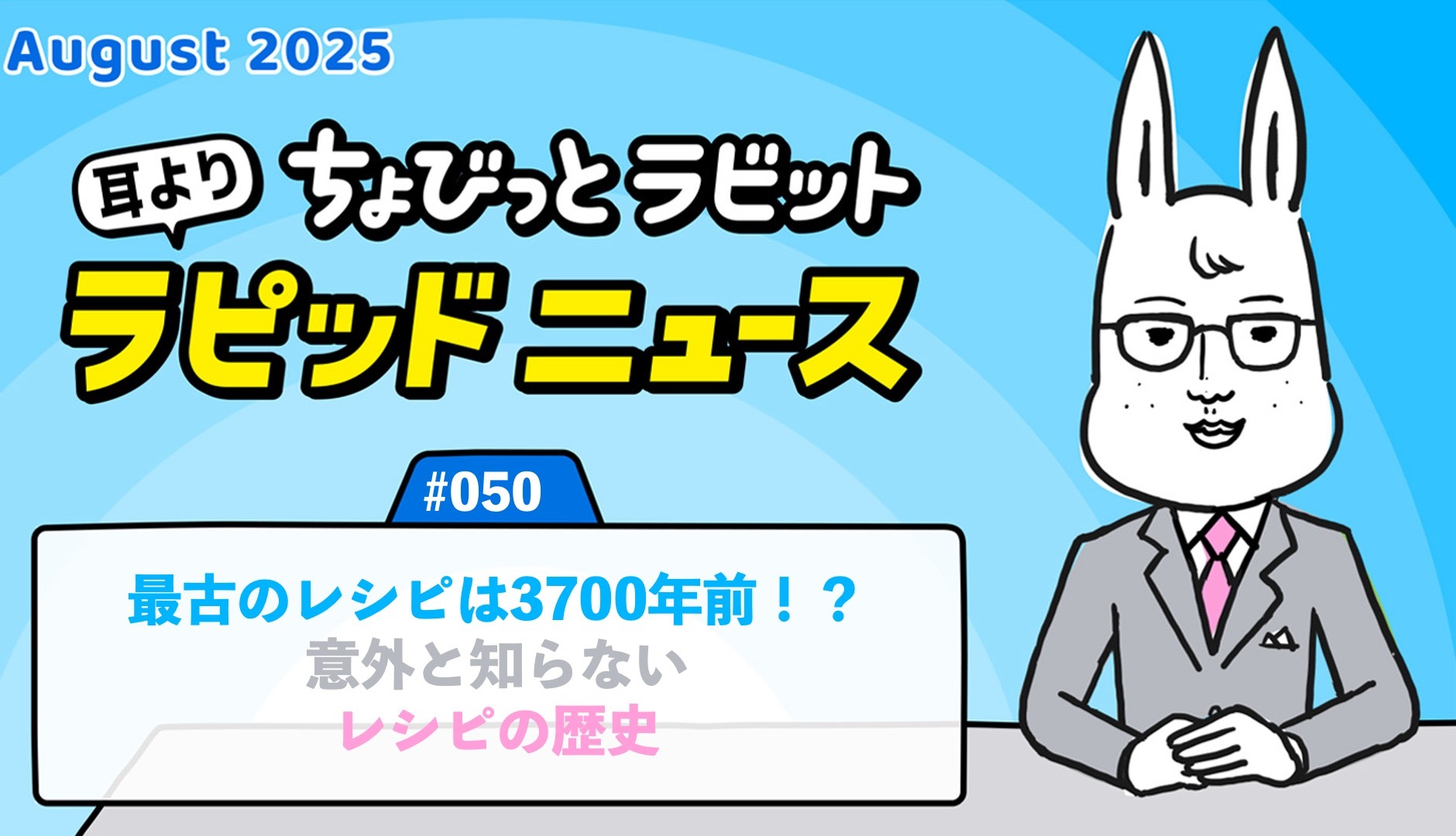
目次
まいどどうも、みなさん、こんにちは。
わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。ここ最近はChatGPT-5がかなり話題になっていますが、みなさんはもうお試しになりましたか?この1年ほどで、AIがいる生活がすっかり当たり前になってしまいましたが、みなさんはどんな風にAIを活用されているのでしょうか?
わたくしのお気に入りの使い方は、今日の料理のレシピをChatGPTとキャッチボールをしながら作っていく、というものなのですが、レシピというのは言って終えばデータベースのようなものであり、人類が体当たりで経験してきた食生活の中で「うまい!」と感じたものが記録として残されている人類の叡智の集合体といっても過言ではないわけであります。ある意味、人類の営みというものは「腹が減った!」「うまいものが食べたい!」「これはうまい!」「わしは満足じゃ!」のプロセスを単純に繰り返してきただけという捉え方もできるわけです。うまいもので胃袋を満たすことが幸福感をもたらす、というのは人類の歴史をどこまで遡ろうとも、おそらく全人類に共通している部分であり、うまいものを探求する知性こそが人類を発展させて来たと言っても過言ではないでしょう。
数あるデータ活用の中でも、レシピというものは日常生活にかなり直結している類のものであり、自分が体験したうまいを他の人とも共有したい、あるいは、他人が作り出したうまいを自分でも再現したい、という気持ちが具現化したものであります。最近ではインターネット上にありとあらゆるレシピが掲載されており、どうやって作っているのかを紹介しているYouTube動画なんかも星の数ほどあるわけなので、今の時代はレシピが有り余っており、うまいをいくらでも再現できる、という極めて恵まれた時代なわけであります。
しかし、レシピの歴史については意外とみなさん知らないのではないでしょうか?今回は、よほど興味がない限りなかなか調べないであろう「レシピの歴史」について取り上げてみたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。
人類がいつから調理をしているのか、というのはなかなか特定が難しいのですが、獲物を火で焼いて食べる、というのは170万年くらい前から行われていたのではないかと言われています。おそらく、レシピとして書くなら、材料:マンモスの肉 適量、調理方法:火にかけて焼く、などのシンプルなものだったと考えられます。焼く以外の調理方法は、少し前に取り上げた土器の発明以後であると考えられており、レシピに書いておくほど調理手順が複雑化するのは必然的にそれ以降となるわけです。
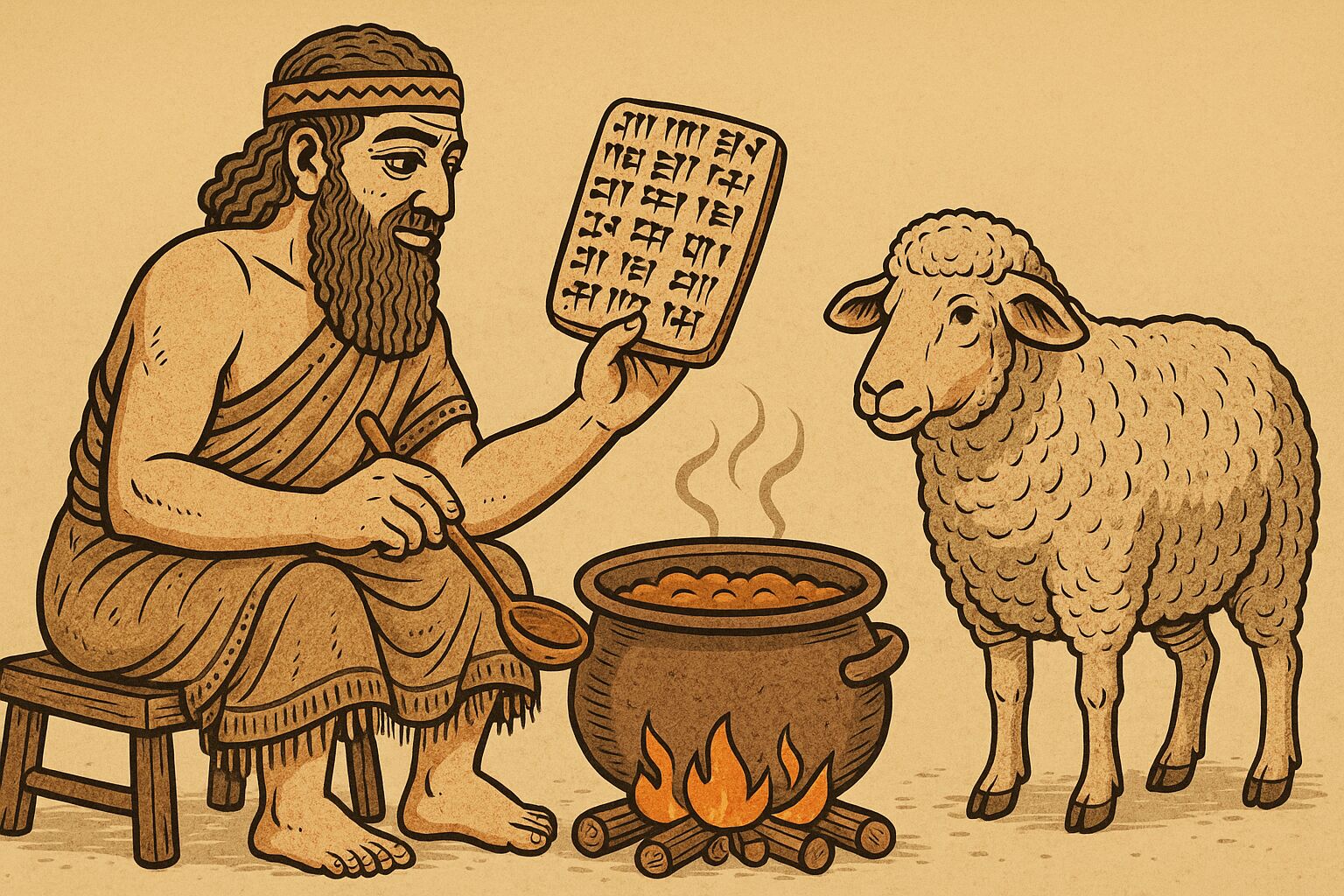
紀元前1700年ごろ、メソポタミア文明で世界最古のレシピ本が登場します。これは、なんと粘土板に楔形文字で刻まれた料理の記録であり、代表的なメニューは「羊肉のシチュー」や「野菜の煮込み」となっています。それ以前にもレシピは書かれていたのかも知れませんが、パピルスなどの記録媒体は保存性が低く、メソポタミア文明では粘土板に刻まれていたため、たまたま残っていたのではないでしょうか。
古代ローマに入ると食文化は一気に華やかな印象になります。4世紀末に作られたと言われるレシピ集『アピキウス』は家政婦向けの章、肉料理、豆料理、海鮮料理などジャンルごとに分かれていて、今の料理本とかなり似た構成になっていたそうです。ただ、一般庶民の食卓というよりは富裕層向けの内容となっていて、ワニの肉や孔雀、フラミンゴの舌など、変わった食材も登場する刺激的な内容となっています。とは言え、食文化がかなり成熟してきていることがここからは読み取れます。
中世ヨーロッパでは、修道院が料理文化を牽引していたと言われ、修道院の厨房は、単なる食事の場所に留まらず、当時の食文化、医療、学問、そして社会貢献の中心的な役割を果たしていたそうです。ひたすら神に祈り、その合間に野菜を切り、スープを煮込む生活。レシピは手書きの写本として受け継がれていきました。ビールの醸造なんかも修道院でやっていたらしく、ビール文化の発展と修道院は切っても切れない関係があるそうです。ビールにホップを使うようになったのも修道院の発明なんだそうです。
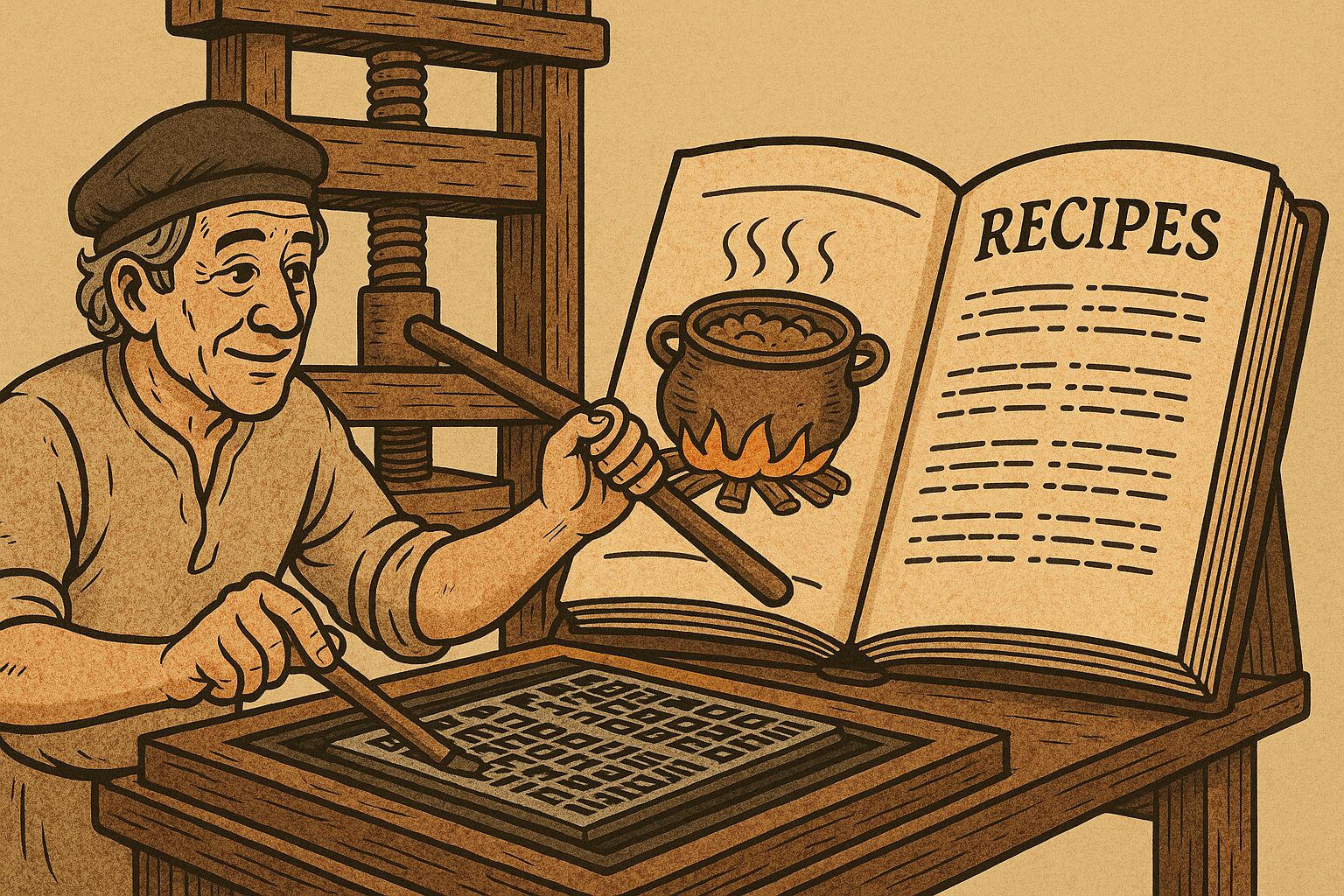
15世紀に入るとヨハネス・グーテンベルクが活版印刷術を開発し、大量生産されるようになった聖書と共にレシピ本も一般庶民に流通するようになります。イギリスでは「女中のための料理書」、フランスでは「貴婦人の家庭料理」など、身分別のレシピ本もこの時代に登場。料理格差社会の歴史もここに始まるわけであります。ただ、この頃から「分量」「焼き時間」「盛り付け」などに関する記述が増え、さらに再現性が向上。今のレシピ本にかなり近いものになってきています。
そして、20世紀になると、ホットケーキミックスやインスタントラーメンなども登場し、料理のスキルに関わらずそれなりにおいしいものが食べられる、という時代がやってきました。冷蔵庫・冷凍庫だけでなく電子レンジという摩訶不思議な調理器具も一般家庭に普及し、「レンジで3分」というレンジでチンするだけで食べられる冷凍食品やレトルト食品も登場。さらに、テレビは「料理番組」という新しいエンターテインメントを発明し、平野レミさんのような型破りのレシピが評判になりました。これまでは破ってはいけないルールだと思われていたレシピが、クリエイティブな自己表現として受け入れられ始めたのもこの頃だと推測されます。
そして、ついにインターネットの登場です。食材の後にレシピと入力すればいくらでもレシピが見つかる時代に突入し、人類は粘土板に書かれた古代文字を解読しなくても今日の夕食が簡単に作れるようになりました。それどころか、自分が作っておいしいと感じたレシピを世界に向けて発信できるようになり、誰でも彼でもレシピ作成が可能になったのです。
また、ズボラ飯、虚無レシピ、包丁を使わない、などいかに効率的に料理をするかについて追求するレシピも人気となっています。日常生活と食生活はどうしても密着しているわけなので、それぞれの時代のライフスタイルにマッチしたレシピが人気になる、というのは非常に興味深い現象ですね。そして、レシピの伝え方も写真付きのテキストが今も主流ではありますが、YouTubeなどによる動画レシピもかなり増えてきていて、そのわかりやすさたるや、料理本や写真では到底敵わない情報量となっているわけですので、料理初心者、という方でも興味さえあればいつでも料理を始められる時代になったわけです。

そして、最近では、わざわざレシピサイトを見なくとも、AIに自然言語で質問すればいくらでもレシピを作り出してくれるようになりました。その恩恵をわたくしは存分に受けておるわけで、冷蔵庫にあるものをAIに伝え、これで何ができるか、あるいはちょっと何か買ってくるとしたら何を買ってきたら良いか、六人分のコース料理を考えたいのだけど、こんなコンセプトで、などと相談しては日々教えてもらい、さらにそれをアレンジする方法を考え、それについての意見や提案をさらにAIに聞いたりしつつ日々の暮らしを送っている今日この頃であります。コスパやタイパに関する提案もしてくれるのでかなり重宝します。
また、人間の料理人に聞くとどうしても料理の知識が偏っていたりしますが、AIは世界各国の料理を多言語で検索してくれるのでアジア料理も中東料理もイタリアンやフレンチや中華や和食など、どんな料理のことについても普通に答えてくれるので、もうAIなしでは生きていけないような気持ちになったりもしております。
レシピ、という単語時代は、ラテン語「recipere(日常的命令形:recipe)」に由来し、元々は薬剤師への処方箋の指示だったそうです。それが転じて料理に用いられるようになったのは18世紀半ばからなんだそうです。思ったより最近なんですね。
ま、何をおいしいと感じるか、という味覚の進化というか変化というのは時代によってある程度はあるのかも知れませんが、食材とその組み合わせと調理方法というのは、数多くあるとは言っても有限なので、そう考えるとレシピ作りはよっぽど奇抜なものでない限り、既存のレシピの組み合わせでほとんど賄えるため、AIの特性とも非常に相性がよく、AIの便利な使い方のかなり上位に入るのではないかと個人的には思っております。はい。
というわけで、再来週の水曜日にお会いしましょう。ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!それでは、アデュー、エブリワン!
(ウサギ社長)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

