




毎年恒例のウイングアーク1st主催カンファレンス「ウイングアークフォーラム」。2020年は名称を「updataNOW 20」に刷新し、オンラインイベントとして開催しました。今年は10月12日の前夜祭を皮切りに16日までの会期中、65超のセッションでお送りしました。
今まさに直面している課題の打開策として期待されるDXですが、このまま欧米型のコピーでは日本のDXはうまく行かないのは誰もが気付いているはずです。では、あるべき日本的DXとはどのようなものなのか。モデレーターとして「フォーブス ジャパン」Web編集部編集長の谷本有香氏、パネリストに株式会社ウィズグループ 代表取締役の奥田浩美氏、株式会社フィラメント CCO/京都芸術大学・客員教授/ヤフー株式会社(当時)の宮内俊樹氏をお招きし、そこにウイングアーク1stのマーケティング本部 執行役員 本部長の久我温紀を加えたメンバーで、ディスカッションを行いました。

冒頭、モデレーターを務めた谷本氏は「『日本からDXを!』といわれてたいへん久しいが、一方で『日本のDXには何かが抜け落ちているのではないか』という議論もされている。議論にのぼりがちなDXには『近視眼的なのではないか』という指摘もある。ならば、どんなDXが日本から出てくればよいのか」と趣旨の説明し、ディスカッションがスタートしました。

フォーブス ジャパン Web編集部 編集長 谷本 有香氏
——本セッションのタイトルにもなっている「仮想現実時代」。これがいったいどのようなものなのか、まずは皆さんのご意見をお聞かせください。
奥田:仮想現実時代とは何かを説明する上で、私が取り組んでいる活動から紹介したいと思います。私は3カ月前からVirtual Reality×Wellbeing「ウェブビーイング・メタバース」という仮想空間で生活をしています。現実世界の10年後に老人ホームに入るのではなく、今のうちに仮想空間の中で老人ホーム的なコミュニティをつくり、そこにウェルビーイング系のスタートアップや個人事業主を集めてしまおう、というコンセプトのサービスです。
これはあくまで仮想現実(VR)のサービスの一種ではありますが、これからの時代はこのサービスのように、自分のからだと自分のからだではないものが“分化・統合を繰り返しながら進んでいく”というふうに考えています。

株式会社ウィズグループ 代表取締役 奥田 浩美氏
——何もかもがオンラインになるのではなく、リアルとオンラインが融合していく時代?
奥田:そうです。実際その仮想空間で3カ月間過ごしてみたのですが、最終的に一番大切だと思ったのが、自分の呼吸の感覚でした。自分の呼吸が今どんな状態になっているかというのが、仮想空間の中にいる自分や、どう幸せであるかという内面と密接に関わってきた。どちらかというと、自分の意識は自分の内側に向いてくるようになりましたね。この生活をもっと続けていけば、何か新しいものが見えてくるような気がします。
——宮内さんはどのようにお考えですか。
宮内:人間の歴史は人間の脳細胞の延長をいかにつくっていくかにあると思っています。例えば「都市」というのも、いわば人間が過ごしやすい場所をバーチャルにつくったようなものだと考えています。もしも同じようなものがオンライン上につくられ、さらにオンラインが分人化していけば、自分の拡張性が高まることになります。私は本業が音楽ライターということもありエンタメが大好きなのですが、仮にエンタメ系コンテンツを4〜5人の自分が同時に楽しめるのだとしたら最高ですね(笑)
実際、コロナ禍でエンタメのコンテンツがオンライン上で爆増していて、とてもじゃないけれど追い切れない。でも人間は『それをどうやったらかなえられるか』を考えることで課題を解決し、自らの欲望を満たしてきました。仮想現実時代は、今の生活を100倍くらい楽しめるようになるかもしれません。

株式会社フィラメントCCO / 京都芸術大学・客員教授 / ヤフー株式会社(当時) 宮内 俊樹氏
——すでにリアルな世界でも分人化が進んでいるのに、仮想現実時代ではそれがさらに進み、欲望をかなえられる分、満足度も上がる。たいへん興味深いお話です。久我さんは、どのようにお考えでしょうか。
久我:お二人のお話は「欲望」がキーワードでしたが、これはとても大事な要素です。デジタルは自分たちのフィジカルな環境になじんでくる過程なのかなと思っています。例えば、テスラの電気自動車はバッテリーをチャージするのには時間がかかりますよね。慣れて習慣化すると違和感がなくなるのかもしれませんが、『そこで何十分も充電する』という行為はなくせるはず。そこで中国版テスラと称されるNIO(上海蔚来汽車)では、バッテリーごと換えてしまう「バッテリーパック交換モデル」を打ち出しています。
それと同様、デジタルをうまく使えば自分たちがやりたいことをエフォートレスな(肩肘を張らない)状態でできるようになっていて、それをどう実装していくかをみんなで考えられる時代になってきているのかなと思います。

ウイングアーク1st株式会社 マーケティング本部 執行役員 本部長 久我 温紀
——お三方のお話を総合すると「DXはテクノロジーを入れればそれでよい」というわけではなさそうです。DX推進の動きは政府・企業の間で活発ですが、現状の日本のDXをどのように見ていますか。
奥田:私は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「IT人材白書」の委員を務めていますが、IPAでは2年ほど前から企業のDX推進の重要性を提言しています。実際に多くの企業でDXの取り組みが進められており、その路線自体は継続してほしい。ただ「DXのDは“Digital or Die”」といわれるくらいに、DXは「当たり前に取り入れるもの」「取り入れなければ死に絶えるもの」。企業各社は“何”をトランスフォーメーションするのか、ということを考えながら参加していく姿勢を求められています。
宮内:Yahoo!天気のようなコンシューマサービスをつくってきた立場から思うのは、現代人にとってスマホはほぼ自分の“手”のようなツールになっていますよね。アプリが思ったように動かなければすごくイライラするし、自分のスマホに入れたアプリに慣れてしまうと会社で使うITサービスの欠点にも気付いてしまったりする(笑)。そうしてせっかく個人のクオリティーやスキルが上がってきているのであれば、企業はそうした個人(ユーザー)の意見をもっと尊重してもよいと思います。
——これまで企業のDXは「より便利に・より効率的に・より合理的に」ということが重視されてきたように思いますが、もっとユーザーの感覚・感情が重視されてもよいはずである、と。
宮内:本来的なDXの考え方では「デジタルで顧客の体験をよくする」という意味合いが強かったことからも、それはうかがえます。特にコロナの影響が及んだ今「どんなツールを入れて、それによっていかに効率を上げ、どのくらいコストを下げるか」みたいな議論に終始されているのが残念でなりません。
奥田:DXという言葉は2000年代前半のスウェーデンが発祥ですよね。基本的には「デジタルが人々の暮らしにある課題を解決する・生活を変えていく」という意義に成り立っていた。決して「産業のデジタル化」ではなかったはずです。宮内さんの先ほどのお話にあったように、個人の間ではすでにデジタル化が進み、みんなが心地よいサービスを選択しています。それなのになぜ、企業でDXがうまくいかないのか。それを考えなければいけないと思います。
——それそのものが「目的化」されてしまいがちな日本のDXにおいては「DXで何を実現したいのか」という視点が重要なような気がします。
久我:お二人がおっしゃっていた通り、DXは人の生活を豊かにする手段です。私たちはすでに毎日の生活が非常に豊かな状態で、身の回りにはさまざまなコンテンツがあふれかえっていますから、その中で新しく何か価値をつくっていくには「モノをつくって、売って、終わり」という旧来の考え方ではなく「どんな体験に豊かさを感じるのか・どんな体験に心地よさを感じるのか」という視点が必要です。それは企業のDXにも同じことがいえるのだと思います。
——今後、日本的DXを追究していくのならば、どんな要素が必要になると思いますか。
宮内:日本人は「0→1の創造性が低い」とかいわれますよね。実際ITの領域ではアメリカや中国に遅れをとっているのかもしれません。でもイグノーベル賞では多くの日本人受賞者を輩出しています。“ちょっとずらす”のが得意なんですよ。今は遅れをとっていても、やがて日本的な感性で新しい価値を生み出せるのではないかという期待値は持っています。そのときには、当社の安宅和人が言っているように「妄想力」がとても大事になると思います。

久我:日本語にしても「雨」という言葉の呼び名には400語超あるとされています。多様性というべきなのかどうか分かりませんが、日本は価値をつくったり見出したりする技術があると私も思っています。それもまた「欲望」が原動力なのかもしれません。
奥田:「欲望」という言葉を使うと、どうしても何か前のめりにそれを欲しているような印象を与えてしまいますが、私の考える欲望は、もっと自分の本質にある「創造的な欲望」です。人々の生活が忙しくなり、身の回りをプロダクトやサービスに囲まれ、目も耳も時間でふさがれてしまうような時代。そんな時代下で「そもそも自分は何をやりたいのか」ということとデジタルをマッチさせる際には、スティーブ・ジョブズが禅の世界に触れてプロダクトをあえてシンプルにしたのと同じように、仏教のような精神世界的な意味合いを知っている日本人が強みを発揮できるのかもしれないです。
——他方、個人的欲望もさることながら、社会的欲望に答えてこなかったのも日本だと思います。本当は困っている人がいて、その方たちが使いたいテクノロジーがたくさんあったはずなのに置いてきぼりにしてしまった。社会的弱者のような方にテクノロジーが届かなかったのはなぜなのか、また今後どうあるべきなのか。
奥田:私は社会課題とITというテーマに10年間取り組んできました。その経験を踏まえれば、これまでは経済的な優位性・合理性に負けてきたことを実感しています。つまり社会課題というものがどこか“キレイゴト”のように捉えられていた。本来の社会課題をオモテで話せば興味関心や貢献が集まり、お金もまわる。私たちからはそれが見えていても、人を説得させられるだけの時代ではなかったような気がします。
宮内:ただ、今はダイバーシティやインクルージョンなどに関心が集まってきました。もともと日本の社会で大切にしてきた価値観・文化でもあるので、もう一度それと向き合えば何かヒントがあるように思います。私はアートやカルチャーも好きなのですが、テクノロジーとそれらをかけ算したり、コミュニティをクロスさせたりしないと、イノベーションや新しいことは生まれない。日本の場合はその点においてはまだ課題を抱えているとも思っています。
久我:どういう視点で社会を捉えているかも大きいのかなと思っています。日本で見る社会課題と世界・宇宙レベルの社会課題はやはり異なりますし、正解がない領域です。それを考えていくためにも、誰かに発信したりディスカッションしたりする習慣が必要なのかも知れません。
——本セッションも終わりの時間が近づいてきました。お三方、最後に一言ずつお願いします。
奥田:DXも会社経営も、そして人生も、片足ずつ歩んでいくことが何より大切です。片足立てはとても不安定で、ときによろめいたりもするかもしれません。でも、もう片足を自由にしておけば、次の一歩を踏み出せます。ぐらぐらしながらも一歩ずつ歩みを継続していただきたいです。

宮内:会社の中ではどうしても経費削減とか業務効率化といった切迫観念にかられてしまいがちです。でも今一度「自分たちが何をしたかったのか」を振り返っていただきたい。それをクリアにしてから、トライ&エラーで小さく進めていくのがDX推進成功の近道です。その先にはデジタルでビジネスを拡大する戦略などがあると思いますが、さらにその先では日本古来の妄想力を使ったビジネス戦略を立てていただきたい。欧米や中国にはない、日本による第三極をつくっていければ、と思います。
久我:自分がどうありたいのか、あるいは、あれやってみたい、これをやったらすごいということを自分自身に言い聞かせる、その大切さを改めて感じました。人類が誰も月に行ったことがないときに「月に行きたい!」と宣言するのはなかなか壮大で勇気がいることだったと思います。でも、かつて誰かがそれを妄想したからこそ、人類は実際に月に行けました。人の意思があって、そこで始めてテクノロジーやデータが活用できます。そんな妄想に時間を投じていきましょう。
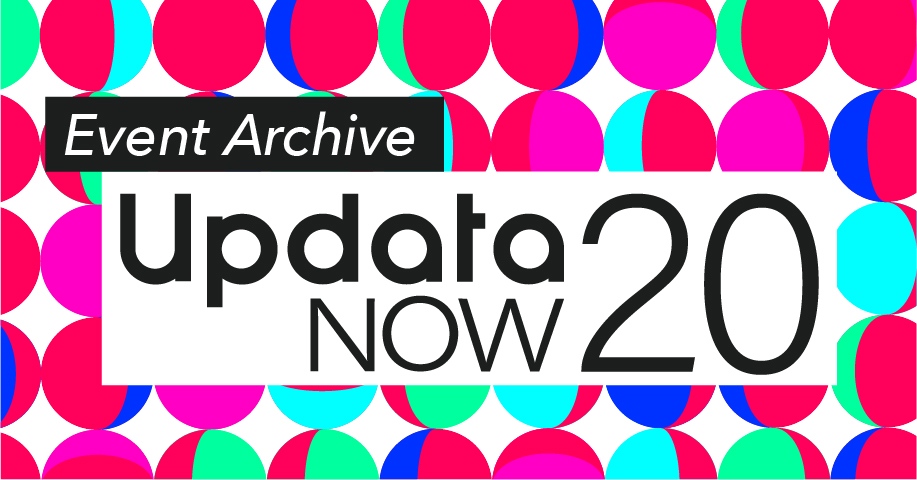
ウイングアーク1stが毎年開催している国内最大級のビジネスイベント「ウイングアークフォーラム」。今年は「updataNOW 20」と名前を変え、10/12~10/16にオンラインで開催しました。 登録数15,000名以上、セッションの総視聴数は40,000を迎えました。 データ活用とDXを基軸に、ネクストノーマル時代に向けた洞察から、各業界・業種の先進的な成功事例、そして、ビジネスを加速する最新のサービス紹介まで、65を超えるセッションの大部分をアーカイブ配信として公開いたしました。 見逃した方はもちろん、もう一度視聴したい方も是非ご覧ください。
見逃し配信は終了いたしました。
ご覧いただき有難うございました。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

