・「BIツールとは?どう使えばいいの?」
・「BIツールを比較する際のポイントは?」
このようにお悩みではありませんか?
BIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業に蓄積された大量のデータを集めて分析・見える化し、迅速な意思決定を助けるためのソフトウェアのことです。BIはBusiness Intelligenceの頭文字。Intelligence=インテリジェンスは知能/理解/知恵などを意味するので、BIはビジネスの意思決定に関わる情報という意味になり、BIツールはビジネスの意思決定をする情報を分析/可視化などするツールとして定義されています。
この記事では、BIツールの仕組みや比較ポイントなどを解説しています。記事の後半では、BIツールの活用方法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
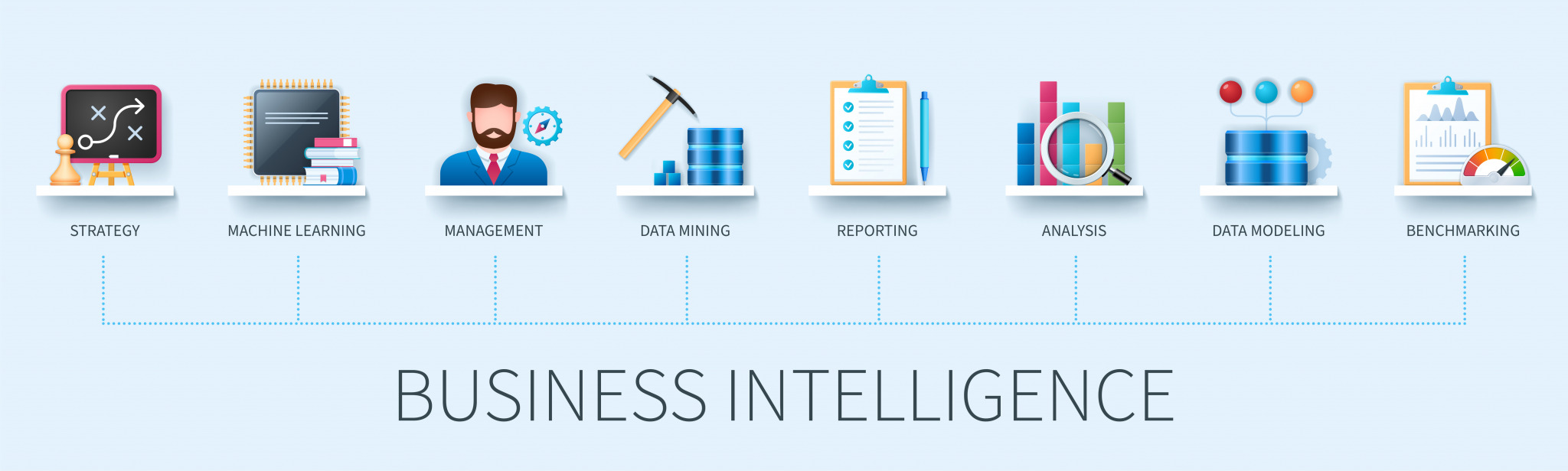
企業がBIツールを導入する理由は、経営の最適化が図れるからです。
従来のビジネスは勘や経験に依存していました。
ところが昨今は顧客の要求・行動、ビジネスの複雑化・多様化が進み、「今、何が売れているのか?」「顧客は何を求めているのか?」が洞察できない状況に陥っています。
ヒト、モノ、カネの流れはデータという形で蓄積しているものの、以下のような課題により「データを活用した経営の最適化」の実現が阻まれてしまいます。
①膨大なデータ量が必要
②データの集計や加工に労力を割けない
③分析方法、結果の活用方法が分からない
これらの課題の解決と同時に様々な経営施策を支援する「BIツール」をご存知でしょうか?
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールとは、ビックデータから必要な情報を抽出し、ひと目でわかるように分析するツールのことです。BIツールを導入することで、データの蓄積や活用に関わる課題を解決し、下記の実践により、経営戦略の精度の向上とリスクの削減を実現します。
①利益を増大、損益を削減する方法の導出
②顧客行動、市場動向の把握と予測
③競合との差別化要因の特定
④自社が抱える問題や課題の発見、対策案の策定
以下の記事では、「BIツール」がビジネスで使われるようになった背景を解説しています。従来までのBIツールがどのように使われてきたのか、今後どのような変化をしていくのかなどについて詳しく紹介しているので、ぜひご覧ください。
BIツールは大きく分けて次の4つの仕組みを備えています。
①インプット
②集計・分析
③可視化
④インサイト
データの入力(インプット)から経営の判断に活用されるインサイトの出力(アウトプット)までの大まかな流れを紹介します。
BIツールでは、データのインプットが可能です。BIツールはデータを源泉にするので、データソースが必要です。社内基幹システム(ERP/CRM/SFA/Excel/WEB)、外部(第三者・2次・購入データ)、IoT、スマホ、SNS、オープンデータ、R連携などがそれに相当します。データは、DWH(データウェアハウス)、ETL(Extract・Transform・Load)を介してBIツールにインプット(入力)します。
BIツールでは、データの集計・分析が可能です。BIツールのエンジンが実施する主機能で入力したデータの収集、分析、集計を実行します。OLAP分析、データマイニング、シミュレーションがこれに相当する機能で、これらについては以下の見出しで詳しく解説しています。
BIツールでは、データをわかりやすく可視化することが可能です。BIツールが集計・分析した結果は、そのままだと数字の羅列になるので、視覚的に捉えられるようグラフなどに置き換えて可視化します。可視化については、以下の見出しで紹介します。
BIツールでは、データのインサイトを抽出することが可能です。インサイトとは自動分析機能のことで、分析対象として最適なデータへアクセスし、そこから統計的にもっとも関連性の高い結果を導き出し、分析担当者のようにグラフと説明文で回答する機能です。BIツールのアウトプットとして、経営の意思決定の判断に役立ちます。
次に、BIツールの選び方を3つ紹介します。
①データの抽出・検索方法はわかりやすいか
②連携するSaaSやアプリに対応しているか
③Excelへの出力に対応しているか
自社に最適なBIツールを選ぶためにも、ぜひご覧ください。
BIツールを選ぶ際は、データの抽出や検索方法のわかりやすさを確認しましょう。BIツールでは膨大なデータから必要なデータを検索するのがほとんどです。そのため、情報抽出のしやすさはそのまま使い勝手に直結します。なお、情報抽出の方法は以下の2パターンであることが多いです。
|
スクリプト(SQL)の記述 |
検索内容を細かく指定したりデータ分析の自由度が高い |
|
アイコンやボタンから選択 |
スクリプトの記述が不要で直感的に操作できるため負担が少ない |
BIツールを使う目的や自社への負担などから情報抽出の方法は検討しましょう。
BIツールを選ぶ際は、連携するSaaSやアプリに対応しているかどうかも確認しましょう。既に自社で活用していたSaaSやアプリなどのデータをBIツールでも使いたいなら、BIツールのコネクタが対象のSaaSやアプリなどに対応しているかどうかの確認は必須です。CSVデータを活用してデータ連携する方法もありますが、はじめから対応しているBIツールを選ぶ方が負担が少なくなります。
BIツールを選ぶ際は、Excelへの出力に対応しているかどうかも確認しましょう。BIツールで抽出・分析したデータを共有したり加工したりする際には、Excelで管理するのがおすすめです。そのため、Excelへの出力が可能かどうかも重要なポイントです。
BBIツールとは「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、企業に蓄積された大量のデータを集めて分析し、迅速な意思決定を助けるためのツールです。経営管理や売上のシミュレーションなどに活用できるもので、近年BIツールを利用する企業が増加しています。BIツールには、例えば以下のような機能が備わっています。
①抽出されたダッシュボードからデータを俯瞰
②OLAP分析をして仮説を検証
③データマイニングを行いデータの性質を整理
④シミュレーションから得た予測で意思決定
企業に蓄積されているデータは、セミナー参加者リストであればエクセル、営業活動は営業支援システム(SFA)、売上は基幹システム(ERP)、サポート・コールセンターは顧客管理システム(CRM)など、会社内で分散しているケースも多々あり、こういった情報を繋ぎ、分析、可視化することにより、意思決定のスピードと精度を高めることに寄与します。
続いて、それぞれの機能について詳しく解説します。
BIツールには、抽出されたダッシュボードからデータを俯瞰する機能が備わっています。例えば、「レポーティング」はダッシュボードなどで情報を共有し、必要に応じて利用できるものです。KPI(重要業績評価指標)のチェックや異常の検知が可能になります。近年、IoTデータを集めてBIで可視化するなど、リアルタイムでデータの収集・可視化を実現するBIツールも登場しています。
以下の記事では、そもそもダッシュボードとは何かを解説しています。ダッシュボードを活用するメリットやデメリットも紹介しているので、参考にしてください。
BIツールには、OLAP分析の機能が備わっています。「OLAP(オンライン分析処理)分析」機能は、蓄積されたデータを多次元的に扱って集計値の参照ができ、分析することでさらにデータからの知見を深めて詳細にするものです。インメモリ型のBIツールは、これらの処理をメモリ上で素早く行えるメリットがあります。
以下の記事では、OLAPツールの基礎知識や役割について解説しています。OLAPツールをより効果的に使うためにも、ぜひご覧ください。
BIツールには、データマイニングの機能が備わっています。「データマイニング」機能はデータを統計的に処理するのでマーケティングに有効で、相関分析などの複雑な統計分析を行うことが可能です。マイニング(mining)とは「発掘」という意味で、「データを分析し、その中から(価値ある)法則を導き出す」という意味で「データマイニング」と呼ばれています。「OLAP分析」が、データの関連性を多次元で見るのに対し、「データマイニング」は、重回帰分析やディシジョン・ツリーといった統計式を用いてデータを分析することを指します。
以下の記事では、インターネット上の文字をデータ化するテキストマイニングについて解説しています。文字データの解析方法や活用例も紹介しているので、ぜひご覧ください。
BIツールには、シミュレーションの機能が備わっています。「シミュレーション」は、過去のデータをもとに予算などを決定する際に、「プランニング」機能でシミュレーションして分析し、結果を計算して最適な数値を導き出します。
BIツールは専門的な知識がなくても利用することが前提で作られているものもあり、一部の人間ではなく、複数の人間で、これらの優れた分析機能を活用し、共有をすることで、業務の効率化が期待できるでしょう。
以下の記事では、BIツールを導入した方が良いかどうかの基準について詳しく解説しています。BIツールで解決できる課題や活用方法も紹介しているので、BIツールの導入に迷ったらぜひ参考にしてください。
企業経営のデータ活用は、経営部門だけが実践しても競争力や売上が向上するわけではありません。経営部門の傘下に位置する営業、マーケティング、人事部門、現場部門の活用も必要不可欠です。BIツールは企業の様々な部門の活用シーンに合わせて、様々な分析や支援方法を備えています。
| 業種・業務 | 分析・支援の種類 |
| 経営部門 | 経営分析・財務分析、経営支援、予実分析など |
| 営業部門 | 営業分析・売上分析、営業支援など |
| マーケティング部門 | 顧客分析、販売時期分析、エリア分析など |
| 人事部門 | 人事データ分析、残業分析など |
| 流通・小売業の現場部門 | ABC分析、在庫分析、バスケット分析など |
| 製造業の現場部門 | 故障率分析、不良率分析、購買分析など |
| バックオフィス全般 | 帳票自動作成など |
BIツールのメリットは、大きく以下の3つです。
①レポート作成が短時間でできる
②膨大な情報の分析をリアルタイムかつスピーディーに行えるので問題の早期解決を目指せる
③システムを横断してあらゆるデータを連携させたデータ分析ができる
従来では専門スキルを持つ人だけが情報の収集や分析を行っていましたが、BIツールを利用することで専門家でなくとも、必要なデータを分析し情報を活用できるというメリットが得られるようになりました。企業がBIツールを導入し、データの分析・加工を行いマーケティングに活用することで業績を伸ばす効果も期待できます。BIツールは複数か所に散在する企業内データを1か所に集めて分析できるので、今までよりも高度な分析が可能になりました。そして、各部署の現状把握が可視化され、わかりやすいデータを分析することが容易になったのです。
企業全体で「誰が、何のために」という目的を共有することで、はじめてBIツールのデータ分析による問題の洗い出しが可能になるといえるでしょう。
BIツールのデメリットは、導入時に集中しており、活用のプロセスが成熟すれば、どれも解消され、残るものは以下のような ラーニングコストの発生くらいになります。
①BIツールを始め、データを活用するための設備投資が必要
②BIツールを使い続けるためのラーニングコスト(保守・更新費用)の発生
③従業員への教育、業務プロセスの改善が必要
しかし、デメリットもBIツールを導入したことによって向上した売上、削減したコストがラーニングコストを上回れば、解消されることになります。
BIで、データを収集・可視化しただけでは、何の価値も生まれません。これを体系化・整理して、価値を生み出す手順としてDIKW(Data, Information, Knowledge, Wisdom)という情報の分類方法があります。これはPMBOK(Project Management Body of Knowledge)で用いられる情報の分類手法で、以下のような4層のピラミッド構造から成っています。
①データを収集する
②集めたデータに定義・意味付けをして情報にする
③情報をビジネスに照らし合わせて汎用的な知識にする
④さらに実践的な場面での活用を経て知恵にする
といった4層のピラミッド構造から成っている。
以下の記事では、データ活用の手法をモデル化した「DIKWモデル」を解説しています。データの分析・活用のためにぜひ知っておいて頂きたい情報なので、参考にしてください。
データを可視化し、知識にするところまではIT部門、データアナリストの領域でも可能ですが、知識を知恵にし、そこから意思決定、アクション、事業、人、組織、企業を動かし、成果に繋げるところは、IT部門、データアナリストだけできません。
それでは、BI活用に成功していると言われている企業では実際どんな使い方をしているのか、事例を見てみましょう。
結論から申し上げると、企業にとって成功要因とならなければBIツールの導入は不要です。
BIツールが注目されている理由としては、企業側のニーズとして以下が挙げられます。
➀企業の競争がより激しくなっている
➁早いスピードのPDCAが求められている
➂意思決定のスピードがより求められている
➃意思決定をする判断するための情報の精度・スピードが必要となっている
また、技術的には以下の要因があるでしょう。
➀クラウド型のBIツールの普及によって、低コストで始めることが可能になったこと
➁IoT・スマートフォンなどデータの取得方法が多様化・容易・高精度になったこと
➂ビッグデータを処理する速度・精度が大幅に進化したこと
そして、もっとも重要なことは、我々の志向・行動が以前にもまして多様化したことによる課題が挙げられます。多様化した人・行動のデータを分析し、そこからインサイトを得るためには、これまでの人の処理・経験・勘だけでは不十分であり、大量のデータ・FACTに基づく、分析、インサイトを得ることが、企業の競争力維持のために必要になってきている背景があります。
上記のようなニーズ・背景・課題を解決する手段として、BIツールが最適解・KSFになっているため、注目されているのです。逆説的に言えば、BIが目的・ゴールのためのKSFにならないのであれば不要ということです。また、Excelや人による可視化など他のツールや役割で代替できるのであれば、他の選択肢でも問題ありません。
フィットネス事業を行っている東急スポーツオアシスでは、BIツールによって顧客との接点を見逃さず、多様化するサービスから顧客に最適なものを提案しています。詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
BIツールを選ぶ際には、ITの専門家でなくても使うことができるようなものがいいでしょう。
「情報を集めてもBIツールの活用が難しい」という場合も多いので、企業で全社、全社員がBIツールを活用するためには、定期的な研修や担当者が巡回することが必要です。BIツールを導入し業務の効率化を実現した事例として、従来のExcelや手書きによる帳票作成をBIツールに移行したことで時間の短縮・コストの削減を達成したケースがあります。BIツールを活用している企業ではペーパーレス化も進んでいます。
また、レポート作成のスピードの遅さの課題をBIツールによるデータの可視化で解決し、レポート作成コストの大幅削減と経営判断のスピードアップが図れたケースなどもあります。グループ会社のIT化の必要性からBIツールを導入した企業では、グローバルレベルでのデータの分析や最適化が可能になり、拠点ごとにバラバラだった企業情報も日次で管理して改善を迅速に行えるようになりました。
このように、BIツールを企業全体で活用しスピーディーな情報分析をすることで、企業のマーケティング戦略が的確になり業績を上げることも期待できます。
BIツールは企業に様々なメリットをもたらしますが、既存の業務プロセスの変更も余儀なく必要となるため、導入は慎重に進めるべきです。導入にあたってのポイントは以下になります。
①自社で抱えている問題や課題がBIツールで解決できるか?
②従業員がBIツールを活用できるか?
③導入実績はどの程度か?同業種の活用事例はあるか?
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
BIツール導入の際は、「自社の課題がBIツールによって解決できるかどうか」を吟味しましょう。
BIツールを導入すれば、自社の業績が向上する!と考えがちな企業は実は少なくありません。問題の原因、課題の解決策が特定できずとも、これらを十分に整理しておかなければ、BIツール導入が解決策になりうるか?が区別できません。
BIツール導入の際は、「従業員がBIツールを活用できるかどうか」を吟味しましょう。
BIツールは製品によって使用性に大きく差があります。プログラミングを必要するものもあれば、マウスと自然言語のキーボード入力だけで使用できるノンプログラミングやノーコード・ローコードのものもあります。導入する部門・従業員とBIツールに求められるITスキルにミスマッチが生じると自然と活用を避けてしまうため、運用方法については十分な検討を必要とします。また推進にあたってはBIツールを提供する側の支援も必要不可欠なのでサポート体制も十分に調べておく必要があります。
BIツール導入の際は、「同業種での導入実績」を確認しましょう。
データ活用、デジタルトランスフォーメーション(DX)への関心に伴い、BIツールの開発・販売に参入する企業が増え続けています。導入実績・活用事例が少ないBIツールは、提供側も市場で試行している状況のため、様々なリスクが潜在しています。また活用事例は自社の問題・解決のヒントやアプローチにもなりますので、導入にあたってはぜひとも参考にすべきです。
最後に、BIツールの種類を3つ紹介します。
|
BIツールの種類 |
特徴 |
|
無料系BIツール |
OSSが採用されており自分で改良できるツールが多い |
|
国内系BIツール |
多機能かつ専門性の高いツールが多い |
|
海外系BIツール |
現場に即したサポートが充実しているツールが多い |
それぞれの種類について詳しく解説します。
BIツールの中には無料で使えるものも存在します。特に、大手IT企業が無料で提供していることが多く、手軽に利用できます。無料系BIツールは、多くの場合OSS(オープンソースソフトウェア)の形が取られており、使用者によって自由に機能を改変することが可能です。
ただし、無料系BIツールには以下のようなデメリットがあります。
・セキュリティ対策が万全でないことがあり、データ収納にリスクがある
・一部機能に制限があることが多い
・カスタマーサポートが充実していないことが多い
有料のBIツールであればセキュリティ対策が万全であったりサポートが充実していたりすることがほとんどなので、データ活用の規模や目的に応じて選びましょう。
日本国内で作られたBIツールは、日本の現場に即したサポートが充実しているものが多いです。英語や専門用語が多いBIツールではかえって作業効率を落としてしまう可能性があるため、誰でも使いやすい点が大きなメリットでしょう。さらに、セミナーが開催されていることも多く、はじめてBIツールを導入する場合でも軌道に乗せやすいのが特徴です。また日本特有のビジネス習慣に合わせた分析レポートやダッシュボードなども準備されていることもあります。
海外で作られたBIツールは、多機能かつ専門性の高いものが多いです。「BI」の概念はもともとアメリカで生まれたこともあり、シェア率は海外のBIツールの方が高い傾向にあります。海外製と言っても日本語に対応しているものも多く、データ分析を専門として担うメンバーが在籍している場合やより高度なデータ分析をしたいのであれば海外系BIツールがおすすめです。
人々の嗜好・行動が多様化したことで、企業が人・行動のデータを分析し、そこからインサイトを得るためのKSF(Key Success Factor = 重要成功要因)の一つとしてBIツールが注目されています。
「BIツールのトリセツ」では、BIツールの概略をまとめたホワイトペーパーについて図を交えながらわかりやすく解説しています。ダウンロードして頂くことで、自社資料の教育や学習用の教材、社内資料作りに活用できるので、少しでも興味がある方は参考にしてください。
最後は、補足的にユーザーの視点からBIの進化をたどってみたいと思います。
初期はBIツールというカテゴリーはまだ存在せず、特定のデータ活用の機能に特化したシステムとして、基幹システムから派生したものがほとんどでした。当時よく使われたものとしては、「意思決定支援システム」「経営情報システム」「戦略情報システム」といったものが挙げられます。ただ、いずれも経営者や決定権者が自分で操作して分析を行うことはできず、リアルタイムな意思決定にはほとんど貢献できませんでした。
1989年にドレスナー氏がBIを定義し、オープンシステムの普及により異なるベンダー間でのデータ連携が可能となり、データ分析の民主化時代が到来しました。ネットワーク化と小型コンピュータの登場により、エンドユーザーがデータにアクセスし分析できる環境が整備されました。データウエアハウス(DWH)の登場により、データの効率的な蓄積と分析が可能となり、BIツールの進化が加速しました。
2020年代には、BIツールは経営層から現場まで広く普及し、経営層からライン・オブ・ビジネス(LOB)の現場まで、全ての人々が自分たちのビジネスのパフォーマンスを最大化するためのツールとして欠かせない存在になっていきます。第4世代BIツールでは、データベースやDWHとのシームレスな連携やAI活用が進み、リアルタイム性やオンデマンド対応が強化され、ビジネスのデシジョンツールとしての重要性が増しています。
[sml-is-logged-in-hide]
無料|新規会員登録のご案内
・すべての資料ダウンロードができます。会員登録済みの方はこちら
[sml-show-template]
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。