



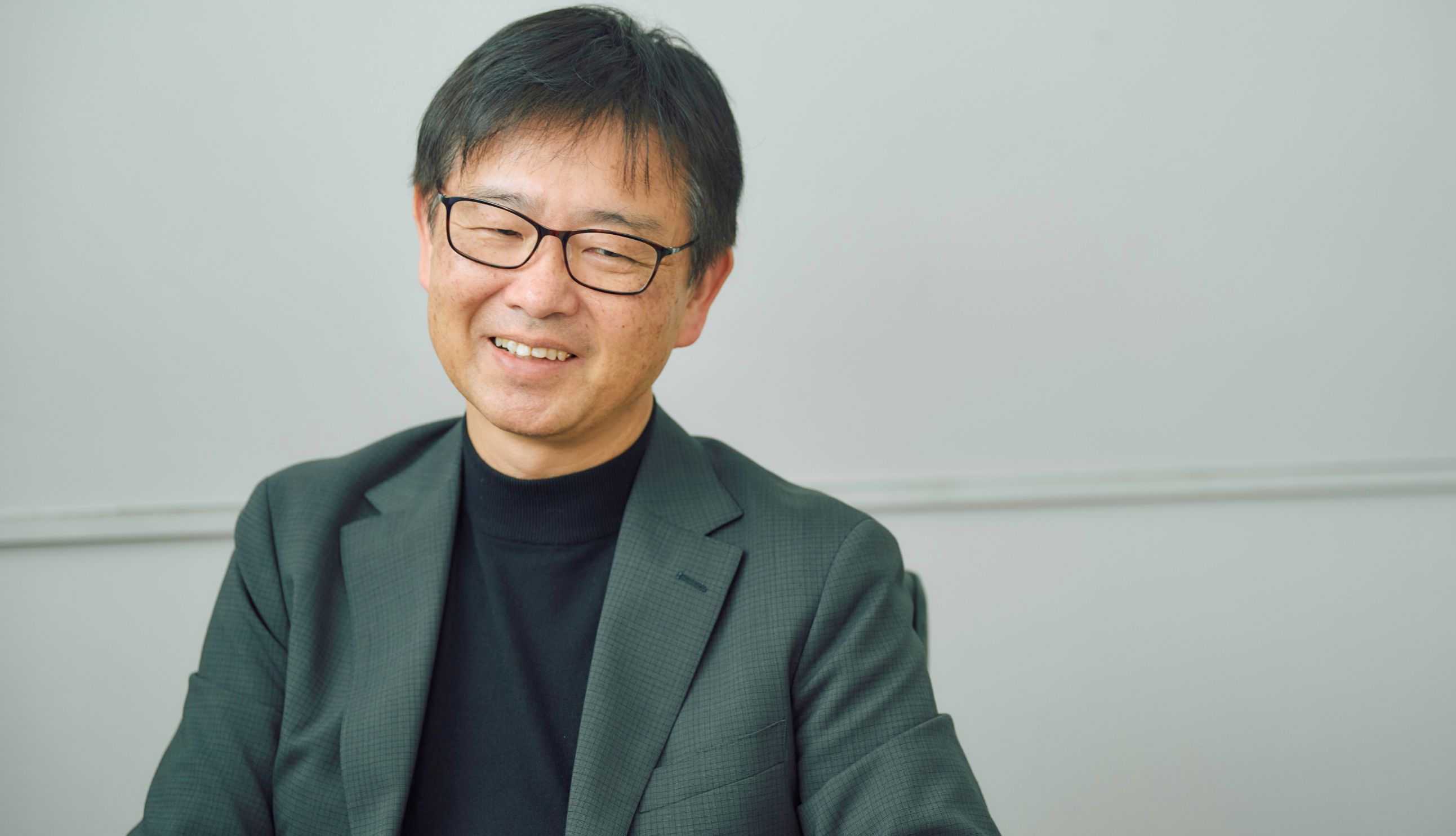
田中氏は現在、ヤンマー建機株式会社の品質保証部・品質企画グループとDX推進グループのリーダーを兼任している(*2024年3月時点)。 頭がスッキリしている朝早い時間から業務に取り組む同氏は、ITだけでなく組織運営にも精通し、マネージメントとITの架け橋として「草の根DX」を推進中だ。
ヤンマー建機に入社したのは2020年のことだ。「35年間日系グローバル企業に身を置き、機構設計や海外工場への出向、海外を含めた調整などを経験しました。帰国後は、ソフトウエア開発のプロジェクトマネージャーや商品企画、グローバルのユーザーをサポートする部門でデータの可視化などにも取り組みました」(田中氏)と現在に至るまでに経たキャリアを説明する。

ヤンマー建機株式会社 戦略部 DX推進グループ 兼品質保証部品質企画グループ 課長 田中 重信 氏
長年のキャリアをチェンジするきっかけとなったのは、九州から東京への転勤が決まった際に開かれた送別会だったと明かす。そこで、ヤンマー建機に転職していた先輩と再会し、「品質保証部で、海外と英語でコミュニケーションできる人材を探している」と誘いを受けた。
ヤンマー建機に入社後、田中氏は品質保証部でのデータ活用を推進。MotionBoard、Dr.Sum、SPA(*現invoiceAgent)、UiPath、AgileWorks、KEEN Managerなどのツールを導入し、デジタル化の実績を次々と築いていった。その成果が評価され、2022年には社長直轄のDX推進グループのリーダーに起用された。
「品質保証部から始まったDX活動を、他部門、さらには会社全体へと広げるという重要な使命を託されました。そのためには、コミュニティの力を活用することが欠かせないと考えました」と田中氏は振り返る。
翌2023年には社内コミュニティを発足。現在、そのコミュニティには200人以上が参加しており、ヤンマー建機におけるDX推進の中核的なプラットフォームとして機能している。

(写真左)データのじかんアンバサダー石井亮介
コミュニティは、単なる人の集まりではなく、組織や個人に多面的なメリットをもたらす存在だと田中氏は考えている。DX推進においても、デジタル活用に消極的な社員の意識を変え、データ活用文化を醸成する「変革の推進力」、実践的なスキル習得や知識共有、アイデアの集積を促す「成長の促進力」、多様な部門間での人材交流や知見共有を通じた「組織活性化」、現場の声を吸い上げ、具体的な課題解決へと導く「課題解決力」など、コミュニティが導き出すメリットは多岐にわたると明言する。
また田中氏は、「これらの力は個別に働くのではなく、相互に作用し合うことで、より大きな効果を生み出します」と付け加え、こうした力を最初に実感したのは、社外コミュニティへの参加だったという。
「2018年の『IoT Day』(NSW株式会社主催)や『SFUG BI分科会 第3回 in 福岡』(株式会社セールスフォース・ジャパン主催)に登壇したのをきっかけに、ウイングアーク1stのユーザーコミュニティである『nest』とつながりました。そこで、所属や世代に関係なく相互にサポートし合い、課題や悩みを解決していく姿を目の当たりにしました。この時の体験を経て、コミュニティ活動が人のつながりを通じて大きな力を生み出すとても有効な施策であると感じました」(田中氏)
同時に田中氏が得たのは、技術的なサポートや問題解決だけでなく、異業種交流による新しいアイデア、さらには精神的な「心の支え」だったという。
田中氏のコミュニティ活動は、社内外にまたがり幅広く展開している。現在は、「nest九州・沖縄ワーキンググループ」と「nest製造業データ活用ワーキンググループ」のリーダーを務める他、UiPathユーザーコミュニティやシムトップスユーザーコミュニティの「現場帳票カイゼン部」にも参加。その活動が評価され、「UiPath Friends Lovers」や「Data Driven Meister」などの賞を受賞している。
「nestを通じて、他社のDX推進者とのネットワークができました。対等な立場で情報交換を行い、製造業特有の課題に対する共同解決策を模索することもあります。こうした協力関係は、DXを進める上で非常に大きな力になります」と、田中氏は実感を語る。
活動のスタンスとしては、部門や業種の垣根を越えた視点を得るために、積極的な情報共有と貢献を心がけているという。その上で田中氏は「継続的な参加と関係性の構築が、コミュニティの力を最大化するポイントです」と話す。
最近では、ヤンマー建機の社内コミュニティにとどまらず、ヤンマーグループ全体やグループ内の各事業会社(ヤンマーグリーンシステム株式会社、ヤンマーパワーテクノロジー株式会社など)との横のつながりを積極的に構築する活動にも注力している。
「社内コミュニティのメンバーが、社外コミュニティとつながる機会を提供しています。特にリーダーシップを発揮できそうなメンバーには、社外イベントでの登壇機会を設けています。これは、個人の成長を促す貴重な経験となるだけでなく、社外からの高い評価を通じてコミュニティ活動自体の価値を高め、ひいては上司からの評価向上にもつながる可能性があるからです」(田中氏)
コミュニティの幅を広げ、さらに大きな成果を生み出す仕かけとして、現在は、「コミュニティのかけ算」を推進しているという。

企業の垣根を超えてBI x RPA の可能性を探る!ユーザー自身による、ユーザー自身のための課題解決とコミュニティの素敵なカ・タ・チ──MotionBoardとUiPathのかけ算で何ができるか?

部門や業種の垣根を越え、国内外のさまざまなコミュニティから得た知見を活かしながら、ヤンマーグループ全体やグループ内各事業会社への情報共有にも注力。コミュニティ同士を掛け合わせることで、DXを加速させる仕組みづくりを推進している。
自らについて田中氏は、「コミュニティに救われた人間」と表現し、「今が社会人として最も忙しく、最も楽しい時期だと明言できます。もしコミュニティに関わっていなければ、ここまで充実した時間を過ごすことはなかったでしょう」と、コミュニティがキャリアに与えた影響の大きさに触れる。そして、いまのキャリア観についてこう述べる。
「キャリアにおいては、自由度と柔軟性が大切です。組織の中で自分の動きが制限されるようになったときが離れるタイミングだと思います。会社という組織は『生き物』のようなもので、経営層や上司が変わることで、それまでの価値観や方針が大きく変わる可能性があることを、これまでの経験から実感してきました。このような変化に対応するため、コミュニティなどを介して社外とのつながりを大切にしながら、自分の信念を持ちつつ柔軟に動くことを心がけています」(田中氏)
現在ヤンマーグループは、グループ全体を上げてDX推進に取り組んでいる。 状況は時々刻々と変化するのでDX推進のアプローチも変わってくる可能性がある。田中氏は、「そのときのために、後に続く世代がDX推進やコミュニティ活動の意義を自らの言葉で上層部に説明できる素地をつくりたい」とし、ノウハウや仕組みを体系化して持続可能な状態にまで導いておきたいと語る。
そして、今後もさまざまなコミュニティに積極的に関わり、特に若い世代と交流することを大切にしたいとして次のように締めくくった。
「若い人たちが抱える『上司が…』『やらせてもらえない』といった課題に対して、積極的にサポートしていきたい。私は今、コミュニティに参加し、DXの世界に触れることで技術の進歩を肌で感じられることに大きな喜びを感じています。20年後、私が80歳になった時、テクノロジーの進化によって世界はどのように変化しているのでしょうか。きっと想像もできない世界になっているに違いありません。その世界を、第一線で体験するために私はこれからも仕事を続け、コミュニティで世代を超えた人々とつながり続けていきたいと強く願っています」(田中氏)


メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

