



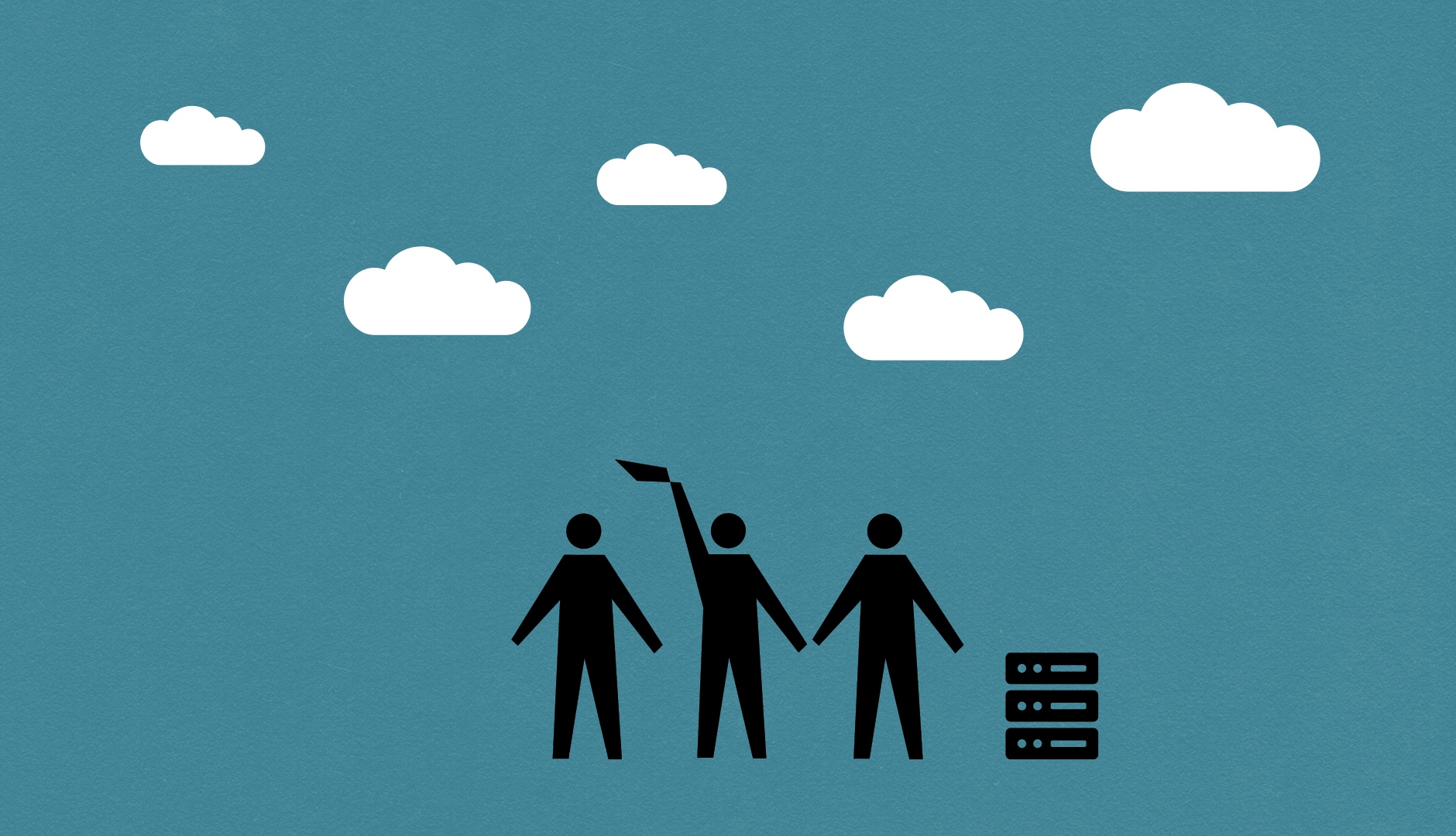
目次
「DX施策の一環として、クラウド導入はどんどん進んでいる。」
そのような認識を抱いている方は多いでしょう。実際、『通信利用動向調査』(総務省)によると、日本企業におけるその利用割合は5年間で56.9%(2017年)→72.2%(2022年)へと大幅に増加しています(※)。
ただし、そのような流れに反する「オンプレミス回帰(Cloud Repatriation)」という用語も海外を中心に2019~2020年ごろから聞かれ始めました。オンプレミス回帰とは何なのか、その3つの理由や実際に選択されている製品の種別などについて詳しくみていきましょう!
※…「全社的に利用している」「一部の事業所又は部門で利用している」の合計。データ出典:「平成 30 年通信利用動向調査の結果」(総務書)「令和4年通信利用動向調査の結果」(総務省)

「オンプレミス回帰」とは、「クラウドの利用をやめ、ITインフラやデータを自社で管理する環境へ回帰する」ことです。
オンプレミス/クラウドは、サーバやネットワーク、データなど自社のIT環境・データ管理の方法であり、下記のように異なります。
オンプレミス:社内で管理して利用する
クラウド:他社サービスとして利用する
ただし、クラウドにも他社と共有の環境を利用するパブリッククラウド、自社内でクラウド環境を占有するプライベートクラウドと、その“クラウド度”にはグラデーションがあり、また、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッドクラウドも存在します。
現在のオンプレミス回帰の流れは、パブリッククラウドからプライベートクラウドやハイブリッドクラウドへの切り替えなど、クラウドの中でより“クラウド度”を下げる(=”オンプレミス度”を上げる)ことも含みます。

では、オンプレミス回帰はなぜ生じているのでしょうか? 主要な理由を3つのポイントでまとめました!
クラウドサービスは利用データ量やオプション機能の利用によって、サブスクリプションプランのアップグレード、あるいは従量課金が行われる方式が一般的です。そのため、企業・サービスが成長し、データ量が増加したり、データのインポート・エクスポートなどの操作が頻繁に発生する場合には料金が大幅に跳ね上がることがあります。そこで、自社内に環境と人材さえ用意できれば、発生するコストが予測しやすく、またカスタマイズ性の高いオンプレミスに回帰するというわけです。
「オンプレミス回帰」事例として有名なオンラインストレージサービスの「Dropbox」や、映像配信サービス「ひかりTV」の事例でも、クラウド利用におけるコストの発生がオンプレミス回帰の理由の筆頭として挙げられています。
その効果は企業やサービスによりますが、なかにはパブリッククラウドのオンプレミス回帰によりITインフラにかかるコストを1/3~1/2に縮小できるという試算もあります。
自社内でデータなどのデジタル資産を管理することで、セキュリティ・ガバナンス強化に務めるというのも、オンプレミス回帰のポピュラーな理由の一つです。今やクラウドとオンプレミスのセキュリティ性に大きな差異はない場合も多く、管理主体それぞれの体制と能力に寄るのが実際のところでしょう。
とはいえ、セキュリティ・ガバナンスを保証するにあたって、デジタル資産を自社の管理下に置くほうががベターという考え方は、オンプレミスのノウハウ・体制が整っている企業ほど採用しやすいはず。開発と連携させることで適切なITシステムの管理・運用を実現するSRE(Site Reliability Engineering:サイト信頼性エンジニアリング)を取り入れている企業ほどオンプレミス回帰に前向きであるという報告も存在します。また逆に、クラウドサービスの運用スキルが不足していることを理由に、オンプレミスを選択するケースもあるようです。
IDC Japanが2020年10月に発表した『2020年 国内ハイブリッドクラウドインフラストラクチャ利用動向調査』において、「オンプレミス回帰の理由」で最も多く回答されたのが「セキュリティを向上したい」(35.8%)。それにつづくのが「データ連携を容易にしたい」(32.9%)、「アプリケーション連携を容易にしたい」(32.5%)でした。
その下位には「ID管理やアクセス管理を一元化したい」(32.1%)、「運用管理を一元化したい」(31.7%)が並び、データの連携やデータ・運用管理を一貫して行うにあたって機器や体制の自由度が高いオンプレミスがベターと判断される例は少なくないようです。
また、同じくIDC Japanの『2019年 国内企業のエンタープライズインフラのシステムタイプ別トレンド分析』では、AIによる解析処理のリソースにオンプレミスを選んだ理由として、「データの保護が重要であったため」「最新技術の追従/採用において優れているため」がクラウドを選んだ理由に比べ、多く回答されています。ここから、セキュリティ性とともにその最新技術の取り入れやすさがオンプレミス回帰の理由の一つとなっていることがわかります。
前述の『2020年 国内ハイブリッドクラウドインフラストラクチャ利用動向調査』でIDC Japanはオンプレミス回帰の結果、企業が選択する製品についてもアンケートを行っています。
選ばれた製品の種別とそれぞれの回答された割合は、以下の通り。
HCI(ハイパーコンバージドインフラ) | 45.1% |
HCI以外のオンプレミスプライベートクラウド | 24.8% |
プライベートクラウドサービス | 24.4% |
従来型のオンプレミスITインフラ | 2.0% |
データ出典:「オンプレミス回帰」の国内動向【後編】「脱クラウド」「オンプレミス回帰」で選ばれる製品とは? IDC Japanに聞く┃TechTargetJapan
「HCI(ハイパーコンバージドインフラ)」とは、サーバー・ストレージ・ネットワーク・ソフトウェアなどを統合管理することを可能にする仮想化技術のことを指します。クラウド・オンプレミスの双方を統合し、ハイブリッドクラウドを実現できる技術であり、その導入には双方の良いところどりを狙う目的があると考えられます。
このように、オンプレミス回帰とはいっても、完全に“脱クラウド”するわけではなく、双方のメリットを得るべく各企業が調整にトライしているケースが多いのではないでしょうか。
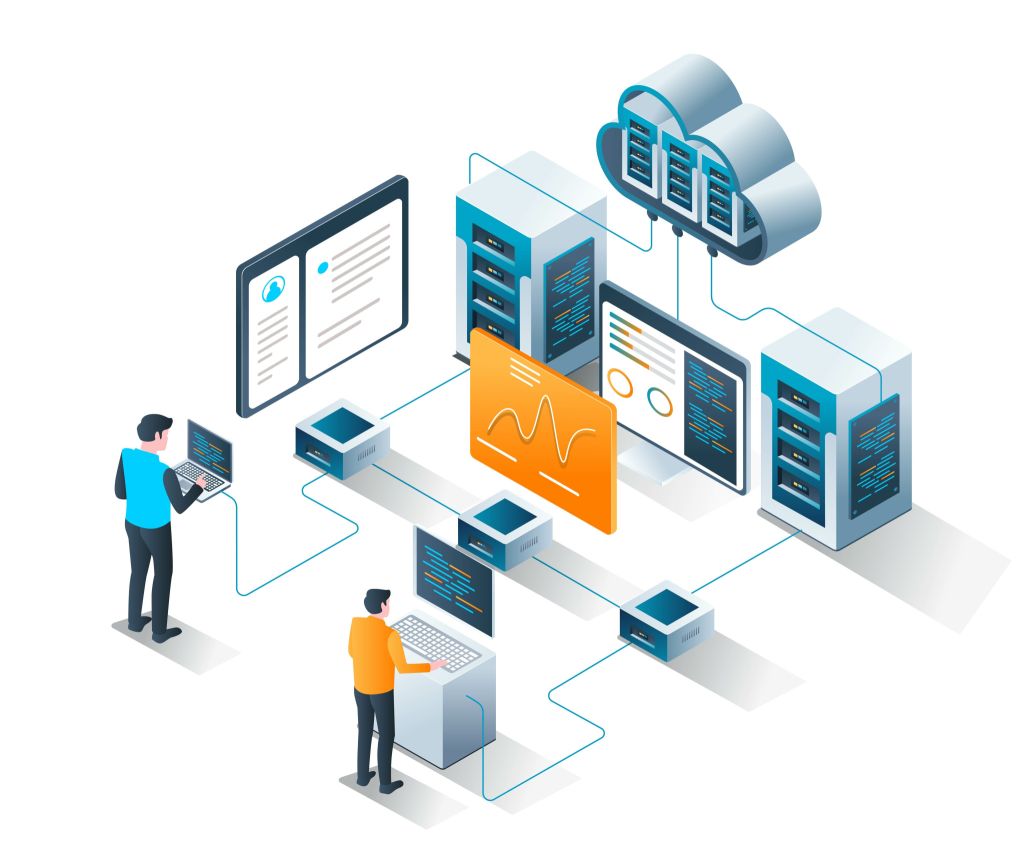
クラウドサービスの普及率が高まるなかで、それに対置される動きとしての「オンプレミス回帰」について解説してまいりました。オンプレミス回帰=“完全なる脱クラウド”ではなく、両者の適材適所での活用を探る「ハイブリッドITの探究」と考えたほうが実態に即していると考えられます。
貴社にとって理想のIT環境を実現すべく、クラウド・オンプレミス双方のメリットをもう一度見つめ直してみることをおすすめします。
【参考資料】 平成 30 年通信利用動向調査の結果┃総務省 令和4年通信利用動向調査の結果┃総務省 Michael McNerney『Supermicro 2022 Predictions: Cloud Repatriation - Return of the On-Premise』┃vmblog.com LORI MACVITTIE『脱クラウド(オンプレミス回帰)とSRE運用の不思議な関係』┃f5 Sarah Wang,Martin Casado『The Cost of Cloud, a Trillion Dollar Paradox』┃andreeessen horowitz 「オンプレミス回帰」の国内動向【前編】「脱クラウド」「オンプレミス回帰」が国内で拡大する理由は IDC Japanに聞く┃TechTargetJapan 「オンプレミス回帰」の国内動向【後編】「脱クラウド」「オンプレミス回帰」で選ばれる製品とは? IDC Japanに聞く┃TechTargetJapan Dropboxの脱クラウド以前と以後【前編】Dropboxはなぜ「AWS」からオンプレミスへの回帰を選んだのか┃TechTargetJapan Dropboxの脱クラウド以前と以後【後編】Dropboxがオンプレミス回帰後も「AWS」を使い続ける理由┃TechTargetJapan 小林啓倫,ITmedia『海外で進む「オンプレミス回帰」 その背景に何があるのか』┃ITmedia オンプレミスでクラウドライクな価値を提供するHCIとは?┃NEC ひかりTVが「クラウドストレージ」をやめて「オンプレミス」に回帰した理由┃TechTargetJapan クラウドは“ファースト”から“セントリック”へ! オンプレミス回帰に見る「ハイブリッドクラウド」の利点とは?!┃OPTAGE for Business クラウドが少ない理由は? AIシステムの半数はオンプレミスで稼働、IDCが調査┃@IT
(宮田文机)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

