




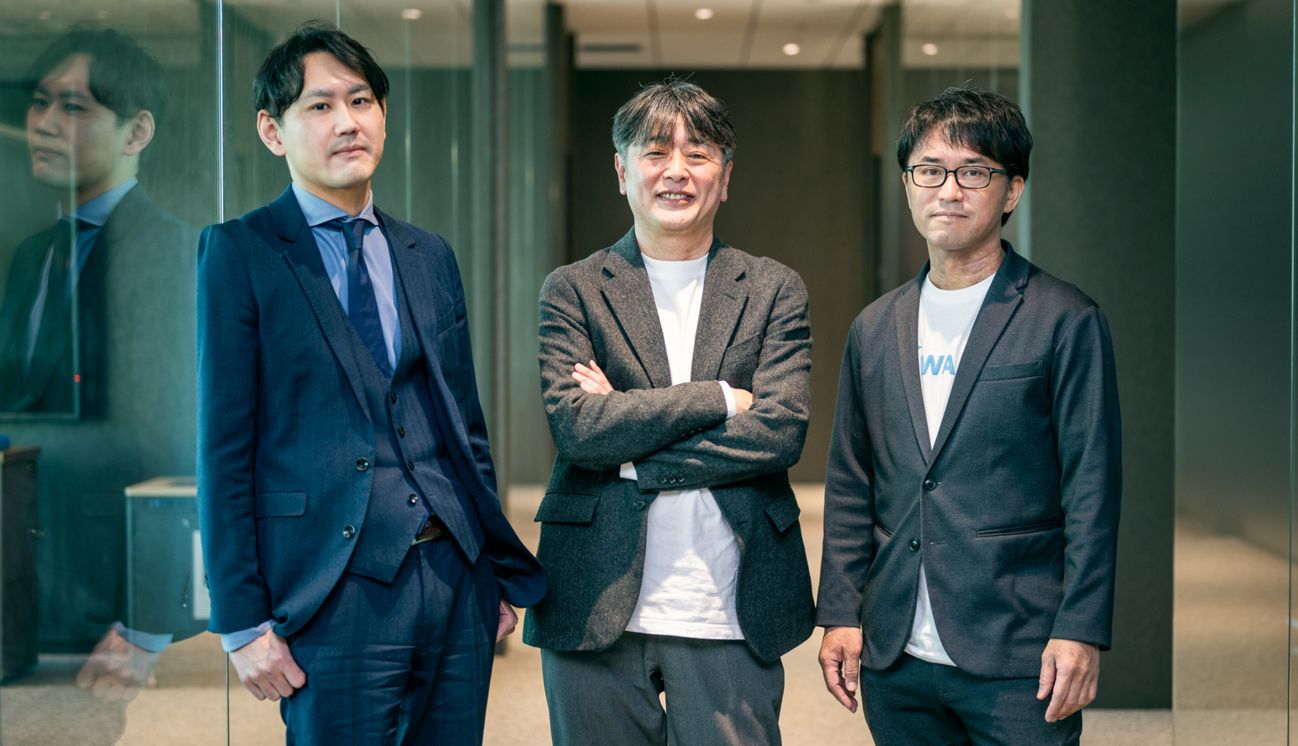
左から、富士通Japan株式会社 FJJ CPS&Retail事業本部 第二流通事業部 第二商社卸デリバリ部 マネージャー 後藤清彦氏
株式会社第一コンピュータリソース株式会社 西日本営業部 部長 森本崇弘氏
ウイングアーク1st株式会社 リージョナル営業統括部 統括部長 中嶋篤志
DXに取り組む企業の課題は、年々高度化・多様化している。こうした状況を踏まえ、FJJの後藤清彦氏は次のように指摘する。「DX時代において重要なのはスピード感です。顧客企業が求めるスピードで課題解決を行うためには、1社のSIerが全てを担うのではなく、複数社が協力し、『マルチベンダー』的な体制を構築し、各社が得意分野を持ち寄る必要があります」(後藤氏)。

富士通Japan株式会社 FJJ CPS&Retail事業本部 第二流通事業部 第二商社卸デリバリ部 マネージャー 後藤清彦氏
FJJは、自治体、医療・教育機関、流通業など多岐にわたる業種を対象にITサービスを提供する企業だ。後藤氏は入社後、文書管理パッケージの業務に携わり、その後ポーランド駐在を経験、欧州市場で金融・製造業向けパッケージビジネスの拡大を担った。現在は、西日本の流通業界の顧客を担当し、アカウントビジネスを推進する立場だ。
「ヨーロッパ市場のIT業界では、超大手企業を顧客とする日本のSIerに近いビジネスモデルが存在しています。しかし、規模を一段下げて中堅企業や中小企業に目を向けると、SIerという概念がほとんど見受けられません。それは企業の大半が、ITベンダーから必要な製品やサービスを直接購入し、それを社内の情報システム部門で導入・運用するというスタイルが一般的だからです」(後藤氏)
IT業界全体の効率化と標準化の流れから、国内の市場も徐々に同様のスタイルに近づいている。Sierは今後、どのような戦略で臨むべきなのだろうか。キーワードは、「役割の明確化」だと後藤氏は言う。富士通グループ自体も「選択と集中」を進めており、最大の価値を発揮できる領域に注力、それ以外はプロフェッショナルなパートナーに任せることで顧客に対する価値を最大化しようとしている。
「例えば、富士通としても、テクノロジーで社会課題やお客様の課題を解決するというパーパスのもと、『選択と集中』の方針を掲げています。そのなかで、社会インフラを支えるような大企業向けの基幹システムや、業界特有の業務知識・高度な技術力が求められる領域については、我々自身が責任をもって対応し、人的リソースも重点的に投下していきます。一方で、標準化が進んでいる領域やコストパフォーマンスが特に重視される特化型の領域については、DCRさんのような経験豊富なパートナーに業務をお任せした方が効果的です。このように役割分担をすることで、顧客にとってもより大きな価値を提供できると考えています」(後藤氏)
DCRは、製造業を中心に基幹システムの開発や運用支援、さらに最近ではクラウドサービスの導入支援など、多岐にわたるITソリューションを提供するSIerだ。同社で、西日本の営業部門を統括する森本氏は、「長年の活動の中でエンドユーザーから直接受注する案件も増加していますが、メーカーやSIerのアンダー(開発請負)として、『開発要員』を提供することがビジネスの中心です。スクラッチ開発中心の時代から、ウイングアーク1stさんなどの製品を活用して顧客課題を解決する時代に変わってきています。その時流を読み、個別製品に特化したエンジニアの育成に力を入れています」(森本氏)と紹介する。

株式会社第一コンピュータリソース株式会社 西日本営業部 部長 森本崇弘氏
今回の共創では、FJJが受注会社、DCRが開発会社、ウイングアーク1stがベンダーとしての役割を果たし、流通業界の顧客に帳票管理ツール(SVF)、ビジネスインテリジェンスツール(MotionBoard)、電子インボイスツール(invoiceAgent)を組み合わせた複合ソリューションを提供し、顧客の課題を包括的に解決へと導いた。
ウイングアーク1stの中嶋は「率直に言うと、FJJは開発も内製することで利益率を高めることができ、一方でDCRも受注会社の立場の方が多くの収益を期待できます。共創を進めるに当たり、その点に関して社内から懸念の声が上がらなかったのでしょうか。特にFJJさんは、フィリピンとマレーシアにオフショア開発拠点を持っており、こうした自社のリソースを使う道もあったのでは」と疑問を投げかける。

ウイングアーク1st株式会社 リージョナル営業統括部 統括部長 中嶋篤志
これについて、後藤氏はこう答える。「今回の共創案件のソリューションの組み合わせは、富士通グループ内に前例がないものでした。また、業務色が強い部分に導入するシステムは、制度や文化の違いなど『隠れた要件定義』が存在することが多く、開発に当たって密なコミュニケーションが必要になります。それを考えると、海外のオフショア拠点に任せるのはリスクが高いと感じました。そこで、invoiceAgentをはじめとしたウイングアーク1stのソリューションを包括的に取り扱っており、さらに受注会社としての経験も豊富で『隠れた要件定義』を読み取ることができるDCRさんと組むことは、当社にとって最良の選択でした」(後藤氏)。
森本氏もこう振り返る。「受注会社としてエンドユーザーから直接案件を受注するだけでは、案件の繁忙期と閑散期の山谷が発生しがちです。その結果、新しい技術を学ぶ機会に偏りが生じ、いざ案件が来たときに最新の技術で即座に対応できない可能性があります。継続的な案件の確保、技術力向上や人材安定化の観点から、今回のような共創の場に開発企業として参画することは、大きな意義があります。もちろん、エンドユーザーから直接案件を増やしたいという思いもありますが、簡単に実現できるものではありません。現時点では大手メーカーやSIerと連携しながら顧客を支援し、同時に自社の技術力を向上させていくというスタンスが重要だと考えています」(森本氏)
一方でウイングアーク1stは、製品提供や技術的な支援にとどまらず、今回の共創のきっかけとなる「場」を提供することとなった。ウイングアーク1stは、製品を取り扱うSIerや開発会社のビジネスの発展を促進するパートナープログラム「WARP」を進めてきたが、その活動の1つであるリアルイベント「WARPパートナー会」がFJJとDCRをつなぐこととなった。これを企画実施したのが、中嶋が所属するリージョナル営業統括部だ。
「ホームページで情報を公開して共創相手を募っても、全国に多くのIT企業がある中で、注目されるのは簡単ではありません。当社もこれまでの実績はあるものの、問い合わせをいただく機会は限られています。そのため、パートナー会のように対面で会える場は非常に貴重です。FJJさんとつながることができたパートナー会では、『多くの参加者と必ず対話する仕組み』が用意してあり、これが大きな役割を果たしてくれました」と森本氏。

森本氏が言及する「仕組み」とは、1対1の自社アピールタイムが終了したら席を横に移動し、参加している全ての企業の方と名刺交換を行い、互いに自社の紹介をするというものだ。仕かけた中嶋は、「いわば『強制マッチング』です。参加者全員に、つながりをつくって帰ってほしい、共創が広がってほしいと考えて企画しました」と明かす。また、同じ目的でSEリソースを求める販売会社とSEリソースが提供できる開発会社をマッチングするプラットフォーム「WARP Scrum」も立ち上げられた。
WARP Scrum※は、ウイングアーク1stが提供する、SEリソースを求める販売パートナーと、SEリソースを提供できる開発パートナーをマッチングするサービス 。本サービスでは、パートナー企業同士の強みを掛け合わせた「共創」を促進し、より高付加価値な提案・支援をスムーズに行うことを目指し、システム構築スキルを持つ開発パートナーと、案件を保有する販売パートナーを最適にマッチングし、IT環境構築における人材不足の課題解決を支援している。
※ウイングアーク1stの「WARP Empowerment Partner制度」に加入するAssociateグレード以上のパートナー企業が利用可能
https://www.wingarc.com/warp_partner/warp_scrum/index.html
今回のようなSIerの共創モデルについて中嶋は、「今回のような共創は、もう1つの重要なプレーヤーである『顧客』を含めて『エコシステム』と捉えることができます。エコシステムにおいて顧客を中心に据えることで、私たちは顧客の声やニーズをとり入れた価値創造が可能になりますし、ベンダーの発想では得られなかった新しいアイデアや革新的なソリューションが生まれるでしょう」と強調する。
エコシステムで顧客が得る恩恵も大きいとして後藤氏は、「顧客は、QCD全てにおいて大きなメリットが得られると考えています。複数のプレーヤーがそれぞれの強みを生かして柔軟にソリューションを提供することで、顧客は高品質な成果物を、最適なコストと短い納期で受け取ることができます。このように、エコシステムは企業と顧客双方にとって持続的な成長を可能にする仕組みです」と期待を寄せる。
さらに森本氏は、エコシステムが顧客の「機会損失」を防ぐ点にも注目した。「顧客が課題解決のために投資を決断しても、そのタイミングで依頼先のSIerにリソースやソリューションの取り扱いがなければ、その課題は解決されず、結果として戦略の遅れを招くリスクがあります。しかし、エコシステムを活用すれば、必要なリソースをタイムリーに確保することができます」(森本氏)と説明する。
森本氏はさらに、IT人材不足という課題に触れ、業界内の「人材の偏在」に着目する。「全ての企業や部門で一律に人材が不足しているわけではありません。一部では手が空いているエンジニアが存在することも事実です。エコシステムを通じて他社と連携することで、この人材の偏在(不足と余剰)を減らすことができるのではないでしょうか。その結果として、日本全体の競争力を高めることにもつながると期待しています」(森本氏)と続けた。
FJJ、DCR、ウイングアーク1stによる共創の取り組みは、DX時代におけるSIerの進化を象徴している。エコシステムを基盤とした「共創を通じた価値の最大化」は、自前主義や連携先の囲い込みを排除したDX推進のロールモデルとして、多くの企業にインスピレーションを与えることだろう。
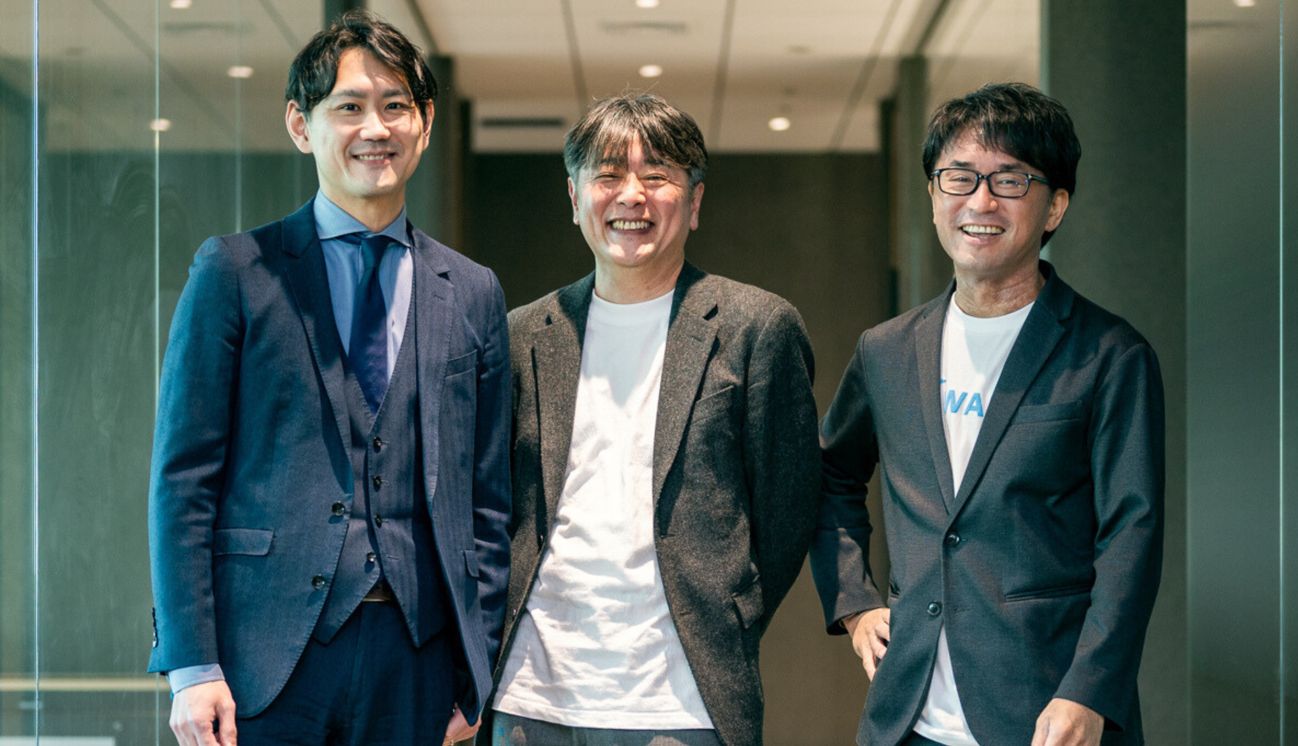
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

