



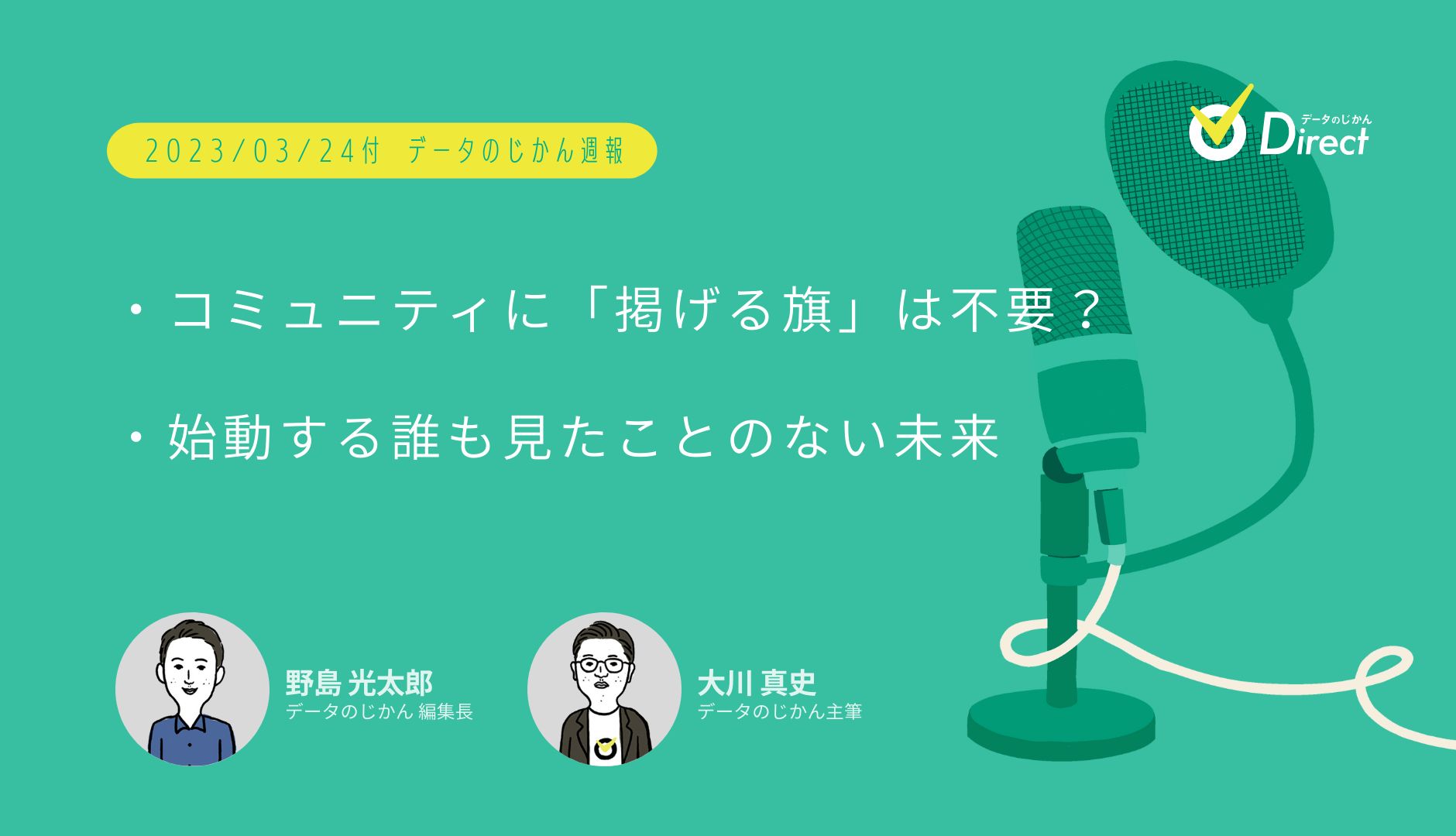
データのじかん週報では、データのじかんの編集部内で会話されるこばなしを週1度程度、速報的にお届けいたします。

『名刺代わりになる自社製品の開発を目的としたゼミナール』の発表会の様子
野島:自社の強みを活かした製品開発セミナーをもって、全7回・約5カ月間に渡った東京商工会議所の「名刺代わりになる自社製品の開発を目的としたゼミナール」が終了しました。講師として携わった大川さんもお疲れ様でした。
東京商工会議所主催のセミナー |
大川:カリキュラムの作成からガッツリ担当したのは初めての経験でしたから、私自身も反省や成果をたくさん得られました。何よりも受講者の声をじっくりと聞けたことが大きな気付きを得られました。本ゼミで登壇いただいた菅原のびすけ氏の「プロトタイピングは終わらない」という言葉は個人的にも名言だと思います。
野島:発表を先に予定を入れて、進捗をなんとか進める「LT駆動開発」という言葉があるくらいですからね(笑)。「締切り駆動開発」でも受講者の皆さんが、がむしゃらにやられていたのが目に浮かびます。発表会の様子はレポートを公開していますが、参加者はどのような方が多かったのでしょうか? 幹部候補生とか?
大川:半分は社長自ら参加していましたね。もう半分は開発部門の方や会社からの指示で渋々参加している人もいました。ただ、最初ははっきりと「会社から言われて」と言っていた人も、最終的にはとても積極的に参加してくれていました。むしろ、講師の私が驚くくらいの熱意のあるコミュニティになったと思います。ゼミでは各受講者の発表やプロトタイプの相互レビューを行うのですが、私たちが促さなくても自然発生的に意見が交わされたのは予想外です。本ゼミの主旨である「自分が発信すること」と「意見を聞くこと」の重要性を理解し、積極的に実践してくれたのだと感じました。私がポツンと置いてけぼりにされてしまうほどに(笑)。
野島:「いやいやでも巻き込んでいく」とか「手を動かしながら変えていく」というプロトタイピングを体言できたコミュニティなのかな、と聞いていて思いました。
大川:そうですね。とにかく時間がないから自分で設計からプロトタイプを作って発表を通じて情報発信し、周囲からフィードバックがくるという体験そのものが本人はもちろん、コミュニティにとっても価値というか重要な財産だったと思います。特に社長たちは普段なら社内外のリソースを活用して設計したり、カタチにしたりするのが当たり前でしょう。それに評価をするにしても、出来上がったモノに対して下すのが通常です。対してゼミでは自らプロトタイプを創り切ったという「達成感」と、思っていなかったフィードバックが新鮮で当事者の意識を変えていったのだと感じました。フィードバックで「すごいっすね」なんて評価があると、目に見えてモードが変わっていきましたよ。

大川:今回のゼミでは、個々の受講者がフィードバックを受ける一方、評価をする側でもあったという環境そのものがコミュニティとして良好に機能した要因ではないかと思います。そういう意味では、このようなゼミやボランティアで掲げられることが当たり前になっている活動を通して解決すべき「課題」や「イシュー」などは必要ないのかもしれませんね。
野島:おお!かなり意見が別れそうな見解ですね!……ただ、私もそれを聞いてとある国外の研究者の方が日本のボランティア団体を研究した資料にあった「受容者⇒準行為⇒一般行為」の3レイヤーで他人を「受け身から転換」させる図を思い浮かびました。そこには他人を巻き込み、ボランティア活動を拡大するための要素として機能的価値や社会関係資本には触れられているものの「課題の設定や共有」が言及されていなかったんですよ。
大川:参加者や第三者との関係性だけで、ボランティア活動なのに解決すべき課題には言及されなかったということは、極論、「なんのためのボランティアか」とか「結果がどうなったか」とかはコミュニティの発展や運営においては関係ないのかもしれませんね。こともあると、「課題を磨く」とか「自分事にする」と言いがちなコミュニティに対しては、大いに参考になる考え方かと思います。
野島:もちろん、すべてのコミュニティに当てはまるわけではないかもしれませんが、今回のゼミを起点として色々と研究していきたいですね。
大川:今週、ぜひ皆さんにお伝えしたいのは私たちが見たこともない未来の足音が、微かに近づいているということです。世界最大級の新エネルギー総合展「スマートエネルギーWeek」に参加したのですが、そこでは数年前は主流だったEMS、VPP/IPP、スマートメーターから「脱炭素経営」や「エネルギー安全保障」、「アンモニア発電」といった新たなキーワード・トピックスに転換した夢のような力、未来を創造した展示が多くありました。
野島:夢のような未来、すごく気になりますね。
大川:例えば、ドローン型のコンクリート3Dプリンターを使ってフレームを設計し、コンクリートをそこに流し込むことで海に風力タワーのコンクリート艦を大量展開する「MIKASA」の取り組みは非常に斬新でした。また、IHIがアンモニア100%で発電するガスタービンを開発を進めるなど「見たことのない世界」を垣間見ることができました。あと、我々にとって注視すべきなのは三井住友銀行が出展していたCO2排出量算定のクラウドサービス「Sustana」です。
野島:三井住友銀行が自ら開発しているんですか!?
大川:そうなんですよ。上場企業に課せられているCO2排出の統合報告書の作成支援ツールで、可視化そのものサービスはある意味レッドオーシャンなのですが、三井住友銀行が自社開発したのが、非常に大きな意味があります。開発メンバーは15人中8人はプロパー、つまり「銀行員」というのが異例ですよね。
野島:基本的に他のメガバンは買収や専門会社とガッツリ組んで開発していますからね。ものすごく興味があります。ぜひ取材したいですね!
大川:三井住友銀行にはまだ表立ってはいないものの、業界の秩序やビジネスモデルを破壊する「イノセントディスラプター(無邪気な破壊者)」がゴロゴロいるのかもしれません。少しお話するとプロトタイプを行員に持たせて、客先に提案しつつ時には厳しいフィードバックをもらいながらも、改善を繰り返すというアジャイル開発をド直球で行っているようでした。「Sustana」は行員に情報を持たせられる「営業ツール」としても使えるうえ、サプライチェーンとしても展開を狙っているようです。
野島:三井住友銀行はカスタマー向けのサービスもいくつもありますし、データをどう活用して展開するか興味がありますね。「可視化」一本だとレッドオーシャンですが、ファーストデータを所有し、さらにサプライチェーンを構築しているのは非常に強みになりますよ。なにより、エネルギーがテーマの展示会に銀行が出展している時代になっているのが変革を感じさせられますね。


広告代理店にて高級宝飾ブランド/腕時計メーカー/カルチャー雑誌などのデザイン・アートディレクション・マーケティングを担当。その後、一部上場企業/外資系IT企業での事業開発を経て現職。静岡県浜松市生まれ、名古屋大学経済学部卒業。
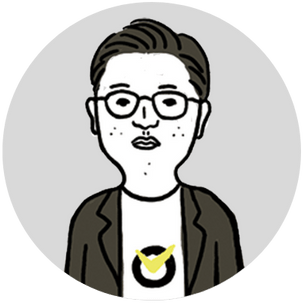
IT企業を経て三菱総合研究所に約12年在籍し2018年から現職。専門はデジタル化による産業・企業構造転換、製造業のデジタルサービス事業、中小企業のデジタル化。(一社)エッジプラットフォームコンソーシアム理事、東京商工会議所学識委員兼専門家WG座長、内閣府SIP My-IoT PF、ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会 中堅中小AG、明治大学サービス創新研究所客員研究員、イノベーション・ラボラトリ(i.lab)、リアクタージャパン、Garage Sumida研究所、Factory Art Museum TOYAMAを兼務。官公庁・自治体・経済団体等での講演、新聞・雑誌の寄稿多数。直近の出版物は「アイデアをカタチにする!M5Stack入門&実践ガイド」(大川真史編、技術評論社)

経済週刊誌の編集記者として活動後、Webコンテンツのディレクターに転身。2020年に独立してWEBコンテンツ制作会社、もっとグッドを設立。ライター集団「ライティングパートナーズ」の主宰も務める。BtoB分野を中心にオウンドメディアのSEO、取材、ブランディングまであらゆるコンテンツ制作を行うほか、ビジネス・社会分野のライターとしても活動中。データのじかんでは編集・ライターとして企画立案から取材まで担う。1990年生まれ、広島県出身。
(TEXT・編集:藤冨啓之)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

