



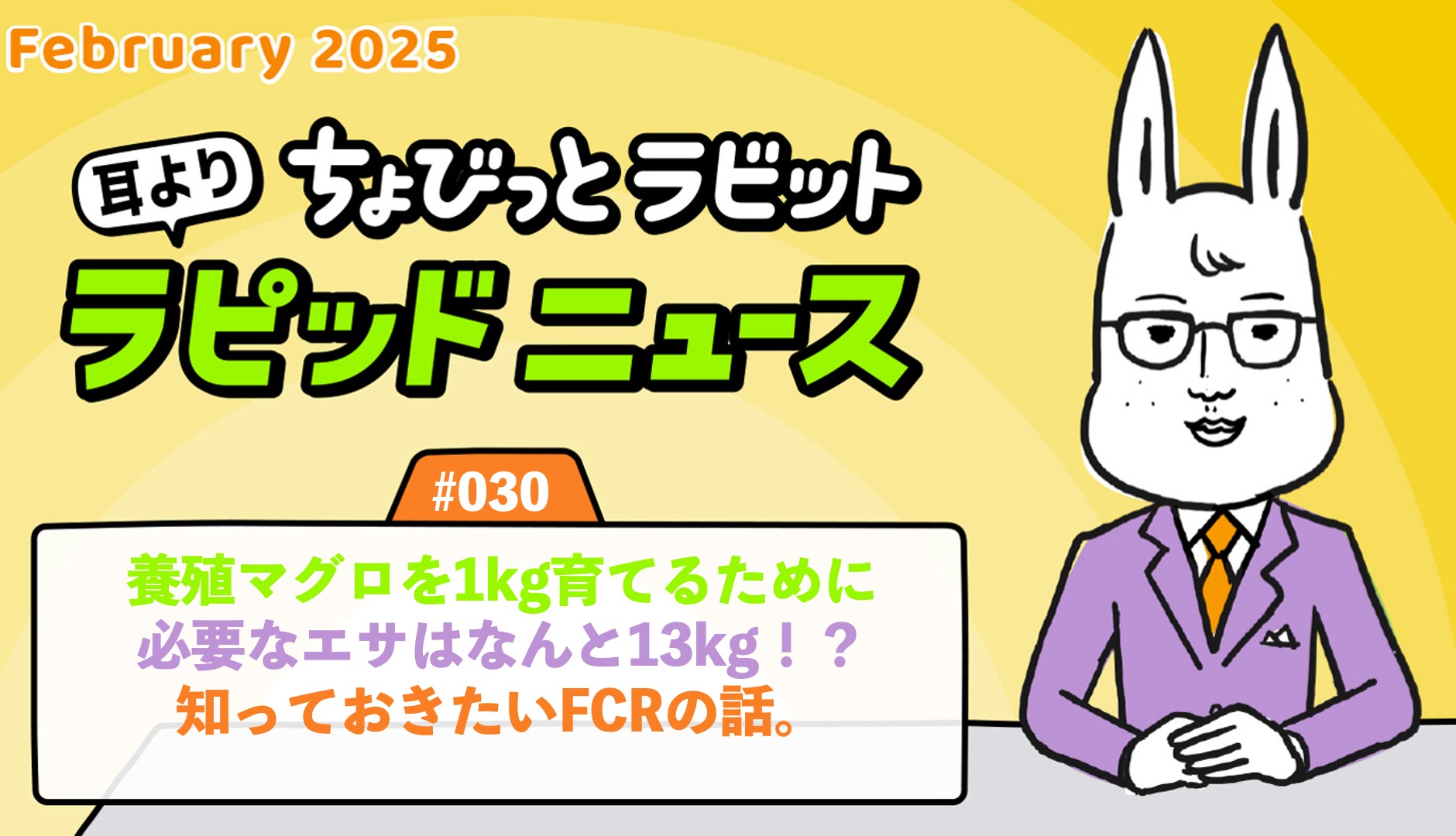
まいどどうも、みなさん、こんにちは。
わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。2月に入り、節分やら恵方巻きやらの毎年の行事が終わり、一年で最も寒い季節に差し掛かりつつありますが、みなさまいかがおすごしでしょうか?
今週も盛りだくさんでしたが、日本では八潮市で起きた道路陥没事故は衝撃的なニュースでした。また、アメリカの首都ワシントン近郊の空港で起きた旅客機と軍用ヘリの衝突、フィラデルフィアで起きた医療用小型機の墜落事故など、飛行機事故が続いたのも正直とても驚きでした。そして、テクノロジー関連では先週に引き続きDeepSeekに関する話題が多く飛び交いました。八潮市の陥没事故は下水道間の老朽化が原因と見られており、つまりこれは他のどこでも起こり得る、ということなので、インフラ整備の問題についてもっとしっかり考えなくてはならない時代に突入したことを改めて認識した次第でありました。
インフラ整備の問題も深刻ではありますが、わたくしは最近非常に保温性の高い水筒や保冷性の高いステンレスタンブラーなどを生活に導入いたしまして、エネルギー効率について最近よく考えるようになりました。そんななか、食料問題、というのもエネルギー効率、という意味ではインプットがあり、アウトプットがあるものなので、当然これもかなり重要な問題となるわけです。しかも食料問題というのは言わずもがな全ての生物に関連する文字通り死活問題であります。その効率の良し悪しを示すFCRと呼ばれる指標があるのですが、今週はこのFCRの重要性についてとりあげてみようかと思っております。
このFCRというのは「Feed Conversion Ratio」、日本語にすると「飼料要求率」と呼ばれる数値であります。これはつまり、牛や豚、鶏などの家畜やサーモンなどの養殖魚の体重を1キロ増加させるためにどのくらいのエサが必要か、ということを示しています。実は、養殖業では飼料費が総コストの60-70%を占めるらしいので、この数値をいかに低く保つか、という部分がどれだけこの事業によって利益を増やせるか、という部分に直結していることになります。
いかに我々が、久しぶりの友人と会食をするたびに、「実は最近めっきり太りやすくなっちゃってさ」「いや、わかるわー、ちょっと食べすぎると全然落ちないよねー」などと会話しているとは言っても、1キロのステーキを食べた時に、その1キロがまるまる自分の体重に上乗せさせるわけではありません。つまり、ニンゲンという種はFCRがかなり高い生物である、ということが言えます。
このFCRですが、鶏で1.5から2.0と言われております。つまり鶏に1.5キロから2キロの飼料を与えると体重が1キロ増える、ということになります。豚のFCRは2.6から3.0くらい、牛は6.6となっており、一般的な家畜の中では鶏が最も効率的であることがこの数値から見て取れます。牛はあまり環境によろしくない、という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、このFCRの高さも一つの問題となっています。(注:FCR数値は研究により上下するのでここではおおよその数値を書いています。)
陸上動物よりも水中生物の方がFCRが低いと言われており、アトランティックサーモンのFCRは1.15くらい、そして最も低いのがアフリカナマズの0.9-1くらい、なのだそうです。おお、だったら、アフリカナマズばっかり養殖すれば食料もじゃんじゃん増えて食糧不足問題は解決するじゃん!ラッキー!と思ってしまいがちだと思いますし、正直わたくしもそう考えたのですが、FCRが1.0未満になるのは餌の乾燥重量と魚の湿重量を比較しているからであり、その魚を日干しにした場合の重量と比較するとやはりどうしても減ってしまうわけです。なので、全人類レベルで食べ物が不足してきた場合、家畜や魚などを食べる、というのは根本的な解決策とはなりえないことになります。つまり、ウサギを食べたりすることなんていうのはもっての他であり、非常に野蛮で決して許されることのない卑劣な行為だと言えるわけでありまして、食べないまでも先日ニュースになっていたウサギ島にいるウサギを蹴ったりするようなこともとても許されるべき行為ではありません。あまりの非人道さにかの羽生善治先生までウサギに関するコメントを発表し、ウサギ界隈はにわかにざわついておりました。
そして、今回そもそもFCRについて考える発端となったのは、近畿大学が成功させて話題になった「養殖マグロ」でした。この養殖マグロは一時期は日本人の食生活を支える鍵を握るのではないかとまで思われていたのですが、蓋を開けてみると、養殖マグロのFCRは13.0と他の養殖魚はもちろんのこと豚や牛よりもはるかに効率が悪く、しかもマグロの餌となる魚はそもそもニンゲンが食べる魚と変わらない、という点も泣き面に蜂ポイントとなっており、泳ぎ続けないと死んでしまう、という習性を持つ筋肉の塊のようなマグロに13キロのニンゲンも食べられるであろう魚を与えないとマグロの体重は1キロ増やせないのです。もちろん、技術が向上してマグロの養殖が可能になった、という点ではこの研究は有益に違いないのですが、これはめちゃくちゃ単純に計算すると、マグロ100グラムに対し、他の魚だったら1.3キロも食べられたのに、ということになり、言ってしまえば1万円で仕入れたものを3000円で売る的なビジネスモデルになりかねず、この悲しい事実に世界は恐れ慄き、これを聞いただけでも、養殖をやるメリット全然ないかも、とド素人でも気が付くレベルの費用対効果の悪さを誇る生き物なのだそうです。
そうなると、近年よく話題にのぼる昆虫食、そう、たとえば、コオロギなどのFCRはどのくらいなの?というところが気になってくるかと思いますが、コオロギも育てる環境や餌の質によってFCRがかなり上下するらしく、実験室レベルで0.5~1.47くらい、であり、条件によっては鶏の方がタンパク質回収率が高い場合もあり、昆虫食べるのって抵抗あるわー、と思っている人がかなりの割合で存在する、という部分を除いても、これはこれで課題が多いのが現状なのだそうです。ま、とにかく、やっぱりマグロは養殖に限る、という発言はやっぱりさんまは目黒に限るみたいなお話であるというのが今の段階での一旦の結論となっています。
そんなわけで、今週は、豊かな食生活とは切っても切れない関係性にあるけれど、あまり耳にしないFCR(飼料要求率)という指標についてピックアップしてみました。FCRに限らず、こういう食の話題に関心がある方は、はせがわゆうじさん著の「もうじきたべられるぼく」という切なすぎて涙がちょちょぎれそうになる絵本もオススメなのでぜひ読んでみてください!色々なものが値上がりを続ける今だからこそ、目先のことだけでなく、未来のことを見据えた時に押さえておきたい指標かと思います。そんなわけで、また来週お会いしましょう。ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!それでは、アデュー、エブリワン。
(ウサギ社長)
・サーモン養殖の勘所 | オカムラ食品工業 ・養殖魚を育てるには、どれくらいの飼料が必要なのでしょうか? | SKRETTING ・水産養殖事業のイノべーション | 世界経済評論IMPACT ・家畜の腸を整える~飼料用酵素の新たな挑戦~ | バイオミディア ・様々な増肉係数(FCR)| Blog:Seoka Aquaculture Consulting ・Feed conversion efficiency in aquaculture: do we measure it correctly? | table ・飼料効率と飼料要求率:定義、計算方法など | UltraBem – made by doctors
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

