




筆者は2021年から基本的にリモートワークで仕事をしていますが、どうも長時間のデスクワークが身体によくなかったようで、この1年ほどは腰の痛みに悩まされていました。
整形外科や接骨院、鍼灸院などをいくつも回ってみたものの、なかなか改善せず。
ようやく「座りっぱなしの姿勢が股関節まわりの筋力低下を招き、支える力が弱くなったことで神経系に負担がかかっている」という診断にたどり着くまで、かなりの時間がかかりました。
最近は、毎朝5キロのウォーキングを日課にし、座りっぱなしの作業をやめてスタンディングデスクで立ちながら仕事をするようにしたところ、少しずつ痛みが軽くなり、身体全体のこわばりも和らいできました。
さらに、スキマ時間には下の写真のようなステッパーを使って、衰えていた筋力を取り戻すトレーニングも取り入れています。これが想像以上に効果的で、体の回復を後押ししてくれているように感じます。

リモートワークで運動不足や腰痛に悩んでいる方には、ぜひ試してみてほしい方法です。
それではまず、今回紹介する記事をダイジェストで紹介します!!
「まち」という共同体をつなげる方法はさまざまです。歴史を通じて、コミュニティの「管理者」は、宗教、民族、政治的イデオロギー、風習、地理的環境などにより、「まち」を一つにまとめあげようとしてきました。しかし、多くの場合、「まち」という共同体に属するメンバーはもっと感覚的なイメージで「まち」をとらえています。このシリーズでは、「感覚」にフォーカスし、それらがどのようにシビックプライドを形作っているかをみていきます。シリーズ第1回では「音響共同体」や「サウンドスケープ」という概念を取り上げ、第2回では音の採取とデザインの方法を紹介しました。第3回となる今回は、音を核にしつつも視覚・嗅覚・触覚といった他の感覚と統合することで、より豊かな「五感で感じるまちづくり」に迫ります。 (・・詳しくはこちらへ)
「AIで検索すれば、大体の情報は出てくる」──でも、それだけで“現場”が見えるか?本企画 「DX Namamono information」 は、そうした問いを出発点にしています。AIや検索では届かない、肌感覚・体験に根ざしたDX/デジタル活用のストーリーを、現地取材を交えながらお届け。一次情報とニュースのクロスリードで、他人事を自分事に変える読解力を引き上げます。今回は、7月初旬に訪れたチェコとスロバキアでのキャッシュレス事情を、都市・郊外・観光地の視点から丁寧に紐解きます。中欧というフィルターを通して、日本との違いと共通点、そして課題と可能性を探る旅へ、ご一緒しませんか? (・・詳しくはこちらへ)
AIも検索も便利だけど、本当に知りたい“現場”は、そこだけじゃ見えない。だからこそ、「DX Namamono information」は、体験を伴うリアルなDX情報を、“生情報”として届けます。大阪・関西万博。そこでは、協会の情報を待つより先に、個人発信の情報が信頼される現象が起きていました。いったい、どういう仕組みでそうなったのか?その情報はどこまで信用できるか?会期終了後の視点も併せて、本記事では、パビリオン待ち時間情報にスポットをあて、実地で“検証”します。 (・・詳しくはこちらへ)
「AI事務員宮西さん」 は、AIやデータ活用をテーマに描かれるオリジナル漫画シリーズです。保険会社で事務員として働く宮西さんは、ある日、社内に新設されたデータ部門へ異動を命じられます。「なぜ私が?」と戸惑いながらも、データ組織の立ち上げに奮闘する宮西さん。その姿を通して、AI時代の職場やデータ活用のリアルを、コミカルかつ分かりやすく描いています。データ部門の立ち上げを検討している方にも、入門編として楽しんでいただける内容です。それでは本編をどうぞ。 (・・詳しくはこちらへ)
2025年7月10日、ウイングアーク1stが設けるエンジニアのためのイノベーションラボ「Data Empowerment Base」で、森永製菓の「DX課題解決型ワークショップ」が開催されました。ワークショップには、同社グループ企業を含む本社・各事業所から17名が参加。インプットから2つのワークショップ、ラップアップまで約4時間となる大ボリュームのワークショップを通し、現場目線の課題をDXで解決するプロセスを学びました。 (・・詳しくはこちらへ)
データのじかんNewsのバックナンバーはこちら
2025.10.13 公開
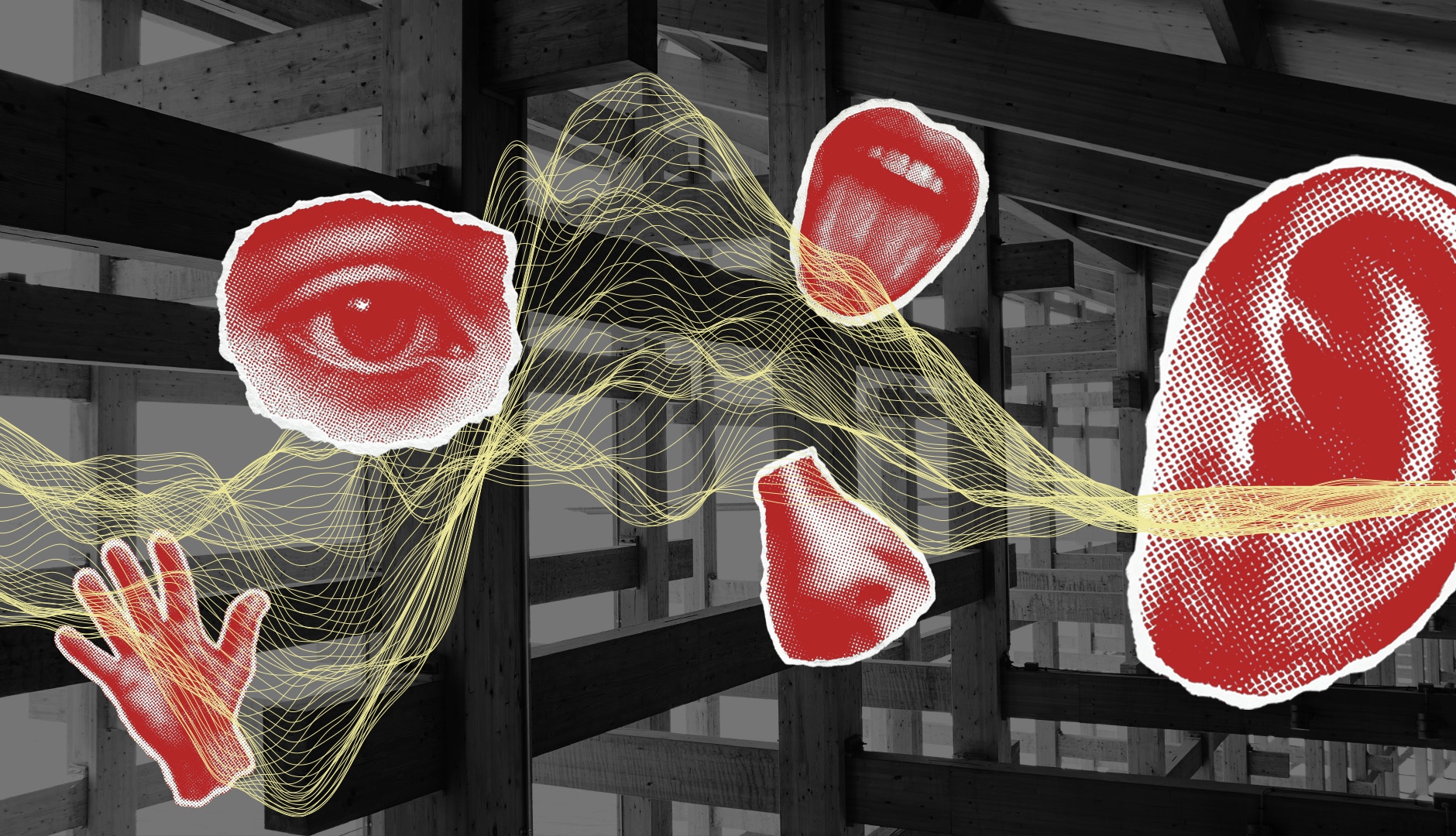
人の記憶や感情は、五感が交わる瞬間に深く刻まれます。本稿では、視覚だけでなく、音・香り・触感といった複数の感覚を重ね合わせた「マルチセンサリー・デザイン」が、まちづくりにもたらす価値を探ります。
大阪・関西万博では、会場全体に設置されたスピーカーから流れる音が空間ごとにテーマを変え、来場者の体験を豊かにしていました。特に世界最大の木造建築「大屋根リング」では、音と木のぬくもりが響き合い、訪れる人々に忘れがたい印象を残しました。
都市の音環境は、まちの印象を左右します。御堂筋や中之島で行われているイルミネーションイベントのように、光と音を組み合わせた演出は、地域ブランドを「体験」として浸透させる力を持ちます。
さらに、嗅覚や触覚もまちの記憶を形づくる要素です。太宰府天満宮のクスノキの香りや、港町の潮風と波音のように、感覚の重なりがその土地らしさを伝え、訪問者の記憶に残ります。
テクノロジーの発展によって、五感を取り入れたまちづくりは新たな段階へ。ARやAIによる感覚データの活用、防災設計など、五感を通じて人とまちをつなぐ発想が、これからの都市体験を変えていくでしょう。
2025.10.16 公開

ヨーロッパのキャッシュレス化と聞くと、西欧諸国の先進的な事例を思い浮かべがちですが、中欧の実情は意外と知られていません。本稿では、7月初旬に筆者が訪れたチェコとスロバキアの現地体験を通じて、キャッシュレス社会の“現場のリアル”を紹介します。
チェコ・プラハでは、公共交通の主力である路面電車が完全にタッチ決済対応。車内の券売機は現金非対応で、タッチ決済機能付きカードを持たなければ乗車券を買うことができません。観光地ではほとんどの店舗がカード対応ですが、テレビ塔のように現金のみの施設も残り、都市とスポットごとのばらつきが見られました。
一方、隣国スロバキアの首都ブラチスラバでは、同じタッチ決済でも仕組みが異なります。カードをタッチすると紙券が出ない完全デジタル式。一方で、公共トイレでは現金払いが必要など、デジタルとアナログが混在しています。
取材を通じて見えてきたのは、“キャッシュレス=便利”とは限らない現実。
都市部ではカード社会が定着しつつも、郊外や特定施設では依然として現金が欠かせません。デジタル化の進展度を一律に語れない中欧の姿が、現場体験から浮かび上がります。
2025.10.17 公開
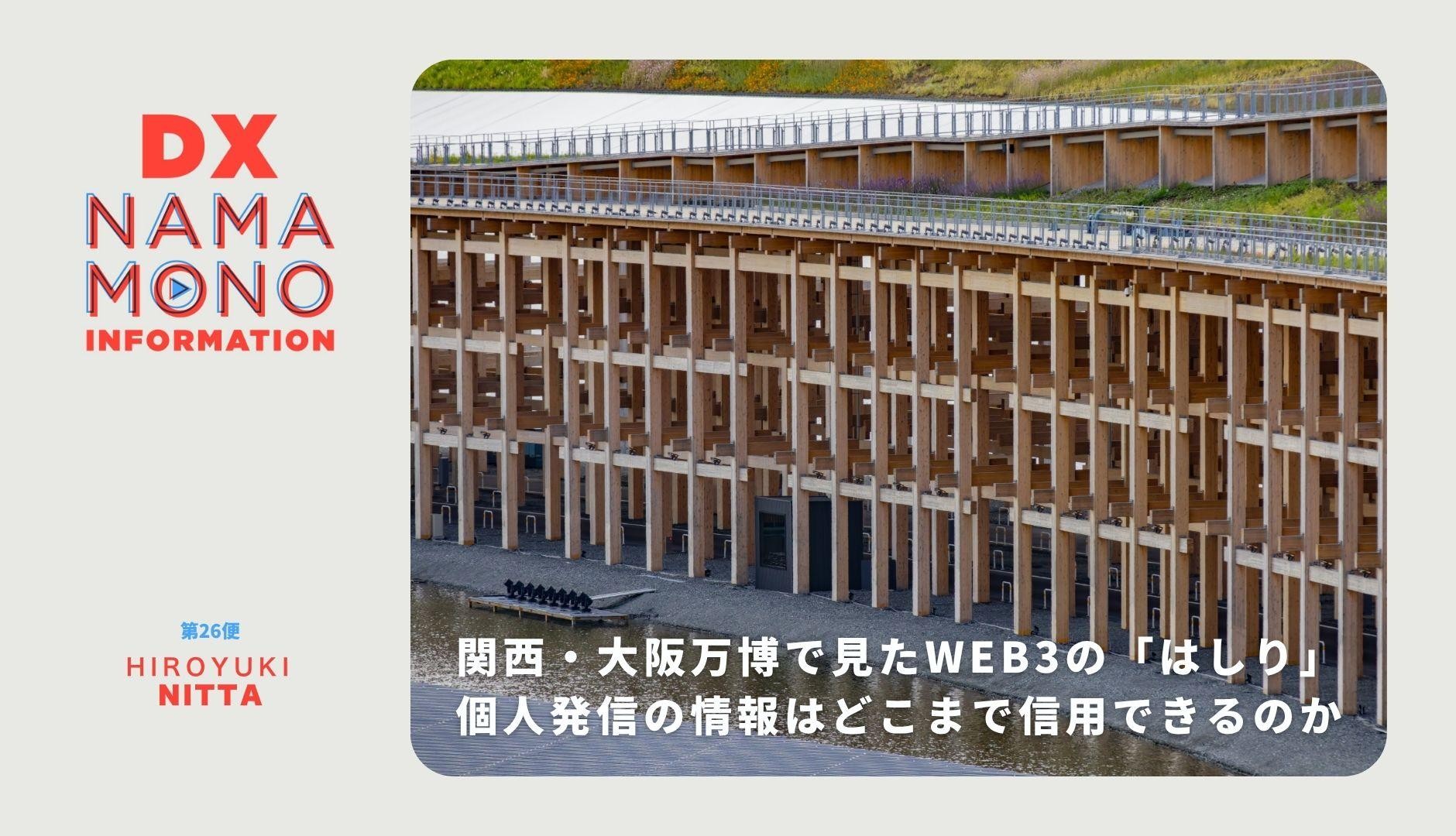
大阪・関西万博は、会期を通じて2600万人以上が来場し、大盛況のうちに幕を閉じました。しかし、その舞台裏では「パビリオンの待ち時間」をめぐる“情報の空白”が、来場者の最大の関心事となっていました。
開幕当初、万博協会は待ち時間の公表に消極的で、情報発信は各パビリオン任せ。そんななかで、個人が自発的に立ち上げたサイト「万博GO」が注目を集めます。来場者がリアルタイムで待ち時間を投稿・共有し、SNSでも情報が拡散。個人発信が公式を補完する構図が自然発生的に生まれました。その後、6月には協会も公式アプリで待ち時間を公表するようになり、公式と個人の情報が並存する“共創的エコシステム”が形成されます。
筆者は実際に現地で両者の情報を検証。「万博GO」のデータは実測値とほぼ一致した一方、協会アプリの情報は未更新や非表示が多く、実用性に欠けていました。結果として、来場者の信頼を得たのは、分散的に支え合う個人発信のネットワークだったのです。
この現象は、情報が中央集権から分散管理へと移る“WEB3的構造”の一端を示しているのかもしれません。万博という巨大イベントの裏で起きていたのは、情報の在り方そのものを問い直す実験でもありました。
2025.10.16 公開

連載第24回となる今回は、「データ組織立ち上げ編」の最終章。AI事務員・宮西さんが、日々の業務改善を通じて「データマネジメントとは何か」を改めて見つめ直す回です。
企画も通り、PoCも成功──順調に見えた中で、松田先輩の一言「でも、データマネジメント担当ってこと、忘れないでね?」が胸に残ります。自動化や効率化を進めるだけでは、本当の意味でのデータ活用にはならない。会社全体がデータを正しく扱い、活かせる状態を整えることこそが、宮西さんの本来の使命でした。
データマネジメントとは、単にデータを集め整える仕事ではなく、組織に“データ文化”を根づかせる営みです。業務改善はその第一歩であり、現場に寄り添いながら全社の仕組みへとつなげていく過程に意味があります。現場の課題を理解し、非効率や誤りの根を見つけることが、活きたデータマネジメントを生む。
宮西さんは、松田先輩の言葉をきっかけに、改めて自分の役割を思い出します。データが正しく使われ、活かされる環境をつくること──それが本当の仕事。そして、宮西京華の物語は続いていきます。
2025.10.14 公開

今回の「DX課題解決型ワークショップ」は、森永製菓の生産技術開発部生産DXグループが主体となり自社向けに開催。森永製菓生産技術開発部生産DXグループ運用担当の木村嘉樹氏が司会進行し、講師はデータのじかんの主筆の大川が務めました。また、オブザーバーとしてITソリューション事業を手掛ける株式会社たけびしも参加。森永製菓からは、本社の生産技術開発部、生産統括部をはじめ、全国から7事業所が参加しました。
同じ会社でありながら普段は働く部署や地域、役職も大きく異なる仲間が集まったワークショップは終始、和やかな雰囲気でありつつも、アイデア出しや課題に向かう姿は真剣そのもの。部署を超えて共通する課題や、ユニークなアプローチ方法を共有する貴重な場をレポートします!

今回は『「感覚」によってつながるまち③~五感でデザインする「まちの体験価値」』という記事を紹介させて頂きました。
先日、国立競技場で開催された世界陸上を観に行きました。せっかくの機会だからと、スマートフォンで写真や動画を撮りながら観戦していたのですが、帰宅してみると、あの瞬間の興奮や空気感がまったく思い出せないことに気づきました。映像は残っているのに、体験の記憶がない。なんだか不思議で、少し寂しい気持ちになりました。
その話を後日、知人にしたところ、「それ、すごく分かる」と同調されました。「観戦のときは、あんまりスマホに夢中にならない方がいいよ。動画や写真なんて、ネットにいくらでもあるから」と言われて、ハッとしました。確かに、撮ることに意識を向けすぎて、あの場の音や振動、夜風の匂い、観客席のざわめき――そんな“感覚”を自分で遮断してしまっていたのです。
この記事で紹介されている「五感でデザインするまちの体験価値」という考え方を読んで、その違和感の正体がようやく腑に落ちました。人の記憶は、視覚だけでなく、音や香り、触感など複数の感覚が重なったときに強く刻まれる。つまり、スマホ越しの記録は“情報”であっても、“体験”にはなりにくいのです。
街やイベント、そして日常の風景も同じかもしれません。見るだけでなく、聴いて、感じて、香りを吸い込んでこそ、記憶になる。そう思うと、五感を通じて世界を感じることは、忙しい現代で失われつつある“人間らしい営み”なのだと感じます。
次にスタジアムへ行くときは、スマホを少しだけポケットにしまって、音と光と風をまるごと記憶に焼き付けてみようと思います。
それでは次回も「データのじかんNews」をよろしくお願いします!

データのじかんは、テクノロジーやデータで、ビジネスや社会を変え、文化をつくりあげようとする越境者のみなさまに寄り添うメディアです。
越境者の興味・関心を高める話題や越境者の思考を発信するレポート、あるいは越境者の負担を減らすアイデアや越境者の拠り所となる居場所などを具体的なコンテンツとして提供することで、データのじかんは現状の日本にあるさまざまなギャップを埋めていきたいと考えています。
(畑中 一平)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
ChatGPTとAPI連携したぼくたちが
機械的に答えます!
何か面白いことを言うかもしれないので、なんでもお気軽に質問してみてください。
ただし、何を聞いてもらってもいいですけど、責任は取れませんので、自己責任でお願いします。
無料ですよー
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

