




目次
インタラクティブセッションには、株式会社ベルニクス代表取締役社長であり、株式会社ベルデザイン代表取締役 CEO 鈴木健一郎氏、コイズミ照明株式会社店舗施設商品部部長の村松洋輔氏、象印マホービン株式会社生産開発本部長の山根博志氏が登壇。エリコンジャパン株式会社バルザース事業本部シニアアドバイザーの田岡秀樹氏がモデレーターを務めた。
はじめに、産業機器向け電源メーカーであるベルニクスの鈴木氏が、ワイヤレス給電事業を展開するに至った経緯を次のように語った。

株式会社ベルニクス代表取締役社長、株式会社ベルデザインCEOの鈴木健一郎氏
「ワイヤレス給電の技術は、100年以上変わらなかったコンセントとケーブルによる『電気の配り方』を刷新し、次世代の電源プラットフォームをつくる可能性を秘めています。しかし、この分野に日本の大手電機メーカーが積極的に取り組んでいない現状に危機感を覚え、挑戦を決断しました」(鈴木氏)
ワイヤレス給電は、電気エネルギーを磁気エネルギーに変換し、空間を通じて伝送する技術だ。この仕組みによりケーブルが不要になるため断線のリスクがなくなり、さらに物体の透過が可能なため、水回りや野外での漏電リスクが低減する。この技術は、日本においては2011年頃から「Qi」(チー)という規格で一部のスマートフォンに搭載されている他、シェアサイクルの充電、内視鏡、搬送ロボット、自動回転扉などに活用されているが、いまだに十分普及しているとはいえない。
こうした背景から、ベルニクスは独自のワイヤレス給電システム「POWER SPOT」(パワースポット)を開発。Qi規格の最大出力(15ワット)の約3倍となる50ワットの送電を実現した。さらに2019年には、社内スタートアップとしてベルデザインを設立し、パートナー企業との協業を通じた新たな顧客価値の創出に乗り出した。
パートナー企業との共創によって生まれた製品は2つある。1つは象印マホービンとの協業で2023年に発売した「POWER SPOT MUG」(パワースポットマグ)と、コイズミ照明と共同開発したスマートライト「siliconeball」(シリコーンボール)だ。
・受電装置を内蔵したタンブラーをPOWER SPOTに置くだけで充電可能
・タンブラーを回すことで温度調節が可能で、丸洗いもできる画期的な設計
・左右に回すことで調光可能
・将来的にはバッテリーを内蔵することで、持ち運びでの使用を可能にする計画

「siliconeball」(左)と「POWER SPOT MUG」(右)
また、POWER SPOTの特筆すべき特徴として、IoTデバイスとしてのデータ収集機能が挙げられる。例えば、タンブラーの場合、使用場所や飲み物の種類、時間帯などのデータの取得・分析することで、さらなる価値創出が期待できる。
POWER SPOTを活用した協業は、他にも広がっている。東急電鉄株式会社の新横浜駅にある「Shin-Yoko Gateway Spot」では、スマートフォンやイヤホンなどを置くだけで充電できるワイヤレス給電を提供。また、三井不動産株式会社が手がける法人向けシェアオフィス「ワークスタイリング 東京ミッドタウン八重洲」には、POWER SPOTを通じたワイヤレス給電の他、siliconeballも設置されている。もちろん、こうしたスポットに設置されたデバイスからは、利用時間や送電ワット数などのデータを収集可能だ。
鈴木氏による共創プロジェクトの説明を受けてモデレーターの田岡氏は、共創パートナーとなった象印マホービン、コイズミ照明の2社に向けて、「ワイヤレス給電に初めて接した際、どのような未来をイメージしましたか」と質問した。
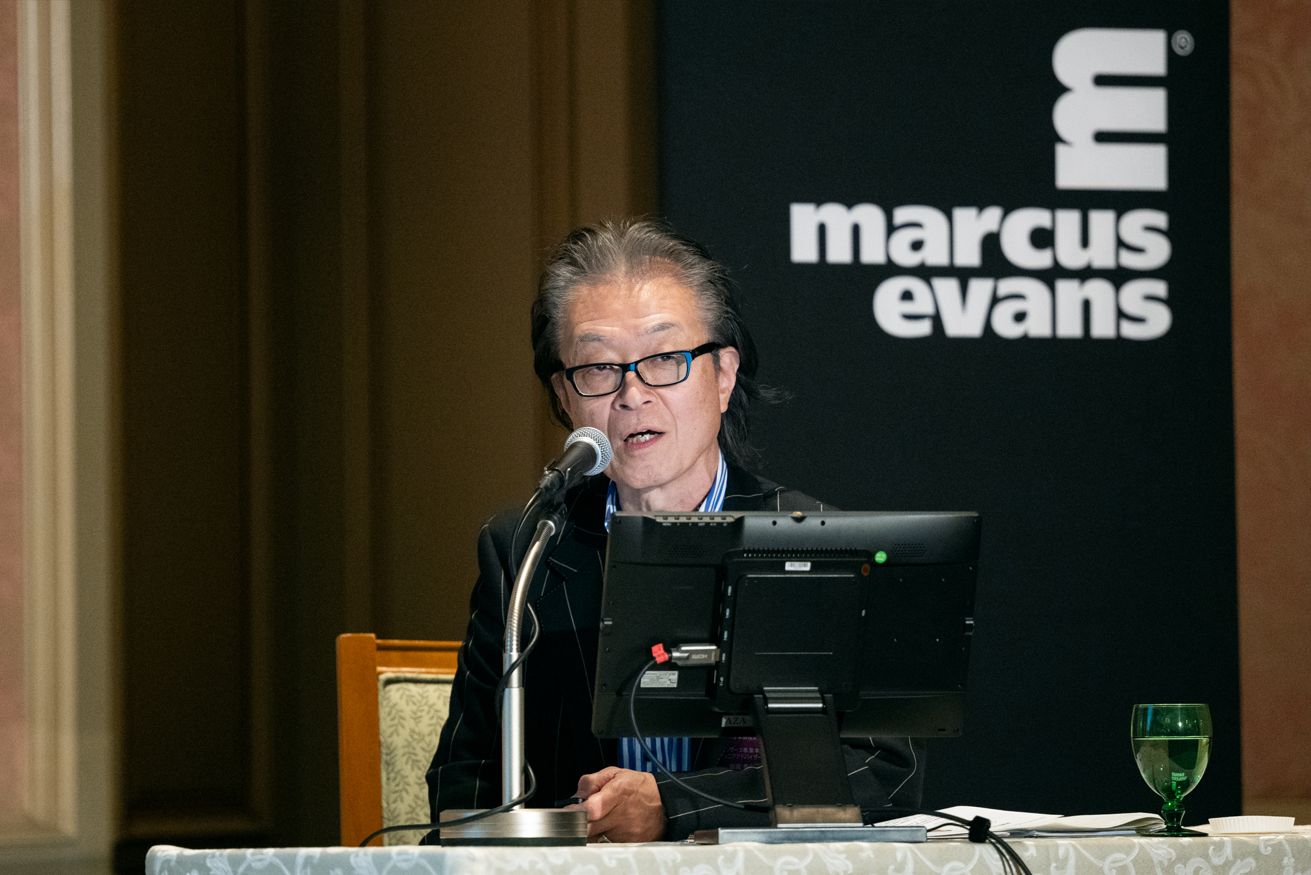
エリコンジャパン株式会社バルザース事業本部シニアアドバイザーの田岡秀樹氏
コイズミ照明の村松氏は、「現状では送電装置に配線がいるので、照明用の電気工事は変わらず必要です。しかし、調光の無線制御が可能になったように、将来的に電源線自体が不要になれば、照明機器の配置計画や電気工事の効率化に大きく貢献すると考えました」と振り返る。
コイズミ照明では、メーカーとして未来を見通すために、「SDGsプロジェクト」「先進技術プロジェクト」が動き出している。村松氏はこれらプロジェクトの推進者を兼任しており、先進技術プロジェクトで無線給電をテーマの1つに設定していたことが、ベルデザインとの協業につながっている。
一方、象印マホービンの山根氏は、「これはいける」と直感したという。「当社は炊飯器などの電気製品以外に、ステンレスボトルをつくっています。しかし、非電気製品と電気は相性が悪く、融合は困難でした。ワイヤレス給電は、これを打開する技術だと感じました」(山根氏)
山根氏は、調理家電や生活家電は将来的に全てワイヤレス給電にすることができると、相性の良さを強調する。そして、「感電の危険がなく、後片づけも簡単になる。これにより、いっそう快適で豊かな生活空間が実現できる」とビジョンを語った。
続いて田岡氏は、「イノベーションに向けた協業・共創に踏み出せずにいる製造企業が多い中で、実現に向けてプロジェクトを推進できたポイントは何か」と切り込んだ。
プロジェクトの成功要因について、村松氏は「キャストの重要性」を挙げる。自らは「課題解決が好きなチームリーダー」となり、スピーディーかつひたすらデザインに打ち込む「愚直なクリエイター」、実験的に没頭できる「腕慣らしが好きな技術者」、モノづくりを担う「一点ものが好きな開発者」が揃ったという。「同時に経営層の後押しを得ることも重要でした」と明かす。

コイズミ照明株式会社店舗施設商品部部長の村松洋輔氏
一方、山根氏は「社内の信頼」と「適切なパートナーシップ」の重要性を強調する。自身が過去にレンジとグリルの自動切換えで調理を簡単にするオーブンレンジ「EVERINO」(エブリノ)、かまどの炎のゆらぎを再現した炊飯器「炎舞炊き」などヒット商品の開発に携わっており、「新製品の開発において、社内から一定の信頼があったことが追い風になりました」と振り返る。
さらに、山根氏が生産・開発・企画を全て管理する立場にあったことから、初期から「いける」と事業可能性について確信があったという。その一方で、「市場開拓は自社だけでは難しい」とも考えていたという。
「POWER SPOT MUGは、製品の性質的にも価格的にも、当社の営業が持つ販売ルートにはマッチしません。そこで鈴木さんが持つ、販路を築いていく行動力や突破力に賭けることにしました」(山根氏)

象印マホービン株式会社生産開発本部長の山根博志氏
最後に、田岡氏は「協業・共創が、製造業の未来を切り開く鍵」と総括。それに対して村松氏は「イノベーションを目指すプロジェクトでは、最終的なゴールは見えません。1歩というより、0.1歩を繰り返す感覚でした。そのような中でプロジェクトメンバーのモチベーションを維持するために、ハードルの低いゴールを設定し、定期的にアウトプットを出すプロジェクト設計が重要です」と語った。
山根氏は「1歩も重要ですが、中韓やアジア企業のスピード感を目の当たりにすると、できるだけ早く道を開き、ポジションを築かなければならないと考えずにはいられません」と危機感をあらわにする。
これに対して鈴木氏も、「ビジネススピードを上げるには、トップの理解度と失敗を許容する企業風土が不可欠」と続け、今回の2社との共創について「ファーストサンプルが出るまでに3カ月かからなかった」ことを成功要因として挙げた。
2社が共創プロジェクトをスピーディーに展開した背景には、企業理念にもとづく風土があったといえる。コイズミ照明は「あかりのありかを求めて」というスローガンを掲げており、「照明が新たに果たせる役割を探す」という意識が社内に根づいている。「ワイヤレス給電という技術に接して、10年後もその商品企画ができると想像できました」(村松氏)
また、象印マホービンの創業時からの企業理念「暮らしをつくる」には、「先を見ること」が欠かせないという。「しっかりしたモノづくりでは、半歩先を見据える必要があります。しかし、全く新しい価値を生み出すには、さらに半歩先を考えなければなりません」(山根氏)
ワイヤレス給電は、製造業の未来を切り開くコア技術の1つといえるだろう。このような技術を基盤とし、企業同士が協業・共創を進めることで、新たな市場や顧客価値を創出していく。今回の事例は、その可能性を示す好例といえる。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

