



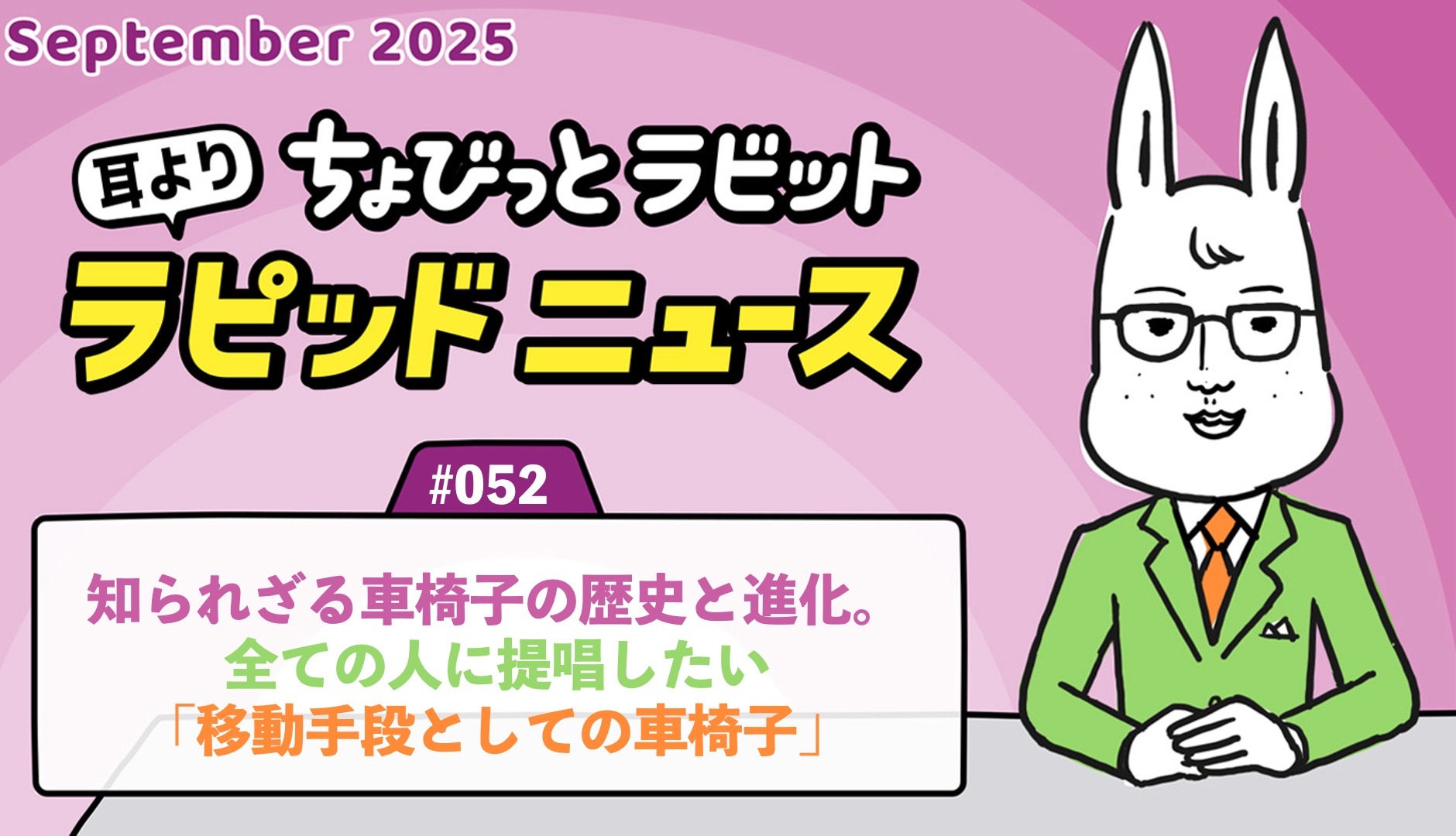
目次
まいどどうも、みなさん、こんにちは。
わたくし世界が誇るハイスペックウサギであり、かのメソポ田宮商事の日本支社長、ウサギ社長であります。つい先日、「石破氏、辞めるってよ」というニュースが日本列島を駆け巡りましたが、そのニュースにあまり多くの人が驚かなかったことに不覚にも驚きを覚えてしまいました。とは言え、後任が誰になるのかについてはとても気になるところであります。
さて、先週は移動格差についてお話ししましたが、超高齢化社会へと新幹線並みの速度でまっしぐらに進むこの日本列島において、免許返納を奨励しつつも車がないと生きていけないエリアにおける高齢者の暮らしをどうやって支えていくかに対しての具体案は特にない、という部分の移動に関する課題というのは非常に深刻なものがあるわけでありまして、今よりも来年、来年よりも再来年、そして五年後、十年後と深刻さは増す一方だと予測されております。自動運転が実現すれば、という声もありますが、法整備の問題もありますし、そもそもの経済的な理由もあり、自動運転車を高齢者が購入して使う、というのは現実的な問題の解決にはならないのではないかとわたくしは考えております。
では、どうすれば良いのか、というところですが、わたくしが着目しているのはずばり移動手段としての車椅子です。つまり、Wheelchair As A Trasnportation、WaaTというコンセプトであります。他のMaaSやSaaSと表記を合わせるのであれば、Wheelchair As A Service、WaaSとしてもよいところではありますが、サービスというよりも交通手段でありますので、わたくしとしてはWaaTという表記を奨励しております。Waatと調べてもスーダンの村くらいしかヒットしないのはわたくしが考えたコンセプトであり、ここで初めて発表するものであるからです。
これは、歩行困難な方が車椅子を利用する、というだけでなく、歩行可能な方も車椅子を自転車や自動車のように一つの交通手段として活用する、という概念になります。これはパーソナルモビリティーと呼ばれたりもしますし、シニアカーのようなものが実際に販売されていますが、まだ十分に普及しているとは言えないでしょう。そこで今回は、車椅子にスポットライトを当て、車椅子の起源からその進化の歴史、そして考えうる今後の展望についてお話ししてみたいと思いますのでぜひ最後までお付き合いください。意外かも知れませんが、かなりSFチックな進化をしてきているのです。

車椅子の原型が登場したのは古代。つまり、座ったまま移動したい、という人類の欲望は古代から存在したということになります。紀元前6世紀の中国には、車輪付きの椅子が存在していたという記録があります。ヨーロッパでも16世紀にはスペイン王フェリペ2世が「肘掛け付き移動椅子」に座っていたそうです。この時代の飛び方が気になるところではありますが、その間人類はあまり車椅子について考えてこなかったと推測されます。その当時のものももちろん今のように自由自在ではなく、ほとんど「人に押してもらうための椅子」であり、家具として椅子に車輪がついた、という形でありました。
つまり、最初の車椅子は「移動の自立」よりも「王族や身分の高い人を楽に運ぶ道具」という位置づけだったことになります。「福祉機器」という発想はまったくもってなかったわけです。
1655年に当時22歳だったドイツの時計職人ステファン・ファーフラーは自走式の手漕ぎの椅子を開発し、これは後に自転車の発明にもつながるナイスイノベーションとも言える大発見であり、多くの発明家がこの概念に触発されたそうです。ファーフラーは幼少期の事故で歩行困難だったそうで、自力で教会に通えるようにとこの自走式の椅子を開発したのだとか。いずれにしても素晴らしい発明ですね。
そして、車椅子が大きく進化したのは20世紀初頭。1932年にアメリカで「折りたたみ式車椅子」が登場します。鉄製ではあるものの、軽量で、車に積んで運ぶことができる車椅子の発明により病院や家庭での普及が一気に広がりました。
1950年代にはアルミフレームが導入され、さらに軽くなりました。スポーツ用車椅子も登場し、1960年にはパラリンピックの原型となる「ローマ大会」が開催され、車椅子は「生活のための道具」という位置付けから、「挑戦と表現のための道具」へと認識を変えて行きました。

1970年代以降は電動車椅子の普及期となります。バッテリーとモーターを搭載し、ジョイスティックによる操作が可能になりました。それまでは「誰かに押してもらう」あるいは「腕力で漕ぐ」しかなかった移動手段が、スイッチ一つでコントロールできるようになりました。
ただし、重量は100kg近くにもなり、段差や狭い通路ではまだ苦労が多かったのも事実です。ここからメーカー各社が「小型化」「省電力化」「走破性アップ」の技術競争に突入していきます。
2000年代に入ると、研究者やスタートアップが「従来の車椅子の限界を超える」製品を次々発表します。車椅子での移動を阻止するものの代表格と言えば階段ですが、スイスの学生たちが開発しているSwecoは階段や段差のある雪道などを進むことができる設計となっています。日本でもLIFEHUB社が開発した「AVEST Launch Edition」という車椅子があり、こちらも階段が登れるようなデザインとなっています。
また、立ち上がったままの姿勢で移動できるモデルである「Qolo(コロ)」などの開発も進んでいます。車椅子ユーザーが身の回りにいないとなかなかこの進化の波に気付くことができませんが、着々と開発は進んでおり、不可能だったことが一つずつ可能になってきているようです。
そして、今現在の最新形が、ホンダが2025年9月8日に発表し、9月24日から発売される「UNI-ONE」です。ホンダ社が二足歩行ができるロボットであるASIMOの開発研究で培った技術を活用し、座ったまま体重移動するだけで操作が可能となっています。操作の基本的な考え方はセグウェイにかなり近いのではないかと想像します。ホンダ社はこれを「モビリティデバイス」と呼んでいるのですが、「車椅子」という単語を避けることで歩行が困難な人だけでなく、誰しもが楽に移動するための椅子、という位置付けにしたいと考えているようです。ただ、現在は月額のレンタル料金が10万円以上となっているため、まだまだ気軽に近所のおじいちゃんおばあちゃんに使ってもらえる移動手段というわけではありません。この価格設定ではまだわたくしが冒頭で提唱した「WaaT」のコンセプトには当てはまらず、そこは残念極まりないのですが、かなりの進歩であることには相違ありません。
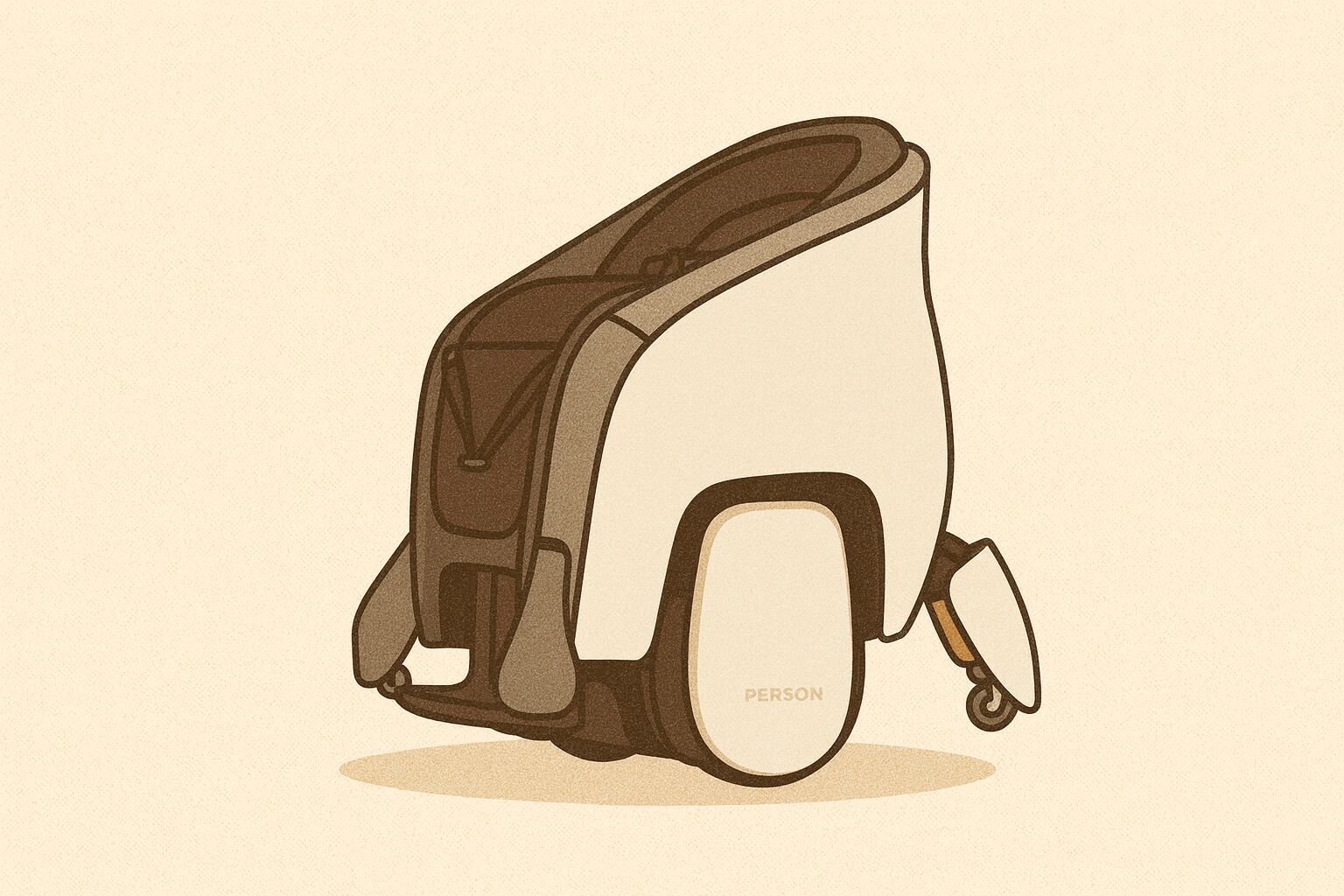
庶民の移動手段は少し前までは自転車が主流でした。自転車は「チャリ」あるいは「チャリンコ」などと軽々しく呼ばれるほど一般的となり、価格帯も極めてリーズナブルなものでした。そこまで安価である必要はないのかも知れませんが、このような移動手段としての車椅子が自転車の代替となる程度に大量生産が可能になればかなり安価で多くの人に普及できるようになるのではないかとわたくしはウサギながら考えておるところであります。
これまでの移動は「早く目的地に辿り着く」にフォーカスしてきたように思いますが、高齢者の生活パターンなどを見ていると、「時間がかかっても確実にかつ体に大きな負担を強いることなく目的地に辿り着くこと」が重要視されても良いように感じております。速度が遅いことは安全性にもつながるわけですし、高齢者にとっては2キロ先のスーパーまでどうやって行くか、そして買い物袋を持ってどうやって戻るか、という暮らしの中のラストワンマイル問題は文字通り死活問題なわけです。そういう意味ではまだまだ車椅子はどこかで「王族や身分の高い人を楽に運ぶ道具」という位置付けを失っておらず、たこ焼きや串カツ、あるいはお好み焼きのような大衆文化と呼べるところまでは降りてきていないと言えます。実際に、日本で障害者手帳を持つ人は約970万人いると言われています。そのうち「下肢不自由」で車椅子を使っている人は数十万人規模ですが、電動車椅子の保有率はまだ2割程度。価格や使える場所の制限が大きなハードルとなっているのだそうです。
UNI-ONEなどの最新型、そして、そこからさらに進化し、たとえば自動運転が可能な車椅子がバスや電車などの公共交通機関がないところで暮らす一人暮らしのおばあちゃん、寝ながら通勤したいお父さん、あるいは帰宅時間が暗くなってしまう塾通いの小学生などにも気軽に使えるようになれば移動格差の解消の一助となり、それによって解決される、あるいは緩和される社会問題が数多くあるのではないかと思い、世のため、人のため、そしてウサギたちのさらなる子孫繁栄のためにわたくしはここにWaaTのコンセプトの重要さを改めて提唱させていただきたく思います。
そんなわけで、また再来週の水曜日にお会いしましょう。ちょびっとラビットのまとめ読みはこちらからどうぞ!それでは、アデュー、エブリワン!
(ウサギ社長)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

