



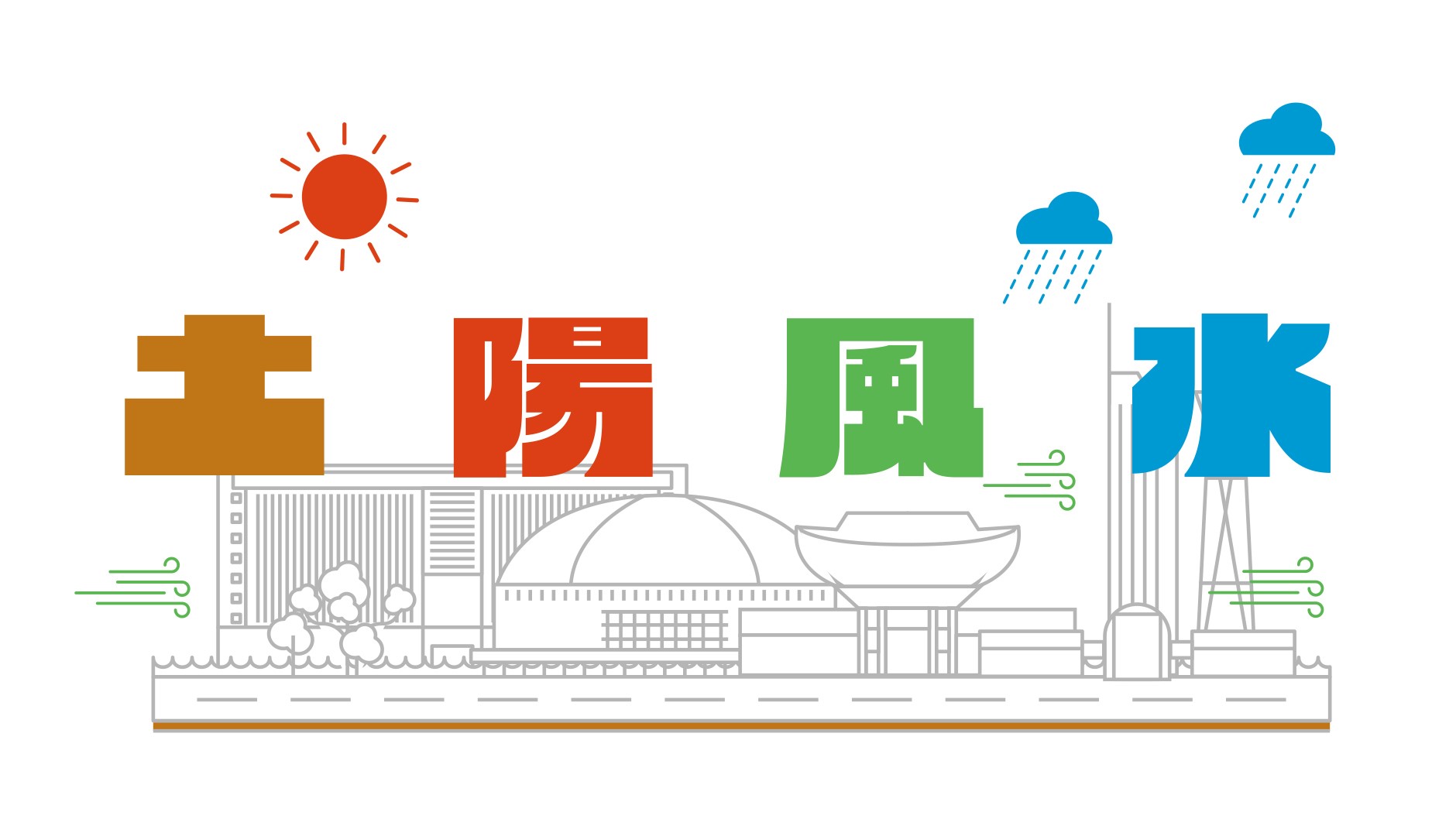
地域・社会が抱えるさまざまな課題解決のためのソーシャルデザインに取り組んでいる筧裕介氏(issue+design代表)は、持続可能な地域には4つの条件が必要だといいます。
土:つながり協働し高め合う「地域コミュニティ」
陽:道を照らしみんなを導く「未来ビジョン」
風:一人ひとりの生きがいを創る「チャレンジ」
水:未来を切り拓く力を育む「次世代教育」
スタートアップはそのいずれの要素にも関わることができますが、とりわけインパクトを与えられるのは「風=チャレンジ」でしょう。文字通りの風、つまり空気の流れが生じるためには「熱」が必要なのと同じように、地域にチャレンジが生まれるためには「熱=個人の思い」が不可欠です。
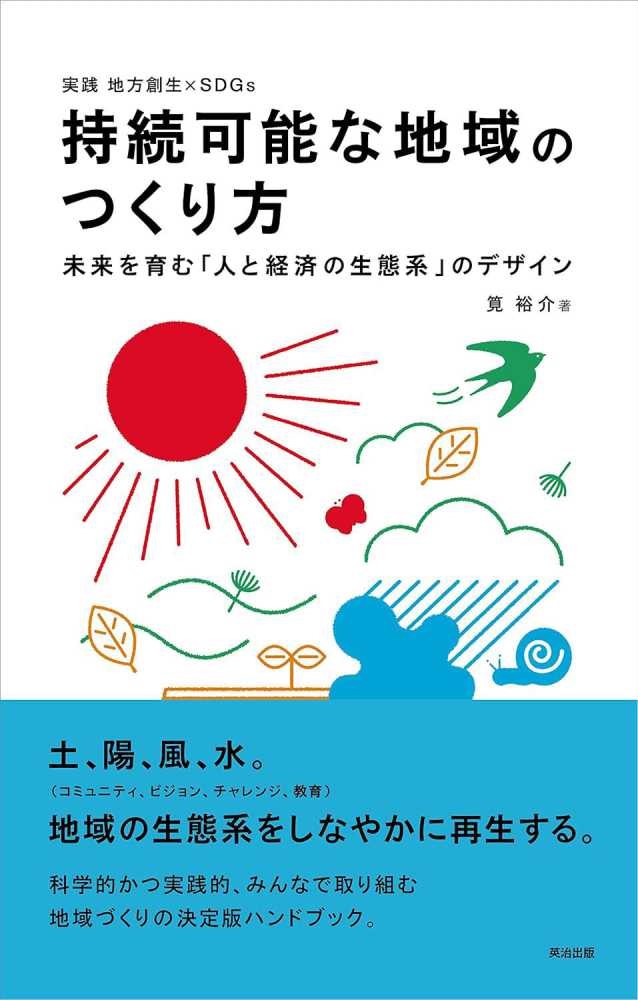
出典:筧裕介著『持続可能な地域のつくり方~未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン』(英知出版)
筧氏によると、「熱」は主に地域の内から沸き立つ「地熱」、よそ者が持ち込む「外熱」、内と外の相互作用で生まれる「化学反応熱」の3つのカタチで生まれるといいます。そして、熱を起こし、持続させるためには仲間が必要であるとしますが、「熱」と「仲間」が掛け合わされ、エネルギーを増幅する作用を持っているのがまさにスタートアップであるといえるでしょう。
イノベーションを起こすための思考プロセス「U理論」の提唱者であるオットー・シャーマー博士によると、誰もが利己的で自分のことばかり考える「小さな自己」と、他者や社会に貢献しようとしたり、新しい何かを生み出そうとする「大きな自己」の両方を持っているといいます。そして、必要としてくれる人がいて、誰か他者のため、社会のためにチャレンジしようとするとき、つまり「小さな自己」を脱却し「大きな自己」にシフトしようとするとき、人は自分の能力ギリギリか、それを少し超える領域のことに挑もうとするそうです。
これをスタートアップに当てはめると、立ち上がったばかりのプロダクトやサービスを必要としてくれる人が地域社会ですぐそばにいると、開発する側はスピーディーに成長できます。スタートアップは大企業に比べ、機動的・柔軟的に対応できるため、地方の自治体とのコミュニケーションもスムーズです。また、スタートアップが順調に成長していくことで地域における雇用創出にもつながることが期待できます。結果的に双方のコスト削減につながるため、Win-Win関係が構築されやすいのです。
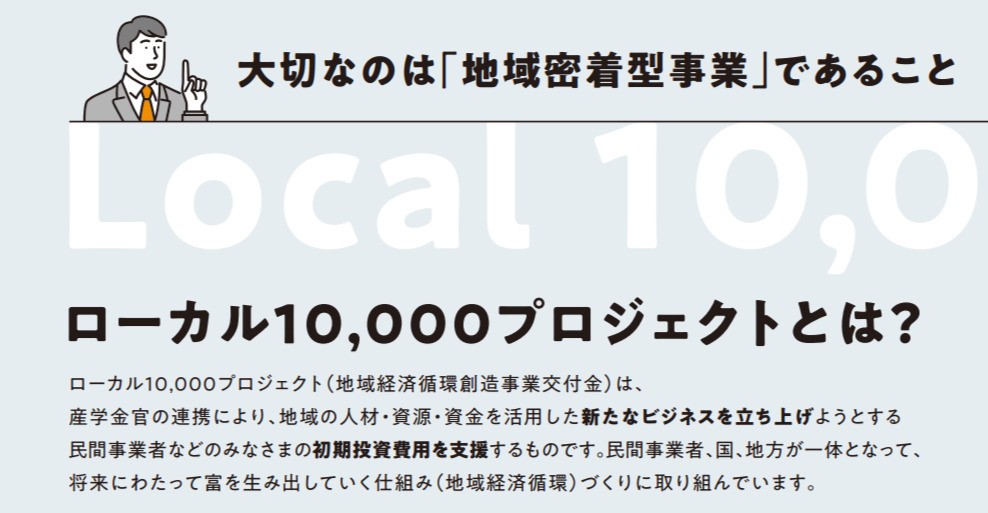
スタートアップが地域活性化や地域経済循環に与えるインパクトに注目して、総務省も令和6年度から「ローカル10,000プロジェクト(地域経済循環創造事業交付金)」を創設しました。これは、産学金官連携により、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者の初期投資費用を支援するもので、交付額の上限は最大5,000万円です。
地域密着型事業であることが必須であり、その土地の資源や資金を活用することや、地域の課題解決につながる事業であること、地域の新たな雇用創出が期待できる事業であることなどが条件に含まれます。具体的には古民家等の空き家や廃校を利用した事業、地元の農林水産物を活用した6次産業化、新商品開発の促進、伝統技術や伝統工芸の承継などがあります。
例えば、ローカル10,000プロジェクトを活用した事例として、長野県佐久市の「Brewing Farmers & Company(ブリューイングファーマーズ&カンパニー)」があります。同社は工場跡地をリフォームし、世界発、エネルギー源の確保から原材料まで全てを自然素材でまかなう持続可能な製法の「どぶろく」製造を行っています。薪ボイラーを整備し、地元の間伐採を活用してエネルギー源を確保しています。

また、スタートアップと地域の困りごとを結びつける試みとして、福岡県ベンチャービジネス支援協議会が主催する「福岡オープンイノベーションプログラム(FOIP)」もあります。
これは、福岡県内の自治体が抱える地域課題を全国のベンチャー企業の製品やサービスによって解決しようというプログラムです。自治体とベンチャー企業が連携し、地域内で展開することで、行政DX、市民サービスの向上、新ビジネスの創出を目指します。
一例として、人口の100倍超の観光客(令和5年は約881万人)が訪れる福岡県太宰府市は「観光の回遊性向上による経済効果の拡大」という課題を抱えていたところ、FOIPを通じて解決策を募り、株式会社TRIPLUSが展開するマッチングサービスを導入しました。
「TRIPLUS」は、50歳以上のアクティブシニアが持つ経験やスキルを、インバウンド向けの体験コンテンツとして仕立てて販売するもので、「太宰府型全世代居場所と出番構想」を掲げる太宰府市の観光戦略とマッチしたようです。
外国人観光客は旅行先の生活様式や文化を体験し、まるでそこで暮らしているかのような日常体験を経験したいというニーズがあります。そこで「TRIPLUS」は、「味噌汁づくり」「おにぎりを握る」「折り紙を折る」など、日本人にとっては日常の「当たり前」に付加価値を与え、コンテンツとして販売できるようにするだけでなく、往々にして地域社会から疎外されてしまいかねないシニア世代に居場所を与え、承認欲求を満たしてくれます。
地域社会においてスタートアップが果たす役割は経済効果にとどまりません。スタートアップは地域社会の各方面のハブ役となり、民間、大学、行政をつなぐ役割を担います。課題解決が実現することで地域社会はますますリバブルな場所になりますし、そこに集うプレイヤーは相互に影響し合い、さらに多くの人を呼び込むことができ、消費も促進されるのです。
著者・図版:河合良成
2008年より中国に渡航、10年にわたり大学などで教鞭を取り、中国文化や市況への造詣が深い。その後、アフリカのガーナに1年半滞在し、地元の言語トゥイ語をマスターすべく奮闘。現在は福岡在住、主に翻訳者、ライターとして活動中。
(TEXT:河合良成 編集:藤冨啓之)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

