



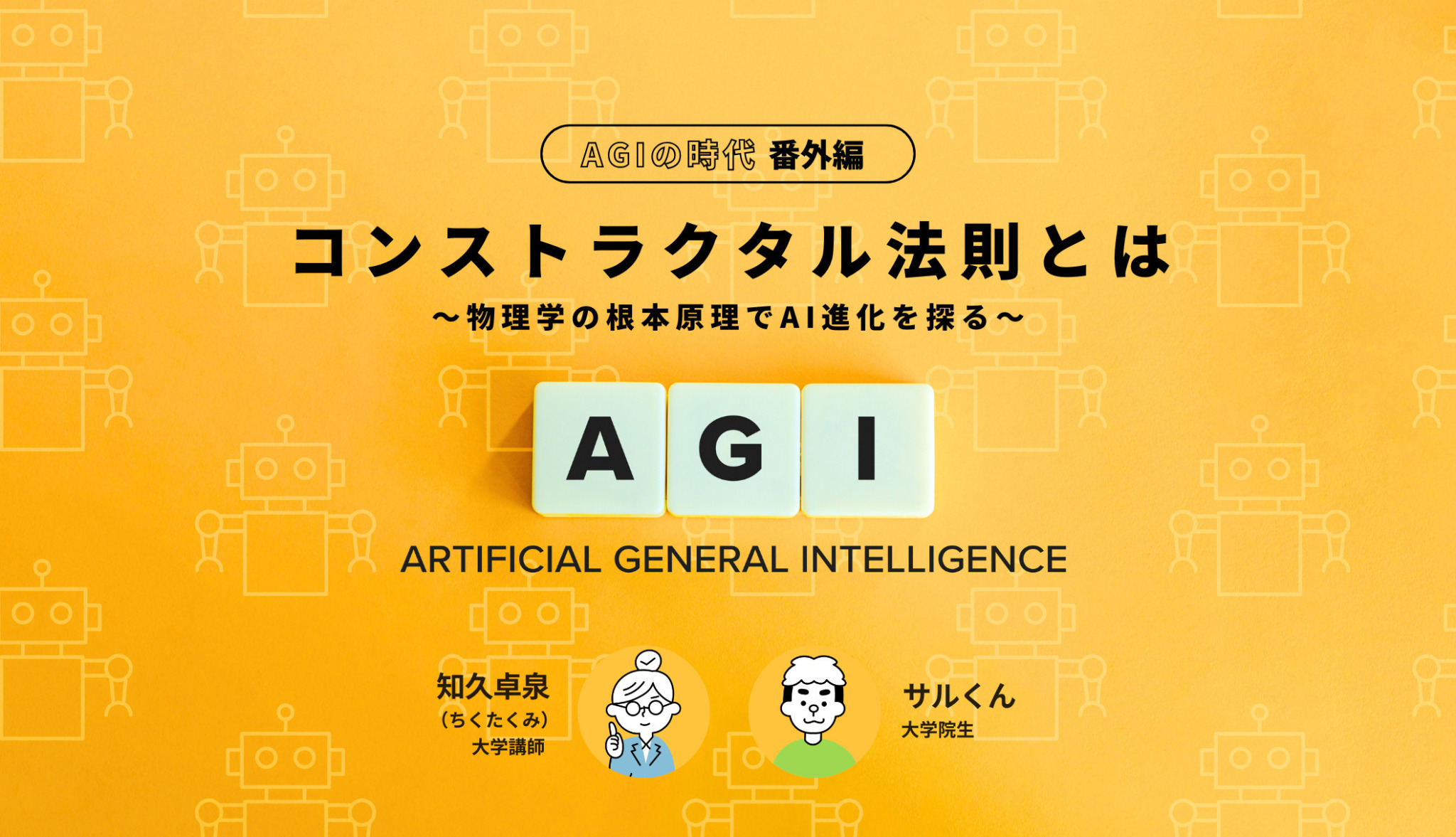


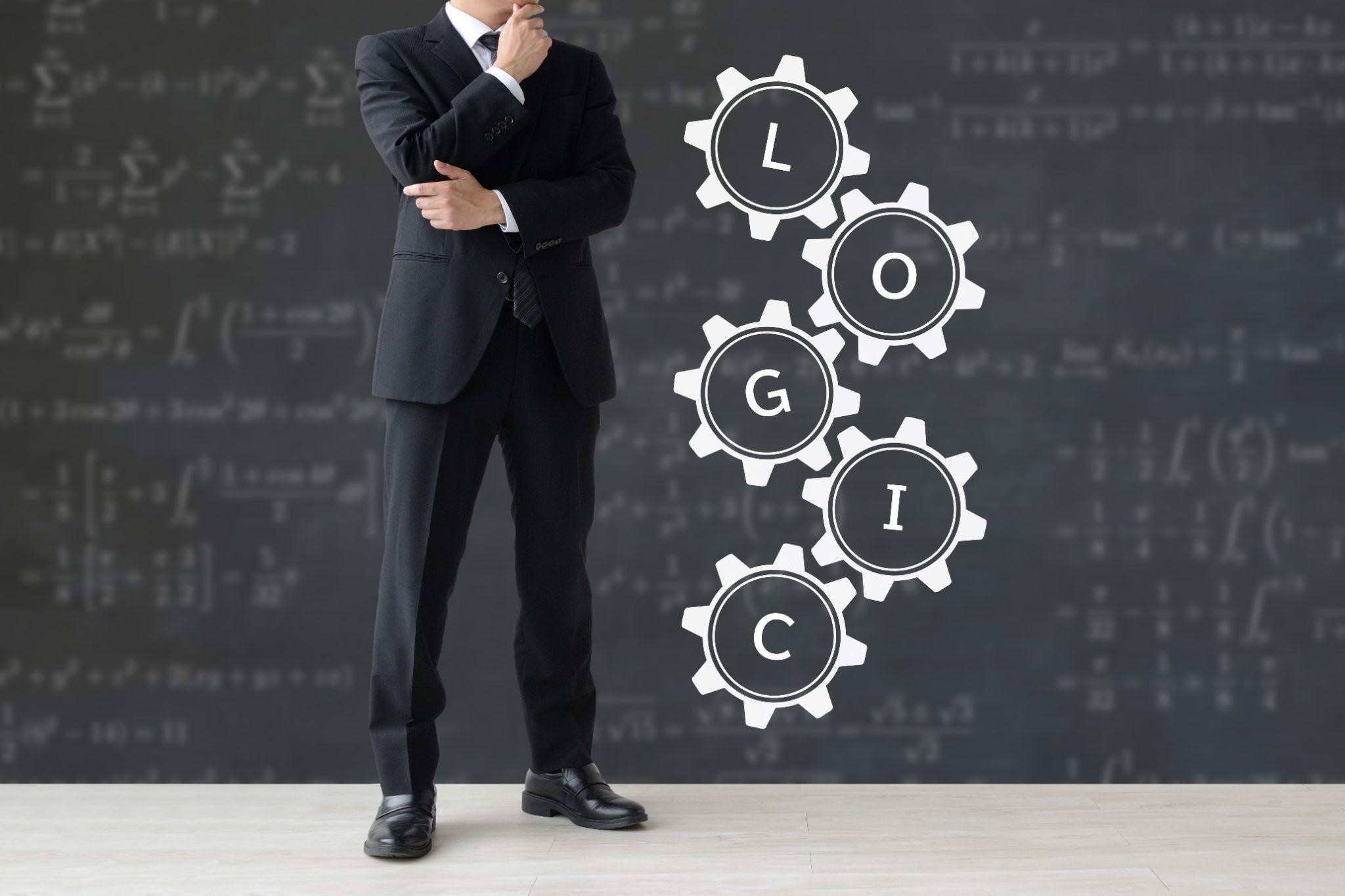
コンストラクタル法則は、ルーマニア生まれでアメリカのデューク大学教授エイドリアン・べジャン(Adrian Bejan)によって提唱された物理学の原理です。この法則は、『生物・無生物を問わず、世界に存在するあらゆる物質は、流れがありかつ自由な領域があれば、より速く、よりなめらかに動くように進化する』というものです。この法則は生物と無生物の両方に適用され、自然界のすべてのもの、たとえば川や木、動物などが、エネルギーや物質の流れを最も効率的に促進するように進化することを示しています。
この法則は、もともとべジャン教授が様々なシステムで熱の流れを研究する際に考案しましたが、この法則が熱システムにとどまらず、非常に広範囲の流動系に適用できると気がついたのです。
べジャン教授は、流動系が流れに対する抵抗を最小限に抑えるように、自らを変化させる傾向があることを観察しました。たとえば、川や小川は、水が高い所から低い所へ流れるのを最適化するために分岐パターンを形成します。同様に、植物や動物の血管系は、栄養素や酸素の流れを最小限の抵抗で促進するように進化します。このような最適化された流れへの進化は、生物学、物理学、経済学、さらには社会組織においてもあることに、べジャン教授は発見したのです。コンストラクタル法則は、次の主要な原理に基づいています。
あらゆる流動系(flow systems)が生じるのは、力(force)が働いているからである。力はあらゆる種類のエンジンに由来し、すべて自然に生じる流動構造である。
環境は流動系の動きに抵抗しブレーキとなり、動きを起こした力は熱として散逸して、環境に伝達される。
流動系は変化する自由があれば、まとまって構成する普遍的特徴・規模の経済(Economies of scale)がある。
まとまった構成は、少数の大きなものと多数の小さなものという階層制(hierarchy)をとる。
進化とは、単なる生物学的進化より、はるかに幅の広い概念であり、物理の概念だ。人類は「人間と機械が一体化した種」であり、各個体は人間の考案した機械(道具)と共に日々進化する。
デザイン(意味を持った形状)の進化は、普遍的な自然現象であり、特有な物理法則で予測できる。生物か無生物かにかかわらず、同じ系(流れ)の中に置かれれば、同じようなデザインに進化する。
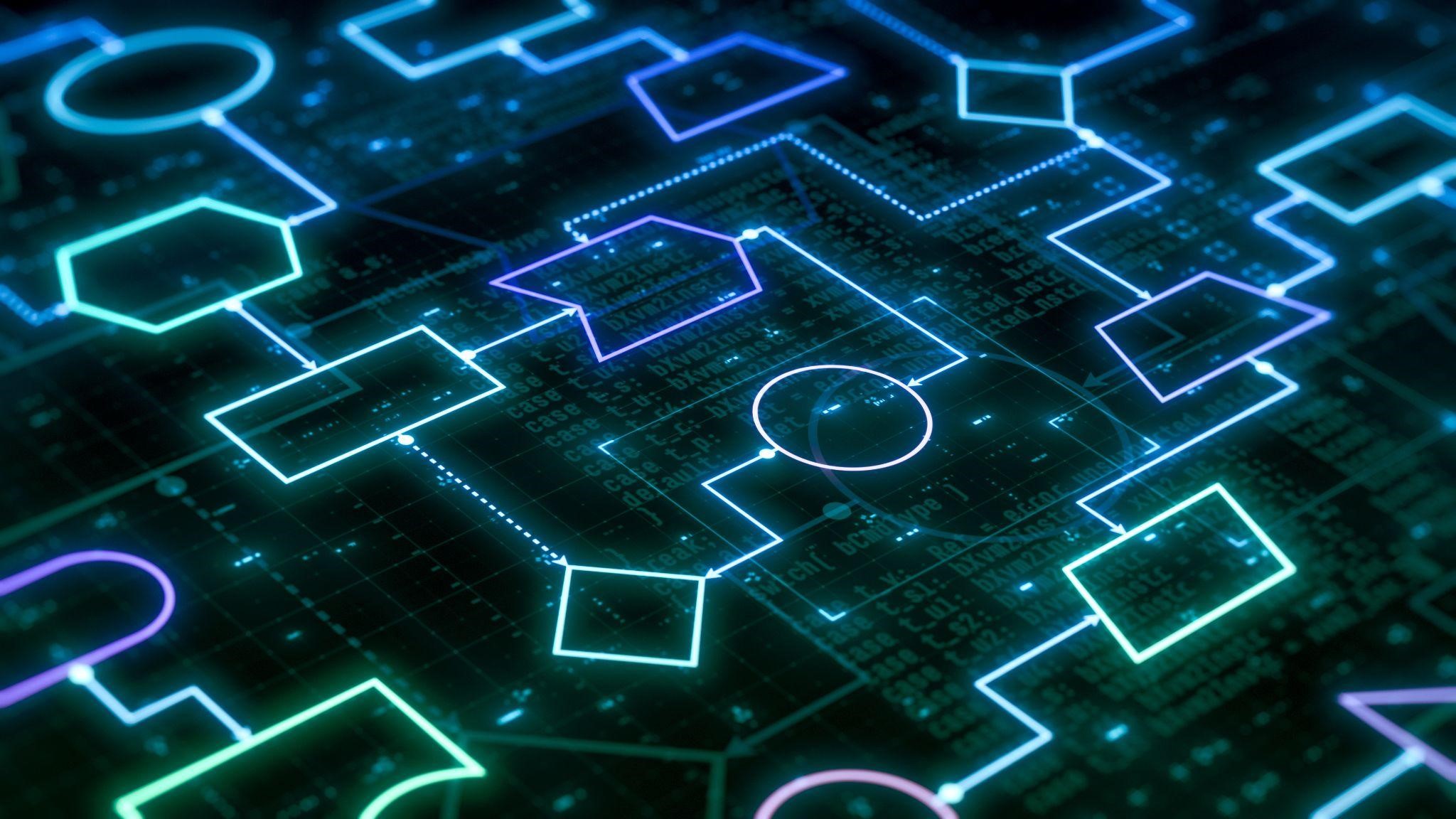
コンストラクタル法則は、さまざまな分野に広範な応用ができます。
生物学では、コンストラクタル法則は、エネルギーや物質の流れを促進する能力に関する生物の進化を説明できます。たとえば、血管の分岐構造は、酸素や栄養素を体全体に効率的に供給するための手段です。同様に、動物の呼吸系も、空気の流入と流出を最大化するように進化しています。
この法則はまた、異なるサイズの動物が異なる代謝率を持つ理由を説明できます。動物の代謝率は、体重あたりのエネルギー消費量で表され、体重が小さいほど大きくなります。これは、大きな動物は広範な血管系を持っており、血液をより効率的に循環させるように進化しているためです。その結果、ハツカネズミよりも象の代謝率は、かなり低くなります。
地球物理学では、コンストラクタル法則は、河川流域、デルタ、山脈などの自然構造の形成を説明できます。これらの構造は、水、堆積物、その他の物質の最も効率的な流れを可能にするように進化しています。例えば、河川ネットワークは水の流れに対する抵抗を最小限に抑える分岐パターンを形成し、地表から水をできるだけ効率的に排水します。
コンストラクタル法則は、さらに社会および経済システムにも適用できます。経済学では、貿易ネットワークや輸送システムの進化を説明します。川が流れの抵抗を最小限に抑えるために分岐ネットワークを形成するのと同様に、貿易ルートやサプライチェーンも、商品やサービスの流れを最適化するように進化しています。
社会システムでは、組織や政府の階層構造の形成を説明します。生物学的システムが栄養素の流れを促進するために進化するのと同様に、社会システムも情報やリソースの流れを促進するように進化します。企業や政府などの階層構造は、これらの流れを効率的に組織するための手段として出現します。
工学において、コンストラクタル法則は効率的なシステム設計の指針となります。たとえば、熱交換器、流体ネットワーク、さらにはコンピュータネットワークの設計は、コンストラクタル法則の原理を適用することで最適化できます。エンジニアはこの法則を使用することで、熱、流体、または情報の流れに対する抵抗を最小限に抑え、より効率的で信頼性の高い技術を設計できるようになります。
その広範な適用にもかかわらず、コンストラクタル法則には批判があります。特に、生物学者や進化論者からは、この法則が進化過程の複雑さを、過度に単純化していると指摘されています。また、この法則がランダムな変異や遺伝的浮動など、進化に影響を与える要因を考慮していないと批判されています。
また、コンストラクタル法則が従来の意味での『法則』ではなく、ガイドラインや経験則であるという主張があります。この法則はシステムの組織に関する貴重な洞察を提供しますが、万有引力のような物理学の法則のように、普遍的に適用されるものではないのかもしれません。
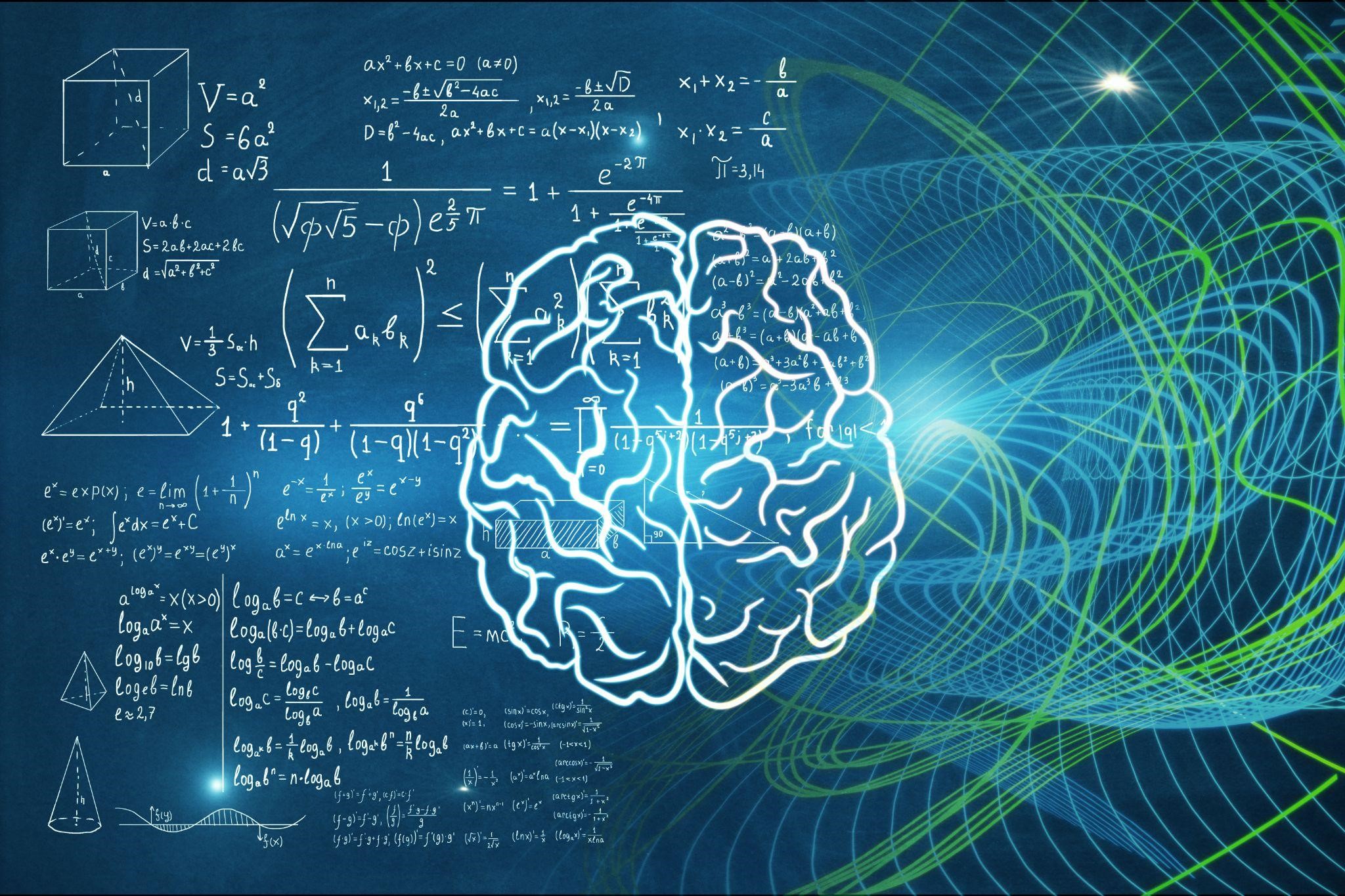
コンストラクタル法則では、進化はランダムではなく、最適化された流動系の普遍的な傾向によって駆動されるとしています。この巨視的視座は、従来の進化観、特に遺伝的変異と自然選択の役割に焦点を当てた進化論に挑戦しています。
さらに、コンストラクタル法則は、一見関連のない現象を結びつける統一原理を提供しました。川、木、動物、さらには人間社会の進化が同じ基本的な原則によって支配されていることを認識することで、自然界の相互関係についての理解が深まります。ただし、大前提として自由が重要になります。動ける自由、変形できる自由が必要です。この条件を満たしていれば、生物学、物理学、社会科学、工学のいずれに適用しても、コンストラクタル法則は、多様な現象を結びつけ、新たな洞察を提供する統一原理となります。批判もありますが、コンストラクタル法則は、複雑なシステムの進化と設計について、科学者やエンジニアの思考に多大な影響を与え続けるはずです。
コンストラクタル法則は、生物・無生物・人工物を含めた自然界すべての進化を理解するための強力なフレームワークだと思います。森羅万象を物理によって一つにまとめあげてしまった統合的見解なのですから、私にとってあまりに魅力的な考え方なのです。

それにしても、チクタク先生はコンストラクタル法則にぞっこんですね。
でも万有引力の発見に匹敵するほどの大発見なら、もっと世間に注目されてもよさそうですが。ボクは今まで一度も聞いたこともないし、日本のマスコミもまったく無視してますよね

べジャン教授は熱力学が専門で、コンストラクタル法則の最初の論文を20年ほど前に発表したのですが、学界からは長い間無視されていました。ところが、熱力学や工学系以外の様々な学問分野から次第に賛同者が現れ、検証されていくことで、20年かけて機械工学の学会でも認められていったのです。
べジャン教授は、『抵抗を受けない学術論文は、すなわち独創性を欠く論文なのである』と言っています。
今では世界各国でコンストラクタル法則のシンポジウムが毎年開催され、多数の論文が発表されて活況を呈しています。しかし日本から発表されたコンストラクタル法則に関する論文を、私はまだ見つけることができていないので、少なくとも日本の学会ではメジャーな話題ではなさそうです

だからほとんど知られていないのか。先生、先ほどの講義を聞いても、前回の講義での質問、”人類は人間と機械が一体化した種であり、各個体は人間の考案した機械と共に日々進化する”、の説明がなかったですよ

ここでの”機械”とは、手の込んだ道具つまり装置を意味し、人工の品をすべて装置としています。
そして、機械やテクノロジーの進化は、進化現象の一種にすぎず、動物の進化と何ら変わりはない、というのがコンストラクタル法則の考え方なのです。
その機械の進化を駆動しているエンジンが人間なので、人類は機械と一体化した“種”なのです。
以前のAI講義の中で、“テクニウム”という言葉を紹介しました。
この言葉はテクノロジーに自由を与えれば可能な限界まで進歩していく生命体のようなものという意味です。
まさしくこの理由を、コンストラクタル法則が説明しているのです

う~む、なんだか言いくるめられたような感じもしますが、ようするに”進化”という言葉の定義を大幅に拡張しているようですね

その通りです。コンストラクタル法則は物理的現象として進化を扱っており、自由に動き、形を変えている生物と無生物のいっさいを対象にしています。進化の考え方を非生命系に当てはめていることが特徴なのです。
さらに、“生命”という言葉は、生物・無生物に関わらず、流動するものという概念でとらえることができる、すべての系(システム)を指し、流れを維持している体系が“生命”だ、という考え方をします

しかしまた、大風呂敷をさらに広げましたね。生命の定義までを物理的視座から捉え直したというか、ここまで概念化したら思想とか哲学ですよ

そうですね。仏教の思想である三法印の一つ”諸行無常”は、”世のすべてのものは、移り変わり、また生まれては消滅する運命を繰り返し、永遠に変わらないものはない”という意味ですが、ギリシャの哲学者ヘラクレイトスの”万物は流転する”と同じことを言っています。
ですからコンストラクタル法則は、古代からある思想を掘り起こしたとも言えます。博識のべジャン教授なら、気が付いていると思いますが

それで、コンストラクタル法則の話が、AIの進化とどう関わるのかが分かりませんが

これで特別講義のコンストラクタル法則の説明は、いったん終わりにします。
今回は、べジャン教授の著書2冊分700頁を無理やり要約してエッセンスだけ話してみました。
次回の講義では、コンストラクタル法則がAI進化に適用できるかを考えてみます
・コンストラクタル法則:「あらゆる物質は流れがありかつ自由な領域があれば、より速く、よりなめらかに動くように進化する」。
・この法則は、生物学、物理学、社会科学、工学のいずれにも適用でき、多様な現象を結びつけ、進化を理解するための統一原理である。
・人類は「人間と機械が一体化した種」であり、各個体は人間の考案した機械と共に日々進化している。
【第2回へ続く】
著者:谷田部卓
AIセミナー講師、著述業、CGイラストレーターなど、主な著書に、MdN社「アフターコロナのITソリューション」「これからのAIビジネス」、日経メディカル「医療AI概論」他、美術展の入賞実績もある。
(TEXT:谷田部卓 編集:藤冨啓之)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!


今までAIの進化について話をしてきて、AGIまでたどり着きました。しかし、さらにその先にあるAIの未来はどうなるか、について考えていると、コンストラクタル法則にたどりついたのです。
そこで今回の講義は特別にコンストラクタル法則について、あくまで概要だけですが説明します。
サルくん、質問や意見は後でまとめて聞きますので、しばらく黙っていてください
ブツブツ・・・