



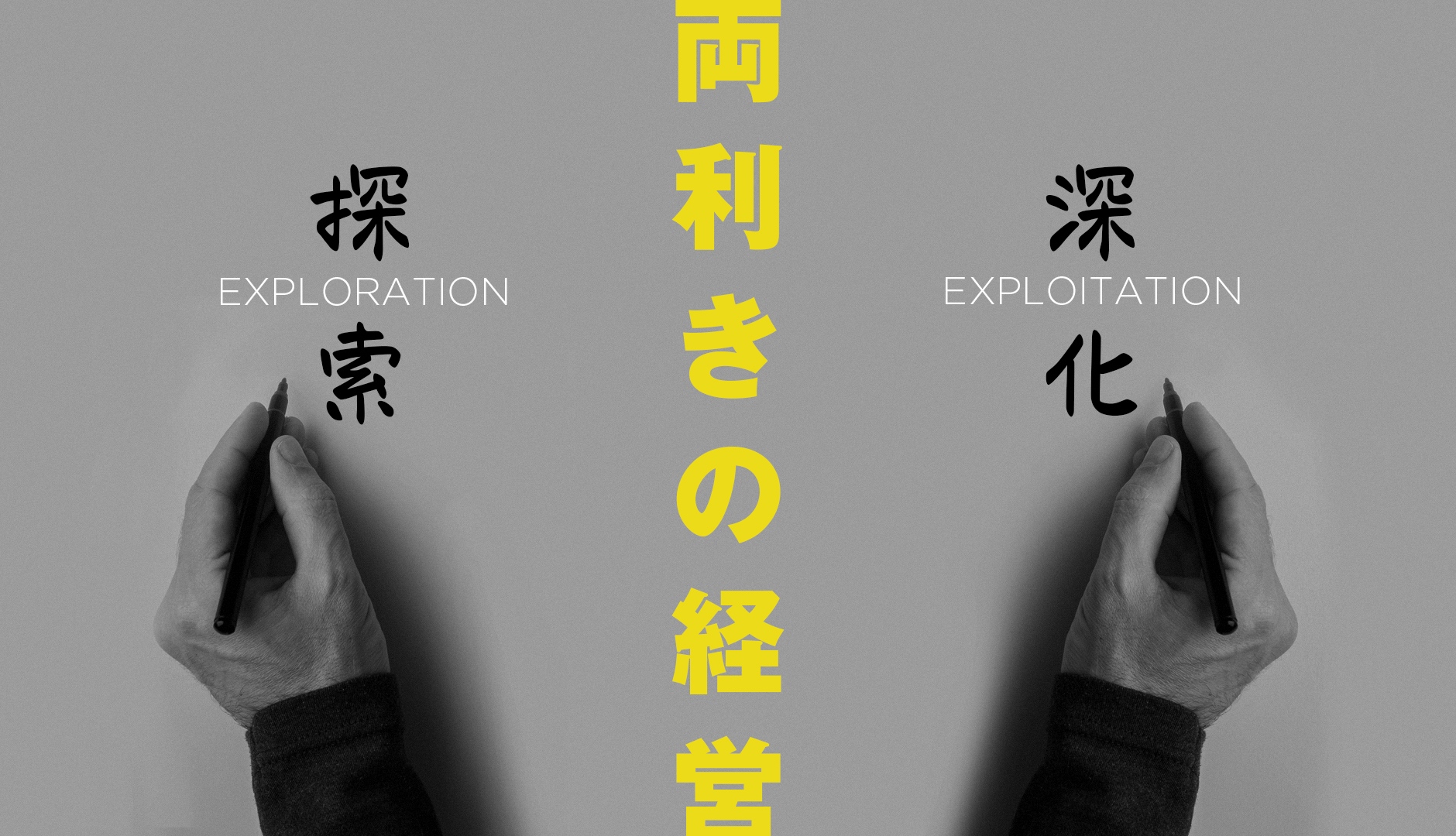
目次
近年イノベーションを起こすために「両利きの経営」という考え方が重要視されています。
経済学者の入山章栄さんも、「世界の経営学の先端で今もっとも研究されているイノベーション理論の基礎が「両利きの経営」である」と語っており、いかに重要視されているかが分かります。
では「両利きの経営」とは、どのようなもので、どのような手法でマネジメントすべきものなのでしょうか。今回は「両利きの経営」について解説します。

「両利きの経営」とは、まるで右手と左手が上手に使える両利きの人のように、「知の探索」と「知の深化」を高い次元でバランスを取る経営状態を指します。
イノベーションは「知と知の組み合せ」に起因して発生します。自社の既存ビジネスモデルという「知」に、異業種や別事業で使っていた手法の「別の知」を組み合わせることで、新しいビジネスモデルや商品・サービスを生み出していきます。そのため企業は、常に「知の範囲」を広げようとするのです。これが「知の探索」です。
しかし現実的な経営の現場で目先の収益をあげるには、「知の探索」で新しいビジネスモデルや商品・サービスを生み出すよりも、今業績の上がっている分野の技術をみがいた方がはるかに効率的です。だから既存事業を発展させるために、技術力を掘り下げます。この掘り下げる手法が「知の深化」です。
「知の探索」は、手間やコストがかかるわりに収益には結びつくかが不確実であると考える経営者も多く存在します。そのため「知の探索」は、組織において怠りがちにされます。すると知の範囲が狭まり、結果として企業の中長期的なイノベーションが停滞していきます。この状況を「サクセストラップ」と呼びます。
つまりイノベーションを目指す企業は「サクセストラップ」に陥らないように、「知の深化」を継続する一方で「知の探索」を怠らない組織体制・ルール作りが求められるのです。この「知の深化」と「知の探索」を、高い次元でバランスを取る経営が「両利きの経営」ということです。
ではなぜ近年「両利きの経営」が注目されているのでしょうか。
それは、現在が「イノベーションを必要とする時代」だからです。VUCA時代とも呼ばれる現在は、様々な変化が短いタームで多発的に起き、企業はその変化に対応していかなければなりません。さらに技術革新で、ビジネスモデルが大きく変化を求められるケースもでてきます。
例えば日本の家電業界も、アナログ時代には技術力が高く、諸外国と比べて日本の製品には付加価値がありました。しかしデジタル時代に変わると、技術力が低くても安価で高品質な家電製品を作ることができるようになりました。そのため技術力よりも価格優位性が高くなり、日本の家電メーカーが苦戦を強いられている状況が続いています。
また現在は、SDGsをはじめとする環境や世界各国の人権への対応や、自然災害や感染症による原材料費の高騰・サプライヤーの分断など、先を見通すことが難しい時代となっています。そのような変化に対応できる組織を作るためにもイノベーションが必要とされており、そのイノベーションを起こすために「両利きの経営」が注目されているのです。

では「両利きの経営」という考え方は、どのように生まれたのでしょうか。
「両利きの経営」は、アメリカのスタンフォード大学経営大学院のチャールズ・オライリー教授とハーバード大学のマイケル・タッシュマン教授との共著『両利きの経営(ambidexterity)』(東洋経済新報社)のヒットにより世界に広まりました。
当初、日本の学術界では「双面性」などと訳されていましたが、経済学者の入山章栄さんが「両利きの経営」という訳語を当てたことで、ビジネス界にも広く知られるようになりました。
同書では、「両利きの経営」によってアメリカの新聞社USA TODAYがイノベーションを起こし復活した内容が記されていますので、簡単に紹介しましょう。
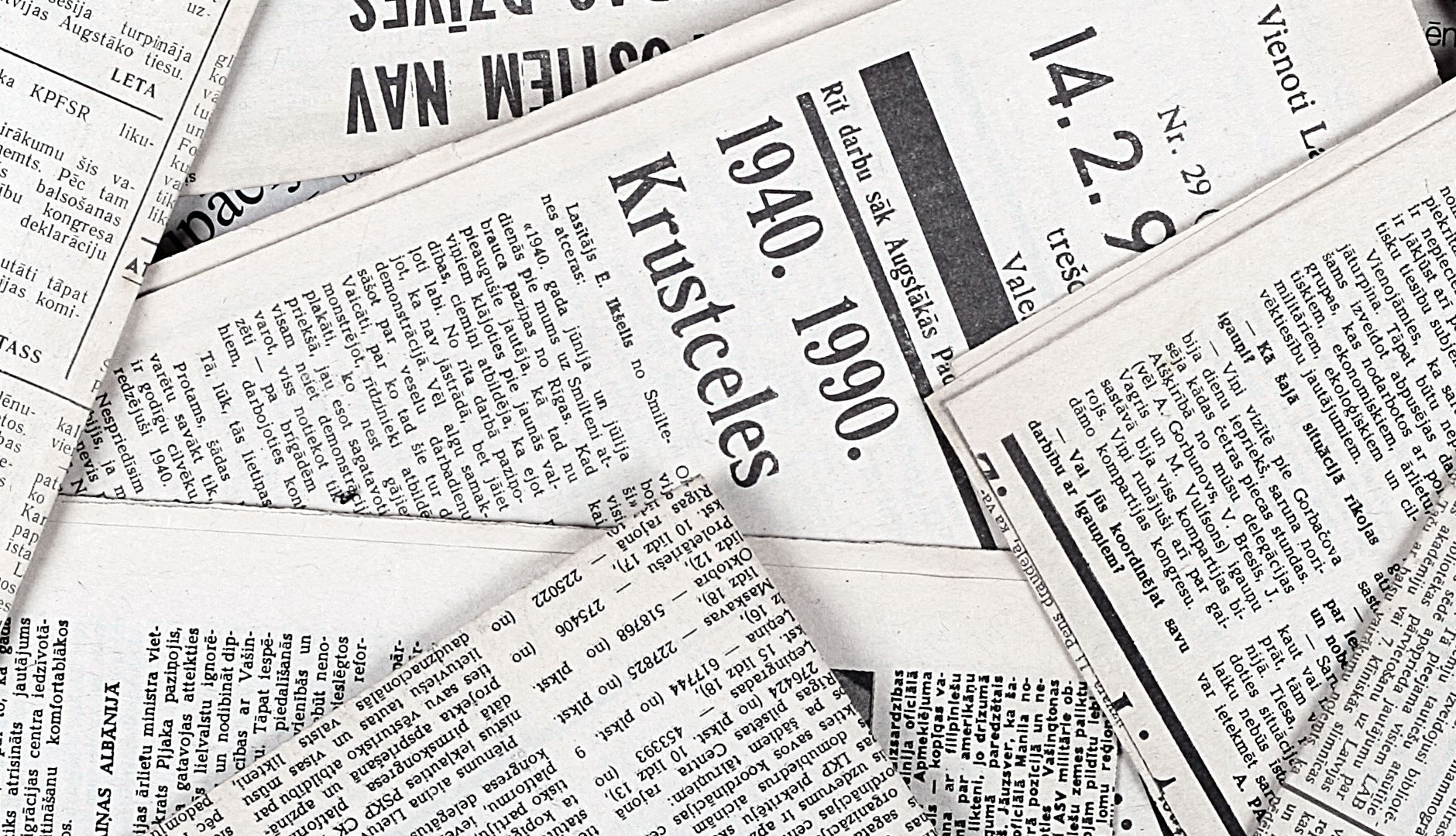
USA TODAYは、1982年に全国紙の発行を始め、1990年代後半には全米で最も読まれる日刊紙を発行する新聞社へ成長した企業です。
しかし2000年代に入ると新聞は、特に若者の間で購読者数の減少が顕著になります。
当時の社長トム・カーリーは、新聞紙という自社商品のニーズが減少する中で、力強い成長と利益を維持するには、劇的なイノベーションが必要だと考えます。そこでカーリーが打ち出したのが「ネットワーク戦略」でした。新聞紙だけを商品と考えるのではなく、新聞、テレビ、オンラインで配信する「コンテンツ制作」という軸を明確に打ち出したのです。
そしてオンラインニュース・サービスのUSA TODAY . COMを立ち上げます。
ところが、USA TODAY . COMはその後の10年間売り上げが伸び悩みます。カーリーは、USA TODAY . COM事業が、従来の新聞事業のオペレーションと乖離しすぎて、新聞社の巨大な資源を活かしきれていないことに問題があると考えていました。
そこで、ニュース記事を3つのプラットフォームで共有することを思いつきます。3つのプラットフォームとは、従来型の1日1回発行する「紙媒体の新聞」、オンラインニュースの「USA TODAY . COM」、そして「テレビ」です。
新聞事業を維持しつつ、テレビ放送やオンラインニュースでイノベーションも追求できる組織を作るためには、それぞれの事業に専門人材が必要だと考えました。それぞれに相反する可能性のある3つの事業は、人材も、事業方針も、ビルのフロアまでも分けました。しかし、この新規事業の担当役員には社内でもカーリー氏と意見の近い人物を配置し、3事業のリーダー・チームが一枚岩になることを求めたのです。
事業間の統一を図るために、「公正さ、正確さ、信頼性というUSA TODAYの価値観」を共通認識としました。事業ごとに文化の違いがあったとしても、全社で同じ価値観を持てるように考えたのです。
そして、オンライン部門とテレビ部門の責任者は毎日編集会議を開くことを決めます。この編集会議を通じて、大きな視点で統一感を持たせるとともに、具体的なニュースでも細部の統一が図られました。人事においても、異なる事業間での異動を奨励し、昇進・報酬決定の際にはコンテンツの共有に積極的だったかどうかが考慮されました。
こうした変革により、USA TODAYは「両利きの組織」となったのです。力のある経営陣が3つの事業を監督し、要所については編集会議で全社の共通認識を確認します。その結果、成熟した日刊紙事業で果敢に競争しながら、オンラインニュース事業を発展させ、テレビ局に速報ニュースを提供できるまでに成長したのです。
それでは、「両利きの経営」を行うためには、どのような組織マネジメントが必要なのでしょうか。
「両利きの経営」において重要なことは、探索と深化が互いに影響し合える環境を作ること。
組織のリーダーが既存事業の成功を深化させながら、既存の組織能力を活用して新市場を探索する両利きの経営を行うことで、はじめて長期の成功がもたらされます。
ただ、一般的に探索事業と深化事業は、お互いに反発しあう要素が多く存在します。
そのため「探索事業と深化事業にまたがる共通のアイデンティティ」が必要となるのです。
探索事業と深化事業の両者に共通のビジョンがない限り、両者は互いを認めることなく、邪魔な存在や脅威と見なす傾向があります。しかし共通のビジョンがあれば、従業員は探索において重要なマインドセットを身につけやすくなります。
先に紹介したUSA TODAYの事例では、戦略的意図として「新聞社は新聞紙の発行ではなく、ネットワークのビジネスになる」とはっきりと打ち出し、探索ユニットと深化ユニットがいずれも同じ組織の一員として協力し合うべきだという正当な理由を示しました。そして、組織全体に適用される共通のアイデンティティを与えた結果、具体的な顧客志向やリスクのとり方などの文化規範はユニットごとに異なるものの、価値観自体は全社共通認識として理解されたのです。
ただ一般的に、企業は事業が成熟するほど「深化」に偏り、イノベーションが起きにくくなる傾向があります。これは「サクセストラップ」と呼ばれ、経済学者の入山章栄さんも「イノベーションに悩む多くの日本企業はこの傾向が強い」と語っています。
この「サクセストラップ」を抜け出すために必要とされるのが、「コングルエンスモデル」と言われる組織体系の4つの基本要素です。
KSF(Key Success Factor)は、戦略を実行するための成功のカギです。
組織として対応すべきこと、カギとなる部門間の連携プレーにどのようなものがあるかを探ります。
そしてKSFを担うのが人材です。
組織内のそれぞれの人材に必要なコンピテンシーは何か、働く上でのモチベーションは十分であるかなどを確認しながら、必要な対応を検討します。
その人材をまとめるのが組織です。
どのような組織構造や管理システム・評価制度が人材の能力を最も発揮できるのか、体制や評価システムや意思決定プロセスなどを構築します。
作り上げた組織の中で、社員の能力が十分に発揮される手法が組織カルチャーです。
どのようなワークフローにすれば生産性が高まるのか、ミスが軽減されるのか、組織としてパフォーマンスが向上するカルチャーを生み出します。
この基本の4要素がうまく噛み合うことで、「サクセストラップ」を抜け出すことができると言われています。

そして「サクセストラップ」を抜け出すと、「知の探索」と「知の深化」についてバランスを取れるようになり、結果的に「両利きの経営」を実現することにつながるのです。
この「サクセストラップ」を抜け出す手法については、「ダイナミック・ケイパビリティ」のページで詳しく解説しています。そちらもご確認ください。
ただし、イノベーションは日本企業の特性と反する場合があるため注意が必要です。
日本企業の強みとしては、品質を重視する思考、現場のオペレーション能力の高さ、チームワークのよさなどがあげられます。そのため、経営を極端にイノベーション型に振り過ぎてしまうと、既存事業の強みを失ってしまうおそれもあり、顧客からも反発が起こる可能性もあります。そのため、経営層のリーダーシップが重要になってくるのです。
では、組織のリーダーは、どのようにマネジメントすればよいのでしょうか。
「両利きの経営」を実現するためには、「知の探索」と「知の深化」の高次での両立が必要です。しかし組織論的には、両者は水と油であり反発しやすい傾向にあります。
「知の深化」は、ビジネスにおいて売上に直結しているため、予算を取りやすい傾向にあります。一方で「知の探索」は、すぐに結果が出るかが不透明なため、予算の確保が難しい場合もあります。
その両者を高い次元で両立するためには、経営陣のリーダーシップが必要です。
両者の対立が最も顕著になるのは、「探索」チームの試みが成功する直前です。「深化」チームは自分たちの存在意義を主張するために、「探索」チームの批判を始めるようになります。その両者を高次元で共存させるべくマネジメントできるのは、経営チームしかありません。しっかりと、両者が高次で両立できるようマネジメントするリーダーシップが不可欠となります。
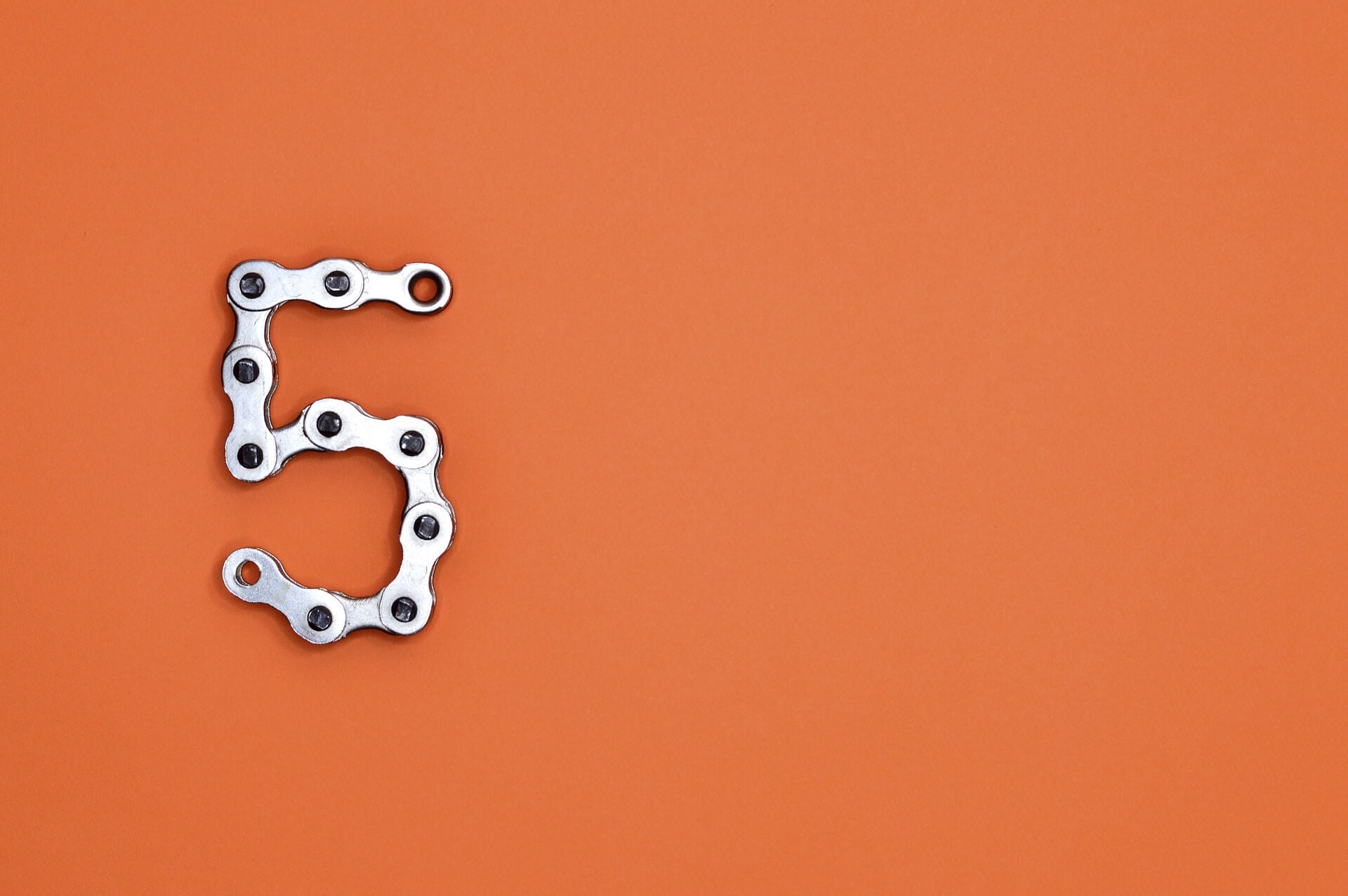
そのリーダーシップを発揮するためには、どのような発想が必要なのでしょうか。
先に紹介したチャールズ・オライリー教授とマイケル・タッシュマン教授の共著『両利きの経営(ambidexterity)』(東洋経済新報社)では、「両利きの経営」を実現している経営陣は、リーダーシップ5原則を備えていると伝えています。
「両利きの経営」の実現において重要なことは、戦略よりもコミュニケーションと考えることです。経営陣全員が真摯に課題に向き合って、しっかりと議論できるチームワークを醸成していくことが重要となります。
VUCA時代の経営課題は、客観性や合理性だけでは決めきれないケースが出てきます。
多様な視点からの意見を引き出しながら、これだと思った方向性を決めたらその軸をぶらさずに組織を牽引するバランス感覚とリーダーシップが必要となるのです。
近年イノベーションを起こすために「両利きの経営」という考え方が重要視されています。
「両利きの経営」とは、まるで右手と左手が上手に使える両利きの人のように、「知の探索」と「知の深化」を高い次元でバランスを取る経営を指します。
「知の探索」とは、ビジネスを広げるために「知の範囲」を広げようとすること。
「知の深化」は、既存事業を発展させるために「技術力」を掘り下げることです。
ただし、「知の深化」に対応する既存事業の担当者と、「知の探索」を担当する新規事業担当者は、それぞれ相反する特性があります。なぜなら、新事業の成功により、既存事業の評価が下がる可能性があるためです。
そこで、両者を高い次元で共存させるために、探索と深化における共通のアイデンティティをつくることが重要となります。そして、そのアイデンティティを現場に落とし込むために、経営者のマネジメント能力が必要となるのです。
「両利きの経営」の実現において重要なことは、戦略よりもコミュニケーションと考えることです。経営陣全員が真摯に課題に向き合って、しっかりと議論できるチームワークを醸成していくことが重要となります。
・日経ビジネス『イノベーションが止まらない「両利きの経営」とは?』
・東洋経済『今こそ「両利きの経営」が切実に問われる理由』
・GLOBIS『両利きの経営を実現する混迷時代のリーダーを育成するには』
・書籍:チャールズ・オライリー教授・マイケル・タッシュマン教授の共著『両利きの経営(ambidexterity)』(東洋経済新報社)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

