DX・データ活用に特化したWebマガジン「データのじかん」を運営するウイングアーク1st株式会社はお笑いタレントの有吉弘行さんを起用したテレビCMを、5月12日(金)から放送開始しました。
CMのテーマでもある「判断材料」は、現在のあらゆる情報が氾濫し、課題が多様化・複雑化する現代のビジネスシーンにおいて成果を挙げ続けるためには、組織の「判断力」や「決断力」を支える重要なキーワードになります。ただ、現場によって千差万別の問題を解決するために求められる「最善の判断・決断を下す力」は経験や知見、マインドだけで組織や個人に培われるわけではありません。
問題の本質を見極めて適切な目標を設定し、正しい判断に必要な材料とエビデンスを収集、活用したうえで分かりやすくデータを共有する。そしてチームで改善を図り続けるロードマップを作成し、最終的に「実行力」を実践し続ける必要があるのです。大切なのは一つひとつの工程だけでなく、全体を見通して「判断材料から実行力」につなげていくことです。そのポイントを解説します。
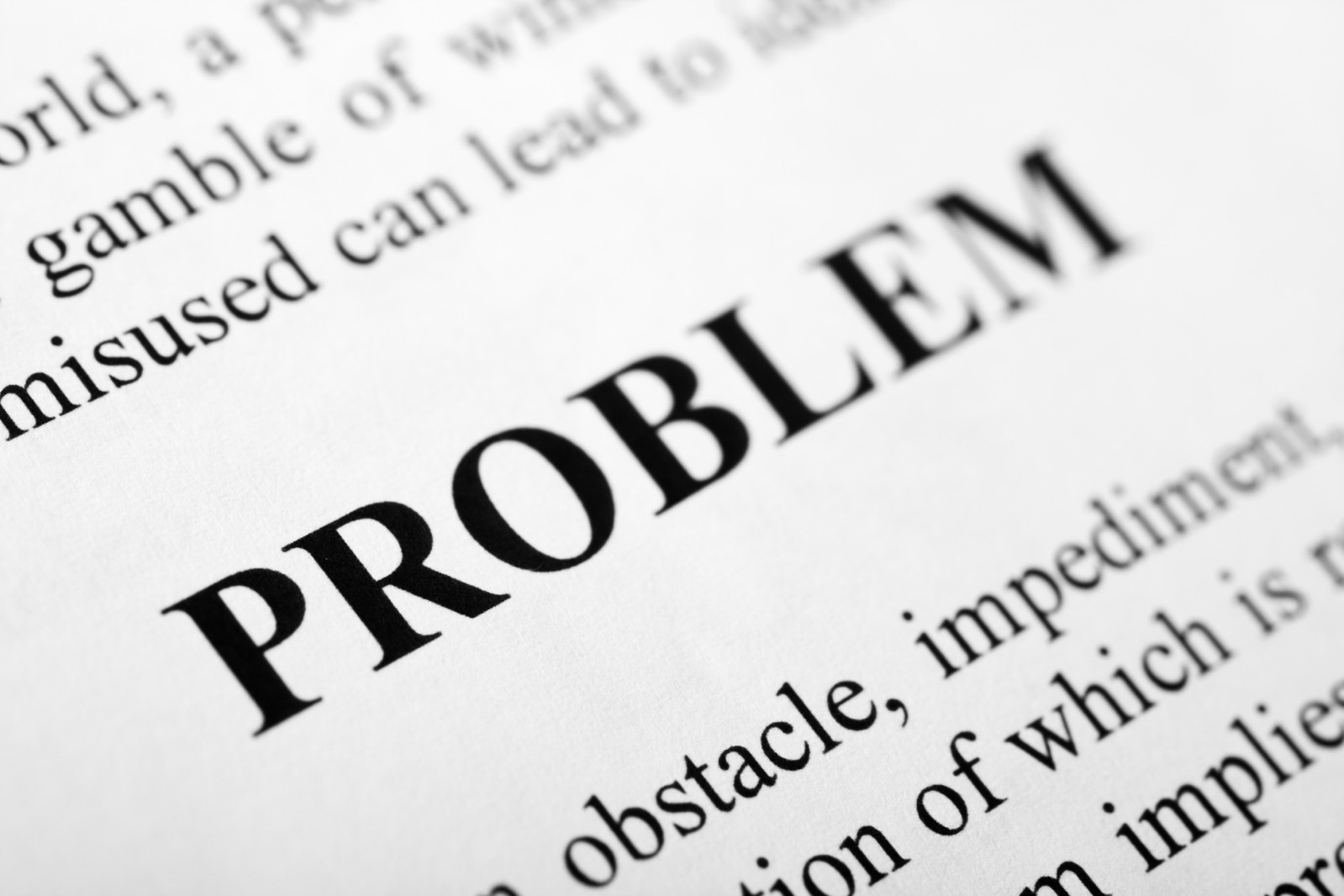
判断、決断はただ漠然と決めることではありません。最初の一歩としては「なんのために」判断を下すのか明確化しましょう。一般的には課題を解決するために判断が求められるケースが多いため「問題定義の明確化」が求められます。
明確化すべき項目はケースバイケースですが、理想的な姿や数値と現状のギャップである「問題の本質」とその問題を解決するために必要な「目標」の2つはマストです。問題は1つではなく、複数ある場合も珍しくありません。そのため必要に応じて、それぞれを明確化する必要があるでしょう。
問題の本質を明確化できれば、判断力・決断力を向上させるためには必要不可欠な「判断材料」と「エビデンス」の収集作業の精度と効率アップにつながります。
定義した問題を解決するために必要な目標設定は、なるべく分かりやすい内容でプロジェクト関係者で共有しましょう。目標を適切に明確化できれば、プロジェクトを遂行するうえで都度、下さなければならない判断や決断の方向性がぶれにくくなります。
さらに自身はもちろん、部署を横断する関係者間の行動が設定した目標の達成に向けられるため、より具体的になります。細かな目標は後工程で設定するため、まずはKGI(重要目標達成指標)などの「問題の本質の解決」を意識した最終目標の設定・共有を意識してみてください。
判断を下すための根拠、手がかりになる情報が「判断材料」です。判断を下すまでのプロセスは①事実を集める②集めた事実を解釈する③事実を論理的にまとめる④選択するに大まかに分解できます。そのため、判断材料が少なかったり、的を得ていない情報が大半を占めている状況では、どれだけ後ろの工程を綿密に行っても正しい判断を下すのは難しいでしょう。
判断材料は、会社や組織の内部・外部を問わず収集することが望ましいです。データドリブン経営を実践している企業であれば、顧客情報や製造、販売に関わるデータなどが蓄積されているため、必要な情報をピックアップしやすいです。一方、外部で公開されている資料をもとに情報を収集する際は、発信元の「信頼性」や調査の「中立・公平性」に注意が必要です。
複数の角度からの情報を収集することで、より俯瞰的・客観的なデータとして判断しやすくなるため、信頼できる資料であっても、なるべく同じテーマ・項目で調査している別ソースも探すことをおすすめします。
エビデンス(evidence)とは証拠や根拠という意味で、ビジネスシーンにおいては主に情報の「裏付け」として使われます。情報を判断材料として扱うか否かは、エビデンスを都度「評価」してチェックすることが大切です。
評価基準としては、調査元・公開元や調査方法、客観的な視点などの「信頼性」、調査結果の「妥当性」、さらにそのエビデンスに基づいた行動による「再現性」を測るのが一般的です。
収集した判断材料を整理して「見える化」することで、「主観的・属人的な要素の排除」、問題の本質とは関係のない「無駄な情報(ノイズ)の除去」などを行えるため、エビデンスをより理解しやすくなるため、適切な判断を下しやすくなります。見える化の基本は「定量化」です。また、定量化した数値をグラフやチャートなどを用いて表現(ビジュアライズ)すれば、より視覚的で分かりやすくなるでしょう。
目標達成に向けた進捗を定量的に把握することは、都度、適切な判断を下すためにも重要なポイントです。重要業績評価指標「KPI(Key Performance Indicator)」を設けて定期的にモニタリングする方法が一般的です。KPIを達成できれば、最終的な目標であるKGIの達成に近づく関係性と理解しましょう。例えば、売上高5,000万円(KGI)を達成するためには、KPIである「商談数」や「受注率」を増やさなければならないということです。
見える化したデータを活用してKPIの設定まで行えば、既に「プロジェクトの実行の可否」や「採用する手法」、「チームの選定」といった大きな判断・決断を下していると考えられます。その下した判断や決断の成否を分けるのは、決めたことをやりきる「実行力」です。
実行力を向上させる最初の一歩は、アクションプラン(行動計画)の策定です。責任者と各担当者の役割を明らかにして共有し、KGIとKPIを達成するために個々が「いつまでに、何をするのか」を明確化するのが大きな目的となります。
いわゆる実務レベルまで当事者が行動できる「タスク単位」まで、具体的な作業内容、期限、責任者といった情報の粒度を細かく設定することが推奨されています。アクションプランを適切に設定できれば、個々の担当者の「小さなゴール」が見えやすくなるため、業務を遂行しやすくなります。
また、責任者も客観的にプロジェクトの進捗をより円滑に管理しやすくなります。このようにアクションプランを策定することで、個人レベルの実行力が向上した結果、組織やチーム単位でも実行力がアップできるのです。
責任者はKPIや個々のアクションプランの進行状況、達成状況に合わせて定期的にフィードバックをする必要があります。フィードバックを適切なタイミングと内容で行えば、問題点の早期発見につながり、トラブルの防止やより効率的な対策を講じることができます。フィードバックをする側は定量的な根拠に基づいた状況整理と分析、改善策の提案が求められます。また、課題や改善点だけでなく個々の目標を達成したり、成果を上げたりしたタイミングでポジティブなフィードバックをすることも、モチベーションをアップさせて実行力を高める要素の1つです。
一方、受け取る側も自身の進捗状況や業務状況をあらかじめ理解し、意見や質問を用意してミーティングなどに望むことも「実行力」の向上において大切なポイントといえるでしょう。
個々の実行力を向上させるためには、継続的な「学習」と「スキル向上」が不可欠です。業務外でも能動的に新たな技術や知識を取り入れ続けましょう。視野が広がり、視座が高くなれば同じ判断材料の質・量だとしても、より効果的な判断や決断を下しやすくなるでしょう。
また、会社としては学習機会の提供やスキルアップを推奨する社内制度の新設、活用の推奨といった環境を構築できれば、より判断力・決断力・実行力の高い組織をつくることができるでしょう。
チーム内のコミュニケーションが円滑かつ積極的に行えるようになれば、判断・決断のプロセスをよりスムーズに進められます。手軽に連絡できるビジネスチャットなどのツールや見える化してビジュアライズしたデータの共有など、自社の環境に合わせた方法でコミュニケーションの向上を図りましょう。個々のマインドも必要ですが、コミュニケーションは一人では成り立たないため、各チームメンバーが相手の意見や立場を尊重しつつ、効果的な意思疎通を図る「空気感」や「共通認識」も大切です。
プロジェクトの成功には、リーダーシップが重要です。リーダーは、チームの方向性を示し、メンバーを適切にサポートすることで、判断力・決断力・実行力を向上させる役割を果たします。
プロジェクトの成功には、責任者のリーダーシップが欠かせません。上流工程での自身が下す判断・決断による方向性を示して、実行する姿勢を見せるのはもちろん、その判断に基づいてチームメンバーをサポートすることが求められます。その結果、メンバーやチームの判断力・決断力・実行力も上げるでしょう。
判断力・決断力・判断材料・エビデンス・見える化そして実行力を高めるためには、以下の要素に取り組むことが重要です。
● 問題定義の明確化と目標設定
● 判断材料とエビデンスの活用
● データの見える化とKPI設定
● 実行力の向上(アクションプラン策定、フィードバック活用、継続的な学習)
● チームワークの強化(コミュニケーション、リーダーシップ)
これらの要素を総合的に取り組むことで、判断力・決断力・実行力を高め、効果的な問題解決や目標達成が可能となります。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。