




目次
現代は「モノが売れない時代」だといわれています。
「モノ余り」や「時間不足」に直面しているからというのがその理由としてあげられます。かつての「3種の神器(白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫)」や「3C(カラーテレビ、自家用車、クーラー)」のように、人々が憧れそのために仕事に励む対象は存在しません。また、無料の娯楽があふれ、企業は人々の「可処分時間」を奪い合うようになっています。
そんな時代に武器となる考え方が「プロセスエコノミー」。その名を冠した本である『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』(幻冬舎、2021)の要約を通して、”「モノが売れない」時代のビジネスの新潮流”をご紹介します!

プロセスエコノミーとは、その名の通り“プロセス(過程)が商品・サービスとされる経済圏”のことを意味します。漫画情報サービス「アル」やクリエイター向けライブ配信サービス「00:00 Studio」を立ち上げたアル株式会社代表取締役の古川 健介(けんすう)氏により、この概念は言葉にされました。
例えば、みなさんは野菜売り場で「生産者の顔やコメント」を見て、野菜を買ったことはないでしょうか。また、Apple社に愛着があるからとiPhoneの新作は手に入れたいと考えている方、開発途上国の人々の生活に悪影響を及ぼさない「フェアトレード」の商品をなるべく選ぼうとする方もいるはずです。
このように、商品・サービスにはその機能や性質だけでなく自分の手元に届くまでの「意味」が付与されています。“「モノ消費」から「コト消費」へ”というフレーズは聞いたことのある方も多いでしょう。モノそのものから、商品・サービスを利用したときに得られる「体験価値=コト」に人々の消費活動のあり方が移行していることを意味する言葉です。
「コト消費」の満足度を左右するのは、その商品・サービスを使ったときだけでなくその商品・サービスが生み出されるまでの過程でもある。
──これが、プロセスエコノミーという言葉に含まれる“発見”です。食品、自動車、音楽、アート、漫画、Webアプリ、エネルギー……、この世で売買されるものすべてにユーザーに届くまでのストーリーがあります。プロセスエコノミーは、そのストーリーをオープンにし、結果生まれる熱狂や応援も含めて企業が生み出す価値とすることを提案しています。
プロセスエコノミーが生まれたり、注目されたりしている背景には、インターネットやSNSなどの発展があります。
インターネットやSNSが発展したことにより、情報の発信と拡散が容易になりました。そのため、誰でも情報発信ができ、情報の広まるスピードが早くなっています。これらの要因から、商品・サービスの評価や口コミなどの情報が多く手に入れられるようになったため、商品の善し悪しが判断しやすくなりました。そこで、商品・サービスをプロセスで差別化することが重要視されるようになったことがプロセスエコノミーの背景です。
プロセスエコノミーとアウトプットエコノミーには、商品・サービスを作り出す過程に注目しているのか、商品・サービスを作り出した後に注目しているのかの違いがあります。
プロセスエコノミーは商品・サービスを作り出す過程でも収益を得る手法で、アウトプットエコノミーは作り出した商品・サービスで収益を得る手法です。アウトプットエコノミーでは、商品の価値がそのまま収益に反映されますが、プロセスエコノミーでは、商品・サービスを作り出す過程も含めて商品の価値となり収益に反映されます。つまり、商品・サービスの価値以外に作り出す過程でも差別化できるかできないかがプロセスエコノミーとアウトプットエコノミーが違うポイントです。

プロセスエコノミーとは、プロセスが商品・サービスとされる経済圏であることを解説しましたが、プロセスエコノミーのメリットにはどのような物があるのでしょうか。
プロセスエコノミーには、以下のような3つのメリットがあります。
自社がプロセスエコノミーに求める効果があるのかを判断するために、得られるメリットについて知っておきましょう。それぞれのメリットについて解説します。
プロセスエコノミーには、今までは獲得できなかった層の顧客を獲得しやすいメリットがあります。
プロセスエコノミーでは、プロセスに対して顧客が課金しながら商品・サービスを応援できます。さらに、プロセスを通して顧客が制作側に対する親近感を得やすいです。そのため、商品・サービスの質だけでなく、応援したい気持ちから商品・サービスを購入する層の顧客を獲得できます。また、応援したい気持ちがあると継続的に顧客を獲得しやすいメリットもあります。
プロセスエコノミーでは、商品・サービスだけでなくプロセスでも収益を得られるため、収益を安定させやすいです。
また、プロセスエコノミーは商品・サービスの制作段階で収益を得られることも、収益を安定化させやすい要因の1つです。商品・サービスが完成すれば、さらに収益を得られるため、商品・サービスの強化や次の商品・サービスの制作にかける資金を得られることもメリットだと言えます。
プロセスエコノミーは、商品・サービスを制作するプロセスを公開するため、制作側のモチベーションを高められるメリットがあります。
クリエイターが作品を1人で作る際には、孤独を感じやすいです。しかし、作品制作のプロセスを公開することで、作品制作の段階から応援してもらいやすくなるため、制作側のモチベーションを高めやすいです。例えば、ライブ配信をしながら作品を制作することで、コメントや投げ銭による視聴者からの応援でモチベーションを高められます。制作過程でモチベーションが下がりやすい場合には、プロセスエコノミーを取り入れてもよいでしょう。

さて、ここまで読み進めたみなさんはこのように考えているのではないでしょうか。
「プロセスエコノミーの概念は分かったけど、実践するには何を考えればいいの……?」
その答えは『プロセスエコノミー』の中にあり、特に第4章で詳しく解説されています。
こちらの動画は、イギリスの作家サイモン・シネックが2009年に行ったTEDトーク「How Great Leaders Inspire Action(優れたリーダーはどうやって行動を促すか)」で、第4章で詳しく取り上げられました。
この動画で紹介されているのが「ゴールデンサークル」という概念。3層構造になっており、中央から順に「Why→How→What」となっています。この図を用いてサイモン氏は人の行動の起点となるのは「Why(なぜ)」であり、Apple、キング牧師、ライト兄弟らはその点にこだわったからこそ歴史に残る成果を残せたことを解説しました。
この「Whyを大切にする」メソッドを、プロセスエコノミーに応用してみましょう。すなわち、「どんなプロセスを見せるか」「どうやってプロセスを見せるか」ではなく、「なぜこのようなプロセスで事業に取り組むか」を起点に考えるということです。
それは、企業のミッションやそれを未来に投影したビジョンから考えるということを意味します。近年、ミッションやCSRを前面に押し出す企業が増加した理由の一端がここにあります。また、哲学や文化人類学などのリベラルアーツを取り上げるビジネス書籍がよく売れているのも、それらが「なぜ」を突き詰めるヒントにも訓練にもなるからではないでしょうか。

書籍『プロセスエコノミー』は、 執筆家・IT批評家の尾原和啓氏により執筆されました。
その本が出来上がるまでの過程も、目次を考える段階から、公開編集会議などでオープンにされ、“プロセスエコノミー”なものとなっています。
尾原氏と東アジアのデジタルビジネスに詳しい藤井保文氏が共同執筆した『アフターデジタル オフラインのない時代に生き残る』(日経BP、2019)は“オンラインとオフラインの境界が存在しない”アフターデジタル”のビジネス環境について中国など世界で実際に起きている事例を通して解説する書籍でした(『アフターデジタル』シリーズ書評に関しては以下の記事をご覧ください)。
同書において紹介されているのが、医療・健康支援アプリ「平安好医生」やマイカー管理アプリ「平安好車主」などで顧客との接点を生み出すとともに行動データを取得し、適切なタイミングで自社商品やサービスを紹介する「中国平安保険グループ」の事例です。
ここで活用されているのは“消費者のストーリー”。行動データをもとに消費者は購買までの段階(=カスタマージャーニー)のどの段階にあるかを整理し、適切なタイミングで働きかけることを目指しています。
ここから、プロセスエコノミーには、企業側・消費者側の2つが存在すると筆者は考えました。企業側にはその商品・サービスを消費者に届けるまでのプロセスが、消費者側には商品・サービスを購入するまでのプロセスがあります。20世紀にはブラックボックス化していたその過程は、情報通信技術の発達により可視化されてきました。
その結果生まれたのが「プロセスエコノミー」という新たな経済圏なのでしょう。

プロセスエコノミーの活用事例には、以下のような5つがあります。
プロセスエコノミーを取り入れるためにも、実際の活用事例について知っておきましょう。それぞれの活用事例について解説します。
歌手やアイドルを目指している人が、オーディションを通して実際に歌手やアイドルとしてデビューするプロセスを放送している番組を、見たことがある方もいると思います。このようなオーディション番組もプロセスエコノミーを活用した事例の1つです。
オーディション番組を通して、デビューまでの努力や苦労を知ることができるため、応援したい気持ちが生まれやすく、ファンを獲得しやすいです。また、ファンを獲得した状態でデビューできるため、デビュー後の収益を安定させやすい特徴もあります。
アーティストのMVやライブ、アニメやドラマなどの作品が完成するまでのプロセスをまとめたメイキング映像もプロセスエコノミーを活用した事例です。
メイキング映像では作品の裏側を知ることができるため、作品の魅力を増やせるだけでなく、制作側と顧客の距離を縮められる効果が期待できます。コアなファンであればあるほど、出演者の素が表れやすいことや、作品の裏側を知りたい気持ちからメイキング映像は人気が高いです。
クラウドファンディングは、制作段階から商品・サービスを応援できる、プロセスエコノミーの事例です。
クラウドファンディングでは、商品・サービスを制作するための資金が足りない場合でも、資金を集められることが魅力で、資金を出資する側も制作中の商品・サービスを受け取れたり、特典を受けられたりするなどのメリットがあります。ただし、クラウドファンディングで資金を集めるためには、共感やストーリーで事業の魅力を伝えることが重要です。
昨今、YouTubeやTikTokなどでライブ配信をする人は増えていますが、このライブ配信もプロセスエコノミーの事例の1つです。
ライブ配信では、配信側と視聴者がチャットやSNSを通してコミュニケーションを取れます。そのため、親近感がわきやすい特徴があります。また、ライブ配信では、俳優・声優・アイドルなどを目指す人が目標を達成するまでのプロセスを楽しむこともできるため、ファンの獲得や目標達成までにひつような資金を集められることも特徴です。
プロセスエコノミーの活用事例として、WebサイトやSNS上でのコミュニティであるオンラインサロンもあげられます。
オンラインサロンの多くは月額制であるため、毎月安定して収益を得やすいことが特徴です。また、オンラインサロン会員と運営者のコミュニケーションが取りやすかったり、コミュニティ内の会員同士の繋がりを作ったりできることも、オンラインサロンの魅力の1つです。
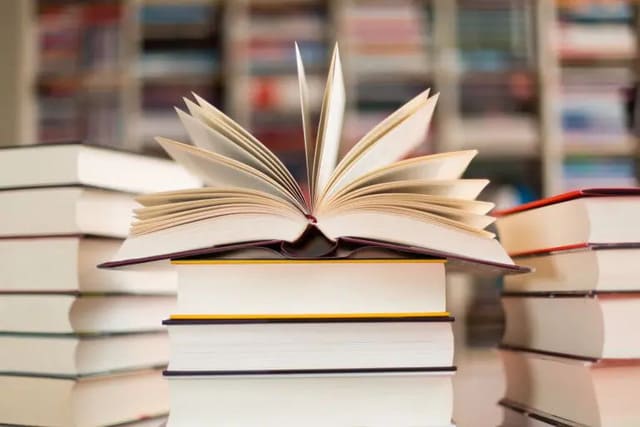
書籍『プロセスエコノミー』を起点に、プロセスエコノミーという概念の実践方法・捉え方について記述してきました。消費者側にもプロセスエコノミーが存在するというのは、筆者個人の考えであり、同書では企業側の「プロセスエコノミー」について、多様な事例や批判的な視点とともに解説されています。182ページと比較的短く、事例豊富で読みやすいため本記事を読んで興味を持った方はぜひ実際に読んでみることをおすすめします。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

