



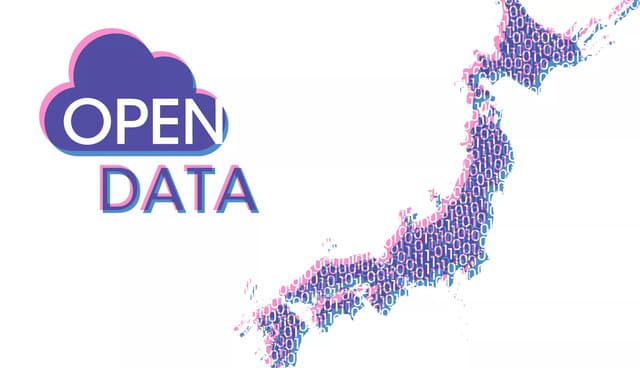
目次
2013年、あるIT用語が大きな注目を浴び、流行語大賞にノミネートされました。膨大なデータのことを表す「ビッグデータ」という言葉です。続けて2014年あたりからは「オープンデータ」という言葉にも注目が集まっています。
オープンデータとはどのようなものか、なぜ注目されているのか、その理由と活用事例についてご紹介します。

オープンデータとは名前のとおり「公開されたデータ」のことを示しています。
オープンデータは、主に国や地方公共団体、事業者が公開しているデータで、貯金に関する調査や住まいに関する調査などの生活に関するものや景気動向の調査など、さまざまなデータが公開されています。

総務省のホームページでは、オープンデータの意義・目的として以下の3つが紹介されています。
参考:総務省「地方公共団体のオープンデータの推進」
上記からもわかる通り、オープンデータの目的としては、経済の活性化や課題の解決、行政の透明化による信頼性の向上などがあります。政府がオープンデータを公開することで、行政の透明化が可能となり、国民から信頼を得ることに繋がります。また、オープンデータを用いて分析をすることで、より効果的な戦略を立てながらビジネスを展開できるため、経済の活性化も目指せるでしょう。

オープンデータの定義には、以下の4つの条件が定められています。
つまり、オープンデータとは営利目的でも非営利な目的でも、無料で誰でも使えるデータで、機械判読できるものであるということです。もし、データの閲覧や利用にお金が発生する場合には、オープンデータとは言えないでしょう。(通信やデバイスなどにかかる費用は除く)

オープンデータの定義について解説しましたが、オープンデータには、以下の2つのような特徴があります。
オープンデータの特徴はオープンデータの定義と重なる部分があるため、一緒に覚えておくと良いです。それでは、それぞれの特徴について解説します。
オープンデータには、著作権フリーであるといった特徴があります。
オープンデータではない一般的なデータベースでは著作権が存在しており、誰でも許可なく利用できません。しかし、オープンデータは著作権フリーであるため、利用するための許可を必要とせず、営利・非営利問わずに誰でも無償で利用できます。
オープンデータの定義にもあったように、機械判読できることがオープンデータの特徴です。
機械判読ができるデータとは、コンピュータで文章や数値などが判別可能で、自動的に加工や編集ができるデータのことです。例えば、紙の資料や手書きの資料、表などは人が見る分には問題ないですが、コンピュータが文章や数値などを判別できないため、機械判読できないデータとなります。また、画像やPDFの資料も加工や編集ができないため、機械判読可能なデータとは言えません。

多くの企業が欲しがっているのが、データサイエンティストだといわれています。
データサイエンティストとは、統計学や数学、データ分析プログラムの知識を駆使して、膨大なデータから事業戦略を導きだす存在です。オープンデータ戦略の推進も、これに似ています。オープンデータの活用による官民協働のサービス提供や改善、企業活動の効率化や新しいビジネスの創出などを促し、日本全体の経済活性化につながることが期待されているのです。
日本がオープンデータに本格的な取り組みを始めたのは、2012(平成24)年とされています。
しかし、世界に目を向けてみると、オープンデータの利用はもっと早くから着目されていました。2004年、アメリカ・イギリスの公的プログラムとして、ケンブリッジ大学が発表したのが、各国のオープンデータサイトを集約したwebサイト「Open Knowledge International」です。2008年には国連が「un.data.org」を、2010年には世界銀行が「World Bank Open Data」を開設しています。続けてニュージーランドやノルウェーなども公式サイトを開設し、その動きは東アジアやアフリカ、西ヨーロッパにも拡がりました。こうして2013年の主要8カ国首脳会議(G8サミット)で「オープンデータ憲章」が採択されたのです。
これを受けて日本では、2012年7月に総務省を主体とした「オープンデータ流通推進コンソーシアム」が設立され、その年の12月に「政府標準利用規約」が制定されました。翌2013年には「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定され、「日本のオープンデータ憲章アクションプラン」が決定されます。そして、2016年12月に施行されたのが「官民データ活用推進基本法」です。日本では2020年までを“オープンデータ集中取組期間”とし、さらに多くのデータ開示が期待されています。

ここまではオープンデータについて解説してきましたが、では、オープンデータはどこで入手できるのでしょうか。
今回はオープンデータが入手できるサイトの中から、以下の3つを紹介します。
上記は、それぞれ日本や日本以外の国の政府が公開しているオープンデータサイトです。さまざまなオープンデータを取り扱っているため、ぜひ参考にしてみてください。それでは、それぞれのサイトについて解説します。
e-Govデータポータルは、内閣府や各省庁などの行政機関が公開しているオープンデータを検索できるサイトです。
以前は行政機関のデータをまとめたサイトは「データカタログサイト」というサイトでしたが、システムの刷新や機能強化のために2023年3月からリニューアルされ、e-Govデータポータルになりました。オープンデータをキーワードやカテゴリで検索できるため、求めているデータが見つけやすくなっています。
e-Statは、日本の政府統計データを閲覧・検索できるサイトです。
キーワードでの検索だけでなく、分野や統計作成した組織ごとにデータを検索することもできます。また、データのグラフや時系列表が閲覧できたり、地図上での表示や地域ごとのデータが表示できたりと機能が豊富なため、求めているオープンデータが調べやすい特徴があります。
Data.govは、アメリカ政府が公開しているオープンデータサイトです。
金融・科学技術・雇用・小売・健康などのさまざまなデータを閲覧できます。ただし、サイトのすべてが英語表記であるため注意が必要です。アメリカのオープンデータが必要な場合には、利用してみてください。

実際にオープンデータを活用した取り組みをいくつか紹介しましょう。
本記事では、以下の7つの事例を紹介します。
ぜひ、オープンデータを活用する際の参考にしてみてください。
「めがねの町」として全国的に知られている福井県鯖江市は、オープンデータの活用にいち早く取り組んだことでも有名です。
観光情報やグルメ情報、Wi-Fi設置場所などを紹介するアプリ「さばえぶらり」や、市営バスの運行状況をリアルタイムで確認できるアプリ「鯖江つつじバスモニター」など、官民協働で市民サービスに取り組んでいます。また、鯖江市役所には「JK(女子高生)課」という部署が設けられています。女子高生が地域活性化に携わることを目的としたこのプロジェクトは「市民主役条例」を制定する鯖江市の特徴が現れているのではないでしょうか。JK課によって開発されたものに、図書館の蔵書や空席情報を教えてくれるスマホアプリ「Sabotaつくえなう!」があります。
「Zaim」は、自分が住む地域の医療費控除や給付金制度を知ることができる家計簿アプリです。自治体によって異なる給付金データを集約し、ユーザー情報と照合することで、国や地方自治体からの補助金・給付金の情報を提供します。こうした情報は自治体のwebサイトや広報をまめにチェックしないと見逃しがちなため「役に立つアプリ」と好評です。
「税金はどこへ行った?」という市民主導のプロジェクトは、オープンデータ推進の目的のひとつである“行政の透明性・信頼性の向上”につながると言えるでしょう。自治体と家族構成を選択すると、自分が支払った税金が1日あたりどう使われているかを調べられます。2023年12月現在では、「税金はどこへ行った?」の活動をしていたほとんどのサイトが閉鎖されており、茨城県つくば市のサイトのみ確認できます。
不動産の売買や自宅の価値を知りたいときに便利なのが、日本全国の不動産の相場を知ることができるアプリ「GEEO」です。不動産価格を予測して地図上に表示してくれるため、不動産取引の健全化に役立っています。
一次データにオープンデータを利用し、さらにユーザー参加で内容を育てているケースもあります。バリアフリー情報サービス「WheeLog!(ウィーログ)」は、車いすでの移動に嬉しいアプリです。アプリを起動して車いすで走行すると、GPSでルートを記録するため、車いすが利用できるルートを共有できます。投稿機能もあり、バリアフリー情報や写真なども共有できるユーザー参加型のサービスです。
外出に不安を抱えるオストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)の悩みを解決してくれるのが「オストメイトなび」です。全国各地のオストメイト対応のトイレがスマホで簡単に検索できるため、外出時のトイレの心配がなくなり、QOL(生活の質)向上につながっています。日本語と英語に対応しているので、訪日外国人にも嬉しいサービスではないでしょうか。
子どもがいる家族に嬉しいのが、全国6万6,000カ所以上のおでかけスポットが検索できる「いこーよ」です。スポット情報やイベント情報、クーポンなどが閲覧でき、現在地からのルートも教えてくれます。ユーザーからの口コミ情報もあり、子育て層の情報交換の場としても活用されています。
このほかにも、信頼性の高いオープンデータにユーザーからの情報をリアルタイムに反映させた例は数多くあります。インフルエンザなどの感染症の発生状況を知ることができる「ワーンニング」や、スマートフォンの位置情報から近くの犯罪・防犯情報を確認できる「Moly」などは、日常生活に役立つアプリです。こうしたさまざまな視点や背景を持つユーザーによって、オープンデータが有効に活用されています。

インターネットの普及により、誰もが簡単に世界中から情報を得られるようになりました。ただし、その情報は正確なものでなくてはなりません。国や地方公共団体などが提供するオープンデータは、とても信頼度の高いものです。オープンデータを活用することで、より正確で公平なサービスを提供できます。地域の活性化や急速に進む少子高齢化への対策などあらゆる方面の課題解決はもちろんのこと、新しいビジネスチャンスとしても、オープンデータの活用には大きな期待が寄せられているのです。
(データのじかん編集部)
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

