




目次
「CIO Japan Summit 2023」は、環境や時代に合わせて変化し続ける経営課題に着目し、競争力の強化や課題解決へ導くための事業戦略支援です。
講演を通して最先端の情報や知識を学ぶだけではなく、One-to-One meetingsを通して、成長を促す企業連携の可能性を見出すことも目的としています。
今回は11月8日(水)、9日(木)の両日に東京都文京区のホテル椿山荘東京にて開催されます。
今回で16回目を迎えるCIO Japan Summitのメインテーマは「データ力」。ビジネスや社会を左右するデータを戦略的に活用し、より良い未来を築くために必要な視点とは何か、各業界のITリーダー19名、企業のIT部門責任者・IT関連のサービスを持つソリューションプロバイダー企業が一堂に会し、現在の市場環境下における課題やビジネスチャンスなどについて議論します。
開催中は講演・ディスカッション・One-to-One Meetings(商談会)・お食事交流会を通じて、現在取り組んでいる課題・問題の解決に加え、国内有数企業のCIOやIT・情報システム部門統括の方々と繋がりが持てる千載一遇の機会でもあります。
参加は、聴講者、もしくはソリューションプロバイダー企業として参加が可能で、双方が交流を深めることで以下のようなメリットをもたらしてくれます。
企業のIT部門責任者の方が対象です。講演、食事会、参加者同士のディスカッション、ソリューションプロバイダー企業とのミーティング等を通じて最新の知見を得ると共に新たな人脈の拡大に活用できます。
IT関連のソリューションをもつ企業が対象です。聴講者側として参加されているトップ企業のIT部門の決裁権者と一対一で商談できる機会があります。

「CIO Japan Summit」は毎回主要な議題を設定しており、回を重ねるごとにそのテーマは日本のDXの進化とともに高度な内容にアップデートされ続けています。遅れていると言われることが多い日本のDXも黎明期を終え、守りから攻めのDXへと過渡期に突入しようとしています。
・命運を分けるデータ力:
ビジネスや社会を左右する重要なデータを戦略的に活用し、より良い未来を築くために必要な視点や考え方を明らかにする。
・人事制度からみるIT人材:
IT人材の獲得・育成・定着を目指すために、雇用制度や評価の仕組みなどを見直し、持続的な企業成長を図る。
・デジタライゼーションによるESG実現:
デジタル技術の進化によりESG推進が現実的となった今、目標達成へ向けた仕組みを構築し、企業の持続可能性や社会的信頼性の向上を目指す。
・破壊的イノベーションが切り開く未来:
生成AIやChatGPTがもたらす変革の可能性を好機と捉え、ビジネスに生かす具体的な施策を検討することで、競争力を高めるチャンスを掴む。
・リターン本格化:
加速的に行ってきたDX投資や新技術導入の成果を検証し、本格的なリターンを得るための取り組みを考える。
・ビジネス牽引のための国際的視野:
CIOやIT部門がグローバルマインドを持つことで、国際展開に向けたIT整備を積極的に進める。

最新動向と展望を知り尽くしていることはもちろん、明晰な洞察を備えたCIOのスペシャリストの方々が現在の市場環境下における課題や潜在するビジネスチャンスについて、調講演・ケーススタディープレゼンテーション・パネルディスカッションを通じて活発に議論します。
住友生命保険相互会社
エグゼクティブ・フェロー デジタル共創オフィサー デジタル&データ本部 事務局長
岸 和良 氏

[プロフィール]
生命保険基幹システムの開発・保守、システム企画、システム統合プロジェクト、生命保険代理店の新規拡大やシステム標準化などを担当後、健康増進型保険“住友生命「Vitality」”の開発責任者を担当。現在はデジタル共創オフィサーとして、デジタル戦略の立案・執行、パートナー企業や自治体などとの共創活動、社内外のDX人材の育成活動などを行う。著書に『DX人材の育て方』(翔泳社)、『実践リスキリング』(日経BP社)などがある。
日本シーサート協議会/SBテクノロジー株式会社
理事長/サービス統括 セールス&マーケティング本部サービス・マーケティング統括部
プリンシパルアドバイザー
北村 達也 氏
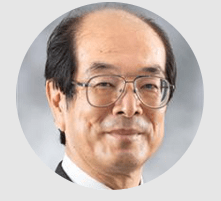
[プロフィール]
1981年、国内大手ゼネコンに入社、情報部門及び支店総務を経験。情報部門においてはプラットフォームの整備やインフラ全般の標準化、構築・運用を幅広く担当する一方で、IT戦略の企画やセキュリティ関連規定の策定、Office365導入による働き方改革の推進を行う。2013年1月にチームリーダーとして組織内CSIRTを立ち上げ日本シーサート協議会に加盟する。2020年1月、SBテクノロジー株式会社にジョイン、主にセキュリティや建設業への提案を担当。2022年6月、日本シーサート協議会の理事長に就任する。
創業150年の大衆食堂ゑびやの徹底的データ改革
有限会社ゑびや 代表取締役社長
小田島 春樹 氏

[プロフィール]
1985年、北海道生まれ。大学卒業後、ソフトバンクグループ株式会社入社。2012年 妻の実家が営む「ゑびや」に入社し、店長、専務を経て2012年に妻家業の食堂ゑびやを継承し、代表取締役社長に就任。2018年、第二創業でデータ分析事業のEBILABを創業、啓蒙、教育活動を通じてサービス業へのデータ分析、テクノロジー活用の拡大を目指す。同社の代表取締役CEO。2020年第3回日本サービス大賞「地方創生大臣賞」受賞。2019グレートカンパニーアワード2019「ユニークビジネスモデル賞」受賞など他多数受賞。
[プログラム概要]
大正時代から続く創業150年の大衆食堂「ゑびや大食堂」が、ITをフル活用し、経営にイノベーションを起こしました。ゑびや大食堂は、伊勢市の観光地でありながら、長い間売上に悩んでいました。その要因は食券制度や手書きの帳簿など昔ながらの変わらない経営が、時代の変化に適応できていなかったことだそうです。
小田島氏が指揮をとり、徹底的なデータに基づく経営判断を行った結果、9年間で売上約8.5倍、収益約50倍を実現しお店を一躍繁盛店へと変えました。加えて、フードロスや労働環境など、社会的な課題にも画期的な改善をもたらしました。また、単にデジタル化だけではなく、人材育成などを通して組織文化や従業員の意識改革を行いました。
同氏は小さな組織や中小零細企業こそ、正しくデータを扱い、経営に生かしていくべきだと語ります。現場とデータをうまく噛み合わせ、次の時代に向けた新しい価値観、サービスを生み出すためのヒントをご共有いただきます。
・データ経営で売上を劇的に増加
・老舗企業にも最新テクノロジーを導入して業務効率UP
・挑戦し続けることで道が拓ける
AI時代に問う:人間こそがデータを通じてストーリーを語る「考える葦」である
横浜市立大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 准教授
小野 陽子 氏

[プロフィール]
東京理科大学工学研究科博士課程修了,博士(工学) Bootstrap methodsや高階論理を用いた抽象数学定理自動証明システム構築など,統計学・数学・情報科学の融合領域を研究 。2018年より横浜市立大学データサイエンス学部准教授 。Women in Data Science (WiDS)を日本初開催となる2018年度からWiDS TOKYO @ Yokohama City Universityとして開催 。アンバサダーとして 、多様な人材をデータサイエンス分野に招き、データからストーリーを紡ぐことで協働する取り組みを行なっている。現在は、データサイエンス倫理におけるバイアス、データサイエンスと多様性、DS3.0 教育の研究に従事している 。
[プログラム概要]
世界的にデータサイエンティストの需要が高まる中、今回は、横浜市立大学のデータサイエンス学部准教授であり、「Women in Data Science」のアンバサダーでもある小野氏がご登壇します。
データという「過去」から未来を紡ぐデータサイエンス人材に求められる態度と、そのための素養について、Society 5.0時代の「温故知新」を魅力的な視点から解説します。キーワードは、「考える葦(アシ)」。データサイエンス人材には、単なる数理統計の知識だけでなく、コンパッション(共感力)を持ち、データを通じてストーリー(ミッションや目的)を考え、伝える能力が求められます。それらは、未来社会を創造する豊かな素養に裏打ちされるべきであると小野氏は強調します。また、昨今話題にあがる破壊的イノベーションとの関係性にも触れていきます。例えば、生成AIであるChatGPTとの関わり方において、単に結果を受け入れるか否かの議論だけでは不十分であり、人間の役割は、あるべき未来社会構築に通じるストーリーを考え、語り、主体的に行動に移すことです。人間が自らの役割を放棄することは、安寧で豊かな未来の可能性を閉ざすことだと述べています。本講演を通して、AIとICTの進歩とその社会実装が進む近未来社会において、データサイエンスを扱う人間の役割が、今まで以上に重要になることを実感できるはずです。
・データサイエンスを自分ごとに
・データから紡ぐストーリー
・考える葦とは
CIOが切り開くITとビジネスのグローバル展開
参天製薬株式会社 執行役員 チーフ デジタル&インフォメーション オフィサー
原 実 氏

[プロフィール]
NEC勤務経験を経て国連職員に転身し、約20年間、持続可能な開発目標(SDGs)の推進に従事。国際電気通信連合(インドおよびスイス)、国連本部(米国)、国連ボランティア計画(ドイツ)、国際原子力機関(オーストリア)の各機関にて、ITサービス、インフラ、セキュリティ組織を統括。2012年より国際労働機関(ILO)国際研修センター(イタリア)にてCIO、次いで国連食糧農業機関(イタリア)にてCIO代理としてIT・デジタル中期戦略を推進。2020年より参天製薬執行役員CDIO。上智大学工学修士、イタリアSDA Bocconi経営大学院・国際機関経営学エグゼクティブ修士、シンガポールEmeritus経営学院・デジタルビジネス大学院学位(PGDip)。スイス・ジュネーブ在住。
[プログラム概要]
現在、参天製薬株式会社のCDIOであり、多くの国際機関でのIT部門の経験を持つ原氏の講演では、グローバルな社会課題への貢献やCIOの役割の魅力について焦点を当てます。約20年間6か国において、国連職員として持続可能な開発目標(SDGs)の推進に従事し、世界が直面する急速なグローバル開発アジェンダにもデジタル・ITが貢献できるよう、組織を迅速にリードしてきました。2012年にイタリアの国際機関のCIOに就任した後、同社へ移り、Santenデジタル戦略フレームワークを策定しました。このフレームワークは、参天製薬が世界中の患者に対して提供する価値を進化させるために、デジタルやITがどのように貢献するかを具体化するものです。同氏が国際機関で体験した多様性に満ちたグローバルな組織の力を、同社内でも作り上げたいという目標のもと、自身はグローバルCDIOとしてスイスを拠点にし、9か国に分散し22の国籍のメンバーで構成されたデジタル&IT組織への変革を実施しました。価値観の違いを尊重し合えるチームを作ることで、刺激があり熱量の多いチームへの変革を加速するという同氏の発想から学べるポイントは多くあります。本講演を通して、CIOやIT部門がグローバルな視野を持ち、既成概念にとらわれることなく、デジタル, ITがもたらす新しいインパクトやイノベーションの開発に取り組むことの重要性を再考していきます。
・グローバルキャリアパスの設計と次世代リーダーの育成
・ビジネス戦略とデジタルIT戦略のグローバル統合
・ビジネス価値の継続的な提供とイノベーション
組織の枠を超えた先に見つけたデジタル革命術
小林製薬株式会社 執行役員 チーフ・デジタル・オフィサー
石戸 亮 氏

[プロフィール]
サイバーエージェント入社、子会社2社の取締役を務め、Google Japanにおいて大手広告主のデジタルマーケティングを支援、イスラエル発のAIスタートアップ企業のデートラマでは日本市場参入を推進。セールスフォース・ドットコムによるデートラマ買収時には、日本市場におけるPMIをリード。2020年4月からパイオニアの全社CDOやカンパニーCMOとして非上場後の再成長期に貢献。小林製薬では2021年よりデジタル戦略アドバイザーを務め、2023年より同社へ入社し、CDOとして全社のDX推進を牽引している。ノバセルの事業戦略アドバイザーも兼任。
[プログラム概要]
インターネットベンチャー企業、外資系企業での仕事を経て、老舗大手日本企業にJoinした石戸氏より、組織の枠組みを超えたデジタル革命への挑戦ストーリーをお話しいただきます。同氏は兼業も含め、様々な経験をもつからこそ、上場企業のなかで文化を活かしたデジタル革命ができるといいます。デジタル革命の根本にあるイシューにも焦点をあて、軌跡をたどることで、持続的成長し続けることのできる組織につながるヒントを探ります。
・DXを推進する思考法
・「DX」「IT」「組織」などの枠組みに囚われない組織変革の考え方
・再現性があり、個人・組織成長の考え方と仕掛け
人事施策から読み解くドミノがITフードカンパニーになれたワケ
株式会社ドミノ・ピザ ジャパン HR部 部長
影山 光博 氏

[プロフィール]
1989年日本マクドナルド株式会社に入社。東北および関東の店舗マネージャーを経験したあと、米国シカゴのマクドナルド店舗に3年駐在し店舗経営を学ぶ。帰国後、ハンバーガー大学にて研修デザインを担当。その後、人事本部にて統括マネジャーとして主に人事戦略、HRBPロールなどを経験。2016年株式会社シャノアール(カフェ・ベローチェ)へ入社し、人事部を担当する。2019年株式会社ドミノ・ピザジャパンへ入社し、HR部を担当する。現在、1000店舗の人材をサポートすることに日々邁進中
[プログラム概要]
デリバリーピザ業界で首位の座を手にしたドミノピザ。業績回復のキーは「今日の晩ごはんはピザにしよう」と日常的に思ってもらえるようになることでした。そのイメージを刷り込むための綿密な戦略があり、その裏にはテクノロジーのチカラがありました。「どれだけ身近に購入できる場所があるか」というオーダーのフェーズでは、デジタルツール改修、注文を最小限に簡単に行えるよう改修しました。専用のアプリでGPSを活用して来店客の位置情報を把握、来店のタイミングに焼き立てのピザを渡すというオペレーションを確立したり、デリバリー時間の極限短縮など、商品提供時間の短縮にトコトンこだわり、顧客視点でのDXを完成させています。
人と組織がついてこないと、巧みな戦略もイノベーションも成立しません。コロナ禍を通して、あらゆる組織が変革を迫られる中、ドミノが素早く変革できた本質は人材にあるのではないでしょうか。今回は人事部部長である影山氏にご登壇いただき、IT人材を引き付けるための人事施策についての試行錯誤ストーリーをお話しいただきます。IT人材を、より包括的な視点で分析し、イノベーションが生まれる組織・人の生み出し方についてヒントを得ていきます。
・”Hungry To Be Better(良くなることにハングリー)”を体現するビジネス施策
・”Employer Of Choice(選ばれる雇用主)”へ向けた人事施策
・CIOとHR部長のコラボレーション
エバンジェリスト(伝道師)が語るCIOの可能性
富士通株式会社 シニアエバンジェリスト
松本 国一 氏

[プロフィール]
1991年富士通株式会社へ入社。情報・通信・モバイルの合計16部門40部署でソフト/ハードの設計から製品・事業企画/販売推進/営業支援まで様々な業務に従事。現在、多彩な業務経験を活かしシニアエバンジェリストとして活躍中。雑誌や新聞、web、ラジオなど多くのメディアで働き方改革の紹介や池上彰氏、八塩圭子氏、佐々木俊尚氏など著名人との対談、ほか学会誌の執筆や日本銀行ラウンドテーブル、複数の高校・大学で講義など幅広く活躍中。
[プログラム概要]
コロナ禍において世界がデジタル化に大きく舵を切る中、デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の現場を大きく変革しています。なぜ日本のDXは進まないのでしょうか。本講演では、その理由やDXの勘違いについて紐解き、新たな可能性について探っていきます。
例えば、コロナ禍で進められたテレワークの流れに制度面から焦点を当て、新しい働き方を実現するためには「どこでも働ける環境や制度が必要」で、その対策が結果的には会社を大きく成長させるための原動力になるといいます。人材確保や副業・兼業による優秀な社員の獲得、労働力人口減少への対策など、挑戦というドアを開けば様々な可能性があります。現場の目的を元にした手段を導入することでCIOこそが会社を支える存在になれると勇気あるメッセージを放ちます。
・デジタルトランスフォーメーションの本質理解が会社を変える
・働き方を変えるためにはCIOの決断が必要不可欠
・会社を価値向上するためCIOの役割は重要に
自治体CDOが語る!破壊的イノベーションは旧態依然の組織を変革できるのか
越谷市役所 最高デジタル責任者(CDO)
川口 弘行 氏

[プロフィール]
芝浦工業大学大学院博士課程修了。博士(工学)。1996年行政書士登録。2004年日本行政書士会連合会高度情報通信社会対策本部WG委員。会津大学短期大学部非常勤講師、東京都立中央・城北職業能力開発センター講師を経て、2009年高知県CIO補佐官。2013年経済産業省CIO補佐官、東京都港区情報政策監。2015年佐賀県情報企画監。2023年越谷市最高デジタル責任者。省庁、都道府県、区市町村におけるCIO補佐官業務に携わり、自身で開発したセキュリティソフトウェアは全国約300団体で利用されている。
[プログラム概要]
社会のデジタル化が進む中、政府が掲げる「デジタル田園都市国家構想」を受けて、多くの自治体でもデジタル変革(DX:デジタル・トランスフォーメーション)に向けた取り組みが積極的に行われています。
いわゆる「スマート自治体」を実現させるには、多様化する住民ニーズに応じた行政サービスの拡大、システムの効率的な運用、新たなデジタル技術の活用、IT人材育成など、多くの課題を解決しなければなりませんが、人口減少により規模の縮小が進む中では現状を維持するだけで精一杯の自治体もあります。
今回は、高知県や佐賀県、経産省、港区などでの経験を多く有し、現在は越谷市の最高デジタル責任者(CDO)である川口氏にご登壇いただき、自治体が取り組むデジタル変革についてお話しいただきます。加えて、最近注目を集めている生成型AI(ChatGPT)の行政分野での活用事例やスタンスについても共有いただき、事業会社、自治体一体となり、日本をトランスフォーメーションしていくための道筋を探っていきます。
・自治体DX
・IT人材育成
・生成型AIの行政分野での活用
データ分析プロによる未来会議:データが形作る世界
三井物産セキュアディレクション株式会社 執行役員
関原 優 氏
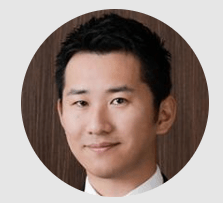
[プロフィール]
大手通信事業者などでセキュリティサービス運用に携わった後、三井物産セキュアディレクションの設立に携わる。20年以上にわたり、IT・サイバーセキュリティのサービス事業に従事し、SOC構築、サイバー攻撃分析、疑似攻撃によるWebサイトやネットワークのセキュリティ診断、自社SIEMなどのセキュリティツール開発、官公庁やグローバル企業に対するセキュリティコンサルティング等を手掛ける。現在は執行役員として、セキュリティ診断部門、SOCやマルウェア解析部門など約180名を率いて事業を推進している。
LINEヤフー株式会社 Data Protection Officer
中山 剛志 氏

[プロフィール]
米国・英国・豪州大手法律事務所、三菱商事(株)、ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))等を経て、2014年 LINE(株)(現 A ホールディングス(株))入社。LINE(株)執行役員CPO/CISOとして、法務・セキュリティ・コンプライアンス・リスクマネジメントを統括。2021年Zホールディングス(株)執行役員プライバシー&セキュリティ統括部長就任.2023年10月より現職。米国ニューヨーク州・ワシントンDC弁護士、英国ウェールズ弁護士、CISSP認定、CGRC、FIP、CIPM、CIPP/E。
株式会社グロースX マーケティング部門 兼 コンテンツ部門 執行役員
松本 健太郎 氏

[プロフィール]
松本 健太郎(まつもと けんたろう) 職業はマーケター、データサイエンティスト。 1984年生まれ。龍谷大学法学部政治学科卒業。大阪府出身。社会人として働く中でデータサイエンスの重要性を痛感し、多摩大学大学院に通って“学び直し”。現在は事業会社で執行役員を務めている。 政治、経済、文化など、さまざまなデータをデジタル化し、分析・予測することを得意とし、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌に登場。報道にデータを組み合わせた「データジャーナリズム」を志向し、本業のかたわら放送作家ならぬ「データ作家」を請け負っている。 また、ビジネス書作家として16冊(約10万部)書いており、うち3冊が海外でも刊行されている。
[プログラム概要]
現代社会において、データは無視できないほど重要な資産となった。データ駆動型社会という言葉が示す通り、企業や組織はデータを活用することで効果的な意思決定やビジネス戦略の策定を行っています。しかし、データがこれほど重要であるが故に、その信頼性を保つことは喫緊の課題です。データが信頼できなければ、企業基盤が揺らぎ、組織の存続にさえ影響を及ぼしかねません。そのため、セキュリティの観点からのアプローチは不可欠です。
本セッションでは、データ分析・解析に関するプロの方々が集結し、データの信頼性を保つ方法やセキュリティ対策について知恵を出し合います。単なる技術的な側面だけでなく、経営リスクとしてのデータプロテクションについても考察し、データが企業や国の未来を形作る鍵であることを認識し、日本の未来を守るための道筋を共に探っていきます。
SBOM入門書:ソフトウェアセキュリティを進化させる鍵
大阪大学 サイバーメディアセンター 教授 / CISO
猪俣 敦夫 氏

[プロフィール]
2008年奈良先端科学技術大学院大学准教授、2016年東京電機大学教授、2019年大阪大学教授、CISO、サイバーメディアセンター副センター長、立命館大学客員教授、一般社団法人JPCERT/CC理事、一般社団法人公衆無線LAN認証管理機構代表理事、大阪府警察・奈良県警察サイバーセキュリティアドバイザ、他多数。
一般社団法人ソフトウェア協会 Software ISAC 理事、共同代表
萩原 健太 氏

[プロフィール]
法政大学大学院公共政策研究科修士課程修了。主に組織的なサイバーセキュリティ対策を専門とし、関連する講演や助言、セキュリティチーム(CSIRT)の構築や運営支援など幅広く行う。つるぎ町立半田病院の事案では現地調査や報告書作成を行い、大阪急性期・総合医療センターの事案ではインシデント発生当日から政府派遣の一員として初動対応支援を実施。その他に(一社)日本シーサート協議会運営委員長、NICTナショナルサイバートレーニングセンター招聘専門員、㈱ビジネスブレイン太田昭和CMO、インターバルリンク㈱代表取締役なども務める。
PwCコンサルティング合同会社 パートナー
丸山 満彦 氏

[プロフィール]
25年にわたり製造業、サービス業、金融機関、政府などの幅広い業種に対するサイバーセキュリティ、ITリスク分野のコンサルティング、監査に携わる。内閣官房に出向し、内閣官房サイバーセキュリティセンターの立ち上げ、政府統一基準の策定、改訂に関与。ISMS制度の立ち上げ、普及にも関わる。内閣官房、総務省、経済産業省などの有識者委員に多数就任しているほか、複数のセキュリティ関連団体の理事、監事も務める。
日本シーサート協議会/SBテクノロジー株式会社
理事長/サービス統括 セールス&マーケティング本部サービス・マーケティング統括部
プリンシパルアドバイザー
北村 達也 氏
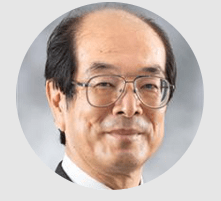
[プロフィール]
1981年、国内大手ゼネコンに入社、情報部門及び支店総務を経験。情報部門においてはプラットフォームの整備やインフラ全般の標準化、構築・運用を幅広く担当する一方で、IT戦略の企画やセキュリティ関連規定の策定、Office365導入による働き方改革の推進を行う。2013年1月にチームリーダーとして組織内CSIRTを立ち上げ日本シーサート協議会に加盟する。2020年1月、SBテクノロジー株式会社にジョイン、主にセキュリティや建設業への提案を担当。2022年6月、日本シーサート協議会の理事長に就任する。
[プログラム概要]
現代のデジタル環境において、ソフトウェアは生活やビジネスにおいて不可欠な役割を果たしています。しかし、ソフトウェアが進化し、複雑化するにつれ、セキュリティの脆弱性も増加していることも事実です。そこで、ソフトウェアのセキュリティを強化するために、SBOM(Software Bill of Materials)が注目されています。SBOMは、ソフトウェアのコンポーネントや依存関係を透明にし、ソフトウェアサプライチェーンの透明性を高めるための仕組みです。
このパネルディスカッションでは、SBOMの重要性、導入の利点、課題、そして将来の展望について討論します。実際にSBOMを導入している企業はまだ少ない中、本パネルは非常に有益なものとなるでしょう。
セキュリティの専門家のなかでも有数の知識人にお集まりいただき、SBOMの活用意味・意義・方法についてケーススタディを交えながらアドバイスをいただきます。
CISO考察:経営陣とセキュリティ専門家のギャップはどこにあるか
JNSA(日本ネットワークセキュリティ協会)
CISO支援ワーキンググループ リーダー、副会長
高橋 正和 氏

[プロフィール]
ソフトウェア開発、品質管理などを経て、1999年よりセキュリティベンダ(ISS社)でコンサルティング事業、マネージドセキュリティサービスの立上げなどを担当。2006年よりマイクロソフト社でCSA(チーフセキュリティアドバイザー)として企業などへのセキュリティ対策の支援を担当。クラウドなどのITインフラの転換に伴い、知識だけでは対応できないことを痛感し、自ら対策を実践することを決断。2016年にPreferred Networks社に入社しCSOに就任。並行してリスク管理、COVID-19対応なども担当。2021年に業務執行としてのセキュリティを題材に「CISOハンドブック」、2023年にCISOの実務に沿った実践的な取り組みとして「CISOのための情報セキュリティ戦略」を出版。
[プログラム概要]
デジタル化の進展と共に、情報システムは企業の生命線として不可避の存在となりました。企業経営をめぐるセキュリティの懸念は現実化し、深刻なセキュリティ事件・事故の報道は後を絶ちません。経営者は、保有する情報資産の侵害が、事業に与える影響を認識し、自らのセキュリティ施策の状況と有効性を把握する必要があります。
高橋氏は著書「CISOハンドブック」に沿った CISO-PRACTSIEと呼ばれるインシデント対応の机上演習を実施し、セキュリティ対策の検証に取り組んできました。この取り組みを通じて、経営者とセキュリティ専門家の間に存在するギャップが明らかになったとそうです。
このギャップの解明を通じて、「経営陣がセキュリティを理解する」のではなく、「セキュリティ専門家が経営や事業にアラインして活動する」ことーすなわちこれが企業の情報を守る盾となるCISOの役割であると説きます。
今回の講演では、経営視点・事業視点からセキュリティの重要性を考察し、新しいアプローチ方法に焦点を当てていきます。
・遵守性の監査と有効性の検証
・経営者に対する透明性と、社会に対する説明責任
レッドチームが支えるNTTのサイバーセキュリティ
NTTセキュリティ・ジャパン株式会社 セキュリティオペレーション部
羽田 大樹 氏

[プロフィール]
NTTセキュリティ・ジャパンに勤務。NTTグループ認定セキュリティプリンシパル。2008年よりSOCにて脆弱性診断、インシデントレスキュー、セキュリティサービス開発、オペレーション、脅威分析マネージャーを経験し、2021年よりRedTeam業務に従事。情報セキュリティ大学院大学でインシデントレスポンスの研究に取り組み、2019年に博士号を取得。情報セキュリティ大学院大学客員講師、マルウェア対策研究人材育成ワークショップ(MWS)、情報処理学会ジャーナル(JIP)、BlackHat Arsenal(USA、Europe)、セキュリティキャンプ全国大会講師、セキュリティのためのログ分析入門(共著)、等。
[プログラム概要]
現実に発生する可能性があるサイバー攻撃のプロセスを攻撃者視点から疑似攻撃を行うレッドチーム。NTTグループ鉄壁セキュリティの秘密は、レッドチームによる脆弱性発見とセキュリティ強化によるものなのかもしれません。
本セッションでは、NTTグループ「Team V」の中核メンバーである羽田大樹氏より、レッドチームがどのように活動し、ミッションを遂行しているか詳しくご紹介いただきます。ゼロデイ脆弱性や新たな攻撃手法の発見などの難しさなど、具体的な手法だけでなく、人材育成やリクルーティング、情報発信についても触れ、レッドチーム活動に求められるスキルセットに焦点を当てていきます。同時に、ブルーチーム視点での対策についても考え、セキュリティをより一層盤石なものにしていきます。
・NTTグループの脆弱性を攻撃者視点から発見
・ミッション(レッドチーム活動、人材育成、リクルーティング、情報発信)のご紹介
・レッドチーム活動に求められるスキルセットとは
・ブルーチーム視点で考えるべき対策
世界共通のフレームワーク”ITU-T勧告 X.1060 ”で盤石なセキュリティ体制を
ISOG-J 日本セキュリティオペレーション事業者協議会 副代表
武井 滋紀 氏

[プロフィール]
NTTテクノクロス株式会社にて各社のセキュリティ運用体制などのコンサルティングに従事するとともにエバンジェリストとして活動。日本セキュリティオペレーション事業者協議会の副代表などとしても活動し、国際標準機関「ITU-T」のSG17WP3 Q3(Study Group 17 Working Party3Question3)に出席し、X.1060のエディタの1人として策定に携わる。NTTグループセキュリティプリンシパル、ISC2 CISSP/CCSP、情報処理安全確保支援士(009938)。
[プログラム概要]
セキュリティはデジタル時代において不可欠な要素となり、CSIRT や SOCなどセキュリティに対応する組織が設けられた。企業や組織によって組織形態は異なるため、明確に定義するのは難しい中でも、セキュリティ対応に必要となるカテゴリーやサービスは俯瞰すれば共通的なものが見えてきます。
ISOG-J(Information Security Operation providers Group Japan)が提唱する「セキュリティ対応組織の教科書」では、求められる共通的なカテゴリーやサービスをすべて書き出し、効果的な組み合わせや、幅広い知見をエッセンスとして取りまとめており、経営者~現場担当者まで幅広く活用できるまさに企業や組織の‘教科書’です。
加えて、昨年には、武井氏も策定に関わりX.1060を日本語化した、サイバーディフェンスセンターを構築・運用するためのフレームワーク「JT-X1060」が公開され、正式な日本の標準としても掲げられました。
本講演では、セキュリティ対応組織の構築から運用、評価まで各フェーズに焦点を当てながら、X1060が共通言語として日本のみならず世界でどのように活用されているのか、ご解説いただきます。
・日本発の考え方が含まれ、日本から世界をリードできる
・SOCやCSIRTの先にあるセキュリティ統括という概念
・各国の利用も想定され、サプライチェーンなどでの共通言語になりえる
激化するサイバー脅威と、信頼性と自由なデータ流通を支えるデジタルトラスト
一般社団法人デジタルトラスト協議会、日本電気株式会社
サイバーセキュリティ戦略統括部、兼、セキュリティ事業統括部、兼、CISO統括オフィス上席プロフェッショナル
林 亮平 氏

[プロフィール]
NEC入社以来、メインフレーム及びオープンシステムの製品計画、パートナアライアンス・M&A戦略推進、ミッションクリティカルシステム事業、パブリックセーフティ事業、サイバーセキュリティ事業等を担当。2017年、東京2020組織委に出向。 テクノロジーサービス局次長として、大会を支えるハイブリッドクラウド、マルチベンダシステムPJを推進し、大会本番時は、24×7のテクノロジーオペレーションを統括。2022年よりデジタルトラスト協議会に参画し、トラストサービスの政策提言、普及活動に取り組む。
[プログラム概要]
我が国における包括的データ戦略の中で、「トラスト」が中心的柱として位置づけられています。今回はデジタルトラスト協議会( JDTF )より、サイバー空間における脅威がますます激しくなる中で、この「トラスト基盤」がなぜ必要で、どのように使われるかについて詳しくご説明いただきます。
包括的なデータ戦略におけるトラスト基盤、トラストサービスの法的課題、欧州での事例など、多角的側面から紐解いていきます。データガバナンスにおける信頼性とトラストの重要性を明らかにし、サプライチェーンに跨るセキュリティ対策やESG対応等、直面する様々な社会課題について洞察することで日本と世界のデジタル未来を築くための一歩を踏み出すことができるでしょう。
・すます猛威を振るうサイバーセキュリティの脅威
・政府や欧州等におけるデータ流通、トラストに関連する動向
・サプライチェーンに跨るセキュリティやカーボンフットプリント等のESG対応
タレント人材活性化のための雇用制度について語る
オルガノアクティ株式会社 経営統括本部 業務改革推進部 情報システムグループ長
原田 篤史 氏
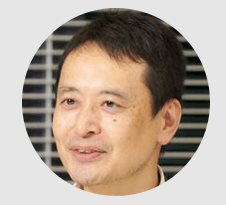
[プロフィール]
1973年生まれ 1996年に大学卒業に鹿島建設のグループ会社に入社、2005年にクボタグループに転職、2007年にオルガノに入社。一貫して水処理プラントのエンジニア畑を進んでいたが、2020年のコロナ禍での緊急在宅勤務対応の先導指揮を執ってから情報システムの部門長となった。オンプレスクラッチの思想だったオルガノのシステムをクラウドシフトに方向転換し、会社の長期経営ビジョン「ORGANO2030」の実現に向けて、オルガノグループ全社員のデジタル人材化を進める。
BIPROGY株式会社
人事部・人的資本マネジメント部・品質マネジメント部 担当 業務執行役員 CISO
宮下 尚 氏

[プロフィール]
1989年日本ユニシス株式会社(現、BIPROGY株式会社)に入社。エンジニアとして活動していたが、2002年に米国法人であるNULシステムサービス・コーポレーション(現、BIPROGY USA)の副社長就任後、コーポレートスタッフに異動。2005年に帰国後、経営企画部に所属。2013年の業務部長、2015年の人事部長を経て、2019年に業務執行役員に就任。現在、CISOであるとともに、人事部、人的資本マネジメント部、品質マネジメント部を担当している。
日立造船株式会社 ICT推進本部 常務執行役員
橋爪 宗信 氏

[プロフィール]
1988年 大阪大学経済学部経済学科卒業
1988年 日本電信電話株式会社入社
株式会社NTTデータに分社後、主に法人系システム開発を担当
同ソリューションサービス事業部長
株式会社NTTデータテラノス代表取締役社長 株式会社NTTデータ
公共部門技術戦略統括部長
2018年 日立造船株式会社入社 常務執行役員 ICT推進本部長(現職)
住友生命保険相互会社
エグゼクティブ・フェロー デジタル共創オフィサー デジタル&データ本部 事務局長
岸 和良 氏

[プロフィール]
生命保険基幹システムの開発・保守、システム企画、システム統合プロジェクト、生命保険代理店の新規拡大やシステム標準化などを担当後、健康増進型保険“住友生命「Vitality」”の開発責任者を担当。現在はデジタル共創オフィサーとして、デジタル戦略の立案・執行、パートナー企業や自治体などとの共創活動、社内外のDX人材の育成活動などを行う。著書に『DX人材の育て方』(翔泳社)、『実践リスキリング』(日経BP社)などがある。
[プログラム概要]
永遠の課題である「IT人材の獲得・育成・定着」を制度的な側面から考えていくセッションです。日本の雇用制度がIT人材やDX人材の活性化を促進するために適切な動きをしているのか、各企業は適切な制度を整えることができているのでしょうか。
さらには、社員一人ひとりが本気で「変わりたい」と思う内発的動機を促すための、組織の動きについても踏み込んでいきます。今回は、異なるバックグラウンドを持つ3名のパネリストが登壇し、デジタル時代における人材戦略や変化し続けることのできる組織づくりについて具体的なアイデアを探っていきます。
オルガノの原田氏は非IT出身ながら情シス部門長として数々の改革を実行。現在はオルガノグループ全社員のデジタル人材化を進めています。日立造船の橋爪氏は経営層向けのDXリーダー研修に力を注ぐ、データのスペシャリストです。BIPROGYの宮下氏はCISOと人事部・人的資本マネジメント部の両視点 豊富な経験を持っています。
本ディスカッションを通して、IT人材戦略に関する視点を広げ、デジタル時代において競争力を高めるためのヒントを得ます。
DX優良企業が語る:昨今の変革祭りで本当に変革したのか?
株式会社日立製作所
ヘルスケアイノベーション事業部 デジタルヘルスケア本部 シニアストラテジスト
宇賀神 敦 氏

[プロフィール]
日立製作所入社後、コンピュータの設計・企画・マーケティング、DVD-HDDレコーダ事業責任者及びコンピュータ販売責任者を経て、2009年より日立データシステムズ社Vice President(米国シリコンバレー駐在)として、サーバ事業のグローバル展開をリード。2012年よりデジタルヘルスケア事業開発に従事し、2015年日立ヨーロッパ社Healthcare Program Director(英国駐在)として英国NHSとの協業事業責任者。2018年よりヘルスケアビジネスユニットChief Lumada Officer、内閣府第2期SIP AIホスピタルの研究責任者。現在、医療AIプラットフォーム技術研究組合専務理事、東京医科歯科大学非常勤講師、AMED課題評価委員、日本医療機器産業連合会データ利活用TF主査を併任。
関西電力株式会社 IT戦略室 IT企画部長
上田 晃穂 氏

[プロフィール]
1997年関西電力株式会社入社。関西電力グループのIT戦略、ITマネジメント推進、情報技術戦略策定等に従事。2016年に株式会社ケイ・オプティコム(現オプテージ)へ出向し、携帯電話サービス「mineo」の責任者として事業戦略、マーケティング推進に従事。2019年から関西電力広報室でデジタル広報・広告業務に従事後、2021年から関西電力IT戦略室 IT企画部長としてIT・DX推進や情報セキュリティ統括に従事。趣味は読書(ビジネス書)と資格取得(技術士[情報工学・経営工学・電気電子・総合技術監理]、中小企業診断士)
[プログラム概要]
本セッションでは、加速的に進められたDX投資の成果を振り返り、本格的なリターンを得るための戦略的なアプローチについて探求します。異なる業界でDXに成功した「DX優良企業」のパネリストが一堂に会し、実践的な知見や経験を共有。成功事例だけでなく、今だから言える、失敗事例やそこから得られた教訓についても率直に議論していただきます。
本セッションを通じて、自身の組織のDX投資の成果を再検証し、本格的なリターンを得るための戦略を見直すことで、さらなる進化の手助けとなるでしょう。
・関西電力:データアナリストなどDX人材を現2.4倍の1000人超へ目標を定め、持続的な成果を追求する。
・日立製作所:ロボット、アバター、タブレットとAIの組み合わせによるテクノロジーと人間の協調や医療AIプラットフォーム活用による医療DXの実現をめざす。
強豪ホームセンター/スーパー座談会:データ革命×ESG経営の勝ち筋とは
株式会社グッデイ 代表取締役社長
柳瀬 隆志 氏

[プロフィール]
1976年生まれ。東京大学経済学部卒業後、2000年三井物産入社、食料本部に所属。冷凍食品等の輸入業務に取り組んだ後、2008年嘉穂無線ホールディングス株式会社に入社。営業本部長・副社長を経て、2016年6月嘉穂無線ホールディングス株式会社、及び株式会社グッデイ社長就任。2017年4月からは、グループ会社の株式会社カホエンタープライズにて、クラウド活用やデータ分析を行う事業にも取り組んでいる。2022年2月「なぜ九州のホームセンターが国内有数のDX企業になれたか」を出版。2022年6月、株式会社グッデイが第1回日本DX大賞「大規模法人部門」にて大賞を受賞する等、DX 関する幅広い取り組みも行っている。
オーケー株式会社 執行役員 IT本部長
田中 覚 氏

[プロフィール]
アクセンチュア、GE、スシローなどでの経験を経て、たなかさとる&COを起業。オーケーではCIOとして基幹システムのモダナイゼーション、店舗DX・本社BPRを実施する一方で、スマホアプリを開発し、CRMやデジタルマーケティングを推進本セッションでは、グッデイ、ヤオコー、オーケーストアと、小売業界の代表的企業が一堂に会す、夢の共演が実現します。
株式会社ヤオコー デジタル統括部 部長
小笠原 暁史 氏

[プロフィール]
1999年オーガニック食品宅配の株式会社大地を守る会に入社、2011年よりIT戦略部の部長となる。2017年にオイシックス社との統合後(オイシックス・ラ・大地)は、システム本部 副本部長と業務本部 副本部長を兼任。2019年10月より株式会社ヤオコーに入社、業務システム企画担当部長、デジタル統括部副部長を経て、2023年3月より現職
[プログラム概要]
小売業界は日々変動する膨大なデータを抱えており、スピード感を保ちながらも、データを綿密に管理し、経営に活かすことが企業の競争力と存続に大きく関わる。AI型自動発注導入などのデータ分析・活用の最新動向、部門再構築等組織作りの工夫、内製化推進など足元の取り組み事例も踏まえて以下のようなテーマを掘り下げます。
・データ活用の最新トレンドと小売業界における実践事例
・環境データと消費者の行動データの組み合わせがもたらす可能性
・データから見えるブランド価値向上と顧客ロイヤルティの関係性
・ESG経営がもたらす多様なビジネスチャンスと社会問題解決への貢献
業界のリーダーが集結し、データの活用と持続可能な未来への挑戦について切磋琢磨することで新たな視点と具体的な道しるべを得ることができる貴重なセッションです。
「CIO Japan Summit 2023」は主催社の厳選な審査を経たITリーダーの方々と最先端のソリューションプロバイダーの方々のみ参加されるサミットです。
そのため、参加基準を設けていない一般のイベントと違い、利害関係が一致する将来のビジネスパートナーや問題解決策の提供者との高いマッチングも実現します。
企業が抱える課題解決に取り組むCIOたちの視点に直接触れられるの機会。ビジネス変革の課題・問題の解決、ビジネスチャンスの獲得の場にぜひともご活用下さい。
| イベント名 | CIO Japan Summit 2023 |
|---|---|
| 開催日時 | 2023年11月8日(水)・9日(木) |
| 開催場所 | ホテル椿山荘東京 〒112-8680 東京都文京区関口2−10−8 |
| 主催 | マーカスエバンズ |
| URL | https://events.marcusevans-events.com/cio23h22/ |

第16回『CIO Japan Summit 2023』のメインテーマは「データ力」。ビジネスや社会を左右するデータを戦略的に活用し、より良い未来を築くために必要な視点とは何か、各業界のITリーダー19名にお話しいただきます。
本サミットは、企業のIT部門責任者・最先端のIT部門関連のサービスを持つソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、IT業界における課題や解決策について議論をしていただくイベントです。
なお、本サミットは『CISO Japan Summit 2023』と同時開催します。
詳細はこちらメルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!

