




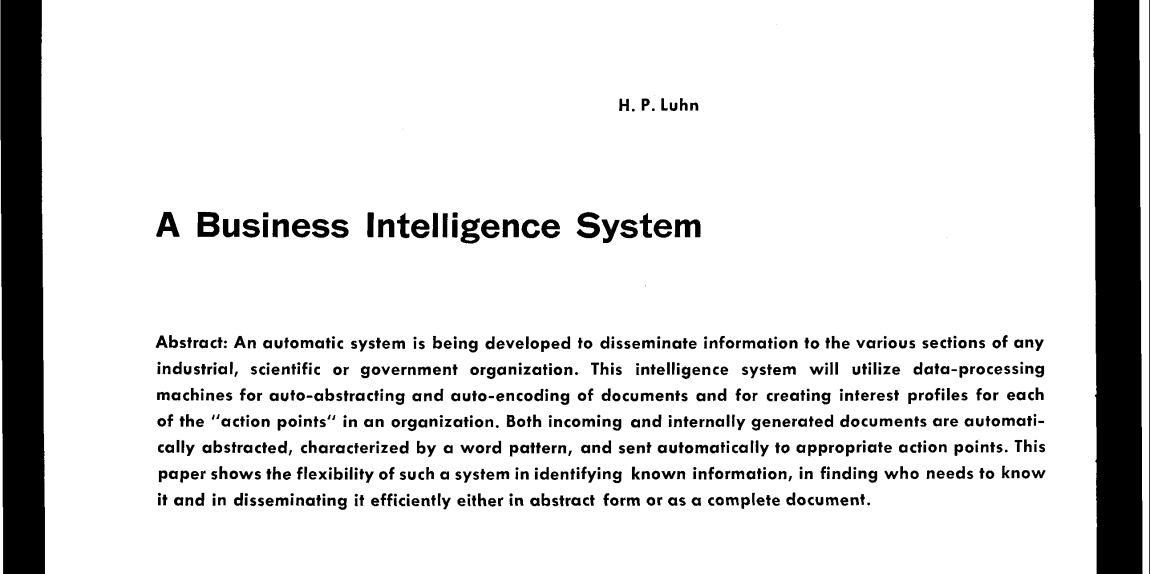
ハンス・ピーター・ルーンによる「A Business Intelligence System」と題する論文
そもそもBIとは、「Business Intelligence:ビジネス・インテリジェンス」のことで、この言葉は、1958年にビジネスインテリジェンスの父とも言われるIBM研究所のハンズ・ピーター・ルーン氏の提唱によって誕生したもの。その後1989年に、米ガートナーのバイスプレジデント 兼 ガートナー フェローのハワード・ドレスナー氏が「(専門家でない)誰もがデータを分析し、分析結果を業務(意思決定)に生かすこと」と、BIの概念を定義したと言われています。現在のBIは、ほぼこのドレスナー氏の定義したものの延長線上に発展してきたと言ってよいでしょう。
平たく言えばBIは、「さまざまなデータを分析し、経営戦略立案や意思決定支援を行う技術」であり、BIツールはその機能を備えたソフトウエアということになります。これも最近は、クラウドサービスとして提供されているものが多くなってきました。単独のコンピュータ上にあるデータから、外部のさまざまなシステム上にあるデータベース、そしてBI分析に特化したデータウエアハウス(DWH)との連携によってBIがその世界を広げてきた歴史を振り返れば、このクラウド化はむしろ自然であり必須の進化だといえるでしょう。
続いて、現在世の中にあるBIツールの機能を見ていきましょう。機能は、大きく3つに分けられます。
①データ分析:データそのものを、用途や目的に応じてさまざまな角度から分析し、そこから事実(ファクト)や気づきを得る分析機能
②ビジュアライゼーション:集計・分析したデータを表やグラフで可視化して、数値や文字の羅列からは見えにくい規則性や傾向を、直感的に把握できるようにする機能
③レポーティング:②で可視化したデータをBIツールのダッシュボード上に表示したり、PDFなどのファイルや紙の資料としてプリントアウトしたりする資料化の機能
こうした機能によって経営陣や現場のスタッフは、最新のデータをもとに業務の分析を行い、ファクト(事実)にもとづいた迅速な意思決定ができるようになります。急速に変化し続ける時代にあって、経験や勘、過去の成功例だけに頼った判断が困難な今、BIツールは企業のビジネスの現場に欠かせないツールといえます。
ここからは、ユーザーの視点からBIの進化をたどってみたいと思います。
BI初期の1970~1980年代は、まだメインフレームと呼ばれる大型の汎用コンピュータや、オフコンと呼ばれた中型機の時代です。このころのBIは、まだ「データ分析」という技術の一部に過ぎませんでした。高度な専門知識を要するため、データサイエンティストや情報システム部門(以下、情シス部門)など、ITの専門家が扱うものでした。
例えば、ある業務部門がデータ分析で最近の業績動向を知りたいと思ったら、まず情シス部門に依頼して、必要なデータを集めてもらわなくてはいけません。メインフレームの基幹システムの中にある経理情報や売り上げ、生産実績など、目当てのデータを抽出、さらにそれらをまとめてデータ分析に必要な形(キューブ)に加工して、そこからやっと本題の分析にかかるといった具合です。
これには非常に多くの時間とコストがかかる上、ビジネスサイドと情シス部門側のコミュニケーションがうまくいかないと、希望と違う、もっといえば使えないデータが出てきてしまいます。当時そうしたことはさほど珍しくありませんでしたが、それでは迅速なデータ利活用や、それによる正確な意思決定など望めません。まだこの当時のBIは、現場のビジネスユーザーには縁遠い存在でした。
また、初期はBIツールというカテゴリーはまだ存在せず、特定のデータ活用の機能に特化したシステムとして、基幹システムから派生したものがほとんどでした。当時よく使われたものとしては、「意思決定支援システム」「経営情報システム」「戦略情報システム」といったものが挙げられます。
ただ、いずれも経営者や決定権者が自分で操作して分析を行うことはできず、リアルタイムな意思決定にはほとんど貢献できませんでした。「現場でデータを活用しながら、リアルタイムにビジネスをドライブする」ことが可能なBIツールの登場には、まだかなりの時間が必要な状況でした。
大きな転機が訪れたのは、1989年のこと。先述のドレスナー氏が、BIを定義して間もなくのことです。ちょうどこの時期は、従来のメインフレーム、すなわち独自のOSやソフトウエアで稼動し、異なるベンダー同士のデータ連携や接続ができない閉じた世界から、オープンシステムと呼ばれる新たな世界への転換期に当たっていました。

オープンシステムとは、WindowsやUNIX、あるいはLinuxなど、共通のプラットフォームを採用していればどこのベンダーの製品でも、お互いにデータのやりとりができるものを指します。今日の私たちから見るとごく当たり前の「データ仕様の標準化・共通化」は、この時代に一気に広がりました。
さらに追い風として、ネットワーク化によって複数のシステムを接続することが可能になり、コンピュータ自体もそれまでの巨大なホストコンピュータだけでなく、パソコンや小型のサーバーなどが次々に登場してきます。1990~2000年代の、いわゆる「エンドユーザーコンピューティング」(EUC)時代の幕開けです。
この時代には、もう1つの大きな技術面のトピックがあります。データウエアハウス(DWH)の登場です。それまでのデータ分析では、先ほども触れたように複数の異なる基幹システムから、その都度必要なデータを抽出し、行いたい分析に合わせた加工をして「キューブ」と呼ばれる分析用のデータをつくらなくてはなりませんでした。
その点DWHでは、あちこちのシステムからデータを吸い上げて、あらかじめ目的に合わせた分析をしやすい形で蓄積しておけるのです。このため、分析の要請から結果の出力までフローが飛躍的に効率化され、分析精度も大幅に向上するというメリットを享受できるようになりました。分析に特化したツールも開発され、ここが名実ともに第1世代のBIツールの登場となったのです。

一方では、ネットワークも急速に進化します。1990年代半ばにはSaaSも普及し始め、それがそれまでのシステム中心のIT利用から、用途に応じたサービスとしてのITという考え方が台頭してきます。それを受けてカスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)やサプライ・チェーン・マネジメント(SCM)、そしてセールス・フォース・オートメーション(SFA)などのクラウドサービスが登場。さらに2008年にはGoogle Clloud Platform、2010年にはMicrosoft Azure(当時はWindows Azure)がリリースされ、現在にほぼ近いクラウドプラットフォームが出そろいました。
この時代になるとEUCはさらに進化し、エンドユーザー、つまり業務の現場の人たちが、パソコンからネットワークを介して基幹システムの中にあるデータにアクセスし、そこからダウンロードしたデータを自分のパソコンの上で自由に分析できるようになります。こうした環境が整ったことで「デスクトップBI」といった言葉が生まれ、現在のセルフサービスBIへと発展していきます。これが第2世代BIと呼ばれるものになります。
こうしたビジネスにおけるIT活用のパラダイムシフトによって、BIツールはその後も注目度を高めていきました。2020年代の現在、BIは経営層からライン・オブ・ビジネス(LOB)の現場まで、全ての人々が自分たちのビジネスのパフォーマンスを最大化するためのツールとして欠かせない存在になっていきます。

その要請に応えるため、BIツールもさまざまな最新技術を取り入れた新製品やサービスが次々に登場しています。AIを採用した第3世代BIツールは、その典型です。初めてBIの定義が示されてから約30年を経て、ドレスナー氏が思い描いたようにBIは全てのビジネスパーソンにとって身近なツールとなり、「データ分析の民主化」が実現したといえるでしょう。
ここまで見てきたとおり、BIツールは、大きく3つの世代に分けられます。第1世代がBI草創期である1990〜2000年、第2世代が2010〜2020年、そして第3世代が現在の2020年以降です。そして第3世代は、この先にある第4世代BIへの重要なブリッジとなる存在といえます。
というのも、この第3世代は、前章で触れたように「データ分析の民主化」を実現した世代であり、セルフサービスBIの実現だけでなく、導入形態を自由に選択できること。さらに導入のしやすさを考慮した設計や、ユーザーサポートおよびコミュニティといった周辺機能や環境も含めて実現しているからです。ウイングアーク1stが提供しているBIダッシュボード「MotionBoard」やデータ分析基盤「Dr.Sum」も、まさにそうした特徴を備えた第3世代のBIツールなのです。
では、この先のBIツールは、どのように進化していくのでしょうか。データ分析の世界では、すでに第4世代のBIツールの在り方を探る動きが数年前から活発化しています。

まず1つが、分析ツールとデータベースやDWHとのシームレスな連携です。すでにこうした構成は、ネットワーク化の流れとともに実現されてきましたが、今後は、さらに緊密かつリアルタイムな連携を実現することで、ユーザーが自ら仮説を立てて必要なデータにアクセスし、分析して結果を引き出す、いわゆる「モダンBI」を強力に進化させていこうという目論見なのです。
すでにウイングアーク1stでも、「Dr.Sum」とMicrosoftのデータビジュアル化ツール「Microsoft Power BI」の連携など、積極的に取り組みを進めています。こうしたコラボレーションは、第4世代BIツールにおけるトレンドになっていくのではないでしょうか。第4世代では、従来のデータベースやDWH連携はより高度になり、リアルタイム性やオンデマンド対応を強化した、ビジネスにおけるデシジョンツールとしての性格を強めていくと予想されています。
そしてもう一つの第4世代BIツールのキーワードは、今一番の注目を集める「AI」です。その1つに、米ThoughtSpot社の開発した、検索機能とAIを活用した次世代分析プラットフォーム「ThoughtSpot」と「Dr.Sum」や「MotionBoard」の連携があります。これはgoogle検索のように、知りたい事柄に関するキーワードを使って検索するだけで膨大なデータを分析し、そこからAIが導き出したインサイトを提供できるというものです。
現在、この第4世代BIツールの領域は、さまざまなベンダーが研究開発にしのぎを削っており、一時も目が離せない状態です。ビジネスにおけるデータ分析・活用に関心のある方は、今後も日々のニュースから目が離せないでしょう。
メルマガ登録をしていただくと、記事やイベントなどの最新情報をお届けいたします。
30秒で理解!インフォグラフィックや動画で解説!フォローして『1日1記事』インプットしよう!
データ越境者に寄り添うメデイア「データのじかん」が提供する便利ツールです。
本ツールは、JavaScriptを用いてお客様のブラウザ上で処理を行います。サーバーとの通信は行われず、入力データはお客様のみの端末内で処理されます。

